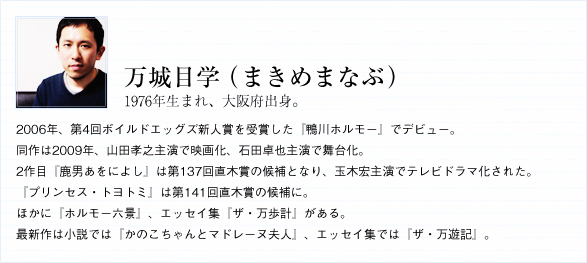京都市の人口の一割を占めるという学生は京都の町にとってお客さん、というフレーズを、私も学生時代に幾度となく耳にしたが、その意味を本当に理解したのは、小説家になり、ふたたび京都に戻ってきたときのことである。
私のデビュー作『鴨川ホルモー』が世に出て、ようやく一カ月が経ったころの話だ。
最近の作家の大事な仕事のひとつに、「書店まわり」というものがある。本が出たあとに本屋をまわり、現場の書店員のみなさんのもとへ「じゃんじゃん売ってください!」とお願いにあがる。気のいい書店だと、サイン本を作らせてくれる。サインが記された本は、返品不可になってしまうので、書店にとっては「これだけは絶対に売る」と約束することと同義になる。
京都に行く十日ほど前、私は東京の大きな書店を回った。まだデビューして数週間の、誰も知らぬ作家など歯牙にもかけられまい――、と戦々恐々として本屋に赴いた私だったが、現実はまるでちがった。東京の本屋はやさしかった。誰もががんばって、と声をかけてくれ、すべての店でサイン本を置くことを許してくれた。私は感激した。こわいところ、冷たいところと思いこんでいた東京の認識を少しだけ改めた。
「東京であれだけやさしかったのだから、京都を舞台に書いていることだし、京都の人はもっとやさしいだろう」
当然、こう考え、私はほとんど凱旋気分で京都の書店に乗りこんだ。
そこで、私は京都の本当の姿に出会う。
京都はまったくやさしくなかった。
誰もが困惑した表情で私を迎え、サイン本も誰ひとりとして置くことを許してくれなかった。京都が好きで、京都の大学を出たことなど、何の関係もなかった。ただ、結果を出しているか否か、それだけが重要だった。
そのとき、ようやく私は、自分が「お客さん」ではなく、一個の大人として対応されていることを知ったのだ。
あれから四年が経ち、今は京都の本屋もとてもやさしく私を迎えてくれる。サイン本どころか、サイン会まで開いていただいたほどだ。それだけに、あのときのシビアな経験はいい思い出になっている。学生という身分でもって、自動的に認められるのではなく、自身の結果でもってもう一度、ゼロから認めてもらえたことが、やはりうれしいのである。