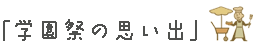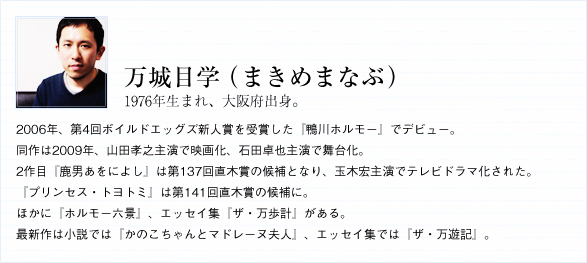秋である。学園祭のシーズンである。
在学当時、私は学園祭に関しある持論を唱えていた。それは、学祭を十全に楽しむことができるのは、模擬店を出店したり、企画を催したりする当事者だけであり、何の関係もない人間がふらっと立ち寄っても、いまいち楽しみを享受できぬままキャンパスを去ることになる、というものだ。
かくして私は大学四回生のとき、このまま学祭というものを一度も楽しまずに京都を去るのはいかにも惜しいと、模擬店参加を企てた。すなわち、「アップルジュース」なる架空の一人サークルを打ち立て、代表者として模擬店抽選に応募したのである。
おそらくすさまじい倍率だったはずである。先輩の号令のもと、あまたの後輩が架空の即席サークルを作り、少しでも出店のチャンスを得ようと何枚も応募用紙をしたためていたはずである。
そんななか、私はたった一枚の応募用紙を運営に提出し、完全にその行為を忘れ去った頃、見事出店の権利を得た旨、連絡を受けた。
困った。
何にいちばん困ったって、すでに応募時のモチベーションが失われていたことである。それでも、私は仲のいい学部の友人五人を呼び、ともに模擬店を出店しないか、ともちかけた。全員四回生、いい加減おっさんばかりである。今さら、きゃぴきゃぴしたこともできない。会議の結果、決定した出し物は「ホワイトシチュー」だった。「誰もやっているのを見たことがないものを売る」という、無謀なオリジナリティーを追求したゆえの結論だった。
男たちはシチューを作った。私の下宿に泊まりこみ、ひたすらタマネギを切り刻んだ。しかし、学園祭当日、シチューはまったく売れなかった。かわいい女の子の呼びこみもいない、ただ男たちが仏頂面でシチュー鍋をかき混ぜている店先に訪れる人などいやしなかったのである。
売れない間に、シチューはどんどん蒸発していった。味はどんどんまろやかになっていった。手抜きのない良質具材の極上シチューである。残ったシチューはすべて男たちの胃袋に収まった。「なぜ、このうまさがわからない」と誰もが憤慨しながら、単なる屋外クッキング場と化したテントのなかでシチューをすすった。
決算を行うと、一万円の赤字が計上された。「模擬店を出しても、そんなに楽しめない」これを知るための高い勉強代と相成った。