 Books Books |
| 新刊紹介 |
| *値段はすべて本体価格で表示 |
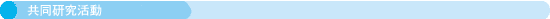 |
 |
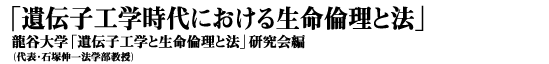 |
本学の人間・科学・宗教研究助成(2000〜2002年度)を受け、2002年9月に本学で開催した日独共同シンポジウム「遺伝子工学の時代における法と生命倫理」の成果を発表した。ドイツから、H=L・シュライバー元ゲッティンゲン大学学長をはじめ9名の報告者を招いたほか、内外から、法律学のみならず、医学、哲学、宗教学などの研究者が参加した。なお、ドイツ語版も、今秋に出版された。
2003年8月刊/581頁/日本評論社/8000円
|  |
|  |
|
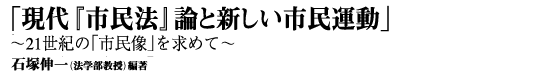 |
本学の社会科学研究所共同研究(1999〜2001年度)における「現代『市民法』論の系譜を検討し、近代法の発展過程の中にこれを位置づけるとともに、これらの理論と新たな市民運動の関係を検討し、21世紀の新たな『市民像』の構築」を目指す研究の成果をまとめた。理論編と実践編に分かれ、後者では、少年法改正、アミティ、薬物依存、刑務所などと市民運動との関係を論じている。
2003年3月刊/267頁/現代人文社/4900円 |  |
|  |
|
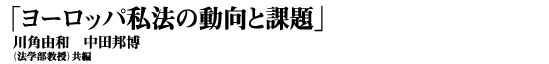 |
本書は3部構成。第1部は、「ヨーロッパ私法の形成と方法論」として、著名な比較法学者であるハイン・ケッツ教授の日本での講演原稿を中心にそれに関連した論稿を収録。第2部は、主にヨーロッパにおける契約法、不法行為法の動きやそうした分野でのEU指令の展開を分析した論稿が収められている。第3部は、今後のヨーロッパでの契約法の展開をみる上で不可欠となる「ヨーロッパ契約法原則」の翻訳を資料として掲載。もっとも、本書は、ヨーロッパ私法の一断面を明らかにしたものにすぎず、今後もこれを基礎としつつ、共同研究を展開する予定。
2003年3月刊/523頁/日本評論社/7000円
|  |
|  |
|
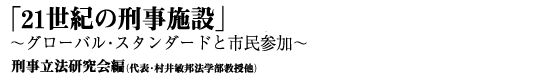 |
刑事立法研究会が、文部科学省科学研究費(1998〜2001年度)「変動する社会における刑罰の実態分析とその改革のマスタープラン」の成果をまとめた。イギリスの保護観察首席監察官R・モーガン氏を招き、2002年3月に開催した国際シンポジウムは、関係者の注目を集めた。名古屋刑務所事件を契機に始まった行刑改革会議における議論にも大きな影響を与えている。
2003年7月刊/364頁(CD-ROM付き)/日本評論社/6000円
|  |
|  |
|
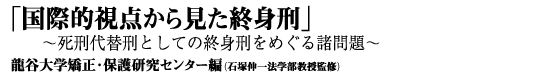 |
同センターが、ドイツから終身刑の研究者であるH・ヴェーバー教授、イギリスから刑務所改革に取り組むNGO、プリズンリフォーム・トラストの事務局長であるJ・ライオン氏を招いて、2003年2月に開催した国際シンポジウムの記録を採録したほか、死刑廃止議員連盟が国会に提出しようとしている死刑執行停止等に関する法案を検討している。
2003年10月刊/175頁/成文堂/2000円
|  |
|  |
|
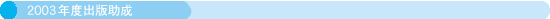 |
 |
 |
わが国の古い文化である文系・理系の垣根を取り払い、情報社会の仕組みや脆弱性の問題を、情報と人間の関係から明らかにしている。コラムや挿絵、ノートなども多く取り入れ、専門的内容を専門外の読者にも分かりやすく解説している。
2003年10月刊/238頁/オーム社/2200円 |  |
|  |
|
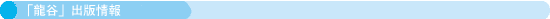 |
 |
『無人島1969-1974』
杉村昌昭(経営学部教授)共訳 |  |
フランスの現代哲学者ジル・ドゥルーズの論考・対談・インタビューなど、単行本未収録の文章を集成したユニークな本。杉村教授は全体の約3分の1を担当。
2003年6月刊/321頁/河出書房新社/35400円 |
|
 |
『住環境の物理学入門』
富田道男(文学部教授)著 |  |
住まいの環境で大切な熱、空気、湿気、音及び照明に関する基本的な物理法則の概略について解説した入門書。
2003年6月刊/166頁/北斗書房/1500円 |
|
  |
『倫理力を鍛える』
田村公江(社会学部助教授)共著 |  |
善悪の基準を解説する応用倫理学のトレーニングブック。現代社会のテーマが多数取り上げられている。ジェンダーフリーと売買春を執筆。
2003年6月刊/239頁/小学館/1500円 |
|
 |
『人間福祉の思想と実践』
山邊朗子(社会学部助教授)共編著 |  |
新しい福祉概念である「人間福祉」の思想的基盤を明らかにし、人間福祉の視点を中心に据えた方法と実践を提示した理論書。
2003年6月刊/250頁/ミネルヴァ書房/3200円 |
|
 |
『国際人権法とマイノリティの地位』
金東勲(法学部名誉教授)著 |  |
外国(韓国)国籍を保持したままで本学法学部長を務めた著者の業績のまとめである。外国人・少数者への差別・人権侵害との闘いがあるからこそ国際人権法が発展したし、又必要である。多民族・多文化共生を国際人権法的観点から論ずる。
2003年6月刊/378頁/東信堂/3800円 |
|
 |
『法然と親鸞―その教義の継承と展開―』
浅井成海(文学部教授)監修 |  |
若い研究者による研究論文集である。法然とその門弟における教義と継承をいろいろな角度より論究したものである。法然関係論文目録集も収められている。
2003年7月刊/608頁/法蔵館/6000円 |
|
 |
『注釈 国際統一売買法Ⅱ』
中田邦博(法学部教授)、
若林三奈(法学部助教授)共著 |  |
「国際動産売買に関する国連条約(ウィーン売買条約)」に関する逐条注釈書。全101ヶ条のうち第Ⅱ巻では、53条以下の注釈を収録している。
2003年7月刊/366頁/法律文化社/5900円 |
|
 |
『スモールタウン・アメリカ』
藤谷聖和(文学部教授)共著 |  |
共和国の理念を支えていたスモールタウンが、時間の経過とともに大きな変容を遂げつつ、未だにアメリカ精神の内奥で、郷愁を誘っている様を描いた。
2003年8月刊/319頁/英宝社/3000円 |
|
 |
『共和国の振り子』
藤谷聖和(文学部教授)共著 |  |
美徳の共和国から世界帝国へと変遷するアメリカの揺らぎと変貌をアメリカ文学のなかに捉えた。
2003年8月刊/386頁/英宝社/3800円 |
|
 |
『月と日本建築―桂離宮から月を見る―』
宮元健次(国際文化学部助教授)著 |  |
月と日本建築の関係について概説し、八条宮智仁・智忠親王と桂離宮、豊臣秀吉と伏見城、足利義政と銀閣寺の3つの事例を通して考察した。
2003年8月刊/230頁/光文社新書/700円 |
|
 |
『香りを聞く』
大田利生(文学部教授)著 |  |
『りゅうこくブックス』、『恒河』に掲載した小文をまとめた法話集。「香りを聞き、光に遇う」「錯覚の中で」「別れと出会い」など心にふれる内容。
2003年8月刊/146頁/永田文昌堂/1200円 |
|
 |
『健康の本質』
谷本光男(文学部教授)共訳 |  |
健康の概念はあいまいで捉えにくいものであるが、ノルデンフェルトは本書において、これまでの健康概念を検討する中から新たな健康理論の確立を目指している。
2003年8月刊/326頁/時空出版/3500円 |
|
 |
『環境倫理のラディカリズム』
谷本光男(文学部教授)著 |  |
21世紀の人類最大の課題の一つである自然環境問題に倫理学はいかに立ち向かうべきか。本書は従来の枠組みをこえて、新たな視点から環境問題に取り組む倫理学の試みである。
2003年9月刊/270頁/世界思想社/1900円 |
|
 |
『クザーヌスと近世哲学』
薗田坦(文学部教授)著 |  |
15世紀ドイツの思想家N・クザーヌスの思想を近世哲学の諸展開への視線のうちで解明し、クザーヌス研究に新たな地平を指し示す。
2003年9月刊/276頁/創文社/5600円 |
|
 |
『MELANCHOLIA』
Sylvain CARDONNEL(国際文化学部講師)翻訳 |  |
村上龍の小説『メランコリア』の仏語訳。
2003年9月刊/254頁/Philippe PICQUIER出版/18.50ユーロ |
|
 |
『古文表現法講義』
出雲路修(文学部教授)著 |  |
古文で作る物語。平安時代の物語を自分で作ってみることによって、物語文学を深く理解する。龍谷大学での講義の記録に基づいている。
2003年9月刊/244頁/岩波書店/2500円 |
|
 |
『公共経済学入門』
西垣泰幸(経済学部教授)共編著 |  |
本学藤澤宜広講師、中村玲子非常勤講師はじめ若手の研究者5名による公共経済学の導入書。スタンダードな理論と租税、年金、地方分権など現実の諸問題を展開している。
2003年9月刊/224頁/八千代出版/2500円 |
|
 |
『イギリスを知るための65章』
近藤久雄(法学部教授)編著 |  |
これからイギリスについて調べてみよう、あるいはイギリスへ出かけてみようという人のためのイギリス紹介。イギリスの様々な面を紹介した。
2003年10月刊/352頁/明石書店/2000円 |
|
 |
『メディア・プラクティス ―媒体を創って世界を変える』
松浦さと子(経済学部助教授)共著 |  |
激変するメディア環境にどう対応するか、メディア実践の成功と失敗の具体例に学びつつ、情報の受け手から能動的な送り手への変貌を促す。
2003年10月刊/288頁/せりか書房/2500円 |
|
 |
『グローバル化のなかの現代中国法』
北川秀樹(法学部助教授)共著 |  |
人、物、金の国境を越えた移動をもたらすグローバル化は現代中国法の動向に影響を与えている。政治、経済、社会の分野から法を論じる。
2003年10月刊/266頁/成文堂/2800円 |
|
 |
『現代児童福祉論』
清水教惠(社会学部教授)共編著 |  |
今日の子どもたちが置かれている福祉問題状況の認識、問題・課題の解決による福祉達成の施策や方法の理解を中心とした児童福祉のテキスト。
2003年10月刊/264頁/小林出版/2900円 |
|
 |
『大阪狛犬の謎』
小寺慶昭(文学部教授)著 |  |
大阪府下全神社928社を訪れ、1255対の参道狛犬を徹底調査。狛犬にまつわる謎を解きつつ、江戸時代の浪花の町人文化の一断面を明らかにした。
2003年10月刊/280頁/ナカニシヤ出版/2200円 |
|
 |
『法律家の歴史的素養』
児玉寛(法学部教授)共著 |  |
実務教育重視のロースクール構想が議論される現在、理論と実務の架橋とは何かについて、19世紀ドイツを素材にラディカルに提示する。
2003年10月刊/208頁/東京大学出版会/3400円 |
|

『ワークブック社会福祉援助技術演習②
個人とのソーシャルワーク』
山邊朗子(社会学部助教授)著 |
 |
個人とのソーシャルワークの技術を学生が学ぶための教材。
2003年10月刊/150頁/ミネルヴァ書房/1700円 |
|
 |
 |
 |
 |
僕らは学文局文芸部OB。歌仙や歌合や句会を下敷きにして、個人的な動機や技術や感性にて書かれる現代自由詩の閉塞を破らんとして、競作に挑んだ。詩の語り手を佐々木浩でも舞出晋一でもない僕・として、自作の詩が書けたら相手に送り、相手から届いた詩の中の詩句から引用して自作の詩の題をつける約束だった。願わくは、ミューズのご加護があらんことを。
ミッドナイト・プレス/1500円
(佐々木浩・1993年文学部哲学科卒業・団体職員・京都府八幡市、舞出晋一・1997年文学部哲学科卒業・会社員・東京都世田谷区) |  |
| |
 |
 |
 |
1作家1冊全33冊別冊1よりなるセレクション歌人シリーズの1冊。短歌500首、散文40枚、略歴と初句索引にプロデューサー藤原龍一郎による作家論「無敵の草食獣」が付く。短歌は既刊5歌集より『勇怯篇・草食獣そのⅢ』を完全収録、『草食獣』『続・草食獣』『草食獣第四篇』『草食獣第五篇』を抄出、散文は「秋の歌人・長塚節覚書」。30年の歌業を問う。
邑書林/1300円
(吉岡生夫・1974年文学部仏教学科卒業・歌人・兵庫県川西市) |  |
| |
 |
 |
 |
住職であり、布教使である著者が、毎月一回日曜学校で行った、子ども会法話集である。10周年記念のⅠに106話を、20周年記念のⅡに86話を載せている。「後生は明るいか?」「生命はだれのものか」「親は死んでも子を育てる」「火中の蓮華」「親の遺言・南無阿弥陀仏」等、子どもから大人までわかる法話満載。浄土真宗の生死観・救済観が明瞭。
探究社/『一子のごとく』I
:1000円、『一子のごとく』II :1500円
(岡村謙英・1977年文学部真宗学科卒業・住職・山口県豊浦郡) |  |
| |
 |
 |
 |
「生きるということの難しさと素晴らしさ」「運命に宿った偶然性と蓋然性との相剋」そうした普遍的なテーマを軸にして綴られた物語。プータローだった主人公・遼が遭遇し、辿ることになった宿命とは?この失われた10年に魂を吸い取られそうになっていた青年が、見つけたものとは…?ちなみに大学構内の描写では、20年ほど前の龍大がモデルとなっている。
鳥影社/2200円
(森山哲成・1984年法学部法律学科卒業・教員・奈良県桜井市) | 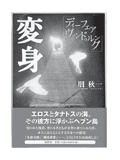 |
| |
 |
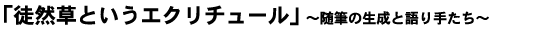 |
 |
徒然草という「古典」もまた、「随筆文学」という内実不明な術語の中に幽閉され続けられてきた不幸な研究史をもっている。本書はテクストの生成する〈今・ここ〉に視座を定め、記憶の表象としての随筆の真実に迫ろうとする。語り手の変貌を追跡することで、徒然草を文学史的な孤立から解き放ち、新たに定位し直すことを目指す。
清文堂/4500円
(朝木敏子・2003年文学研究科博士課程日本語日本文学専攻修了・本学非常勤講師・富山県新湊市) |  |
| |
 |
| ■トップページへ |
 |