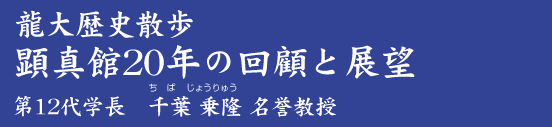
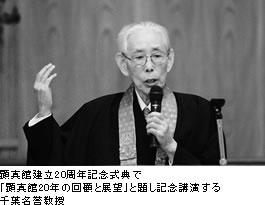 |
 |
この深草学舎は、昭和36年の親鸞聖人七百回大遠忌記念事業の一つとして開設され、経済学部が設立されました。昭和41年には経営学部、昭和43年に法学部がそれぞれ増設されました。
このころ発生した大学紛争は、昭和44年にわが大学にも波及し、同年6月に深草学舎は大学改革を要求する全共闘学生によって封鎖されました。さらに9月には「本願寺権力の大学介入反対」を叫んで本願寺に押しかけ、御影堂に突入を図る事態が発生しました。こうした様相から、大学のあるべき姿、特に宗教教育の在り方、建学の精神の再認識の必要性を痛感させられたのでした。そして顕真館の誕生を促すことになります。
昭和49年、紛争はようやく鎮静化に向いました。このころ日本の経済はインフレのため、物価は毎年上昇していましたが、大学は紛争のため学費を値上げすることができず、学生数を増やしてついに定員の2倍に達しました。そのため学生からの「マスプロ教育反対」「立ちんぼ授業をなくせよ」という強い要求となりました。当時の学長は「私は学費の値上げはしない」といって学長を退任されてしまい、その時、文学部長をしていました私は、学長事務取扱に任命されて、学費問題の処理をせざるを得なくなりました。
対策として、財政を安定して運用できるようにとスライド制学費を導入する1期12年間の長期計画ができあがりました。この計画の要点は、学生数を減らして教室等の教育研究の施設を充実改善する、教員は2倍に増員して教育研究内容の充実を図るという思い切ったものです。
やがて二葉憲香先生が学長に就任され、まず緊急を必要とする教室など教育施設が整備され、ついで礼拝堂などの施設を整備することになりました。昭和53年に「深草学舎礼拝堂建立趣意書」が発表され、建学の精神を具現化する教育施設の原点としての性格を持つ建物として、広く学内外のご協力を得て建設することになりました。
4年後の昭和57年に、大学の教職員、卒業生、保護者および有縁の方たちのご協力で建設資金は目標に達し、同年10月に起工式を、2年後の昭和59年3月に竣工式が行なわれました。私は礼拝堂が完成する前年に学長に選ばれて、竣工式に参列させていただくことになったのでした。
この礼拝堂は、親鸞聖人のご著書『顕浄土真実教行証文類』(『教行信証』)から「顕真」の二字を拝借して「顕真館」と名付けられました。また礼拝対象のご本尊さまは、施設委員会の答申に基づき、阿弥陀さまのお木像ではなく、本願寺に伝来の親鸞聖人ご自筆の「南無阿弥陀仏」の六字名号を模写彫刻した簡素なご本尊にいたしました。
さて、この顕真館の特徴は、簡素な内陣と、正面入口に掲げられた平山郁夫画伯が描かれた祇園精舎の陶版画であります。祇園精舎は釈尊の一代結経、つまり釈尊がお説きになった多くのお経の中で、結びのお経である阿弥陀経をお説きくださった場所として、私たち浄土教徒にとってご因縁の深い精舎であります。
顕真館の竣工式の後に行なわれましたレセプションで、私は次のようなご挨拶を申しました。
平安時代に、藤原頼通が宇治平等院に阿弥陀仏像を安置した鳳凰堂を建てます。その落成法要の時の有様が『沙石集』という本に記されています。多くの人びとが「藤原頼通公は、この世にお浄土を再現してくださった」と褒めたたえました。ところが、ある一人の僧が「藤原頼通公は、このお堂を建てたために地獄に落ちるであろう」と言いました。なぜなら「鳳凰堂を建てるために人びとから苛酷な税金を取り立て、また建築に携わった人たちを安い賃金で酷使した悪行の報いである」ということです。
顕真館は皆様のダーナー(寄付)による浄財で建てられましたので、その点で私の地獄行きは免れるかもしれません。しかし、浄財をいただいて建てた顕真館の今後の運営を誤ると私は地獄に落ちることになります、というようなお話をしました。
 顕真館建立20周年記念行事を開催
顕真館建立20周年記念行事を開催 |
顕真館の活動について申しますと、竣工しました翌々月の5月1日に記念講演会を開催し、本願寺の前門さまが「21世紀と仏教」と題してお話をしてくださいました。 その中で前門さまは、人間の間違った行動、醜い行為が存在する限り、その矛盾や誤った中で生きていく限り、宗教を求める気持ちがおのずから生まれてくる。仏教は科学と大きく矛盾するところがないので、21世紀の人びとの支持を得られるものと考えられる、とお話しくださいました。そして、日本仏教の活動の現状が葬式や法事に重点がおかれているだけでは、一般の人たちの支持を得られない。それだけでは宗教の本義が表せない。あくまでも信仰を求め、自らも信じ人をも信じさせる布教活動が大切である。以上のような趣旨のお話をしてくださいました。 顕真館ではこれ以来、著名な信心深い方たちにおいでいただいて、親鸞聖人のみ教えに学ぶ集いが開かれてきました。今後ともこのような催しを強化充実していただきたいと思います。そしてこうした顕真館の活躍とともに、建学の精神を全学構成員に普及徹底するのは私たち僧籍にある者の役目であります。 いまの大学の実情は、僧籍にある者の多い古い学部の老朽化が目立っているように思います。もちろん大学の施設は時代を経るにしたがって老朽化します。しかし、教育・研究については、年々進歩し発展すべきであります。しかもいま日本は少子化時代となり、いわゆる大学冬の時代を迎えました。このような時代を生き抜くためには、教員の資質を向上させ、優れた研究成果を、分かりやすく学生に理解してもらう必要があります。 親鸞聖人は『教行信証』の第六巻化身土巻の終りのところに、中国の道綽禅師の著された『安楽集』の中のお言葉を引用されています。それは「前に生れんものは後を導き、後に生れんひとは前を訪へ、連続無窮にして願はくば休止せざらしめんと欲す。無辺の生死海を尽さんがためのゆえなり」と記しておられます。 先輩は後輩を導き、後輩は先輩に学んで教学の進歩に励むようにと諭しておられるのです。私たちは親鸞聖人のお言葉に添うよう努力しなければならないと思っております。 (平成16年12月10日の記念講演抄録) |
| ←トップページへ戻る |