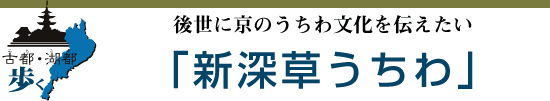鮮やかな色彩感覚で
現代に甦った幻の深草うちわ
「新深草うちわ」の絵柄は、京都の名所図絵の挿絵に日本画の技法を使い、手描きで彩色を施したもの。コンピューターグラフィックで鮮やかに彩色したものもある。「都名所図絵」は当時の京都ガイドブックのようなもので、天明7(1787)年発行の「拾遺都名所図絵」の中には「深草の里 団扇店」という題の絵もあり、往時の伏見街道の賑わいや深草のうちわ店の繁盛の様子が見てとれる。
現在、「深草うちわ」の地紙は琵琶湖産のヨシ紙を使用。「ヨシは水の浄化作用がある植物ですが『魔を祓う』という言い伝えもあるんです。それで、このうちわで扇いで『魔よけ』という意味でも使っていただきたいという思いで使い始めました」という住井さん。
骨になる竹は徳島産真竹の3年ものを使用。一節の竹を7〜8等分に分け、節を境にうちわの上部の骨の部分を細かく割き、約42本の骨を作る。骨は丸亀(香川県)の専属の職人に依頼して送ってもらっている。
送られてきた骨に地紙を貼る「貼り」や「撫ぜ」、「かまきり」「うちきり」「スジ入れ」などの作業は店の二階で行なっている。一本一本、すべての工程が手作り。丁寧で細かい手仕事に驚かされる。貼りの作業は毎年2月に始めるが、貼る際には糊の溶き加減が重要で、その日の気温や天候にも左右されるそうだ。
「新深草うちわ」は現在、157景。そのうち京都は114景を数える。祇園祭や大文字の送り火などの祭事や、醍醐の花見、東福寺の紅葉など季節の風物詩が詳細に描かれ、鮮やかに彩色されている。実用品でありながら風情があり、贈り物や飾り物としても好評を得ている。「『深草うちわ』は飾り物にされる方が多いのですが、私どもとしては実際に使用してほしいと思っています。紙が破れた場合は張り替えもできますし、骨の部分の竹は腐らないので一生もちます。昔は自分で扇ぐより、大切な方に涼を送るために扇いであげるというのがうちわの役割でしたので、普段の生活の中で使っていただきたいですね」と話す住井さん。現代にも通じる鮮やかさで甦った「深草うちわ」。ぜひ、手にとってその想いを感じてみたいものだ。 |
 |
 |
 |
| 彩色都名所図会の新深草うちわ |
 |
 |
| 骨のささくれている部分を取り除く |
 |
 |
| 骨の間隔をそろえ、少し濃い目ののりで貼る |
 |
 |
| 「撫ぜ」は地紙と骨をなじませる力加減が難しい |
 |
 |
| 撫ぜ終わったら乾かないうちに干す |
|