|
|
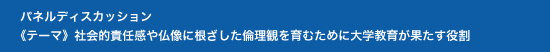 |
| パネルディスカッションでは、UCデービス校より、ラリー・ヴァンデルホエフ学長の他、エンリケ・ラヴァ二ア工学部長、ズヘア・ムニール工学部教授、龍谷大学からは若原道昭学長、四ツ谷晶二理工学部長・理工学研究科長をパネリストとして迎え、GP責任者である大柳満之理工学部次期学部長・理工学研究科長がモデレータ役を務めました。モデレータが「倫理観の希薄化に大学教育が関わる事例」や「社会的責任感や倫理観を培うために必要な教育プログラム」など、いくつかの疑問を投げかけ、各パネリストがそれに答える形でおこなわれました。 |
| 大学教育の立場から考える 倫理観の希薄化が起こす問題の属性 大柳 国内、世界を含めて倫理観の希薄化が進んでいるなか、大学教育が何らかの原因に関わっていると思われる事例を挙げてください。 Lavernia 一つは本来の理想とすべき教育と現状の教育に差がある事です。大学教育の目的は本来、知性だけでなく肉体や精神も高めていくことにありましたが、今日の我々の教育制度では、キャリア重視のトレーニングや情報提供に留まっています。もう一つはグループよりも個人の努力を重視するあまり、幅広い視野や一般論などの全体的な物の見方を忘れがちである事です。 Munir 倫理の希薄化や社会的な問題というのは決して新しいものではなく、何千年にわたり仏教や他の宗教が理想的な社会を求めるために思考してきた課題です。しかし、現代の状況は、個人が社会とのつながりを意識できない、社会の一端を個人が担っているという責任を忘れているという傾向が強くみられ、問題化しています。個人の利益や金銭的な成功ばかりが重視され、精神的な達成感が軽視される…。その結果、データの捏造や詐欺行為といった様々な問題が引き起こされています。 四ツ谷 日本で実際に起こった事例を二つ挙げますと、最初の問題は偽装です。神戸の震災時、鉄筋の量を減らし、手抜き工事をおこなうという耐震偽装の問題が明るみに出ました。もう一つは、ハムの製造に当たり、使用していた地下水にシアンが含まれていたのを工場長が上司に報告せず、そのまま使用し続けたという事件です。社会が求める安全管理への取り組みを怠った事、また、シアンが含まれていた事に対し、原因を徹底究明するという技術者としてあるべき姿勢が欠けていた事が、教訓的な問題として表面化しています。 大柳 そういった様々な問題が噴出する原因はどこにあると考えられますか? 若原 近代化のなかで生まれた人間中心的な考え方が原因の一つであるように思います。宗教の世俗化、自由と平等という指針の上に国家権力を築く民主化、高度に工業化された生産をめざす産業化、農村から都市への大規模な人口移動による都市化といった近代化のプロセスのなかで、実証可能な科学的知識が最高のものであるという科学至上主義的な考え方や合理主義が生まれ、人間中心主義の思想を形成してきました。グローバル化した現在、激しい経済競争により、これらの思想がさらに強まり、利己的で思いやりや優しさのない、欲望の塊へと人間を変化させています。自らの生き方を見つめ直さない限り、持続可能な社会は築けないでしょう。 Vanderhoef 大学に全ての責任があるとは言いませんが、このような問題の解決のために大学が果たす役割はあると思います。その一つとして、社会に対し様々な原則や価値観を多方面から提案すること、例えば、本学で実践している留学制度などは、倫理観を確立するよい機会です。より多くの経験を積み、人生や価値観を変えるチャンスを与える事が大学に求められていると感じます。 適切な倫理観を育むために
Munir 大学教育が倫理観の育成に対してどれだけ貢献できるのか、まだ十分に実践されていないため、明言はできません。しかしながら、数年前からアメリカでも日本でもおこなわれている、「一般教養のコースを全ての学生に課す」という取り組みは、倫理観を育むには非常に良い方法であると思いますし、学生が他の文化に触れることができる点で有効です。ただし、学生に社会的な責任感を教えていく事で、具体的に教養教育がどのような効果がもたらされるかというのを、どういう風に実証していくかを考える必要はあるでしょう。 四ツ谷 龍谷大学には「仏教の思想」という科目が必修としてあります。理工学部では、仏教をわかりやすく噛み砕いた本を学生に配付するなど、仏教の思想を学生が理解するためのサポートをしています。また、精神的なサポートに注力したキャリア教育もおこなっていますが、技術者のための倫理観の養成という点では、まだ十分にできていないという感覚があり、反省すべき点であると思います。 大柳 改めて、大学で倫理観を養うための教育をおこなう意義はどこにあるとお考えでしょうか? 若原 文部科学省や中央教育審議会の言葉を借りますと、21世紀の日本社会は「知識基盤社会」であり、新しい知識や情報、技術の創造が不可欠とされています。創造力のある人間を育てる事によって、新しい製品を生み出し国際的な競争に勝ち残るという、そんな社会の実現のために、世界に通用するような大学教育をおこなう事が強く求められてきております。大学としてその教育の要求に応えるために、現在、教養教育が重視されています。本学では、建学の精神に基づいて教育をおこなう事で、どんな職業にも社会にも通じる豊かな精神性を備えた人材を育てる役割を果たせると考えています。 Vanderhoef 大学卒業後も、継続的に知識を高めるための努力をおこなうべきであるという事を大学教育の一部として教えることが大切です。特に倫理観や行動規範を作り出す力は、生涯続く問題として、学習していかねばなりません。 大柳 倫理観を培うために、どのような教育手段が実際に考えられますか? Lavernia 学生が我々と協力しながら作業をしたり、文化の異なった学生同士が共同研究をすることで、グループの中の個人の位置づけを理解させることです。しかし、より大切なことは、教育者自身が世界中で社会的な倫理観の必要性を感じて、それを促進すべく努力していく事だと思います。 Munir 一つは、様々な価値観を持った人々が平等に教育を利用できる環境を作る事、二つ目は、教養教育にディスカッションセクションを設け、学生と対話しながら、社会的な責任感を導き出す事です。さらに、実地体験を積極的に提供し、学生が社会的責任を肌で感じることが可能なインターンシップやボランティアなどの推進も、有効であると考えられます。 四ツ谷 自分が他者の立場だったらどういう風に行動するかというような、想像力を働かせるトレーニングをする事です。技術者兼社会学者として、直接対峙する事のない末端のユーザーや未来の世界といった、見えない部分にも神経を行き届かせる事ができる。そんな風に想像力を広げられる人材こそが、技術者になるべきであると思います。 大柳 有難うございました。最後に、双方の学長からメッセージをお願いします。 若原 本学では、大学のめざすべき姿として、2000年から2009年までの第四次長期計画のなかで「共生(ともいき)をめざすグローカル大学」という言葉を掲げています。「ともいき」という言葉は、仏教の根本思想である「縁起」という意味合いを持っています。ただ一人で生きているのではなく、目に見えない無数のつながりのなかで、支えられて存在しているという考え方です。私達はその縁起思想に基づき、倫理性や社会的責任を備えた人材を、育てていきたいと思います。 Vanderhoef アメリカに端を発した世界的な金融不安は、様々な危機をはらんでいますが、その危機を無駄にしてはいけません。そういった危機が起こる原因を倫理の問題として掘り下げ、改善点を発見し、より良い倫理観を持つ社会へ進むためのチャンスとして捉えるべきではないでしょうか。危機的な状況こそ大きなチャンスです。そのなかで、しっかりとした価値観を示し行動していく事が、我々の役割ではないかと思います。 |
 |
 |
 |
||
| Larry N. Vanderhoef(ラリー・ヴァンデルホエフ) 学長 1994年カリフォルニア大学デービス校学長に就任。科学研究基金獲得額を米公立大学12位に押し上げるなど、大学の発展に貢献。専門分野は植物生化学。PhD。 |
Enrique Lavernia(エンリケ・ラヴァニア) 工学部長 カリフォルニア大学アーバイン校教授を経て、2002年カリフォルニア大学デービス校工学部長に就任。2009年同校副学長就任予定。専門分野は無機材料科学。学会賞受賞多数。PhD。 |
Zuhair Munir(ズヘア・ムニール) 工学部教授 1972年カリフォルニア大学デービス校に就任。1998年から研究部門の副学部長を経て2002年まで工学部長を務める。専門分野は無機材料科学。学会賞受賞多数。PhD。 |
 |
 |
 |
||
| 若原道昭 学長 1982年龍谷大学短期大学部講師に就任。助教授を経て1992年から教授。短期大学部長や副学長を務める。2007年より学長に就任。専門分野は教育哲学。教育学修士。 |
四ツ谷晶二 理工学部長 1989年理工学部創設と共に、龍谷大学理工学部教授に就任。2005年理工学部長に選出され、現在に至る。専門分野は数学。理学博士。 |
大柳満之 理工学部次期学部長 大学院GPプログラム「東洋の倫理観に根ざした国際技術者養成」代表。1989年龍谷大学理工学部助手、講師、助教授を経て2001年に教授就任。学長補佐やRECセンター長を務める。専門分野は無機材料化学。工学博士。 |
|
| ←トップページへ戻る |