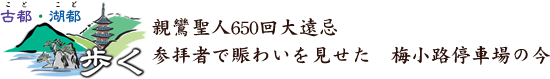《梅小路公園芝生広場》
かつて梅小路停車場があったとされるところは、芝生広場となり市民の憩いの場となっている。 |
|
大遠忌のために作られた
梅小路停車場
2011年、親鸞聖人750回大遠忌法要を迎える西本願寺では、御影堂の大修復や全国の博物館を巡回する「本願寺展」の開催など、様々な関連行事が開催されている。
半世紀に一度の浄土真宗で最も大切なこの法要は、1911(明治44)年におこなわれた「親鸞聖人650回大遠忌」でも同様に、国内はもとより海外からも熱心な門信徒達が訪れた。法要は、第1期と第2期に分かれ、1期は3月16日から25日までの10日間、2期は4月7日から16日までの10日間おこなわれた。御影堂の周囲には25000人の参拝者を収容する1300坪の大掛出が設置され、勤式と舞楽は隔日に朝と夕方の2座があり、勤式では朝夕ごとに3千名もの僧侶が交代して勤めたという。
参拝者は当初、第1期が11万5千人、第2期が10万5千人と見込まれていたが、実際は前者が57万5823人、後者が43万1616人と予想をはるかに上回った。大遠忌の様子を記録した『遠忌大観』には、106歳という高齢で参拝した女性や、信心を重ねて一途に京をめざした少年少女の物語などいくつもの信者達のエピソードが残されている。龍谷大学は、学舎を布教本部や宿泊所として提供するなど大遠忌に協力した。なかでも、布教を目的とした「独立学生総班」を学生が結成し、200名余りの龍谷大学生が期間中各宿泊所を慰問したり、路傍伝道をおこなったという。
100万人を超える参拝客が利用した交通手段の一つとして、鉄道が挙げられる。鉄道の歴史を少し辿ってみると、1872(明治5)年、新橋-横浜間が開通されたことを皮切りに、1877(明治10)年、京都駅が開業。神戸-京都間が結ばれると、1889(明治22)年には新橋-神戸間
が完成し、京都-新橋間を全通する東海道線が誕生した。また、京都では、京都-園部間が1899(明治32)年、京都-綾部が1910(明治43)年につながるなど、東に東海道線、西に京都鉄道(現在の山陰線)、鉄道網が急速に整備されていた時代であった。
そんななか、大遠忌では相当の参拝者が京都駅を乗降する事が予想されたため、大混乱を避けるべく、京都駅とは別に参拝者専用の駅が作られた。それが「梅小路停車場」である。梅小路にはもともと京都駅が開業するまでの間、大阪-京都間に暫定的に設けられた「大宮通仮停車場」があった。本願寺への足の便が良い事からこれを「梅小路停車場」に作り変えたとされるが、他にも様々な説がある。
停車場は1910年11月頃に起工し、線路を中間に挟んで、東行きと西行きのプラットホームがそれぞれに設置された。ホームには無数の旗を飾り、待合所の柱には紅白金巾を巻きつけるなど、乗客らを歓迎するために様々な工夫がこらされた。乗客の出迎えと見送りの際には、法話による布教や花火、楽隊の演奏などが華々しくおこなわれたという。
梅小路停車場は、大遠忌の終了をもって解体されたとされる。しかし、1913(大正2)年から「梅小路駅」として貨物取扱いの拠点となり、1990年に移転するまで各地からの貨物運搬の役割を担ったようである。
梅小路停車場がどこの場所にあったかは、大宮通塩小路付近に存在したとする書籍が出版されている。現在は、梅小路駅の跡地として「梅小路公園」が作られており、そのなかにある芝生広場付近が、梅小路停車場のあったところと解釈して間違いなさそうである。
|