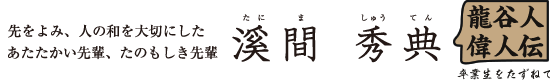「人間関係が事業の成否を決める」小林一三が託した阪急ブレーブス
阪急電鉄では車掌、運転手など様々な業務をこなし、溪間は社内でも一目置かれるような存在となった。
1960年代、北千里駅に日本で初めて自動改札機が導入されて話題になった。また、それまで個別に設けられていた上下線のプラットホームを1カ所にすることにより、駅の勤務者数のスリム化が図られた。
これら現在の鉄道のスタンダードとなる改革が実現した背景にも、溪間の努力があったという。
そんな実績が認められたのだろう、ある時小林一三が職場に訪れ、溪間にこう言った。
「君は坊主なんだろう、仏の教えを聞いたものは『人間』と言うものが、いつか判って来る、内の会社に人間だけが寄って仕事をしている宝塚歌劇団と阪急ブレーブスがある。機会がきたら、そのどちらかをやりなさい。人間関係が事業の成否を決めるものであることが、坊主である君にはきっと判かる時が来る(※5)」
それから15年後の1968年、その話は現実になり、溪間は阪急ブレーブスの球団代表に。就任当時のブレーブスは、「灰色のブレーブス」と揶揄された弱小球団を、闘将と言われた西本幸雄監督が初のリーグ優勝へと導き、常勝球団への基礎が固まってきた頃である。
溪間は、仏教者としての視点を野球に活かした。「日本一になろうと思ったら、日本一の練習(因)を積まねばならない。日本一になれたら、俺達が(我)俺達の力で日本一になったのではなく、主戦投手がケガもせず、皆んな、それぞれの力が結集して、優勝(果)が出来たのだと言う(縁)を喜び、見えざるものへの恩恵を想え(※6)」と、選手に釈尊の説かれた教えを交えて話した。ある試合で投手が完全試合を達成した時は、「本人をほめるよりバックの選手たちのおかげだよ(※7)」と語りかけた。
1973年、西本監督の跡を継いだ上田利治監督もまた、溪間と同じような事を選手に度々働きかけていた。
「自分がチームを先導して引っ張って行くのでなく、ともに試合を戦う仲間の気持ちで、ゴールまで走って行こうじゃないか」。
そんなチーム一丸の勝利は、阪急ブレーブスを3年連続日本一へと導いた。
「1時間19分の空白」は、阪急ブレーブス4連覇なるかという時に起こった出来事であり、その試合に敗れてV4は幻と消えた。
試合再開を求めるスタンドの声にも動じない上田監督を、溪間があの時、どう説得したのだろうか。どんな圧力にも屈さなかった上田監督が渓間の説得に応じたのは、二人がいかに信頼しあっていたかを物語っていると言えるだろう。
ブレーブス一筋で活躍してきた選手がトレードの危機に直面した時があった。その選手なりの野球人生を考えた結果、残留を決定し生涯ブレーブスとして引退の花道が用意された。このような事も溪間の尽力があったからと言われる。 そういった采配も、小林一三の「人間関係が事業の成否を決める」という言葉に対しての溪間自身が出した答えであったのだろう。
 |
 |
球団社長の職責を終えた後、溪間は自坊の職務を全うしつつ、ボーイスカウト大阪連盟副コミッショナーとして、民生委員保護司を務め、青年の育成に奔走した。
|
「お念仏だけが子孫へと伝え残す唯一の財産」
住職としては「人々の中に入って、人々と共に」が信条の溪間。「社会の荒波にもまれてこそ、はじめて人間ができあがり、真の伝道者たりうる」というメッセージを残している。
「私にとって野球は『青年大衆と仏道』を結びつける方法としてであったのである。事実、法座に呼ばれて、野球を例話に引くと若い人が興味をもって仏教を理解してくれたことがどんなに多かったことか(※8)」と溪間は自らをこう振り返っている。
溪間自身が激しい社会の荒波の中で、堂々と逞しく活躍してきた経験は、地位や名声を得るためでもなく、手柄をひけらかすためでもない。仏道を実践し、真の伝道者になるための道のりであったのかもしれない。
1989年7月1日、溪間は闘病の後、68歳の生涯を閉じた。
同人雑誌『仏と人』の中で溪間は最後、こんな文章を残している。
「土地も、金も、地位も、名誉もすべて百年の後にあとかたも無くなってゆくに違いありません。お念仏だけが、子孫に伝え残して行ける人間の唯一の財産なのでしょう」。
※2〜8 無名会同人編集『渓間秀典師を偲ぶ 「仏と人」特別号』(永田文晶堂)より |