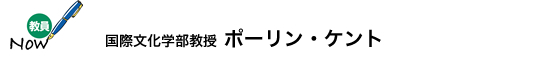真の国際化は
文化的背景の理解から
国際文化学部で外国人から見た日本の文化、日本社会の学説史を教えるケント教授。なかでも『菊と刀』の著者であるルース・ベネディクトの研究は、ライフワークとも言えるものだ。戦時中、アメリカの情報局が日本人を知るためにベネディクトに調査研究させた資料をもとに、ベネディクト自らが書き上げたのが『菊と刀』である。日本の文化は恥を基調とし、菊の優美を愛すると同時に刀を崇拝するという2面性を持つ とされ、日本では今日もなお読み継がれるベストセラーとなっている。
ケント教授とルース・ベネディクトの出会いは千葉大学3年生のとき。担当教授に『菊と刀』を紹介され、日本と西洋の罪と恥の文化の比較をおこない卒論にまとめたことに始まる。国際日本文化研究センター勤務時代、アメリカのヴァッサー大学でベネディクトが残した資料に触れたことで、ますますその人物像に惹かれていく。
戦時中のアメリカでは、敵国である日本についての知識が乏しく、日本人をサル、害虫などと言っていたという。ベネディクトはそんな偏見や人種差別と闘いながら、日本人を人間として正しく理解しようとした。
「自分達が何気なくやっている行為も、ほかの民族や国から見ればおかしなことである場合があります。人間の行動は、文化的な背景によって異なる。真の国際化は、それを理解することから始まります」。

外国人と身近に接する
国際文化学部の役割は重要
『菊と刀』が世に出てから60年余り。世界は国際化が急速に進展し、ますますお互いの民族や固有の文化を理解し尊重しなければならない時代を迎えている。しかし、「日本は政治も企業もマスコミも、そして多くの大学も、まだまだ国際化されているとは言えません」とケント教授。
その一例として、「少し前にニュースになったインドネシア人の介護福祉士の受け入れにしても、彼女達の給料や待遇などの保証は曖昧なままです。しかも、3年後には日本人でも難しい国家試験を、日本語で受けさせようとしている。本当にそれでいいのか、それで問題は解決するのか疑問です」。
そのうえで、「日本は、国内にあるコンフリクト(葛藤、紛争など)をどう解決するかについて深く考えていない。日本人は紛争をきらい、コンセンサスを求めて裏で根回ししながら提案するという、曖昧なやり方を通してきました。グローバル化を考えれば、問題点をもっと明確にしていかないと世界で通用しないし、国境を越えて活躍する人材も育ちません」と厳しく指摘する。
この差し迫る重要課題に、龍谷大学はどう対処するべきなのだろう。すると、ケント教授は表情を和らげ、龍谷大学の国際文化学部は、専任教員の40%が外国人であることを評価する。オーストラリア人、アメリカ人、中国人、韓国人など多彩な顔ぶれの教員とふれ合うことで、学生達は外国人との接し方を学び、自分達に大切なのは相手がどこの国の人間かではなく、同じ人間として接することだと気づく。箱ではなく、中身を見ることの訓練をする。「国際化社会における人材を育成するという観点において、龍谷大学の国際文化学部が果たす役割は重要です」と語気を強め、さらに、実際に学生を教える立場から、こう語った。
「社会を変える原動力となるのは若い大学生。ポテンシャルのある若い人々が集まる大学がエキサイティングでなければいけません。外国人の教員と学生が一体となって様々なテーマについて考える。面白いと思いながら取り組めば頭が働く、いろいろ思考をめぐらし、次へ次へというパワーも生まれる。考えることこそ勉強。それが国際化を進めていく。龍谷大学がその見本を示す大学となるよう、私も努力したい」。
アフラシアの研究が
教育現場に刺激を与える
ケント教授はまた、多文化共生を前提にした龍谷大学アフラシア平和開発研究センターのセンター長も務めている。ここでは、例えば紛争というものを広くとらえ、戦争は紛争が武力的にエスカレートした結果だが、そうならないために、戦争へと向かうプロセスを断ち切り、回避することをめざしている。
したがって、目の前の問題はとことん明確化する。そうでないと正しい解決に導けない。問題を把握し、問題が起こる根源となる人々の声を聞く。対象となる国家および文化を理解し、底辺から問題解決を探る。上からの提案ではなく、問題となるピンポイントをしっかりと見つめるのだ。
センター設立から5年目の今年は、その活動の最終年にあたるが、あと3年間研究を継続したいと文部科学省に申請する準備を進めている。「国家と和解」の研究を続け、他の国を参考にしながら日本における最善の「移民政策」の方策を考え、解決の基本となる言語による「コミュニケーション」についても研究して行く予定だ。
「このような研究を進めることによって、教員が教える内容も一層深まる。教育現場で、教員と学生がお互いに刺激し合うという相乗効果が生まれます」。龍谷大学は面白い大学だと繰り返すケント教授。国際化を見据え「これからが楽しみ」と、満面の笑みが広がった。 |