 |
 |
センセーショナルなキャッチコピーを掲げて、加藤和彦氏が知的な表情を浮かべている。このウィットに富んだポスターは、本学を中退後、日本の音楽界の第一線を走り続けてきた加藤氏が、「面白い企画だ」と賛同してくれたことで実現した。受験シーズンを狙って1995年の1月から2月にかけて、首都圏を中心に主要都市で駅貼り広告がおこなわれるとたちまち脚光を浴び、メディアにも取り上げられた。
加藤氏はポスター制作時、「大学でほかに役立つことがありましたら、いつでも僕を使ってください」と、大学関係者に話していたという。しかし、2009年10月17日、加藤氏の突然の訃報により、ご本人から協力を直接得ることはできなくなってしまった。「帰って来たヨッパライ」「あの素晴しい愛をもう一度」「タイムマシンにおねがい」など数々の名曲は、私達の胸に深く刻まれ続けることだろう。
彼の人となりはどうであったか、「ザ・フォーク・クルセダーズ」設立メンバーの一人、平沼義男氏の話を交えて、振り返る。
|
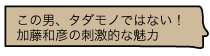 |
|
「加藤tさんは身長が高くてお洒落で、カッコ良かった」。
すらっとした長身の体にアイビールックがキマっていた。名前しか聞いたことのない英文のフォークソング専門誌に、フォークソングファン憧れのバンジョーと12弦ギター。母親は当時では珍しかったジーンズを履きこなし、ニコニコしながら、「焼きたてのクッキーはいかが」「カルボナーラ、ぺペロンチーノをどうぞ」と、スパゲティならぬ得体のしれないパスタ料理をすすめてくる、この人、タダモノではないぞ…。
若者のバイブル誌『MEN'S CLUB』1965年9月号の読者欄。「フォーク・コーラスを作ろう。当方、バンジョーと12弦ギター有り。フォークの好きな方連絡待つ」という加藤の投稿に集まった、京都府立医科大学2年生の北山修、浪人生の井村幹生、芦田雅喜。そして高校3年生の平沼義男は、同じ60年代の日本に住んでいるとは到底思えないような、ハイセンスな加藤家に度肝を抜かれた。強烈で、ゾクゾクするほど刺激的だった。その場で、グループ結成が決まり、加藤はアメリカのグループ「ジャズ・クルセイダーズ」から名前を取って「ザ・フォーク・クルセダーズ」とした。井村、芦田は受験のためすぐに脱退し、三人で活動を続けることになった。
加藤はもの静かで、プライベートな話はほとんどしなかったという。練習以外の目的で集まることもなく、メンバー同士、友達付き合いはないクールでストイックな関係。「週2回ほど練習で集まって、それ以外の日は個人練習に没頭しました。指から血が出るくらい、死に物狂いで練習しましたよ」。平沼は当時をこう振り返る。模範となる映像もコード表もない時代だ。レコードから流れる音だけを頼りに、弾き方を必死にたどった。加藤のギター能力は抜きん出ていて、難しい曲もすぐに自分のものにしていたという。
2年ほどが経ち、外国曲のコピーに飽きた彼らは、様々なジャンルの音楽を取り入れて、アレンジソングやオリジナルソングにチャレンジするようになる。メンバー全員がお笑い好きとあって、音楽に笑いの要素も加わった。北山が話芸で盛り上げ、ユニークなパフォーマンスで沸かせるスタイルからいつしか「笑いのフォークル」と呼ばれ、学生主催のコンサートには引っ張りだこだった。
加藤は音楽には厳しかった。演奏中、平沼がコードをうっかり間違えると、加藤からジロリと、冷ややかな視線が飛んだ。しかし、怒ってもその時だけ。後を引くことはなく、普段の加藤はいつもニコニコと、穏やかだった。
|
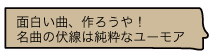 |
|
ある時、加藤が一人の男を連れてきた。河原町をぶらぶらしていたら、たまたま出会って、意気投合。面白いから連れて帰ってきたのだと言う。その男は松山猛と名乗った。楽器はからきしだめだが、博学で話が面白い。練習に参加するともなく、なんとなく一緒にいると、ある日「こんなん書いてきたけど…」と歌詞を持ってきた。
「面白い!やろうや」。早速、加藤が曲作りにかかった。加藤は当時から作曲、編曲にもずば抜けた独自のセンスを持っていた。あらゆるジャンルの音楽に精通し、実験的な奏法や録音技術を熱心に研究していた。松山のユニークな歌詞をどう面白くアレンジするか。考えるうちに、テープを早回しするというアイデアが浮かんだ。
そして生まれたのが「帰って来たヨッパライ」である。偶然というよりも、加藤の研究の積み重ねから生まれたものだった。「プロをめざしているわけでなく、仲間と歌っていれば楽しいなという動機」と加藤が後に語っているように、その努力は、もっぱら遊びを目的としていた。実際に加藤は大学卒業後、コックになることを具体的に考えていたという。ほかのメンバーも同様に、平沼は家業を継ぐ、北山は精神科医の道に進むと決めていた。プロになる気持ちは毛頭なく、ただ純粋に面白いこと、楽しいことを音楽に詰め込んで、青春を謳歌していただけだったのだ。
「上手とか感動したとか、そういうコメントはいらなかった。売ってやろうという気持ちもない。ただ、聞いてて面白い。皆も面白がるだろう、という思いだけだった」(平沼)。
|
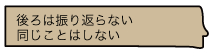 |
|
そんなフォークルに大きな転機が訪れたのは、それぞれの将来に向けて解散の準備を進めていた時のことだ。解散の記念にと、「帰って来たヨッパライ」「イムジン河」など今まで歌ってきた曲を収録し、アルバム「ハレンチ」を250枚作った。制作費の30万円は、音楽をやめて堅気になるという約束を交わして、北山の父親から借りた。レコードも作って、解散コンサートも華々しくおこなって、何も思い残すことはなかった。
ところが困ったことに、レコードが全く売れなかった。制作費の30万円すら回収できず、三人は売り込みに奔走した。父親に大きな借りがある北山は特に必死になって、あらゆるラジオ局に曲を持ち込み、マネージャー的役回りをこなした。
そんな必死の売り込みが運命を変えた。「帰って来たヨッパライ」がラジオ関西の女性ディレクターの目に留まり、ラジオで流れた。途端に、ラジオ関西始まって以来、電話回線がパンクした。リクエストが殺到したためだ。
フォークルは、一瞬にして有名になった。日本中のレコード会社から、プロデビューの話を持ちかけられた。平沼は、「解散ときっぱり決めていたから、気持ちも離れていた」と、申し出を受ける気は毛頭なかったという。
加藤も最初は拒んでいた。コックとして就職先も決まりかけていたからだ。しかし、北山の再三の説得についに折れ、龍谷大学経済学部を中退する。そして、平沼に代わり、はしだのりひこが加わり、1年間という期限付きでデビューを決めた。契約先に東芝音楽工業(その後の東芝EMI)を選んだのは、加藤が愛してやまなかった「ビートルズ」が東芝と契約を結んでいたためである。
そうしてプロとしてスタートを切った「ザ・フォーク・クルセダーズ」は、「帰って来たヨッパライ」で、280万枚という大ヒットを飛ばし、日本初のミリオンセラーに輝いた。作詞、作曲からジャケットのデザインまで、加藤を中心とした自作自演のスタイルは、作曲家が手がけた曲を歌手が歌うという従来の音楽界の通例をぶち破り、シンガーソングライターという存在を世に知らしめた。
「ザ・フォーク・クルセダーズ」解散後も、加藤の才能は進化し続けた。名曲「あの素晴しい愛をもう一度」、「サディスティック・ミカ・バンド」、スーパー歌舞伎、ゲームソフト、映画など幅広く音楽を手がけ、作曲家として、またプロデューサーとして手腕を発揮した。
「後ろは振り返らない。同じことはしない」が、加藤のモットーだったという。寡黙で音楽に厳しく、過去の栄光に縛られることはなかった。常に厳しいまなざしで自分を見つめ、前へ前へと進んできた。スタイルは変えずに、自分に厳しく、独自の道を歩み、孤高の人で、先駆者で、どこまでもカッコ良い。そんな加藤の人物像が浮かび上がる。 |
| |