 |
| *値段は全て税込価格で表示 |
 |
 |
『日本企業の国際フランチャイジング
ー新興市場戦略としての可能性と課題ー』 |
| 川端 基夫(元経営学部教授・現非常勤講師)著 |
| 近年コンビニや外食店の国際化が進展しているが、その多くはフランチャイズという手法による進出である。高齢化や人口減少で国内市場の縮小が深刻化し、海外市場の開拓が急務となる昨今、日本企業の海外市場戦略はどうあるべきか。本書は、この問題を国際フランチャイジングの視点から分析した、我が国初の研究書である。 |
| 2010年2月刊/274頁/新評論/2625円 |
|
| |
 |
『中高生の社会化とネットワーク
ー計量社会学からのアプローチー』 |
| 工藤 保則(社会学部准教授)著 |
| 本書は、青年期前期・中期にあたる中学生・高校生という存在を、社会化という観点から社会学的に位置づけることを試みたものである。五つの質問紙調査のデータから考察を進めた結果、中学生と高校生は地域特性の影響を他者を通して受けながら、生活する地域のなかで「生徒としての社会化」をはかっていることが捉えられた。 |
| 2010年2月刊/206頁/ミネルヴァ書房/5250円 |
|
| |
 |
『近代イラン知識人の系譜
ータキーザーデ・その生涯とナショナリズムー』 |
| 佐野 東生(国際文化学部准教授)著 |
| 今世紀に台頭著しいアジア・アフリカ地域。その結節点というべき中東にあって、反米かつイスラーム体制のイランは異彩を放つ。その底には19世紀以来のナショナリズムの潮流があるが、イランという特殊な場は時にそれを激流と化さしめた。その渦中にあって、知識人タキーザーデが近代の「国生み」に向けいかなる舵取りをしたか。 |
| 2010年2月刊/383頁/ミネルヴァ書房/3990円 |
|
| |
 |
『木の文化の形成
ー日本の山野利用と木器の文化ー』 |
| 須藤 護(国際文化学部教授)著 |
| 「木の文化」は、大筋において日本の基層文化を言いあてている。それを体系的に、また具体的に裏付けてみたいというのが、大それたテーマに挑戦するきっかけであった。この国には、常民層が接してきた、山野に対する知恵と知識の分厚い蓄積があり、それを文化にまで高めていった事実がある。その事実をこの書の柱にした。 |
| 2010年2月刊/379頁/未來社/7140円 |
|
| |
 |
『通行権裁判の現代的課題』 |
| 岡本 詔治(法科大学院教授)著 |
| わが国の通行権に関する民事裁判を総合的に研究したものである。通路敷と沿道地の所有権は、多数集合して通行使用目的のもとに集団的な利用秩序を形成しているので、そこに私的所有を超えた公共的な空間が存在しているという視点(「地縁秩序」論)を析出したうえで、近時の注目すべき一連の最高裁・下級審判決を統一的・整合的に分析した。 |
| 2010年2月刊/425頁/信山社/10290円 |
|
| |
 |
 |
龍谷大学仏教文化研究叢書26 |
| 『仏教とカウンセリング』 |
| 友久 久雄(文学部教授・特任)編 |
| 本書は、本学の仏教文化研究所附属「仏教とカウンセリング研究センター」における、過去2年間の研究成果をまとめたものである。その内容は、宗教や心理学は何ができるかという問題を、仏教とカウンセリングの接点から検討したものであり、現代の悩める人々への対応を考える際に参考となる数少ない研究書である。 |
| 2010年3月刊/288頁/法藏館/3675円 |
|
| |
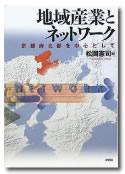 |
龍谷大学社会科学研究所叢書第85巻 |
『地域産業とネットワーク
ー京都府北部を中心としてー』 |
| 松岡 憲司(経済学部教授)編 |
| 今日の私達の生活はネットワークに支えられている。わたしたちは、人と人とのつながり、企業と企業の取引など、様々なネットワークの中にいる。本書は、伝統的産業から現代のものづくり、さらに交通、観光まで京都府北部の様々な産業を、ネットワークという視点から捉えてみようとしたものである。 |
| 2010年3月刊/262頁/新評論/2940円 |
|
| |
 |
龍谷大学社会科学研究所叢書第85巻 |
『アジアICT企業の競争力
ーICT人材の形成と国際移動ー』 |
| 夏目 啓二(経営学部教授) 編著、細川 孝(経営学部教授)ほか 共著 |
| 今日、中国、台湾、韓国、インドのアジア諸国・地域は、世界の工場、世界の市場として発展を続ける。本書は、アジアのICT産業の発展を支える重要な要因として、ICT人材の形成とその国際移動に注目する。ICT人材というヒトの育成とその国際的な移動の実態を捉え、アジア諸国・地域がグローバルな産業構造にいかなる影響を及ぼすのか、を探求している。 |
| 2010年3月刊/258頁/ミネルヴァ書房/3150円 |
|
| |
 |
龍谷大学社会科学研究所叢書第87巻 |
| 『包摂と排除の比較政治学』 |
| 高橋 進(法学部教授)編著、石田 徹(法学部教授)ほか 共著 |
| 本書は、日米欧の先進社会において、社会の解体を招きかねないほど先鋭化している多次元的な「社会的排除」を歴史的・構造的に分析し、あるべき「社会的包摂」の道を検討した共同研究の成果である。社会モデルに焦点を当て、「排除」の克服の方途を探り、新しい社会モデルの再構築に向けて、比較政治学的な考察を展開している。 |
| 2010年3月刊/231頁/ミネルヴァ書房/3675円 |
|
| |
 |
龍谷大学西域研究叢書5 |
| 『旅順博物館所蔵新疆出土漢文浄土教写本集成』 |
旅順博物館・ 龍谷大学西域文化研究会
三谷 真澄(国際文化学部准教授)ほか 共編 |
| 中国旅順博物館が所蔵する大谷探検隊収集の約26,000点の漢字断片から、浄土教典籍のみを抜粋し、全166点の図版・録文を解説・一覧表を付して刊行したもの。20世紀初頭に同定された断片(81点)は「浄土一」と題する藍冊に整理されているが、共同研究で新たに判明した断片を加え、「浄土一補完版」または「浄土二」の集成をめざした。 |
| 2010年3月刊/141頁/龍谷大学西域文化研究会/非売品 |
|
| |
 |
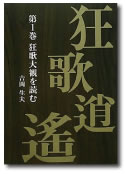 |
『狂歌逍遙 第1巻 狂歌大観を読む』 |
| 吉岡 生夫(1974年文学部卒業・歌人・兵庫県)著 |
| 5句31音詩という概念を導入し、日本語の歴史を重ねることによって歌の歴史に新たな視座を開いた本書は、狂歌を鑑賞し、また歌の明日を示唆する。 |
| 2010年3月刊/448頁/ブイツーソリューション/3150円 |
|
| |
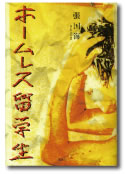 |
『ホームレス留学生』 |
| 張国海(2008年法学部卒業・会社員・奈良県)著 |
| 中国人の若者が借金をして来日。バイトをしつつ公園に寝泊まりしながら、生活費と学費を捻出し100万円貯め返済。龍谷大学入学、卒業…そして就職。 |
| 2010年3月刊/174頁/風詠社/1260円 |
|
| |
 |
『土地を奪われゆく農民たち
ー中国農村における官民の闘い』(王 国林著) |
| 中田和宏(2005年大学院文学研究科博士課程修了・高校教諭・大阪府)、 田村俊郎(2005年大学院文学研究科博士課程修了・高校非常勤講師・京都府)共訳 谷川道雄(元龍谷大学文学部教授)監訳 |
| 工業化と都市化が進む中国、土地収用問題を通して官と闘う農民の姿を鮮明に描いた、著者の実地調査に基づく記録。現代中国理解の一助となる1冊。 |
| 2010年2月刊/592頁/河合文化教育研究所/5040円 |
|
| |
 |
『福井の山と川と海と原発』 |
| 山崎 隆敏(1971年経済学部卒業・和紙会社経営・福井県)著 |
| 20年前の2冊の著書の総集編。福井県のダム・林道や全総など開発の歴史を総括。原発による地域振興の検証と脱原発の現実的可能性についても論及。 |
| 2010年7月刊/284頁/八月書館/1785円 |
|
| |
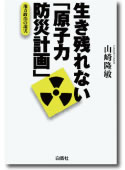 |
『生き残れない「原子力防災計画」
ー地方政治の現実ー』 |
| 山崎 隆敏(1971年経済学部卒業・和紙会社経営・福井県)著 |
| チェルノブイリの訪問ルポをもとに「福井県原子力防災計画」を検証。12年間の地方議員経験をもとに、形骸化した議会の具体的改革案についても提唱。 |
| 2010年7月刊/250頁/白馬社/1575円 |
|
| |
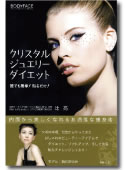 |
『クリスタルジュエリーダイエット』 |
| 辻 亮(2000年経営学部卒業・経営コンサルタント・大阪府)著 |
| ツボの本場、台湾からやってきた、クリスタルジュエリーを使用した、内面から美しくなれるお洒落な痩身術。ダイエット・リフトアップ・快眠を図る。 |
| 2009年12月刊/171頁/白誠書房/1470円 |
|
| |
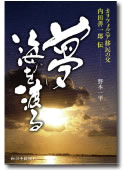 |
『夢 海を渡る
ーカリフォルニア移民の父・内田善一郎伝ー』 |
| 野本 一平(1955年文学部卒業・会社役員・米国:カリフォルニア州フレズノ)著 |
| 北米への多くの日本人移民のなかでも、特に「カリフォルニア移民の父」と呼ばれる「内田善一郎」についての詳細とその背景をしるす。 |
| 2008年3月刊/168頁/南日本新聞社/1470円 |
|
| |
 |
『後生の一大事 ー蓮如上人和歌評釈ー』 |
| 中本 保三(1971年文学部卒業・兵庫県)著 |
| 蓮如上人の和歌を300余首とりあげ、各歌の出典・詠作時期・語釈・詠作場所・鑑賞に分けて丁寧に評釈したもので、著者のライフワークの成果である。 |
| 2010年3月刊/172頁/西村印刷/非売品 |
|
| |
 |
『清輔雑談集』翻刻 |
| 藤田駒代・亀井久美子・北田真喜子・作山紀子・佐竹三郎・澤葉克己・中屋善策・ 水谷俊信・宮原真貴子(2009年文学部卒業)共翻刻、大取一馬(文学部教授)監修 |
| 本書は和歌説話を集めた『清輔雑談集』の全文を初めて翻刻したものである。翻刻者は2009年度、本学社会人の日本語日本文学演習の受講生9名。 |
| 2010年3月刊/158頁/學林舎/非売品 |
|
| |
 |
| |
| 『グリムのメルヒェンと明治期教育学』 |
| 中山 淳子(名誉教授)著 |
| グリムのメルヒェンが「童話」に矮小化されたのは、明治の御雇教師によるヘルバート学派の『第一学年』が原因と指摘。童話への可否の影響を実証した。 |
2009年4月刊/450頁/
臨川書店/8400円 |
| |
|
『「うつ」からの回復:
新しい心理社会療法』 |
| 黒川 昭登(名誉教授)著 |
| 学校でも職場でもまともにやっているにもかかわらず、自分はダメだ、ときびしい人が「うつ」になる。本書は、自分にやさしくなる方法を説く。 |
2010年5月刊/223頁/
金剛出版社/2730円 |
|
| |
『わかりやすい福祉支援の記録
ー個と環境との相互作用の視点からー』 |
| 栗田 修司(社会学部教授)著 |
| 豊かな生活の実現を念頭に、記録について研究した成果である。著者が関わった支援やスーパービジョン、研修、授業で得た知見も活用している。 |
2010年3月刊/140頁/
相川書房/1680円 |
|
| 『総図解 よくわかる古代史』 |
| 平林 章仁(文学部教授)共著 |
| 日本古代史の重要な問題について、写真・図・イラストなどを付して、わかりやすく解説したもの。 |
2010年3月刊/282頁/
新人物往来社/1470円 |
|
| |
『古代豪族の謎 「古事記」
「日本書紀」 から読み解く』 |
| 平林 章仁(文学部教授)共著 |
| 日本の古代国家形成に大きな役割をはたした有力豪族について、『古事記』『日本書紀』を通してその実像解明をめざして、関連問題について論じた。 |
2010年4月刊/318頁/
新人物往来社/700円 |
|
| 『なぜ人は市場に踊らされるのか?』 |
| 竹中 正治(経済学部教授)著 |
| なぜマネーゲームは暴走するのか?元大手銀行のチーフディーラーでエコノミストかつ大学教授の著者が、自身の体験と経済学の知見を交差させながら読み解く。 |
2010年2月刊/243頁/
日本経済新聞出版社/1575円 |
|
| |
| 『聖なるもの』(R・オットー著) |
| 久松 英二(国際文化学部教授)翻訳 |
| 宗教を「聖なるもの」の非合理的体験(ヌミノーゼ)として捉え、現象学的・宗教哲学的に考察を展開した、20世紀を代表する宗教学の基礎的名著。 |
2010年2月刊/465頁/
岩波書店/1197円 |
|
『開発の社会史
ー東南アジアにみるジェンダー・
マイノリティ・境域の動態』 |
| 加藤 剛(社会学部教授)共編 |
| 島嶼部東南アジアの3カ国に見る開発現象について、副題が示す3種の周縁世界に焦点を当て、各国の開発政策史の担当を含む12人の執筆陣が寄稿。 |
| 2010年3月刊/540頁/ 風響社/6300円 |
|
| |
| 『ドイツ保守革命』 |
| 國重 裕(経営学部准教授)共著 |
| ナチスの先駆とされるドイツ保守革命の思想を、4人の作家・哲学者の言説から分析する。ドイツ・ナショナリズムの多様性が浮き彫りになる。 |
2010年2月刊/256頁/
松籟社/3360円 |
|
| 『有機EL技術と材料開発』 |
| 木村 睦(理工学部教授)共著 |
| 電子ディスプレイと照明として最近の発展が目覚ましい、有機EL技術の概説。著者は特に、高機能ディスプレイに必要なトランジスタ駆動を説明する。 |
2010年5月刊/279頁/
シーエムシー出版/4410円 |
|
| |
『認知と社会の語用論:
統合的アプローチを求めて』 |
| (ジェフ・ヴァーシューレン著) |
| ジェフ・ヴァーシューレン教授により書かれた、語用論研究の総合的アプローチの全訳。ヨーロッパの語用論の歴史的発展、認知言語学にも言及したもの。 |
2010年6月刊/427頁/
ひつじ書房/3675円 |
|
『質的調査の方法
ー都市・文化・メディアの感じ方』 |
| 工藤 保則(社会学部准教授)共編 |
| 「社会調査士」資格取得科目の、「質的な分析の方法に関する科目」に対応したテキストである。また、文化やメディアを学ぶ際のガイドにもなっている。 |
2010年2月刊/157頁/
法律文化社/2520円 |
|
| |
| 『子どもと地域社会』 |
| 工藤 保則(社会学部准教授)共著 |
| 「子どもの発達過程において地域社会はどのような意味を持っているのか」を考察する本書の中で、「中学生の社会化」を地域の中で捉えようとした。 |
2010年5月刊/181頁/
学文社/2100円 |
|
| 『アクチュアル行政法』 |
| 本多 滝夫(法科大学院教授)共著 |
| 行政権の民主主義的な法的制御の方法・手段を、体系的に説明した教科書。行政活動の適法性要件をリスト化している点に特長がある。 |
2010年4月刊/337頁/
法律文化社/3150円 |
|
| |
| 『概説国際物品売買条約』 |
| 中田 邦博(法科大学院教授)共編 |
| 本書は、昨年施行された国際物品売買条約(CISG)の概説書である。近時の債権法の改正にも影響を与える、同条約の内容を知るのに適切な文献となろう。 |
2010年6月刊/211頁/
法律文化社/3990円 |
|
『EUの言語教育政策
ー日本の外国語教育への示唆ー』 |
| 脇田 博文(国際文化学部教授)共編著 |
| 多様の中の統合をめざすEUにとって言語教育は重要な役割を果たす。本書は、21カ国の言語教育政策を概説し、日本の外国語教育の示唆とする。 |
| 2010年5月刊/321頁/ くろしお出版/3990円 |
|
| |
| 『新キリスト教保育指針』 |
| 児玉 衣子(短期大学部教授)共著 |
| ナチスの先駆とされるドイツ保守革命の思想を、4人の作家・哲学者の言説から分析する。ドイツ・ナショナリズムの多様性が浮き彫りになる。 |
2010年7月刊/105頁/
キリスト教保育連盟/1200円 |
|
| 『先端医療の社会学』 |
| 黒田 浩一郎(社会学部教授)共編 |
| 近代医療の1970年頃から今日にかけての「先端的」ともいうべき展開を捉える、社会学的な定義と視点を提示し、脳死・臓器移植などの展開を分析する。 |
2010年7月刊/229頁/
世界思想社/2100円 |
|
| |
[仏の来た道2003
ーシルクロード文物と現代科学]』 |
| 入澤 崇(文学部教授)編、三谷 真澄(国際文化学部准教授)ほか 共著 |
| 2003年に、大谷探検隊派遣100周年を記念して、本学で開催された同名シンポジウムの報告論文集。2編の基調講演と25編の学術論文から成る。 |
2010年2月刊/269頁/
東方出版/8400円 |
|
『十八世紀 イギリス文学研究
第4号』 |
| 福本 宰之(文学部教授)共著 |
| 全体は3部構成で、大まかにそれぞれのキーワードを並べると、異文化、言葉、舞台ということになろう。18世紀英文学の研究者には必読の書。 |
2010年5月刊/433頁/
開拓社/5460円 |
|
| |
| 『ソーシャルワークを支える宗教の視点』 |
| 西川 淑子(社会学部准教授)共訳 |
| オバマ大統領にも影響を与えたという、「平静の祈り」で有名なニーバーが、宗教による社会福祉への貢献について歴史的に考察している。 |
2010年2月刊/214頁/
聖学院大学出版会/2100円 |
|
|