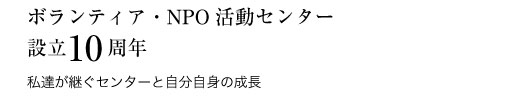 |
| |
 |
(右から)
よこぜき
横関 つかささん
法学部3年 大阪学芸高等学校出身
たけもと まり
竹本 真梨さん
法学部3年 城ノ内高等学校出身
いわお あやの
嵒 彩乃さん
社会学部3年 高槻北高等学校出身
たかだ やすと
高田 靖人さん
社会学部4年 履正社高等学校出身 |
| |
ボランティア・NPO活動センターが設立された2001年は、くしくも日本が提案して国連で決議された"世界ボランティア年〟でもある。センターでは学生へのボランティア紹介や講座・イベントの実施、NPO・NGOとの協働などをおこなっている。学生スタッフが約100名と多く、教職員と同じ視点で協働・運営しているところが特徴である。そんなセンターの運営に携っている学生達に話を聞いた。 |
| |
今までと違う
新しい生活が待っている |
彼らがセンターの学生スタッフとなったきっかけは何だろう。瀬田キャンパス代表を務めた高田靖人さんは、「もともとボランティアに興味があったわけではなかった。出会った先輩達が活き活きしていて何か普通の大学生と違う視点を持っているように見えて魅力的だった。参加することで、今までとは違う新しい生活が待っている気がしたんです」と語る。
副代表の嵒彩乃さんは「臨床福祉学科の実習前に経験を積んでおきたかったから」。深草キャンパス代表の横関つかささんは「友達からセンターのお花見に誘われて。その場で何か楽しいことがありそうだなと、ぴんときたんです」と微笑む。副代表の竹本真梨さんは「高校時代はバドミントン一筋だったので、大学では今までとは違うことがしたかった」と、各々がそれぞれのきっかけを振り返ってくれた。 |
| |
〝気づき〟を境に自分が変わる。
変化こそ、やりがい。 |
学生スタッフはセンターで、ボランティア希望の学生に対して、様々なボランティア活動の紹介をおこなうほか、講演会や体験イベントなどを企画して、福祉・国際・環境・地域貢献など、多様なテーマの問題を考える機会をつくっている。
それらの活動のやりがいについて聞くと、竹本さんはしばらく考えた後「気づくことかな」と切り出した。「あるとき、野宿者支援に携わることがあったんです。私はそれまで、そうした生活があることをほとんど知らなかった」。野宿者支援活動では、京都市伏見区の河川を回り、食料品や入浴券、冬はカイロ、夏は蚊取り線香などを届ける。ひっそりと暮らす野宿者達と会話してみて初めてわかることが多くある。
横関さんが頷いて続ける。「社会的な問題について、自分の目に見えてなかったものを、切り捨てることができなくなりました」。
横関さんが視野を広げるきっかけになったのは、フェアトレードについての講演会を企画したときだ。発展途上国の製品を適正な価格で購入することで自立と発展を促す、フェアトレードの取り組みに触れ、途上国の貧困を知った。自分の世界がいかに狭かったか、そして知らない世界を知らないままにしてはいけないことを痛感したという。
「例えばテレビで火事のニュースを見ても、自分には関係のないことだと見過ごしてしまいますよね。でも、隣の家が燃えていたら他人事ではいられない。ボランティアに参加すると、たとえ何万キロ離れた国で起こっている問題でも、自分の居場所と地続きの問題だと実感できるんです」キーワードは〝当事者意識〟だと話す。
高校時代までは引っ込み思案で人前で話すことなど考えられなかったという嵒さんは、センターの活動を通して性格が明るくなったという。「高校時代の友人には『別人みたい。昔はそんなに自分の意見を言える子じゃなかった』と言われます。でも、ボランティアを通じて社会の現実を目の当たりにすると、否応無しに〝自分の意見〟を持たざるを得ません。そしてその現実をたくさんの人に知ってもらいたいと感じるのは、当然のことなんです」。ボランティアを通して自分が変わっていく実感があった。 |
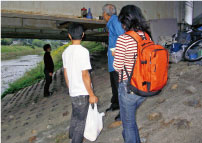 |
2009年からNPO法人JIPPOと協力して
おこなっている「伏見区野宿者支援プロジェクト」 |
| |
|
| |
形ある行動と、
形のない対価。 |
センターの活動に参加したばかりの頃は、偽善者だと思われる気がして、友人達に『ボランティアをやっている』となかなか言えなかったという高田さん。しかし、現在ではそうした気持ちは完全に晴れた。
「活動に参加していくうちに、ボランティアは与えることではなく、見識や経験、能力など自分自身を成長させてくれるものだと確信できました。対価がお金ではないだけ。力を貸す側も借りる側も対等なんです」。
また横関さんはこう話す。「センターの取り組みは、建学の精神と重なる部分も多いと感じるんです」。参加するうち、それを実感するようになったという。
「私も誰しも、完璧な人間なんていません。でも自分ができることがあるのならできる範囲でいいから補い合えばいいと思うんです」。 |
 |
 |
大津市の丸屋町夜市に参加。屋台運営や、商店街を
取材したパネル展などを実施した。(2010年8月) |
体験ボランティア「森にふれあい森に学ぶ」
(2010年8月) |
| |
魅力ある組織づくり。
もっと身近なボランティアへ |
センターの未来について話題が移ると、全員が声を揃えて「もっとセンターの活動を広めていきたい!」と目を輝かせた。
「そのためには、学生の社会参加がもっと自然になればいいなと思っています」と嵒さん。
竹本さんが続ける。「学外の利用者さんはもちろん、学内の学生がどんなボランティアを望んでいるのかについても、しっかりニーズを汲み取って運営に反映したい。『参加したい』と思ってもらえる組織づくりが大事。そう思ってもらえれば、自然と人が集まってくれるはずですから」。
設立から10年を経て、現在では約100名の学生スタッフが自発的に集まる。そして学生は運営にも主体的に携わる。同センターが築いてきた絆は着実に強くなっている。 |
| |
| 《ボランティア・NPO活動センター10年の歩み》 |
・1997年10月 教員有志によりセンター設置を提案
・2001年 4月 センター設置
・2001年10月 深草センター開設(紫光館1階)
・2003年10月 瀬田センター開設(青志館2階)
・2010年センター 設立10周年 |
| |
| ボランティア・NPO活動センター10周年事業 |
記念祝賀会
センターの関係団体や学内などの
関係者をお招きし、祝賀会を開催 |
記念講演会
テレビジャーナリストの水島宏明氏のご講演
(テーマ「今、自分が社会に対して出来ること」) |

祝賀会で、学生スタッフの突撃インタビューに答える水島氏
(2010年12月) |

(2010年12月) |
|