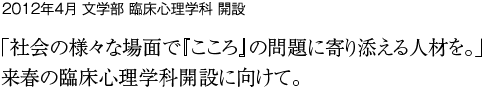 |
| |
 |
| �Տ��S�����k���u��l�Ǝq�ǂ��̂�����̃N���j�b�N�v�i2004�N�J�݁j |
| �N�ł����p�i�L���j�ł��邱����̑��k����.�Տ��S���m���߂�����w�@���̎��K�{�݂ɂ��Ȃ��Ă���B7�N�Ԃ̑��k��6,600������B |
| |
�@�Q�O�P�Q�N�S���A���w���ɗՏ��S���w�ȁA��w�@���w�����ȂɗՏ��S���w��U���J�݂����B
�@����܂ł̑�w�@�ł̗Տ��S���w�̈������ɔ��W�����A�ߔN�A�Љ�I�v���̍����ΐl�����̃X�y�V�����X�g���琬���悤�Ƃ������̂��B����܂��܂��d�v�Ȋw�╪��ƂȂ�Տ��S���w�ɂ����āA�w������Ƒ�w�@���炪�ڑ����邱�Ƃ̈Ӌ`�͑傫���B |
| |
 ���J��w��w�@���w������ �Տ��S�����k�� ���J��w��w�@���w������ �Տ��S�����k��
�u��l�Ǝq�ǂ��̂�����̃N���j�b�N�v
�J�E���Z���[
���܂� �Ђ�̂�
���� �_������
|
| |
| �Տ��S�����Ăǂ�Ȋw��H |
�@���X�A���G�����錻��Љ�̂Ȃ��ŁA�����̐l�X���S���I�ȃX�g���X�ɂ��u�����Â炳�v������Ă���B����Ȃ�����̖����w�Ԃ̂��Տ��S���w���B
�@�u�Տ��S���w�Ƃ́A�l�̔Y�݂�X�g���X�ɏœ_�����āw������̖��x�ɂ��đΐl�I�ȃA�v���[�`�����邽�߂̊w��ł��B�����ł́A�w������̖��x�����l�X���������邽�߂̎��H�������Ȃ��A���̎��H�̂��߂̗��_��Z�@����������̂ł��B�����ėՏ��S���w�̌������ʂƂƂ��Ɋe��啪��Ŏ��H����̂��Տ��S���m�ł��v�B�����b���̂́A�{�w�Տ��S�����k���u��l�Ǝq�ǂ��̂�����̃N���j�b�N�v�̃J�E���Z���[�A�����_�����B
�@�Տ��S���w�́A�����ėՏ��S���m�́A���{�ł͍�_�W�H��k�Ђ̔�Ў҂ɑ��邱����̃P�A��A�w�Z�ł̃X�N�[���J�E���Z�����O���Ƃ����������ɒ��ڂ����܂����B
�@�u�w��Ƃ��Ă̑̌n���ł����̂͂P�X���I��������ł����A�����ɔY�݂��������A�l���̐����Â炳���y�����邩�͐l�ނ̕��ՓI�ȃe�[�}�B���[���b�p�ł͎v�z��N�w�����ď@���Ƃ��ČÑォ�瑶�݂��Ă��܂������A���{�ł����l�ɒn��̂����̏Z�E����Ȃǂ����̖�����S���Ă���ꂽ�悤�ł��ˁv
�@�ł́A���̗Տ��S���w����I�w�i�ɂ��Ċe����Ŋ���Տ��S���m�Ƃ͂��������ǂ̂悤�ȐE�ƂȂ̂��B
|
| |
| �l�Ɋ��Y���w�� |
�@�Տ��S���m�̊����͑�ʂ��āu�Տ��S������v�u�Տ��S���ʐځv�u�Տ��S���w�I�n�扇���v�u�����E�����v�̎l�̗̈�ɕ��ނ����B
�@�u�w����x�͂�����S���e�X�g�B���k�˗��҂̂�����̏�Ԃ𖾂炩�ɂ��邽�߂ɗl�X�Ȏ���⌟���������Ȃ��܂��B�w�ʐځx�͑��k�˗��҂Ƃ̑Θb�A�܂�J�E���Z�����O�ł��ˁB�w�n�扇���x�͓���̌l�����ł͂Ȃ��A�n���E��A�w�Z�Ȃǂ̃R�~���j�e�B�ɏ�������l�X�̂�����L���P�A����Ƃ������́B�ЊQ���̔�ЎҎx���Ȃǂ�����ɂ�����܂��B�܂��A�w�����E�����x�͂����O�̎��H�I��@�����m���Ȃ��̂Ƃ��邽�߂Ɋ�b�ƂȂ钲�����������������Ȃ����Ƃł��v
|
| |
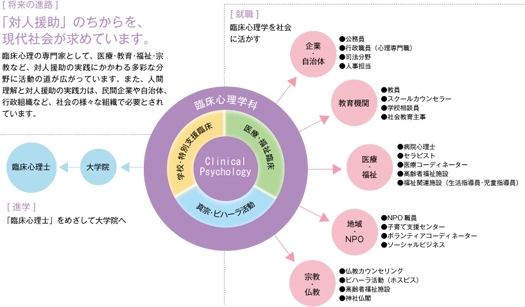 |
| |
| ���ƌ�̊���̏� |
�@����Љ�ɂ����ėՏ��S���m���K�v�Ƃ����E��͍L�͂ɂ킽��B�A�E��Ƃ��Ă����Ƃ��������番��̂ق��ɂ��A��Õی��╟������A�i�@�E��������A�J���E�Y�ƕ���Ȃǖ����ɂ��Ƃ܂������B
�@�u�Տ��S���m�̓��F�Ƃ��āA�����镪��ւ̔ėp���̍������������܂��B����͗Տ��S���w�̊�b�Ɂw���k�˗��҂Ɋ��Y���x���Ƃ����邽�߂ł��傤�B�[�I�Ɍ����A�������ΐl�R�~���j�P�[�V�������ɂ���Ƃ������ƁB�ł�����A���k�˗��҂ƌ��t��ӎv���ʂ���ꏊ�ł���ΐ��E���ǂ��ł��A�ǂ�ȕ���ł��K�v�Ƃ��������Ȃ̂ł��v
�@���番��ł̓X�N�[���J�E���Z���[��q��Ďx���A��������ł͍���Ҏx���B�i�@�E��������ł͔ƍߔ�Q�ғ��x���A�J���E�Y�ƕ���ł͊�Ɠ��J�E���Z���[�ȂǗՏ��S���m���Љ�ʼnʂ��������͑���ɂ킽��B���݁A�Տ��S���m�͑S���Ŗ�Q���l�߂����݂��邪�A�n��╪��ɂ���Ă͂܂��s�����Ă��錻�������B |
| |
| ����܂��܂��d�v�Ȋw��� |
�@�Ⴆ�A�s�o�Z�ɔY�ގq�ǂ��₻�̗��e�A�ΐl�W�ɔY�ގЉ�l�A�Ƒ��Ƃ̊W�ɕs����������҂Ȃǁu��l�Ǝq�ǂ��̂�����̃N���j�b�N�v��K��鑊�k�˗��҂͗l�X�ȁu�����Â炳�v������Ă���B
�@�������b���u���k�˗��҂Ɋ��Y���v�A�v���[�`�Ƃ́A���k�˗��Ҏ��炪�����������鎅����T���`����Տ��S���m�������Ȃ��Ƃ������́B�������ē��ݍ��݂������A����ł����ꂷ�����ɑ��k�˗��҂ƂƂ��ɍl���A�Y�݁A���̋ꂵ�݂����L����B
�@�u�����炪�b������ł��A��������ł������܂��A�������ă}�j���A���̂Ƃ���ɂ����Ȃ��̂����̎d���B���k�˗��҂��Ƃ̑Ή����l���A�J�E���Z�����O�ȊO�ɂ��V�Y�Ö@�┠��Ö@�Ȃǂ����p���đΏ�����K�v������܂��B�w��Ƃ��Ċw���Ƃ����ł͎��ۂ̑��k�����̏�ł͂���Ȃ����Ƃ����풃�ю��ł��B��w�@���ɂȂ葊�k���ł̎��H���n�܂�ƁA����Ȍ���̓���ɔY�ގ��K���������B���B�X�^�b�t�͑��k�˗��҂̕��X�ɐڂ���悤�ɔނ���K���̔Y�݂��A���k�ɓ����Ă��������Ǝv���Ă��܂��v
�@�������g�A�Տ��S���m�����P�O�N�ɋ߂Â����Ƃ��������A���k�˗��҂ւ̑Ή��͓��X�Y�݂̘A�����Ƃ����B
�@�u���̑��k�����J�݂����܂ł͕s�o�Z�������k�̑��k�������Ă��܂������A���̍�����Y�݂����������ƂȂ�Ă���܂����B�l�̂�����A���̔Y�݂�ꂵ�݂��x���Ă����Տ��S���m�͓����Ɏ������g�̂����������ǖʂ������B�w���B�ɂ́A�w������̂����ɓ��퐶���ł������Ȑl�ɏo��A�����ȊO�̐l�B�̑��l�ȍl������m���Ăق����ł���ˁv |
| |
 |
�V�Y�Ö@�������Ȃ����� |
|
| |
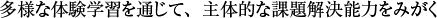 |
| |
 |
| ��l����q�ǂ��܂ŗl�X�ȔY�݁A���k�ɑΉ�����B�P��̑��k���Ԃ͂S�T���ŁA���k���e�͎�邳���B�Տ��S���m���i��L�����w�����U���ƗՏ��S���m�S���̌v�P�O�������k�ɂ�����B |
| |
| �w�т̃|�C���g |
| |
�@�Տ��S���m�̎��i���擾����ɂ́A�w���ł̂S�N�Ԃ̊w�тɉ����đ�w�@�ɐi�w����K�v������B�w���ł͂P�A�Q�N����S���w�y�їՏ��S���w�̊�b�I�Ȋw�K�̊��ԂƂ��A���_�𒆐S�Ɋw�ԁB
�@��w�@�ł͊w���Ŋw���_�̎��H����̂Ƃ������K�������Ȃ��A��葊�k�˗��҂ɋ߂��ꏊ�ŗՏ��S���w�̌���Ŋ�������̂ƂȂ��Ă���B
�@�Q�O�O�S�N�ɊJ�݂����{�w�Տ��S�����k���u��l�Ǝq�ǂ��̂�����̃N���j�b�N�v�́A���̑�w�@���̎��H����̒��S�ƂȂ��Ă���{�݂��B�V�K���k�\�����݂͔N�Ԗ�P�O�O���A���k���͔N�ԂP�O�O�O�����A��������Տ��S���m�{���Z�̑��k�{�݂Ƃ��Ă͈ٗ�̑������B����̔N��w�╪��ɕ炸�A�ǂ̂悤�ȑ��k�˗��҂ɂ��^���ɑΉ����Ă������ʂ��A���k�����ƂȂ��Ă�����Ă���B
�@���̑��k���͑�w�@���B�ɂƂ��Ă��A���[���Տ��S���m�̌����m��@��ƂȂ��Ă���B���K�ɂ͑��k�������̎�t�Ɩ����͂��߁A�J�E���Z�����O�ւ̓��ȁA�q�ǂ��B�ւ̗V�Y�Ö@�Ȃǂ̎Q�����܂܂�Ă���A�����H�I�ȓ��e�ƂȂ��Ă���B
�@�u�Y�݂�ꂵ�݂Ȃǂ́w������̖��x�ɑ����Ɍ���������͂���܂���B�����炱���A�w������x�Ɍ����������߂ɂ͗l�X�Ȍo�����瓾��m���⎩���Ȃ�̍H�v���K�v�ƂȂ�̂ł��B���̂��߂ɂ��l�Ɛڂ��邱�Ƃ��ꂾ���ő傫�Ȋw�тƂȂ�܂��B�Ⴆ�Α����̎�t�Ɩ��̂悤�ȒZ�����Ԃ̂Ȃ��ł����k�˗��҂̕\���̑傫���ȂǁA���ӂ��Č���ƋC�Â����Ƃ͂�������͂��ł��v
�@�w���B�ɂ͏����A�߂�������Ƃ͂����ĈႤ�̈�̌�����̌����Ăق����Ə�������͘b���B
�@�u���ƌ�ɓ��蕪��̌���ɓ���Ɛ�含�͍��܂�܂����A�ق��̗̈���w�ԋ@��͂قƂ�ǂȂ��Ȃ�܂��B��ÁA�����A����……�B��������֘A����̈�������Ă��܂����猈���Ė��ʂɂ͂Ȃ�܂���B�w�����ゾ���炱���ł���w�ѕ��ŁA�ł��邾�������̌o�������Ăق����ł��ˁv |
| |
 |
��t�Ɩ������K�̂ЂƂ� |
|
| |
| ���J��w�Ȃ�ł͂̃J���L������ |
| |
�@�R�N���ȍ~����͂��ꂼ��̊w���������߂�������ɂ��킹�āA��啪�삩��I�����Ċw�ԎO�̗̈悪�ݒ肳��Ă���B
�@�u��Ì���╟���{�݂ł̉����Z�p���w�ԁw��ÁE�����Տ��̈�x�ł́A���a�Ȃǂ̐��_�Ⴊ����A���̉Ƒ��A�����{��{�݂̎q�ǂ��B���x���邽�߂̃A�v���[�`���A�w�w�Z�E���ʎx���Տ��̈�x�ł́A���B�Ⴊ����m�I�Ⴊ���̎q�ǂ��B�ɑ��ċ���@�ւł̃T�|�[�g������Ƃ������̂ł��B�܂��R�̈�̂Ȃ��ł������Ƃ������I�Ȃ̂��w�^�@�E�r�n�[�������̈�x�ł��傤�B�{�w�̌��w�̐��_���������ꂽ���g�݂ŁA���Ƃ��ΏI������Â̊��҂���ɑ��A�����I�Ȏ��_�ɂ��J�E���Z�����O�������Ȃ��Ƃ������̂ł��v
�@�]���A�Տ��S���w���{�̂Ƃ��Ă����̂͑ΐl�W�𒆐S�Ƃ��釀�Љ�����c�ޏ�ł̔Y�݇����B����A�Տ��S���w�ȁE�Տ��S���w��U�̊J�݂ɂ����蕧���I���_�荞�w�^�@�E�r�n�[�������̈�x��������ꂽ���Ƃɂ���āA�{�w�Ŋw�ԗՏ��S���w�ɂ́A���l�ԂƂ��Đ����A�����}���邱�Ƃɂ��Ă̔Y�݇��ɂ܂ł��̗̈���L���邱�ƂƂȂ����B |
| |
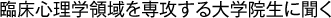 |
| |
 |
 |
���w������ ����w��U
�C�m�ے�2�N�� �Տ��S���w�̈�
�Ђ�͂� ��傤�����@�@
�L�� �Ȉ����� |
���w������ ����w��U
�C�m�ے�2�N�� �Տ��S���w�̈�
�����͂� �@���@�ȁ@�݁@�@�@�@
���� ��ޔ����� |
|
| |
| ���_�Ǝ��H�̃M���b�v |
| |
�@�����̑�w�̐S���w���𑲋Ƃ��A�����{��{�݂̐S���E���o�Ė{�w��w�@�i�w�����L������́u���J��w�ł����w�Ԃ��Ƃ��ł��Ȃ��Տ��S���w�̓��e���d�������v�Ƙb���B
�@�u�w��������ɉƑ��Ö@�ɊS�������A���݁A�Տ��S�����k���̎���������Ă���g��勳���Ɏw�����Ă������������ƍl������ł��B���k���������A�Ƒ��Ö@�̗��_�Ǝ��H���o���ł���ꂪ����̂͗��J��w�Ȃ�ł͂ł�����v
�@����w�̕��w���𑲋ƌ�A��x�̏A�E���o�Č��݁A�{�w��w�@�ŗՏ��S���w���w�ԉ�������́A�ȑO���炸���ƊS�̂������Տ��S���m�ւ̓������߂��ꂸ�ɐi�w�����߂��Ƃ����B
�@�u�w���𑲋ƌ�A�w�K�m�Ƒ�w�����̓�̎d�����o�����܂������A�ǂ�������������z�Ƃ���q�ǂ��ւ̂��������͓�������B���炽�߂Ď����������������̂�����������l�����Ƃ��ɁA��͂�q�ǂ��̎x���ɂȂ�d�����������Ǝv������ł��B�i�w�����߂��͎̂Љ�l�ɂȂ��ĂT�N��̂��ƂȂ̂ň�匈�S�ł����v
�@�L������Ɖ�������A�o�������Ⴆ�ǂ��������x�͎q�ǂ��Ɋւ�錻����o�����Ă���B�������A��l�Ƃ����k���̃J�E���Z�����O�ɓ��Ȃ��邽�тɁA���_�Ǝ��H�̈Ⴂ���v���m��悤�ɂȂ����Ƃ����B
�@�u���ۂɑ��k�҂̕���O�ɂ���ƁA�ǂ̂悤�ɐU�镑���Ă����̂����f�����Ȃ��ǖʂ�����܂��B���_�Ƃ��Ċw���Ƃ̑S�Ă����ۂ̌���ŗL�����Ƃ͌���Ȃ��B�Տ��S���m�͏�ɍאS�̒��ӂƋC���������߂��邱�Ƃ�m��܂����B�S���w����錾�t�Ƃ��Ă悭�w�l�Ɋ��Y���x�ƌ����܂����A��������H���邱�Ƃ̓�����������Ă��܂��v�i�L������j |
| |
| �������g�̕ω� |
| |
�@���݁A�L������͕����̈�̐S���E���A��������͔��B���k����S��������Ȃǂ𑲋ƌ�̐i�H�Ƃ��čl���Ă���B�܂��A��l�Ƃ����J��w�ȊO�̊O���{�݂Ŋw�K�x���Ȃǂ̃{�����e�B�A�Ɍg��邱�ƂŁA�ϋɓI�Ɋw�т̋@��Ă���B
�@�u��w�@�ł͊F�A�����I�Ƀ{�����e�B�A��T���Ď����̊S�����镪����w��ł��܂��ˁB�ӊO�������̂́A�S���E�͔�������Ȃ��Ɠ���Ƃ������ƁB�q�ǂ�����Ȃ�ŐV�̃Q�[����A�j���̘b��A��l�Ȃ玞�����Ȃǂǂ�Ȃ��Ƃɂł����������������̈����o�������������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ���ł��B���������Ӗ��ł��A���̎d���́w�����x���������@������Ǝv���܂��v�i��������j
�@�L��������A�Տ��S���w���w�Ԃɂ�A���������g�̓��ʂ��ω����Ă������ƂɋC�Â��Ă����Ƙb���B
�@�u������傫���ς�����̂́A���퐶���ł��l�̘b���悭�����悤�ɂȂ������ƁB���t���瑊��̐[����������ݎ��悤�w�͂��悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃł��ˁB�ł��A��b�ɖv�����Ă���̂ł͂Ȃ��A�ǂ����q�ϓI�Ɍ��Ă��鎩��������B����Ȏ������g�̕ω��ɂ͂ƂĂ������܂����v |
| |
| �w������̃��b�Z�[�W |
| |
 |
�ԏ��O�� �w�� |
|
�@���t�A�V�݂ƂȂ�Տ��S���w�Ȃ͐S���w�̊e�̈�̊w�p�Z�@�A���H�����f�I�Ɋw�тȂ���e����̐����C�������l�Ԃ��琬������j���f���Ă��܂��B����ł́A�l�X�ȕ���ɂ����Čʂ̑Ώۂ͂��A�X�e���I�^�C�v�ɗ������悤�Ƃ���X���������ł����A���̕��@�ŕ��G�Ȑl�Ԃ𗝉�����ɂ̓V���v��������Ɗ����Ă��܂��B�{�w�̌��w�̐��_�ɂ�����悤�ɁA�l�Ԃ͐l�Ԃ̎v�҂����͂��炫�̂��ƂŐ������ꂽ���݂ł���ƎƂ߂Ă����ׂ��B�����������Ӗ���������ゲ�ƂɕϑJ������H���e��A�e�̈�̒m�I�A�g�͕s�����ƍl���Ă��܂��B
�@�l�Ԃɂ��Đ[���l���A���҂Ƃǂ̂悤�Ɍ������������̂��͐l�ނ̕��ՓI�ȔY�݂ł�����A����Љ���L�̖��ł�����܂��B�Տ��S���w�Ȃɂ́A������Đl�ԂƂ��Ă̂���悤���A�܂��͈琬���Ă������Ƃ����҂��Ă��܂��B |
|