|
|
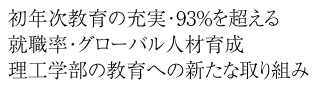 |
| 社会情勢やライフスタイルが大きく変化するなか、理工学教育も従来どおりのあり方では、時代に対応することができない。「人間力の養成」を中心に据えた理工学部の先進的な取り組みの数々は、大柳理工学部長をはじめとする理工学部全教員の問題意識から生まれたものだった。 |
●「基礎学力の定着」に重点 |
「今、大学教育は社会から何を求められているのか??。理工学部の教育内容を見直すにあたり、大学の使命をあらためて考え直すことが出発点となりました」と話すのは、2009年に理工学部長に就任した大柳満之教授。
「現在、学生達の多くが『なぜ学ぶのか』『卒業後はどのような進路を選択すべきか』と、人生の根源的な悩みを抱えています。理工学部では教養教育・専門教育と並行して、学生が社会的に自立することができる『人間力』を育むために、幅広い意味でのキャリア教育をおこなっています。そして、その過程で教員自身の教育力を向上させることも大きな目的としているんです」
なかでも注目すべきは初年次教育の充実度だ。理工系基礎学力の定着を目的としたこの取り組みのきっかけとなったのは、留年者・退学者に対する追跡調査だった。
「およそ6年間にわたり調査をおこなったところ、留年者・退学者の多くが初年次に数学や物理などの基礎科目につまずいていることがわかったのです。理工学分野では、基礎科目からの地道な積み重ね無くして成り立ちません。まずは4年間しっかりと学ぶ力をつけるため、あらゆる角度から学習支援をする必要がありました」

フレッシャーズ・ステップアップ・サポート
数名ずつの少人数クラスで、初年次生の様々な
相談にきめ細かく対応
この取り組みは、龍谷大学教育改革支援制度(通称「龍谷GP」)に採択された教育プログラムで、全学に先駆けた取り組みでもある。学生が多様化するなか、理工学部ではこの取り組みを通して入学後間もない初年次生一人ひとりに向きあい学習支援をはじめ、学生生活支援・キャリア形成支援などをおこなっている。その成果は着実にあらわれつつある。
「学習支援を担う『初年次学習支援センター』では、上級生や元高校教諭のシニアアドバイザーによって学生達に個別学習指導をおこなっています。高校教育と大学教育の隙間を埋める役割も担い、理工系基礎科目につまずきそうな1年生をきめ細やかにサポートしています。また、学生に様々な対応をするため、少人数クラスの『フレッシャーズ・ステップアップ・サポート』を組織しました。教員と大学院生を交えた定期的なクラス会では、学生の履修状況から学生生活にいたるまで、幅広くアドバイスをおこなっています」
また、学生のモチベーションを高める取り組みとして「学習意欲向上プログラム」を実施。卒業生や就職内定者が体験談を語るセミナーや学習懇談会を通じて、社会に出ることへの目的意識を明確にする支援をおこなっている。
|
●社会的自立につながる教育を |
2年次以降のバックアップ体制も万全だ。大学院生を中心としたチューター制度を充実させている。チューターは、教養課程や専門課程、コンピュータ実習にそれぞれ配置し、幅広く個々の学生に合った学習サポートをおこなっている。加えて文章表現能力を養うライティングセンターにもチューターを配置し、学生にレポートや卒業論文、就職活動には欠かすことができない論理的思考と文章表現技術に関する指導・アドバイスをおこなっている。
また、物質化学科では、3年終了時に、入学時からの学力定着をはかる到達度試験を昨年3月から実施している。
「これは、学生の定期試験だけでははかりきれない学修の『定着度』を、卒業研究をはじめる4年生になるときに確認するためのものです。残念なことに現在、就職活動において企業は、大学での成績を全面的に信用していません。それは、大学の定期試験偏重の学力評価に対する不信感のあらわれでもあります。大学の役割は学生を卒業させることではなく、学生自ら自分に合った進路を選択できる主体性を育む『社会的自立につながる教育』だと考えています」
龍谷大学らしい取り組みとしては、15万人を超える卒業生のネットワークを活かした『校友サポートねっと』がある。仕事内容の疑問や不安をWEB上で、その職種に就業する校友に質問できるシステムだ。また、学生自身が個性や能力を自己認識するための『e-キャリアポートフォリオ』は、学生自身が大学で修得した学問が社会でどのように活きるのかを知るためのものだ。

海外キャリア実践実習における最終発表会
実習終了時に学内外の大勢の聴衆を前に
最終発表会をおこなう
国内外におけるキャリア実践実習も、理工学部のキャリア教育における大きな特色だ。とくにIT分野のメッカであるシリコンバレー・ロサンゼルス(アメリカ)での実習は、学生のグローバルな視点を養うまたとない体験となっている。
「国内実習では関西地域を中心とした地元企業に、海外実習ではカリフォルニア州の日系企業にご協力をお願いしています。実習終了時には毎年、実習に参加した約400名のなかから選抜された学生達が、最終発表会をおこなうんです。実習から戻ってきた学生は参加前と比べて目の色が違う。これは学生の成長をあらわす何よりの収穫ですね」
「社会的自立」と「基礎学力の定着」に焦点をあてた理工学部の取り組みは、毎年、多彩な分野で活躍する卒業生を生み出している。2010年度の理工系有効求人倍率は3・5倍を超えており、全国有効求人倍率の1・28倍と比較すると驚くべき高水準であり、就職率も93%を超えている。この原動力となっているのが学生、教員、OBが一体となった実践的キャリア教育だ。
|
●教員一人ひとりの奮い立つ気持ち |
意識向上に努めているのは学生達だけではない。理工学部の教員もまた、教育内容を日々進化させるための取り組みをおこなっている。
「授業アンケートを通じて集めた学生達の声を教育に反映させるため、教員自身が各授業科目に関して自己採点をおこない、その結果をもとに授業内容を常に見直す文化を育んでいます。あわせて、卒業生や学外有識者で構成する外部評価委員会に、理工学部の教育研究活動に関する評価をお願いしています」
理工学部の教員による目覚ましい研究成果とその教育内容は、すでに学内外から高い評価を得ている。その一環として、物質化学科及び大学院物質化学専攻では日本で唯一、学部・大学院を通してJABEE(日本技術者教育認定機構)の認定を受けており、教育水準の高さを証明している。
「大切なのは教員一人ひとりの奮い立つ気持ちです。学生の学修意欲向上も教育制度づくりも、理工学部の全教員が一丸となっておこなわなければ実現できません。そういう意味では私達教員の『人間力』も常に試されているのです。また理工学部の教育成果を常に社会へと還元していきたい。そのために毎年、大型コンピュータや電子顕微鏡などをはじめとする最新の実験装置を導入して設備面の充実も進めています。学生はもちろん、すでに社会で活躍されている方々にとっても、価値を感じてもらえる教育研究拠点として、発展をめざしたいと考えています」
|
理事
理工学部長・理工学研究科長
おおやなぎ まん し
大柳 満之教授
龍谷大学理工学部教授。
早稲田大学大学院理工学研究科博士課程修了。
工学博士。
1989年、龍谷大学理工学部物質化学科助手に就任。
講師、助教授を経て2001年より教授。
2009年より理工学部長に就任。
学長補佐、RECセンター長を務める。
文部科学省平成19年度 大学院教育改革支援プログラム
「東洋の倫理観に根ざした国際的技術者養成」及び
平成22年度就業力育成支援事業「社会的自立につながる実践的キャリア教育」取り組み実施代表者。
専門は無機材料化学。
|
 |
|

|