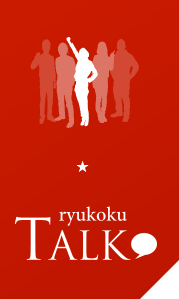――では最初にLeD’sの活動について教えていただけますか?
小原: 法学部についてのイメージを高校生に詳しく伝えることが僕たちの活動の目的です。そのため昨年からオープンキャンパスでの模擬裁判を行っています。
――法学と聞くと “難しい”とか“固い”というイメージがありますね。そういうイメージを変えるということですか?
小原: そういう面もあります。そのイメージのせいで法学部を受験の候補から消してしまうのは、ちょっともったいない、何が自分に合っているかっていうことは実際に見てみたりやってみたりしないと分からないと思うんです。なのでいろんな情報を高校生の皆さんに伝えて、法学部の近寄りがたいイメージを少しでも和らげてあげられればと思っています。
――昨年からということなのですが、模擬裁判で昨年から変えた点、変わった点はありますか?
小原: 去年は判決を出さなかったんです。高校生に有罪か無罪か、どうしてそう思ったかっていうのを考えてもらったんですけど、今年は無罪という判決を最後に出して、それに納得がいくかいかないか、考えてもらいました。
――どうしてそのように変えたのでしょう?

小原: 弁護側も、検察側もどっちが言っていることも正しいんですよ。そこを裁判長とか裁判員がどうくみ取るか、ということになるんですが、そうなると判決に納得のいかない人も出てくるんです。そこをどう考えるか、なんで納得がいかなかったのか考えることが法学部の魅力の一つだと思うので。
――他にもお二人が思う法学部の魅力ってありますか?
古川:物事を考える際に、一般的な見方と法学を通した見方と二通りの見方ができるようになるっていうのはあると思います。
小原: 判例なんかを読んでいると「こんな事件本当にあったのかな?」っていう事件もあるんですよ。そういう事件に対して裁判所はどういう判断をしたのかなということを調べていくうちにこういう見方や説もあるんだな、って分かると自分の中で大きな変化がありますね。裁判の判決だけ聞いて納得するんじゃなくて、どうしてその判決になったのか考えよう、と思うようになりました。それも法学部ならではかな、と思いますね。
――お二人がLeD’sに関わるきっかけは何だったんですか?
小原: 友人に誘われたったいうのもあるんですけど、自分が法学部に入った時、法学部って法律のことを勉強するんだろうなってくらいしか知らなかったんです。でも深くやっていくうちに楽しいなと思う面も出てきました。誘われたとき、そういう面を高校生に伝えて彼らの進路を決定する材料になればと思ったこともありますね。
古川:自分も誘いを受けた面もありますし、法学部が実際に何をやってるかっていうのはオープンキャンパスやパンフレットでしか伝わってこないと思うので、オープンキャンパスを通して法学部について知ってもらえたらと思ってLeD’sに携わろうと思いました。
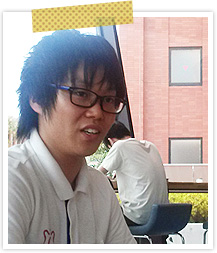
――小原さんはLeD’sの代表をされていますが、代表としての苦労はありますか?
小原: メンバーに指示を出して動かすっていうのはすごく難しいな、と感じましたね。振り分けや分担などを考えることが大変でした。去年の模擬裁判は一定の人で作ってしまった、という面があったのでその反省を踏まえてできるだけみんなで準備をして、終わったときの達成感をみんなで共有できるように、というのがありました。
――古川さんは去年から模擬裁判に参加されてると思うのですが、去年と何か変わったなと思うことはありますか?
古川: 仕事の分担が決まっているので、会議に出るだけでなく家に帰ってからも作業があったり、次の会議までに考えおかなければならないことも増えて、やることは増えました。でもみんなに仕事が分けられてその過程でみんなとのコミュニケーションがたくさん取れた、ということもあってそういうことは模擬裁判を作っていく中で印象的でした。
――最後にLeD’sの今後の目標を聞かせてください!
小原: 高校生の皆さんに満足してもらえるような企画とそれを実行する力をつけて、法学部の魅力を面白く伝えていきたいですね。
古川: 一人でも多くの人に、法学部の良さや法律を勉強すれば将来こういうことに役立つんだよ、っていうことを知ってもらえたらと思います。