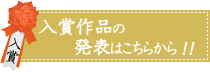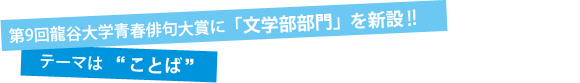第9回を迎える龍谷大学青春俳句大賞では、新たに「文学部部門」を設けました。
記念すべき最初のテーマは「ことば」。
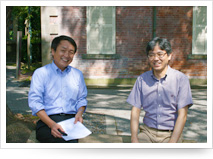
でも、「ことば」って言われても漠然としていて、どんな俳句を作ったらいいのか、わかりにくいかもしれません。そこで、テーマに関連したお話を、文学部長の越前谷宏先生(近代文学)と日本語日本文学科の安藤徹先生(古典文学)にうかがいました。投句の際の参考にしてください。文学部での“学び”の一端もかいま見えるはずです。
○新設された「文学部部門」では、なぜ「ことば」というテーマを選んだのですか?
越前谷:
龍谷大学の文学部は、英語で“faculty of letters”と表記します。レターと聞くと、すぐに「手紙」のことを思い浮かべるかもしれませんが、「文字」「活字」「文学」「学問」などの意味もあります。それらを大きくまとめるならば「ことば」、あるいは「ことば」にかかわる知的な領域のことだと言ってよいでしょう。つまり、文学部の“学び”の核心にあるのは「ことば」なんです。そこで、ほかでもない「文学部」部門のテーマならば、やっぱり「ことば」しかない! そう考えました。
安 藤:
実は私には「もっといい」と思っていた別の案があったのですが(笑)、お話を聞いて意図するところがよくわかりました。ときどき文学部を「文学」部だと思っている人もいるようです。でも、本当は「文」学部なんですよね。もちろん、文学も学ぶけれど、それだけではない。宗教も哲学も歴史も含めて、いわゆる「人文学」はすべて人間の精神的活動の所産で、同時に「ことば」なくしては成り立たないものです。文学部は「人文学」という、人間そのものを問う根源的な学問領域を対象とするわけですが、そこには「ことば」へのまなざし、「ことば」へのこだわりがなくてはいけません。その意味で、今回のテーマはいかにも文学部部門にふさわしいものですね。
越前谷:
人は空気や水がなければ生きていけない。いっぽうで、空気や水が自由に使えなくなったときにはじめて、その存在を、そしてそのありがたみを感じ、考えます。「ことば」も同じです。作家の大江健三郎さんが、『新しい文学のために』(岩波新書、1988年)の中で、「言葉というものは、人間の根幹に発する特別な存在である。言葉は人間にとって、呼吸の次にあるほど根本的なものだ。言葉によって、赤んぼうは人間となってゆく」と述べているのも参考になります。
安 藤:
ふだん、なにげなく使っている「ことば」は、しかしそれなくして人は生きていけない大切なものだ、ということですね。日常生活では、つねに「ことば」を意識し、それに鋭敏に反応するなどということをしていては、かえって円滑なコミュニケーションがとれない。ところが、危機的な状況に立つと、一つひとつの「ことば」が切実な重みをもって実感されることがあります。このたびの大震災では、そのような経験が深く積み重ねられていることでしょう。
○そうした「ことば」の重みをふだんから見極めるには、どうすればよいのでしょう?
越前谷:
「ことば」にこだわる、「ことば」を見極めるということは、ありふれた「ことば」、手垢にまみれた「ことば」に潜む力を意識的に掴み取り、理解し、創造的に使用してみることです。ふたたび大江さんのことばをお借りすれば、「ありふれた、日常的な言葉の、汚れ・クタビレをいかに洗い流し、仕立てなおして、その言葉を、人間がいま発見したばかりででもあるかのように新しくすること。いかに見なれない、不思議なものとするか、ということ」ですね。大江さんはそれを「言葉を「異化」すること」だと言っています。そして、「異化」によって、「言葉でいながら、ひとつひとつ粒だって、ものの手ごたえをかえしてくるように感じられる」ようになる、と。
安 藤:
「ことば」を“活か”すも殺すも「異化」次第、か……。ここ、笑うところです(笑)。
越前谷:
笑いの強制は勘弁して!(笑)。まあ、「ことば」にこだわるという点では、ダジャレもまたよし(笑)。ことば遊びも「異化」の方法になるんじゃないですか。
安 藤:
ふと思い出したんですが、歴史学者の河西英通さんが面白いことを言っています。「人文学(じんぶんがく/じんもんがく)」は「自分学(じぶんがく)」であり「自問学(じもんがく)」だ、でも「自慢学(じまんがく)」になってはいけない、と(「人文学―じんぶんがく―じぶんがく―自分学」『人文学へのいざない』溪水社、2008年)。こうしたことば遊びの中に核心的、あるいは革新的なものが育まれるのかもしれませんね。ことばそのものへの沈潜なくしてことば遊びはできないわけで……。
越前谷:
オヤジギャクの正当化ではないと信じましょう(笑)。
安 藤:
もちろん(笑)。それはともかくとして、私は授業で学生たちに繰り返し同じことを伝えています。うまくつまずけ、そして何でもいいから手に握って立ち上がれ、と。目の前に大事な問題がころがっていても、それにつまずかずにスルーしていたのでは、結局何も気づかず、何も得られないことになる。でも、つまずいてばかりでも前に進まない。また、つまずいても、何事もなかったかのように立ったのではつまずき損です。まさしく「ことば」によって成り立っている文学を学ぼうとするとき、その出発点にあってほしいのは「ことば」にうまくつまずくことです。それを、大江さんにならって「ことばを「異化」する」ことだと言い換えてもよさそうです。
越前谷:
「ことば」を異化することは、文学にかぎらず人文学全体にもあてはまる大事な姿勢です。そして、俳句を作るときにもきっと必要になると思います。
○ところで、そもそも「ことば」とは何なのでしょう?
安 藤:
語源としては、「言=事(こと)+端(は)」が有力ですね。古くは「事」=「言」と考えられ、両者の区別がはっきりしていなかった。「事」は「言」によって直接表現され、逆に「言」が「事」を実現する。いわゆる「言霊(ことたま)」信仰を思い浮かべるとわかりやすいかもしれません。その後、「事」から「言」が分離し対象化される過程で、「言=事」の一部分(あるいは分身)としての「端」である「ことば」が意識されるようになった、と想像されます。表現の自立、「ことば」そのものへの目覚め、とでも言えるでしょうか。
越前谷:
「ことば」は事実と緊密な関連を持ちつつも、それからの“離れ”が決定的に重要になるんですね。「ことば」とは「事」そのものとはちがう。「言」独自の世界が開かれる。しかし、そうだとすると、「ことば」がどこか浮ついたもの、うさんくさいものにも見えてきてしまいそうですが。
安 藤:
語源から学びたいことは、「ことば」とは内部に事実そのものを宿しているわけでもなければ、たんに事実を反映するわけでもない、ということです。「ことば」が事実との距離を含み込むことで、その事実をいかに捉え、表現し、伝達し、共有・共感すべきか、という問題が浮上する。「ことば」そのものを工夫しなければならない。そして、工夫された「ことば」が、むしろそれまで見えていなかった風景を想像的にあぶり出し、真実を照らし出し、未来を創造することになる。そうした「ことば」の力を見逃したくありません。
越前谷:
子どものころ、教師から「思ったことを素直に書きなさい」、「感動したことをそのまま書けばよい」と言われて困ってしまったことを思い出しました(笑)。思ったこと、感動したこと自体はたしかな事実として私の心の内にあったとしても、いざそれを表現しようと思うと、なかなかうまく書けない。「素直に」とか「そのまま」と言っても、心の中の風景を「ことば」に移し替えるのはとてもむずかしいですから。実際の風景だって同じです。それをしようとしたのが写実主義ということになるんでしょうが……。
安 藤:
擬音語だってそうですね。実際に聞こえた音をそのまま写し取ったものが擬音語ということになるはずですが、じっさいにはそのままと言えるかどうか。やはり、そこにどのような「ことば」(文字や音)で表現するかという工夫が求められる。ときには、ルールをはみ出さなければ表現できない、なんてこともあるでしょう。たとえば、「あ」に濁点をつけるような表記を創作することで、はじめて描くことのできる音の風景がある。どう音声として再生するかは別にして(笑)。