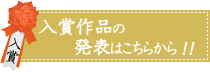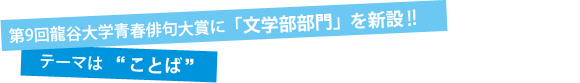第9回を迎える龍谷大学青春俳句大賞では、新たに「文学部部門」を設けました。
記念すべき最初のテーマは「ことば」。
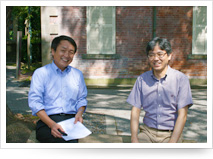
でも、「ことば」って言われても漠然としていて、どんな俳句を作ったらいいのか、わかりにくいかもしれません。そこで、テーマに関連したお話を、文学部長の越前谷宏先生(近代文学)と日本語日本文学科の安藤徹先生(古典文学)にうかがいました。投句の際の参考にしてください。文学部での“学び”の一端もかいま見えるはずです。
○考えてみると、「言葉」という表記も面白いですね。
安 藤:
日本初の勅撰和歌集として知られ、後世に与えた影響も絶大な『古今和歌集』は今から1,100年以上も前に成立した作品ですが、その仮名序の冒頭に「やまとうたは、人の心を種として、よろづ言の葉とぞなれりける」とあるのは有名です。そこでは、和歌とは「人の心」という種から生い茂った「言の葉」だ、という認識が示されています。植物の生成にたとえているんですね。
越前谷:
和歌の伝統の中から生まれた俳句も、この比喩があてはまると考えていいですか? 俳句は「人の心」という種から生い茂った葉である、と。ここでちょっと考えてみたいのは、種子と葉の関係、「心」と「ことば」の関係です。さきほどの話に戻ってしまうようですが。この比喩は、どのような関係を見定めようとしているんでしょう?
安 藤:
種から芽が出て成長し、やがて葉が茂る。ここで大事なのは、どんな葉になるか、何枚どこにつくかを種がすべて決定しているのではない、という点だと思います。実際には、日当たりや水の具合など、さまざまな要因が作用します。似たような種から芽生えた草は、しかし一つとして同じ枝葉を茂らせない。同じ種類の草木であったとしても、です。俳句もそうでしょう。同じものを見、同じような感動をしたとしても、5・7・5という定型に茂る「ことば」はちがうものになる。どんな「ことば」が茂るのか、それはけっして心の中に完全にプログラミングされているわけではない。そこに表現することのむずかしさと面白さとがあるんでしょう。とくに、俳句というきわめて短い定型詩では。
越前谷:
たとえば、こんな句があります。「古寺に斧こだまする寒さかな」「わが恋は空の果てなる白百合か」。これらにはどんな「人の心」が宿っていると思います?
安 藤:
いや、俳句の解釈はむずかしくて……。でも、「古寺に」の句からは心身に染み込んでくるような清らかな静寂さを感じます。「わが恋は」の句は、いわゆる「高嶺の花」でしょうか。
越前谷:
なるほど。実は、これ、コンピュータが作った句なんです。もとは哲学者の黒崎政男さんの『哲学者はアンドロイドの夢を見たか』(哲学書房、1987年)に紹介されているもので、私は英文学者の大橋洋一さんの『新文学入門』(岩波書店、1995年)から知りました。
安 藤:
それでは「人の心」というのは……。コンピュータのプログラマーの心? コンピュータの心? それはさすがに変です。ならば、読んだ私の心でしょうか。
越前谷:
私たちは、たしかな「心」があってこそ「ことば」が存在しうる、と思い込みすぎているのかもしれません。また、「ことば」はそれを発する者の所有物だ、とも。しかし、実はそうではない。むしろ、「ことば」として表出されることで、はじめてそこに籠められているように感じられる「心」がたしかな形を持って把握できるようになる。「ことば」はそれを受けとる側の人間がいて、はじめて意味が生成される。そうした発想の転換も必要ではないでしょうか。
安 藤:
俳句を詠むときに「心」など無用、感動など要らない、ということではないですよね?
越前谷:
もちろん。種となる「心」がなければ何も芽生えないですから。でも、たとえば劇的な感動がなければ句は詠めないとか、はっきりと心で掴み取れたものがなければダメだとか、そんなことはないだろう、ということです。ささやかな体験でも、何とも言いがたいようなわずかな心の動きでもいい。それを5・7・5に季語を籠めて詠んでみようとする、そのプロセスの中で「ことば」が磨かれ、結晶し、そして読者へと届けられ、「心」が結実する。そんなイメージを持ってみるのもいいのではないか、ということです。
安 藤:
日本語では、“詠む”も“読む”もともに「よむ」です。俳句を詠むことは読むこと、「ことば」を読むことは詠むこと。創作と解釈、創造と受容の関係を考えるうえで、この語はたいへん示唆的です。
○それにしても、「ことば」をテーマにした俳句というのはちょっとむずかしそうですね。
越前谷:
あまり身構える必要はないと思います。日々の生活には「ことば」が溢れているんですから、そうした身近な「ことば」にまずは敏感になってみることです。安藤先生の言い方で言えば、「ことば」につまずくことですね。
安 藤:
はい。いつもなら聞き逃し、見逃してしまいそうな「ことば」に対して、ちょっとだけ意識を向ける。そうすると、見慣れていたはずの「ことば」が急に何かを訴えてきます。その「ことば」に少しだけ心が揺らぎます。それをうまく掬い取り、決められたルールのなかで表現を磨き、「ことば」として定着させる。
越前谷:
e-mailも手紙も、雑誌も新聞も、歌も会話も、テレビドラマも映画も、グチも噂話も、教科書も授業も宿題も、愛のささやきも悪口も、「ことば」抜きにはありえません。教室の黒板に書かれた先生の読みにくい字、駅の看板のキャッチコピー、試合中に掛け合う声、図書館の本に印刷された文字。みんな「ことば」です。
安 藤:
たとえば、青春俳句大賞の「青春」という「ことば」に立ち止まってみる。調べると、「朱夏」「白秋」「玄冬」という「ことば」があることがわかる。すると、青春というものが人生のある特別な“季節”、しかも独特の色を持った季節なんだということに気づかされます。30年近く前に出版された本ですが、高田求さんの『青春の色は何色か』(新日本新書、1983年)は、青春の「青」は英語のブルーだろうか、と問いかけています。ちなみに、高田さんは日本語のアオはグリーンでもあることを指摘し、「万緑の中や吾子(あこ)の歯生えそむる」という中村草田男の句を挙げながら、青春の色は生命力溢れる「緑」だ、いや「緑」であるはずだ、と述べています。私の青春は何色か? 私にとって青春の風景はどのようなものか? こんなところからも、句は生まれてくるかもしれませんね。
越前谷:
ところで、安藤先生の青春の色は何色でした?
安 藤:
私の青春は……どこか霞のかかったような、ぼやけた色をしていたような。まあ、いいじゃないですか、それは(笑)。
越前谷:
はい(笑)。それでは、青春俳句大賞の過去の受賞作の中から、参考になりそうな作品をいくつか挙げてみましょうか。少しは具体的にイメージしやすくなるかもしれません。
安 藤:
私のお気に入りの一つは、第6回の高校生部門で入選した塚原佑果さんの「動名詞分詞不定詞蝉時雨」という句です。夏休み中の講習で英語を学んでいるんでしょう。「動名詞」「分詞」「不定詞」というこむずかしい「ことば」が教壇から降り注いでくるけれども、それが蝉の鳴き声に紛れ、あるいは蝉の鳴き声そのもののようにしか聞こえない。そんな風景が思い起こされ、いや自分の高校生のころをまざまざと思い出させてくれます。つらい思い出が。はい、たしかにこれは青春の風景です。
越前谷:
第8回の高校生部門で入選した井上皓貴さん「インテグラル並ぶ黒板時鳥」は数学の授業。夏休みの講習ならば、第3回の高校生部門で入選した岩田怜子さんの「憂鬱と書いては消して夏期講習」というのもあります。教室の風景ということで、第7回の高校生部門で入選した西廣一隼さんの「黒板に文字びっしりと日日草」も参考になるかもしれませんね。
安 藤:
第4回の高校生部門で優秀賞をとった中川明紀さんの「授業中せ・し・す・するせみの声」も面白い。さあ、古語の動詞のサ行変格活用を覚えましょう! でも、またしてもそれは蝉の声に紛れしまう。古典文学を専門としている者としては面白がっている場合ではないか(笑)。でも、「せ・し・す・する・(すれ)」と活用して、最後の「せよ」が「せみ」へと流れ込む勢いは見事!
越前谷:
授業の風景以外のものもいくつか挙げてみましょう。
「未送信メール削除し遠花火」(第2回高校生部門入選、鈴木幸恵さん)、
「「夏」の一字は最短の少年詩」(第3回短大・大学生部門入選、成井藤彦さん)、
「台風に君の名前をつけてみる」(第3回中学生部門入選、唐澤久美子さん)、
「秋草になら泣く訳を話そうか」(第4回高校生部門優秀賞、河野光梨さん)、
「春は曙鍵付の日記帳」(第4回高校生部門最優秀賞、森保緯さん)、
「汗かいて上ル下ルの京の街」(第4回中学生部門入選、安田祥さん)、
「貝寄風(かいよせ)や親に見せないその手紙」(第4回中学生部門最優秀賞、内藤来夢さん)、
「大袈裟に伝へる噂ラムネ飲む」(第5回高校生部門入選、山田耕平さん)、
「ごめんねと夕焼ごしに友の声」(第5回中学生部門入選、鈴木まどかさん)、
「今にして祖父の一言茄子の花」(第6回短大・大学生部門入選、岩田怜子さん)、
「墓そうじ磨いて出た字寛政だ」(第7回高校生部門入選、中西満蔵さん)、
「白玉や言つてはいけないことを言ふ」(第8回短大・大学生部門入選、岡田苑子さん)、
「京ことば耳に優しくところてん」(第8回、中学生部門入選、石川智輝さん)。
安 藤:
いずれも、文学部部門のテーマにふさわしい作品ですね。「ことば」へのこだわり方は一様ではないし、また「ことば」といってもいろいろある。さまざまな切り口から果敢に「ことば」に挑戦し、「ことば」から挑発されてほしいと思います。
○最後に、文学部部門に応募しようと考えている方にメッセージをお願いします。
越前谷:
投句をきっかけに、一人でも多くの方が「ことば」にこだわり、「ことば」を大切にし、「ことば」を磨こうとする姿勢を養ってくださることが、私たちの何よりの喜びです。それは、文学部の“学び”の擬似体験ともなるでしょう。「文学部部門」はどなたでも応募できます。とにかく、何らかの点で「ことば」にかかわっていればOKです。みなさんの句を読む=詠むことを楽しみにして待ちます。ぜひ積極的に投句してください。
安 藤:
「ひとりひつそり竹の子竹になる」(種田山頭火)。竹の子、集まれ! 「ことば」への目覚めは飛躍的な成長をもたらすはずです。
なお、俳句の作り方については、「第9回青春俳句大賞」のHPに説明がありますので、ぜひそちらを参照してください。
最後に、我々も一句ひねりますか?
越前谷:
いや、それだけはやめておきましょう。変なメッセージを発しそうですから(笑)。
安 藤:
たしかに(笑)。