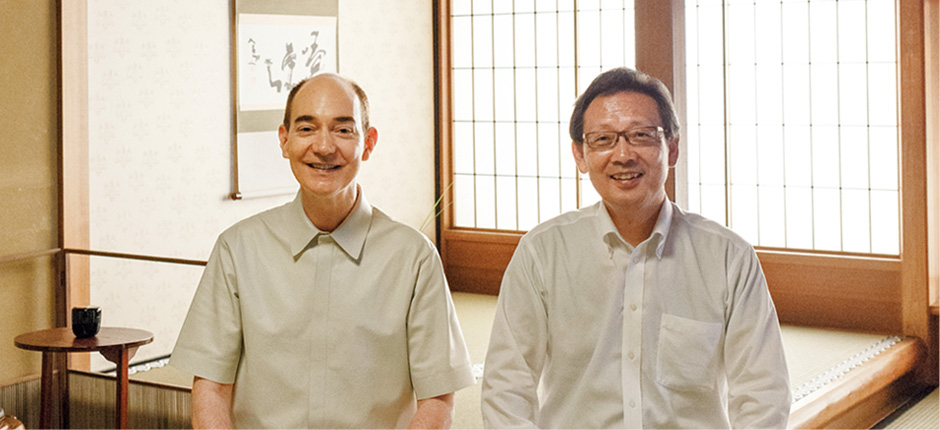

![]()
本学は、2015年4月に「農学部(設置認可申請中)」の新設と、国際文化学部を深草キャンパスに移転・改組し「国際学部」の開設を予定している。2013年12月に大阪で開催したグローバルシンポジウム、「『多文化共生』とグローバル社会に求められる学びとは」(読売新聞大阪本社共催)では、日本近世文学の専門家であり、落ち着いた物腰と本質を突く発言でコメンテーターとして人気の、東京大学大学院教授ロバート キャンベル氏に基調講演をいただいた。
今回は本誌のために、日本文化の特質を問い続けるキャンベル氏と赤松学長が、日本らしい「農」と「食」の探求のあり方や、グローバルに活躍する人材育成の課題について語り合った。

赤松:キャンベル先生はアメリカから日本にいらして、江戸、近世文学を専門に研究されていますが、日本文化に興味を持たれたきっかけは何だったのでしょうか。
キャンベル:小さい頃から読書、フランス語などの外国語の勉強、映画やファッションなどの視覚的な文化に惹かれていました。心のあり方への探求は、人によって、哲学や宗教などに陶冶されると思いますが、私の場合は、視覚的なもの・・・形や色の表現、時による変化などから、人間として逃れられない喜怒哀楽や文化的な違いを見いだすことに興味があったのです。そして10代の後半で、決定的な瞬間はないのですが、フランス語や他のインドヨーロッパ系の言語とは異なる「日本語」という、もう一つのフロンティアとの出会いがありました。日本は視覚芸術が優れていて歴史も長く、西洋のモダニズムの基礎に日本の美学の要素があることも知っていました。それから文学が非常に面白いと感じました。翻訳から入り、日本語を学んでからは原文で読むようになりました。日本独特の美学に関心を持ったのです。
赤松:長く日本にいらっしゃいますが、「日本の伝統文化」という概念についてのお考えをお聞きしてみたいですね。私の専門は仏教史ですが、その立場から見ると、日本文化は必ずしも全体をひとくくりで説明できるものではないと思います。例えば仏教も古代、朝鮮半島を通って伝来したルートもあれば、中国のほうからも来たりしていました。昔から日本は、周辺国から技術や文化を取り入れて、モデルチェンジしながら、より交流を広げようとしてきました。多文化共生ですね。伝統を守ろうとして新しいものや異なるものを排除するのは、少し違うかなと。日本ならではのものはコレ、と違いを強調するのではなくて、周辺地域までもう少し俯瞰して理解をしていったほうが好ましいのではと思うのです。
キャンベル:まったく同感で、日本人は、他と違うことを一つひとつ棚卸しをして塗り込めていくよりも、ゆるやかにつながっているという考え方を持つことが大切ですね。もう少し視点を引いて、歴史的経緯や、海に囲まれている地理的な状況をとらえたいですね。島国ではありますが周りは最高の潮流に囲われ、海道が世界中につながっている。非常にさかんな人物交流があって、世界中から、モノや、仏教のような精神文化をもらった。そして実は逆に優れたセンスを世界と共有できる環境にありますよね。日本の本当の底力であったり、怒濤の近現代を生き抜いて、なお今もあるものは何か、ということを考える上でも、world historyのなかの動きとして、俯瞰して見てみる視点がものすごく大事だと思うんですね。

赤松:日本の食も世界中から刺激を受けて発展してきました。和食はユネスコの無形文化遺産に登録され、盛り上がっていますね。しかし一方で、加工技術の進化や流通の影響で均一化も進み、安全が脅かされている面もあるなと。「食」さらに「農」を考えることは文化を考えることにもなりますね。
キャンベル:世界で様々な流れがあって、独自の言語や食文化との断絶のある国も多いなかで、日本は自国の言語と食を保っています。さらに今では、特に東京は、世界中の多様な食があつまる特異な空間です。昔から、災害対策のための備蓄文化や、「もったいない」の思想、炊き出しというコミュニティ活動、お米経済や食物の贈与習慣、祈りの場での供物としての食物など、食を抜きにして日本文化は語れませんし、江戸時代の俳句もほとんど食無しには作れません。食が精神文化の礎を築いたと言っても過言ではないでしょう。おっしゃるように、食の均一化に問題意識も感じず、食品の製造過程も考えずに生きるということは、今まで日本がつくってきた文化的なメリットを放棄することになると思います。
赤松:本学の農学部の新設も、多くの現代人の関心があり、人間の一番の生存のもとである「農」と「食」、そこをもう一度見直してみようという意図があります。世界的には飢饉はまだまだ各地で起こっています。そんななかで「農」と「食」、「日本の歴史」をふまえながら、学部をつくったらどうなるのだろう、と。人間の営みのなかで、自然に対する働きかけをして、収穫する。得たものを、エネルギーとして吸収する。それを超えた深いところで、いのちを支える、いただくものとして考えていく。浄土真宗の精神を建学の精神に掲げる大学として、全てのいのちを大切にする「平等」の心や、生かされていることへの「感謝」の心を育むためにも、「農」と「食」を今この時代に打ち出していくことに、大きな意味があると思っています。
キャンベル:食の倫理と言ってもいいと思います。最近アメリカでは、「フードディフェンス」といって、流通や製造処理現場への計画的なテロ攻撃に対してどうするかが大きな関心事で、いろんな動きがあります。しかし日本では、もともと農民一揆のように食を奪って再配分させることはあっても、食物を傷つけたり、破壊したりするのは、考えにくいことですよね。
日本の食に対する心性と、グローバリズムな時代のなかで食が置かれている状況。結構そこに、世界に発信していくべき役立つ要素があるんじゃないかなと思うんですね。私はぜひ、この文と理が融合した、域を超えた研究と実践を、龍谷大学の新しい農学部の理念と実践に期待したいですね。アメリカではできないことです。食の倫理学はできても、実際の生産や流通の学びとドッキングした形で、それが生産、流通、栄養学をどう変えていくか、なかなか同じ土俵で語られるということがないんです。龍谷大学のような場所でこそ、むしろそれが自然にできる。新しいイノベーションの土壌がそこにあるんじゃないかなと期待しています。
赤松:ぜひ、期待に応えられるようにしたいと思います。
![]() 広報誌「龍谷」2014 No.78(Ryukoku University Digital Libraryへ)
広報誌「龍谷」2014 No.78(Ryukoku University Digital Libraryへ)

![]()
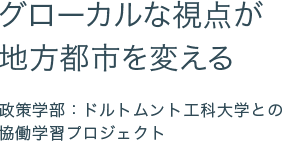
政策学部が昨年からおこなっている、ドイツ・ドルトムント工科大学との協働学習プロジェクトが、内外から高い関心を集めている。これは、両大学で都市計画について学ぶ学生達が互いの国の特定地域が抱える課題について、グループワークやフィールドワークをおこない、英語を共通語として調査や意見交換をするという内容だ。事前・事後学習を充実させ、国際的な視点を取り入れた課題解決型のプログラムは、単なる語学留学にとどまらない学びの機会を生んでいる。
プロジェクトは2013年10月から2014年9月まで、約10カ月間にわたっておこなわれ、対象地域として日本からは尼崎市と福知山市、ドイツはデュースブルグ(Duisburg)とアルテナ(Altena)が選ばれ、それぞれの地域に各大学の学生が交互に滞在して街づくりについての課題を議論した。
プロジェクトを担当したのは、政策学部の村田和代教授(英語・異文化コミュニケーション)と、阿部大輔准教授(都市計画・建築計画)。言語と街づくり、双方の学びをバランス良く取り入れたところにこのプロジェクトの特色がある。
研究対象となる地域の選定については、京都市・ドルトムント市の周辺から、いくつかの共通点を持った都市が対象となった。「デュースブルグはドイツ有数の工業地帯にあり、重工業が衰退してから、産業構造の変化や人口減少などの大きな社会変革を経験しました。将来的に同じ問題に直面する可能性が高い尼崎市と比較することで今後の都市計画におけるヒントが見つかるかもしれないと考えたのです。また、大都市圏に隣接する地方都市として衰退の危機にありながらも活性化への取り組みをおこなうアルテナと福知山市には共通の課題も多く、ドイツと日本の街づくりを考える上で最良のフィールドでした」(阿部准教授)
この協働学習プロジェクトには、ドルトムント工科大学から13名、龍谷大学からは1年生から大学院生までを含む9名の学生が参加した。今年2月には、ドルトムント工科大学から教員と学生が2週間の日程で来日し、深草キャンパスを拠点に尼崎市、福知山市のフィールドワークをおこなった。
「ドルトムント工科大学の学生は空間計画学を専攻しているため、建築や空間設計の視点から都市を見ていたのが印象的でした。例えば『車のスピードを抑制するため、道路をもっと緑化すべきだ』というように、まずは都市全体の設計図を描こうと考える。一方、龍谷大学の学生は街づくりの視点から、都市政策や活性化案などに着目することが多かったですね」(阿部准教授)
当初は、ドルトムント工科大学の学生から次々と出る「日本らしさ」への質問に、龍谷大学の学生が困惑することも多かったという。「日本の住宅密集地では、庭の植木が少し道路にはみ出ていることなんて珍しくありませんよね。そんな、私達にとっては当たり前の風景も、ドイツ人からすればまったく理解できないこと。また質問には明確な回答を求めてきますから、『下町っぽいね』なんて曖昧な返事では納得してもらえません。(龍谷大学の)学生達は、これまで考えもしなかったであろう日本の生活環境や文化をあらためて見直し、それを英語で必死に説明する場面が多く、それも良い学びになったと思います」(阿部准教授)
そして、3月には龍谷大学の学生がドルトムントを訪問。各都市を歩き、気づいた点を地図に描き込んで議論する日々が続いた。交通事情や移民問題など、10日間の滞在で数えきれないほどの現地事情を学んだ。
「学生達に感じてほしかったのは、日本とドイツの事情を分けて考えずに相対化すること。一つの都市で起きている現象は、世界中のどの都市でも起きる可能性がある。グローバルとローカルを柔軟にとらえるグローカルな視点が、一つ地方都市の問題解決につながるんです」

異文化コミュニケーションを専門とする村田教授は、このプロジェクトで最も印象に残った点に「母国語を使わずに議論をする利点」を挙げる。「龍谷大学の学生にとって良かったことは、相手も英語のノンネイティブだったことです。ドイツ人はとても英語が上手ですがネイティブではないので、同じノンネイティブを相手に伝わりやすく話し、一生懸命聞くことに慣れています。それが英語に苦手意識がある日本人にはとても相性が良かったんです」(村田教授)
しかし、最初からコミュニケーションが円滑だったわけではない。事前講義で英語を集中的に学んだものの、両大学の学生が京都で初めて顔をあわせたときには、龍谷大学生のほとんどがうまく話すことができなかったという。
「最初の1週間は通訳を通してなんとか会話している状態でしたね。でも、驚いたことに2週目頃から急にスイッチが入ったように、全員が日常会話から議論までをこなせるようになったんです」(村田教授)
その理由は、プロジェクト以外での交流だった。龍谷大学の学生達は学習以外の時間にドルトムント工科大学の学生を誘って観光やカラオケ、居酒屋などでともに過ごした。言葉がうまく伝わらなかった1週間、まずは友人として関係を育んでいたのだ。「ドイツ訪問時にも同じように、ドルトムント工科大学の学生達が街を案内してくれて、後半のワークショップでは、当たり前のように英語で議論が交わされていました。プログラム終了後にはドルトムント工科大学の教授から『うちの学生の英語力も上がりましたよ』とも言われました。英語は都市計画という課題に取り組むために必要なツールでしたが、学生達にはその習得プロセスでも多くの気づきがあったのではないでしょうか」(村田教授)
プロジェクトに参加した政策学部の大西妃歌さんと藤野里咲さん(ともに参加当時3年生)は、「ドイツ滞在はあらためて日本の街づくりを考えるきっかけになりました。自分の意見をうまく伝えられないときはもどかしかったですが」(大西さん)、「疑問に感じたことはすぐに質問する、主張はしっかり伝える。議論のあり方や視点の多様さを学んだことが、大きな経験になりました」(藤野さん)と振り返る。
このプロジェクトは、2014年度後期から「政策実践・探求演習B」として正式な科目となる。今後はドルトムント工科大学以外との協働学習も視野に入れ、より実践的な学びの機会としていく予定だ。
![]() 広報誌「龍谷」2014 No.78(Ryukoku University Digital Libraryへ)
広報誌「龍谷」2014 No.78(Ryukoku University Digital Libraryへ)

![]()
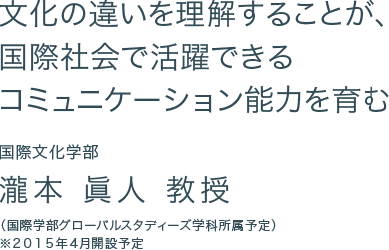

学生達が身振り手振りを交えて英語でメッセージを話す、その視線の先にはビデオカメラ。少し撮影してはビデオを止め、メッセージの内容や言葉選びをグループで話し合っては、またビデオカメラに向かう。
これは、瀧本ゼミが取り組むビデオプロジェクトのひとコマ。メルボルン大学(オーストラリア)と連携し、学生同士で定期的に交わしているビデオレポートの制作風景だ。
「私達は英語を、メルボルン大学側は日本語を学ぶ学生達が互いにテーマを設定し『母語ではない言葉でいかに自分の意見を伝えることができるか』を主題にビデオの制作をしているんです」と瀧本眞人教授は説明する。
制作したビデオはインターネットの動画サイトにアップロードして、メッセージ内容や言語の伝わりやすさなどについて意見交換しているという。
「テーマの設定から、リサーチ、撮影、編集などあまりに作業が多いため、このビデオプロジェクトはゼミの時間外におこなっているんです。つまり、学生達の自主性によって継続しているプロジェクトです。日本側のテーマは、『英語の支配、移民について』など、日本人の英語観や英語圏の文化を考えるものが多い。そこからさらにグループごとにテーマを設定し『日本人はなぜ英語に憧れるのか』といった具体的な問題について、自分達の言葉で伝えるようにしています。必要とあれば、学外へ出てアンケート調査をおこなうグループもあり、単なる国際交流にとどまらない学びの機会となっています」
このビデオプロジェクトをはじめとして、瀧本教授の講義には、単に言語学習にとどまらない実践的な内容が多く盛り込まれている。それは、20年以上を英語圏で過ごし、通訳者・翻訳者として活躍してきた瀧本教授自身の経験から生まれたものだ。
瀧本教授は、大学3年生の時に1年間の留学を経験し、大学院修了後は日本の民間企業に就職。充実した日々を過ごしつつも、「いつかは海外で働いてみたい」という漠然とした夢を持ち続けていたという。
「『ニュージーランドに新設される大学で教鞭を執らないか』と誘いがあったのは28歳の時でした。その大学では『国際関係論』を教えていましたが、海外で生活していると様々な場面で通訳や翻訳を頼まれることも多くなり、やがて本格的に通訳を学ぼうと考えるようになったんです」
ニュージーランドの大学を退職した瀧本教授は、オーストラリアのクイーンズランド大学大学院に入学。通訳・翻訳の手法や、異文化間コミュニケーションについて学び、卒業後はモナシュ大学の教員として後進の育成にあたった。また、大学教員として働くかたわら、通訳者・翻訳者としての仕事も多く経験。国際会議の同時通訳や政府発行書類の翻訳など、幅広い分野で活躍した。
瀧本教授の講義が机上の学びにとどまらず、コミュニケーションのあり方に重点を置いているのも、この豊富な実務経験に所以する。

「通訳・翻訳の世界には、明らかな誤訳はあっても、絶対的な正解はありません」と話す瀧本教授。
「学生達によく話すのは、『文章をそのまま訳すのではなく、その言葉に込められたメッセージを伝えなさい』ということ。単なる英文和訳・和文英訳ではなく、書き手と読み手のことをイメージして、最適な言葉を選ぶことが大切なのです」
それが「訳」と「翻訳」の違いだ、と瀧本教授は言う。プロの通訳者・翻訳者にも個性があり、それこそがコミュニケーションの妙だ。特に同時通訳のようにスピードが求められる場面では、臨機応変な意訳が必要となる。
「例えば、1950年代に翻訳出版された『ひとまねこざる』という絵本の原文には『スパゲティ』が登場しますが、翻訳者は当時の日本人の生活感覚を考慮して『うどん』と訳しました。わかりづらい言葉を、読者の文化内で同じ意味を持つ言葉に置き換える大切さを考える良い事例です」
翻訳の方法は時代や文化によって変わる。一言一句を正確に訳すことよりも、文脈の意味を損なわずに理解しやすい言葉に置き換える柔軟さは、優れた通訳者・翻訳者に必須の感覚だと瀧本教授は言う。
「そのためには、双方の文化を深く理解する必要があります。いくら自動翻訳ソフトの精度が上がっても、通訳者・翻訳者が社会から必要とされる理由はここにあるんです」
来年度、国際文化学部は、国際文化学科とグローバルスタディーズ学科から成る国際学部へと改組し、深草キャンパスへと拠点を移す。国際文化学部が培ってきた留学サポートなどの強みをさらに高め、より国際色豊かな学部へと生まれ変わる。特に新設するグローバルスタディーズ学科では、半年間以上の海外留学の必修化や、専門科目の約8割を「英語のみ」または「英語・日本語の併用」でおこなう(2年次以降)講義方針など、社会で通用する国際コミュニケーション能力を効果的に養う内容が盛り込まれている。
また、英語水準向上のため、TOEIC®730点以上をはじめ、所定の英語運用能力の修得が卒業要件となるのも大きな特色だ。これは現在、国際文化学部に在籍している学生には適用されないが、瀧本ゼミでは「後輩に負けたくない」と、全員が卒業時のTOEIC®730点をめざして邁進しているという。
「3年生から取り組むにはかなりハードルが高い目標なので、私からは『ゼミ全員で平均730点をめざしてはどうだろう』と提案しましたが、学生達は真剣な議論を経て、あえて高い目標に挑戦することを決めたんです。もちろん結果も大切ですが、その意識の高さがなによりも素晴らしいと感じました」
来年からスタートする国際学部の新しい学びが、国際文化学部生にとっても良い刺激となっている。それは、学生達が、卒業後に国際社会で活躍することをはっきりとイメージしているからだろう。
「外国語の習得は、自分の生き方を変えアイデンティティにも関わってくる。これから社会に羽ばたいていく学生達にとって、海外で教育者、通訳者・翻訳者として活動してきた私の生き方が、良きロールモデルになればうれしいですね」
![]() 広報誌「龍谷」2014 No.78(Ryukoku University Digital Libraryへ)
広報誌「龍谷」2014 No.78(Ryukoku University Digital Libraryへ)