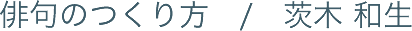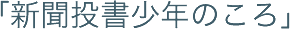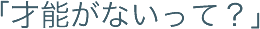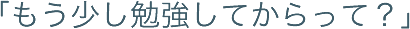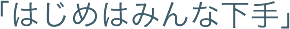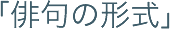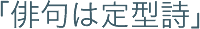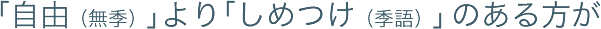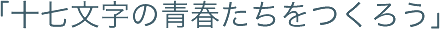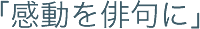![]()
- HOME
- > 俳句のつくり方
私が俳句を作ろうと思ったのは、購読していた「朝日新聞」の奈良版に、右城暮石選による「朝日大和俳壇」が創設されたからでした。誘われて、奈良県立郡山高等学校の文芸部に入部してまもなくの、昭和29年の晩秋のころでした。
葉書に三句書いて投句した中の一句、〈落葉焚く煙真上にたちのぼる〉が新聞に掲載された朝の感激を今も忘れることができません。「俺の俳句が新聞に出てる」といって見せると、「ほんまか、うれしいことやなあ、葉書くらいなんぼでも買うたるから、続けて出しや、それで高校時代の思い出ができたらこしたことないがな」と一番喜んでくれたのが母親でした。続けて投句するといっても、俳句は五・七・五で詠む、季語を用いるということを知っている程度でしたし、現代俳句といっても教科書に出てきた作品を知っている程度でした。
投句をはじめて半年ほどして、〈夏蜜柑色さえすぎし場末の店〉という句が巻頭になり、「この蜜柑は顔が歪むほど酸っぱいに違いない」という選評も載せられて、「見てみィ、俺の句がトップや」と文芸部員に見せてまわった日のことを覚えています。
俳句をはじめてみませんかと誘ったとき、返ってくることばで一番多いのは、「私は才能がありませんから」という返事です。そんなとき、私は「雪だるまづくり」の話をします。
いくら積雪量が多くても、雪をまるめ、転がしていくことをしない限り、雪だるまは仕上がりません。うっすらとしか雪が積もっていなくても、雪の玉をつくって転がしているうちに、たとえ枯れ芝まじりであっても雪だるまはできてきます。雪を才能に、雪だるまを俳句に置き換えてみますと、いくら才能があっても俳句を作ることをしなければ、作品を残すことはできません。才能がわずかしかないと仮定しても、俳句を作ろうと努めることによって、作品が生まれてくるのです。
とにかく、まず作ることです、と話をします。俳句を作らないうちから、俳句を作る才能がない、素質がないなどと決めつけてしまっては、自分がかわいそうです。
次に多いのが、「ことばも季語も知りませんし、もう少し勉強してからにします」という返事です。そんなとき私は、どうしたら泳げるようになるか、「水泳入門」の話をします。
もう少し勉強してから、というのは、下手な泳ぎでは格好が悪いから、と畳の上で形を整えてから泳ぎはじめるというのと同じです。いくら畳の上で、泳ぎの形がよくなっても水に浮くことすらできません。まず水に入ることをしなければ、絶対に泳げるようにはなりません。水に入ること、すなわち俳句を作りはじめること、そして作り出して、その中で勉強をしていくのです、と話をします。さらに、こう語り継いでいきます。
私が俳句をはじめたのは高校一年生ですし、ひとり新聞俳壇への投句がそのはじまりですから、自分に才能があるとか、ないとか、そんなことを思ってみたこともありませんでした。自分の見たもの、思ったことを五・七・五の調べにのせて作る、それだけを考えていました。今も、才能があるとも素質があるとも思っていませんが、とにかく俳句をつくる道を選んだ自分のために、自分の俳句を作ろう、向上していこう、と思っているだけです。
ことばだって季語だって、十五歳だったのですから、そんなに豊富ではなかったはずです。奈良盆地の小さな町に住んでいましたし、歳時記も容易に手に入れることのできない時代でした。それでも季節のことば?季語?を、例えば、一月・二月は季語だ、桜・菜の花が、鰯・鮎が、とんぼ・兜虫が、西瓜・トマトが、寒し・暖かが、雪・雷が、入学・卒業が、四月馬鹿が、クリスマスが・・・季語だとヒントを送れば、三、四百の季語を現代の高校生でも書いてしまいます。私もせいぜいその程度であったと思います。私が作句をはじめたころを思い出してこう語れば、私は才能がないから、私はことばや季語を知らないからといって、俳句を作りはじめることにためらいを持つ人はいなくなったと思います。何よりも、俳句の道を選んだのは私だ、私は自分のために俳句を作るのだ、という覚悟を持つことによって、ものの見方も捉え方も変わってきますし、ことばを、季語を吸収する力もついてくるのです。
これは高齢者の俳句のすすめかもしれない、と思っておられるかもしれません。しかし、私は中学生にも、高校生にも俳句の道に入って欲しいという思いをもっています。中学生、高校生に俳句の実作をすすめ、これまで彼らの作った作品を三十万句以上も見ています。
私が地方版の新聞俳壇に投句をはじめたのは高校一年生の時ですが、中学生時代から俳句を作りはじめて、俳句を作る喜びを知り、句作を継続していったならば、私を追い越す作家がつぎつぎと生まれてくるにちがいありません。そんなことも期待しています。
私は作句をはじめてから一年半ほどの間、朝日新聞大和俳壇に投句して、選を受けるということを続けました。当時は俳句の入門書を手に入れることもできず、現代のように『俳句年鑑』や『俳句研究年鑑』といったものもなく、どんな結社誌があるのかも知りませんでした。
幸いなことに新聞俳壇の選者だった右城暮石先生が、「運河」という主宰誌を創刊され、その結社に入会しました。句会に出て、たとえ表現が拙くても生活感の存在する作品を大切にしたいという話を聞き、「高校生なんだから、勉学するという生活を大事にしないといい作品は生まれませんよ」といわれたことが今も強く印象に残っています。
そのころ、文芸部員で学校図書館にあった文学全集の中の一巻、『現代短歌・現代俳句集』をテキストにして俳句を読んでいました。読みはじめていって、すっと胸に飛び込んでくる作品の多かった作家が西東三鬼でした。そのにこやかな顔写真も私たちに語りかけているように思え、俺たちの句をこの人に評してもらおう、と私が言い出し、手紙を書き、文芸部誌の「若竹」も送りました。すると、まず、返事の来たことに大感激でした。そして、「現在の大家でも、元はみなへたで幼稚であったのです」ということばに、よし、やるぞ、と励まされました。私は俳句を作ろうとしている人に出会ったとき、この三鬼のことばを思い出して、「はじめはみなへた」ということを呪文のように語っています。
俳句入門には、特別な資格もいりませんし、年齢制限もありません。ことばも季語もいま使っている、知っていることばを動員して、俳句を作ればいいのです。そして、「はじめはみなへた」と思えば、自信をもって俳句の道に入っていけるに違いありません。さあ、自分のために、自分の俳句を作る出発をしましょう。
俳句をはじめようと決意したら、「五・七・五、十七音の調べにのせて、季語を用いながら、とにかく俳句を作ることです」と説いてきました。こういって、過去、中学生、高校生に俳句をつくるようにすすめて、いや、宿題というかたちで作らせてきました。
ところがある時、「『五・七・五で作れ』『夏休みの宿題だから夏の季語を用いて作れ』というのはしめつけ教育だ。もっと自由に俳句を作りたい」という声があがりました。
そこで、定型、季語を入れるというしめつけをはずして、自由に作りなさいといったら、「逆に自由といわれるとかえって難しかった」「なんや知らん、自然と五・七・五のしらべにのせようと思っている」という声が返ってきました。
いま、中学校、高等学校の国語の教科書に現代俳句としてどんな作品が掲載されているか紹介します。
桐一葉日当りながら落ちにけり
海に出て木枯帰るところなし
滝落ちて群青世界とどろけり
少年の見遣るは少女鳥雲に
霜の墓抱き起こされしとき見たり
かなしめば鵙金色の日を負ひ
鳥わたるこきこきこきと缶切れば
白葱のひかりの棒をいま刻む
約束の寒の土筆を煮て下さい
水枕ガバリと寒い海がある
彎曲し火傷し爆心地のマラソン
曳かれる牛が辻でずっと見廻した秋空だ
鉄鉢の中へも霰
陽へ病む
高浜虚子
山口誓子
水原秋櫻子
中村草田男
石田波郷
来加藤楸邨
秋元不死男
黒田杏子
川端茅舎
西東三鬼
金子兜太
河東碧梧桐
種田山頭火
大橋裸木
これらは六冊ほどの教科書から抽出したのですが、いろんな傾向の作品があります。しかし、圧倒的に多く掲載されているのは、五・七・五、十七音という定型で詠み、一句の中に季語を読み込んだ作品です。さらに文語表現をとっている作品です。
高浜虚子の〈桐一葉〉という作品から黒田杏子さんの〈白葱の〉までの作品がそれですが、伝統俳句といわれているものです。
次の川端茅舎と西東三鬼の作品は、五・七・五、十七音という調べにのせ「土筆(つくし)」「寒い」という季語を詠み込んでいますが、虚子などの作品とちがって、口語表現となっています。
金子兜太氏の作品をみると、五・七・五、十七音という定型の調べに素直にのせるのではなくて、口ずさめばわかるように、定型と抗おうとして定型の側にとどまり、存在の強さを表そうとしています。
河東碧梧桐、種田山頭火、大橋裸木の作品は、定型ではない、自由律俳句といわれるものです。山頭火の句には、「霰(あられ)」という季語がありますが、季語を意識したものではなく、体験し、感動したものとしてのその存在を鮮やかに描いています。表現型式が定型ではなく非定型、即ち自由律なのですから、口語表現をとっています。
これまで採り上げてきた作品を整理してみますと、有季定型俳句、無季定型俳句、自由律俳句とに分けることができます。
相撲の土俵の大きさ、卓球台の大きさ、テニスコートの大きさも、その直径が、縦・横の長さが決められ、ネットの高さも決められているから、競技として成り立っているのです。決められた大きさをいっぱいに使い、さまざまな術を駆使して戦うから、緊張感も高まり、競技をしている者も充実感を覚え、見ている者も感動をするのです。
俳句も五・七・五、十七音という定型を思う存分に使って表現することで、作品が引き締まり、いきいきとして、作者も「やったぁ」という充足感を持ち、読者にも「いい作品だなぁ」と感動を与えるのです。
中学生、高校生に俳句は定型詩であると説き、定型を守って俳句させているもう一つのねらいは、文語表現に慣れることによって、少しでも古典文学作品の理解を深めるのに役立つのではと思っているからです。
文語表現はもう変化することのない表現ですから、俳句の定型は文語表現を要求していると考えているからです。文語表現が俳句をはじめようとする人の妨げになっているということも聞きますが、好き嫌いは別として、ほとんどの人が学校で古典文学を学び、文語表現を少しは身体に覚え込んでいるのですから、「だれのためでもない、自分のために俳句をはじめよう」と思ったのですから、それを呼び覚ましてほしいものです。
俳句は五・七・五、十七音の定型詩である。この器を使って勝負、と思って出発してください。
各季語は俳句のいのちであると思っている私は、中学生、高校生にもちろん俳句をはじめようという成人の方にも定型を重んじることとともに、一句の中に季語を入れて俳句を作ることをすすめています。
一句の中に季語を入れる、これも定型と同じように約束ごとと思って、有季の作品をつくることからはじめてください。できれば一冊だけ歳時記を買い求めて、夏の季節なら夏の季語の項を拾い読みする形ででも読んでください。心をとらえてくれる季語に出会うにちがいありません。俳句をはじめようと思っている人、俳句をはじめて間もない人にこれを書いているのですから、有季定型の俳句をしっかり作ろう、と訴えているのです。
いずれ無季俳句の世界へ歩を踏み入れるのも自由ですが、まずは、有季定型俳句と取り組んで力をつけることです。
生徒たちに、次の時間から俳句の授業に入ります、俳句も作ってもらいます、というと、「エッー、おじんくさい」ということばがきまって返ってきます。これまで十句と読んだことのない、一句も作ったことのない俳句に対して、「年寄りくさいもの」という先入観を持っています。
ところが、若さを主張する彼らがはじめて作った俳句がなんとも「年寄りくさい」のです。もう三十年以上も前でしょうか、私がふきだしたものですから、職員室で話題になった「作品」があります。〈寒い日はこたつにあたって蜜柑食べ〉というのですが、同じような内容のものがいくつもでてきたのです。それ以降、中学生の「年寄俳句」の見本として笑いながら語るのですが、はじめて俳句を作らせると、その十年後も、いまも似たり寄ったりの作品が並びます。
「先生、オーバーに言ってるでしょう」との声があがりましたので、十三人の名前入りで、〈正月はこたつに入りみかん食う〉〈寒いのでこたつに入りみかん食う〉〈十二月こたつ入ってみかん食べ〉〈テレビを見こたつに入りみかん食う〉〈テレビつけ炬燵に入り蜜柑食う〉といった「作品」を示したことさえあります。なるほど、中学生らしい若さの感じられる句だ、とこれではいうことができませんね。そこで、私の青春時代の作品を示します。
オーバーの胸雪まみれ逢ひに行く
和生
そして、「どんな場面を詠んでいるかわかるやろ」といいますと、「いまの嫁さんとのデート」と生徒たちは眼をかがやかせてきます。「いや、ちがう」といって笑い、「意外と若さを主張することができるやろう」といい、こんな作品も示します。
さくらんぼ好き買うて来し妻が好き
渡辺杜公
すると、「わぁ、のろけや」とよくわかっています。こんな句を知ったあとの生徒たちの作品は目に見えてかわってきます。
寄りそって落葉の道を歩きけり嶽
校舎裏恋うちあけて卒業す
タンポポの花占いの好きと出て
光博
寺嶋良弥
大杉友顕
もちろんこれらの俳句は作品集を作ったとき、とにかく何もいえない、窮屈な器だと思われる俳句でも、こんな世界が詠めるのです、と書いてほめたたえました。そして、中学生、高校生の生活の中から、十七文字の青春たちをつくろう、と呼びかけています。
俳句は自然のものに、人間とその暮らしに触発された感動を詠い上げる詩です。俳句をつくる時は、五感をフルに使うことと、と自分に言い聞かせています。「視覚」、「聴覚」、「嗅覚」、「触覚」、「味覚」。これらの五感を通して受けた感動をことばに託してみましょう。
芭蕉も「見るに有、聞くにあり、作者感るや句と成る」といい、「物の見えたるひかり、いまだ心に消えざる中に云ひとむべし」といっています。咲き満ちた桜を見て、ああ美しいなあと思ったり、時鳥の渡ってくるころ、少し郊外に出て鳴き声を聴き、心をゆさぶられたら、その感動を俳句にしてみてください。