2024.09.27
【法学部企画広報学生スタッフLeD’s】丹羽 徹先生インタビュー
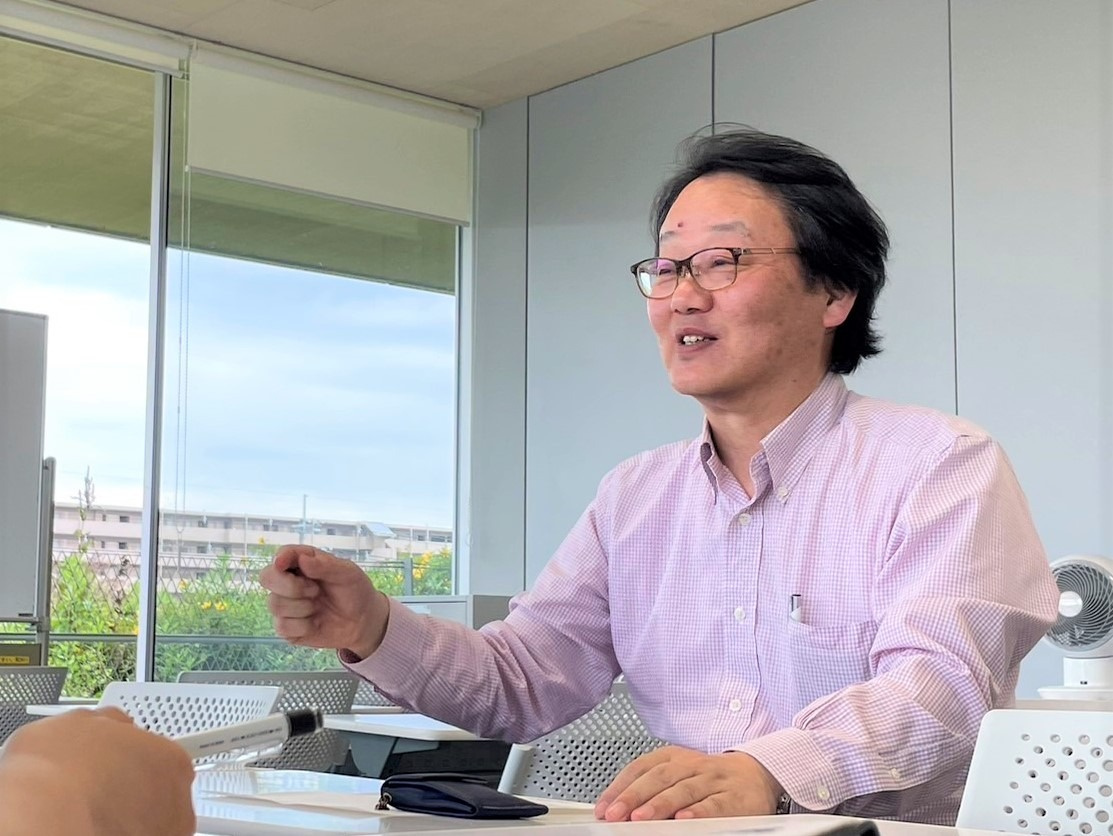
1.丹羽先生ってどんな人?
Q1.どのような経緯で法学部に入学されたのでしょうか?
皆さん方は高校2年生ぐらいで文系理系で分かれたと思うんだけど、当時、僕が通っていた高校は高校3年生で文系・理系とかに分かれていました。文系でも国公立か私学とか受験科目によって少しずつ違っていたので、それで分かれていました。法学部に行こうかなと思ってたんだけど、実はちょっと迷ったところがあって‥。成績をみると完全な理系人間なんですけど、興味のある学部がなかったので、文系に決めました。
理屈・論理を考えるの嫌いではなかったんです。数学は得意でした。数学って法学部の学生にとっては必要な科目で、って言うと嫌な顔する学生がいっぱいいるんですけど、絶対的に必要なんです。計算ではなく、いわゆる証明問題。論理的に理屈で考えていくってのは好きだったので、それができるところが法学部かなと思って、法学部を目指すということにしました。その後も色々紆余曲折はあるんですけどね。
Q2.学生時代は、どのような大学生活を送っていましたか?
言うほどのことは何もしてないです。
家庭教師のアルバイトを週に2日か3日かなやって、 あとはテニスのサークルをやってたので2週間に1回ぐらいそれをやり、時々図書館にも行っていました。 あと何してたかな‥。ずっと友達となんか喋ってたかな。そんな感じの生活をしていました。あとは、3年生とか4年生ぐらいかになって、友達と飲みに行くっていうところですね。
当時、バブルの走りの時期だったので、恩恵は受けてないんですけど‥。まだ学生だったし、その後大学院に行くんですけど、その時がちょうどバブルの時期だったんです。だから最もバブルの恩恵を受けない人っていうか、バブルによって色んなものが高くなっていったりしたんで、損害を受けた人なんだけど‥。まだ走り頃ってそうでもなかったんで。その頃ね、日本酒が流行ってたんですよ。で、飲みやすい日本酒がやたら出てきた。多分ね、吟醸酒とかがものすごく多く出てきたような、色んな種類が出てきた、そういう時代でした。
3年生の途中ぐらいから大学院生とかと色んなことをしていました。今でもやってるんですけど今で言うと、社会活動みたいな市民運動をずっとやってきてるんで、そういうものを一方でやりながら学生時代は過ごしていました。
入学当初は司法試験を受けようと思っていたんです。法学部に行ったんだから司法試験かなという風に思っていて、弁護士にもなろうかなっていう気持ちもあったんです。せっかく法学部に来たんだから、1回ぐらい司法試験受けてみようという感じで。司法試験、受験料高いのに記念受験として、1回だけ受けたんです。だけど、「この試験、自分には絶対合わない」と思ったんです。なんでかというと、まず短答式から始まるから答えが必ずあるんですよ。要するにこれが正しい、ここは間違ってるっていうのがあるじゃないですか。で、微妙に違ってても、こっちがより正しいっていうのが正解になるじゃない。そういうのが嫌だったんですよ。 だから、絶対に合わないなと思って、1回受けただけでやめました。その後は司法試験を受ける気は全くなくなった。あとは、3年生の途中ぐらいから大学院生とか一緒にいろんなことをしてたんで、研究者という道もありかなと思った。
僕ね、学部のゼミが 3回生と4回生のゼミなんだけど、僕が受けてたゼミは大学院生も一緒だったんですよ。 英語の原書を読むっていうので。3年生の時は大学院生の方が多かったというゼミだったんですよ。学部生2人で大学院生6人ぐらいいるっていう、そういうゼミだった。4年生になったら、さすがにそれはひっくり返ったんだけど。だから、そういうところで大学院生とかと一緒にやってたっていうこともあって。で、それで、そういう道もありかなと。
Q3.学生時代の先生にとって大学とはどんな場所でしたか?
また、大学生生活を送る上で先生が重視していたことはありますか?
あんまりないですね‥。その理由は簡単で、例えば、今だったら就職のためとかって言えるじゃない。なんせ僕は就職活動したことがない人なんです。皆さん必死になって自分から就職活動するじゃないですか。バブルだったので、向こうから来たから。当時は携帯がない時代なんで電話がかかってくる、あるいはゼミの OBがゼミに来て「来ない?」っていう風に言うっていうようなことが一般的だったんです。
これ言うと今の学生は、ものすごい腹立つかも‥(笑)。 例えばね、今は就職試験を受けに行くってあるじゃないですか。当時はまず、先輩と会うってことから始めるんですね。だから就活の方法が今とは全然違うんです。資料請求なんてほとんどする必要がないんですよ。向こうから送ってくるから。
例えば、先輩と会って飯食いに連れてってもらってね。それで、その気になった人は、 例えば東京本社だったら、東京へ面接とか試験受けに行くじゃないですか。今は皆さん自腹ですよね。当時は交通費、日当までもらえたんですよ。すごい賢い学生は連続して東京の会社の面接を入れるんですよ。就職試験の面接とか試験だから、学生は「うちに来ます。」って面接毎に言いますよね。だから、同日に同じ地域の面接を複数個受けても全部交通費、日当が貰えるんですよね。そういう時代だったので。だから、就職活動で一生懸命やってるっていう雰囲気が大学全体の空間としてあんまりなかった。そういう時代なんで、公務員になるのもあんまり人気がなかったんですよ。大体公務員ってね、景気悪い時が人気あるんですよ。僕も一応公務員は受けたんですよ。親との関係で。どうなるか分からない様な世界なんで、研究者ってのは。 一応受けて、一応合格したんです。行かなかったんだけど。だから、司法試験もあんまり人気なかったんですよ。そんな状況だったらわざわざ苦労してまでそんな試験の勉強する必要ないじゃん。だから、同級生は公務員も少なかったですね。でも、 公務員でも地方から来てる人は県庁とかが結構多かったのかな。だから、地元で就職したいって人が県庁を受けるっていうのは何人かいたけれども、それ以外ってあんまりなくて、今に比べると少なかったです。あと司法試験を受けて、弁護士やってる同級生ってほとんどいないんだよ。記念受験してる人もあんまりいなかったと思う。今から40年ぐらい前で1万円ですから。そう簡単に受けられる試験ではない。だから、何回も何回も受けられる試験ではないので。
だから、そういう空間の中にいたのでのんびりしてましたよ。
あと、1学年、160人だったんで。160人プラス社会人で入ってきた人が10人ぐらいいたかな。今でもそうなんだけど、国立大学ってすごい1学年の人数少ないんですよ。多分ね、東大京大で今300数十人、それが1番多くて、それ以外は大体150人から250人ぐらいが一学年でいますね。
法学部ですから、卒論を書く必要もないし。のんびりと過ごしてましたよ、学生時代。だから、やっぱ今と全然時代が違うから、学生生活で何してたかって言われると、 サークル活動、一生懸命やった人はいるんだろうけど‥。別に、さっき言ったみたいに、2週間に1回ぐらい友達同士っていうか、7、8人のサークルだったんで、テニスコート1面借りてちょうどいいぐらいじゃないと。サークルだからさ、大学のテニスコートを使えるわけじゃないから。で、誰かが、どっかのテニスクラブの会員かなんかになっててそれで、連れて行かれたっていう‥。
質問者:公務員の方も受けられて合格したけど、行かなかった理由はありますか?
丹羽先生:大学院に行こうと思ってたから。
いい成績で、ほとんど勉強しなかった。だって、行く気ないからさ。
行く気ないから、そんな一生懸命勉強する気もないしさ。で、なおかつ勉強しなくていいところを受けたからね。受ける時。
Q4. 教員紹介のホームページをより、子どもの権利に関心を抱かれたのは管理教育として有名なところで学校生活を送られていたことからと拝見しました。具体的に学校生活のどのような場面で、子どもの権利について関心を抱かれたのでしょうか?
また、同ホームページより子どもの権利の対象となるのは民法、少年法、社会保障法などの法分野にかぎらず、教育学などの近接学問分野にも視野を広げる必要があると拝見しました。子どもの権利は様々な分野と関わりがある中で、先生が憲法を専門分野に選ばれたきっかけはありますでしょうか?
生まれも育ちも愛知県で、 皆さんはあんまり聞いたことがないのかもしれませんけど、日本全国で管理教育で有名な県っていくつかあって、東の千葉、西の愛知って言われたんですよ。あと四国の方に行くと、愛媛県もそうなんだけど、そういうところで育ったので、なんていうか、その頃から自覚的に何かあったってわけじゃないんだけど、なんとなく雰囲気として、なんか少し息苦しいところがあるかなっていう風に思っていました。今でも、高校生って政治活動しちゃいけないっていう、文科省の通知があるじゃないですか。1970年ぐらいの学園紛争の時、文科省が出した通知があって、それが生きていて最近18歳成人になった時にも、高校生が選挙権を持つんだからって話になったんだけど、文科省の通知は相変わらず高校生が政治活動するのは望ましくないっていうのが出ていて。で、とりわけ、学校側あるいは教育委員会側からすると、学園紛争の時の経験があるので、学校内が荒れるのを極力嫌がったっていう。本当はね、抑圧するから荒れるんだけど‥イタチごっこなんですよ、あれは。それで、愛知県はずっとそれが生きていたのは、三校禁っていうルールがあって、3つの学校を禁止するって書くんだよ、三校禁って。要するに、 3つの学校、3つ以上の学校の人たちが集まって何かをするっていうことを基本的には認めないんです。公式にやるんだったらいいんだけど、自分たちの自主的な活動でそういうことをするのは認めないっていうのがあって、別にそれ自体はこちらがなんかしようとしてそれを禁止されたってわけじゃないんだけど、やっぱそういうのっておかしいんじゃないかっていうのがあったんですよね。
で、僕行ってた高校は周りが田んぼの田舎にあったんです。高校の選択は、学校群制度ができたころで、二つの学校をひとくくりにして、合格者はいずれかの学校に自分の希望とは関係無く振り分けられる。それは学校の平準化のために考えられた制度でした。僕が行ったところは、地域の有名進学校ともう1個の学校っていうので塊が作られていたんですよ。結局、家から遠い方の田舎の学校に振り分けられてしまった。そうだからかどうかはわからないけど、のんびりしていました。割と自由に気ままになんかしてたっていう高校生でした。
高校時代はそういう生活をしてたんだけど、やっぱり周り見るとなんかおかしい状況があったんです。管理教育するのに1番便利なのは、競争させることなんですよね。要するに 分断するんですよ。競争させるってのは結局分断することなんで。だから進学率をやたら上げたがるっていう。特に僕が高校生になった頃って今とは全然違っていて、高校8クラスだったかな、中学校9クラスだった。でも、それでも学校数が足りなくて新しい高校できる。その学校を地域の中で選んでもらえる学校にしなきゃいけないからっていうんで、何に力入れるかっていうと、進学に力入れるわけですよ。そうすると、ある学校は、朝の0時限から夕方7時限まで授業がある。学校が朝7時台から始まって7時間目までやっても19時には多分ならないと思うんだけど、そういうようなことをやって競争させるっていうことをやっていた。おかしいでしょ、それって。あと、なんでそれをするのかっていうと、結局、進学率高める、進学率高めるのも私学じゃなくて、やっぱり国公立の数増やすっていうのが、愛知県って田舎なんで保守的なんでね、官尊民卑ってのがあるんですよ。そうすると、国公立大学にどれだけ行けたかっていうのは勝負になるので、学校の先生もすごいえぐいことやったんですよ。国公立大学だったらどこでもいいって。だから、進路指導がそういう指導になるんですよ。
こういう学校で起きてる理不尽なことを見ていて、それで関心を持った。で、特に政治活動とかってのもそうだし、それから、「君が代日の丸」やっぱり問題だと思ってましたよ。
君が代日の丸歌わされたし、僕はちゃんと君が代の歌詞は書けるんですけど。僕が在学中に国旗掲揚塔ができたんですよ。学校の門を入ってすぐの建物、職員室とかの建物の屋上に国旗掲揚塔ができたんですよね。運動会とかする時の掲揚とは別にあるんですよ。それはグラウンドの方にあるんですよ。で、県教委からそういうのを揚げろっていう指示が来てて、それで作ったみたいなんだけど。「国旗、大切にしましょう」みたいなこと言っときながらさ、あげっぱなし。24時間、雨の日も風の日もずっとあげっぱなし。ここでもおかしいだろうって思うこといっぱいありました。国旗掲揚塔は1番南側の建物の上に立っていたんですよ。で、そうなるとどうなるかっていうと、午後になって風が強い日に、ちょうどその旗がはためいた時に教室に影ができる。パタパタと影が映ってさ、授業の邪魔になるっていう。
ある意味不合理なことってのはいっぱいあるなってことが分かって、その不合理さをどうにかしようと思ったというのが研究者になろうと思ったっていうことと、憲法を選んだっていうことの理由ですよ。
質問者:先程、冒頭で話されていた息苦しいところっていうのはどういうところでしょうか?
丹羽先生:理屈に合わないことがいっぱいあるなと思うところですね。
質問者:管理教育っていうのは、生徒を管理しないながら進学率を伸ばそうとしてるような教育を指すっていう認識で合っていますか?
丹羽先生:子供たちを管理する、要するにそれは変な話だけど、悪いことしないようにっていう。その学校の先生から言うとですよ、悪いことしないようにってことですよ。進学率をあげるというのはその手段ですね。だから、それは受験の方に目を向けさせて、それでそれだけやってればいいっていうようなことですよ。
Q5.先生が過去に憲法の研究を続けていく際に、その途中で心が折れそうになった出来事、経験などはありましたでしょうか?
そんなもんしょっちゅうじゃない?これも大学院の時の話なんだけど。大学院によって大学院の有り様が少しずつ違っているので、私がいたところはって話なんだけど、簡単に言うと、修士論文を書く時に皆で寄ってたかって書かせるわけですよ。要するに溜まってもらったら困るからって。学年を順番に上がっていってもらって、出ていってもらわなきゃ困るから。なるべく学年の下の方で溜まらないようにしたいわけですよ。だから修士論文も2年で書けっていうのが基本で、後輩に迷惑がかかるからっていっていうプレッシャーをかけられながらやっていたっていうので、ちょっとしんどいところがやっぱりあったなっていうのと、もう1つも同じようなことなんだけど、博士課程3年が終わって、その後、今はそういう制度がなくなってるんだけど、助手になるっていう制度があって、その時に、論文がないと助手にはなれないので、論文を書けっていうのが、至上命題なんですよ。ほぼできてたんだけど、最後のところでどうしても納得できないなっていう部分があって、どうしようかなって思ったんだけど、書けと言われて、書きましたけど。それはね、やっぱりね、本当にどうしようかなって思いましたね。出さないって選択肢もないわけじゃないなと。最後、出しましたけど。だから、そこで心折れそうになったんだけど、折らせてもらえなかった。
あとはね、ずっと心折れそうになってるのが1個あって、ずっとやりたいことがあるんだけれど、自分がやりたいことだけできるわけじゃないんですよ。就職しちゃうと、特に。原稿を頼まれたりすることがあるので、そっちの方でずっと時間を取られていて、もう20年ぐらい僕は子どもの権利の歴史研究をずっとやりたいと思ってるんだけど、そのために本を何冊も買って持ってるんだけど、それができてないっていうので、だからそれを、やれるかなって気持ちにはなったかな。でも、それはやろうと思ってるんだけど。これやりたいなと思ってる時に他の仕事がちょっと入ってくると、心折れますよ。
Q6.休日は何をして過ごされていますか?
何もしません。基本的に何もしないっていうのが休日なので。でもなかなかね、純粋に休日ってなくて、頼まれた原稿書かなきゃいけないとか、それを休日だっていうんだったら、そういうこともしているんだけど。そういうのを一切無視すると、休日何してるかっていうと、何もしない。もちろん日常的な買い物とか、どこかに行かなきゃいけないとかそういう日常のことはしますけど、特に休みだからといって何かをするっていうことは基本的にない。逆に、何かをするために休みにするってことはあるけど。バレエとかオペラを見に行くっていうことをしているので。それは東京にでも行きますから。休日の過ごし方としてはそういうのかなって。あとは、1週間とか2週間で海外に行っている。休日で海外に行くっていう。仕事で行くんじゃなくて。でも実際全く仕事しないわけじゃないんですよ。でも、休みでいった方が自由なことができるので。だから向こうに行って、コンサートとかオペラとかに行ったりするっていうこともしてるんだけど、この5年間行ってないので、ちょっとそれがストレスになっている。今年の冬ぐらいには行こうかなって。ちょっと安い飛行機のチケット出ないかなと思ってる。
質問者:教員紹介のホームページに冬のパリが好きっていうのもここの海外にっていうところに繋がるんですかね。
丹羽先生:そうそう、だから割と年末年始にパリにいることが多かった。5年前に行ったのも12月だったんで。夏休みがなかなか行けないんだよね。飛行機代高いしね。冬は微妙なタイミングで行くと安いんですよ。で、年末の20日過ぎの行ける1番早い時期に行って、12月31日か1月1日に向こうを出発してくる便で帰ってくる。そうすると飛行機代が安い。1日の便で帰ってくるのが1番いいかもしれない。一応、年越しができるので。パリにいると花火も上がるし。エッフェル塔の後ろからね。
2.丹羽ゼミってどんなゼミ?
Q1.最近のゼミでの活動をお聞きしたいです。
ゼミの活動そんな特徴的なことしてなくて。ここ1年2年ぐらいは教科書を分担させて、内容を紹介して、あと指定している教科書が何年か前の本なんで、新しい情報をそこに加えて報告をしてもらって、それに基づいて討論をするっていう。人数少なくて半分ぐらい雑談になるんだけどね。
質問者:どのような雑談をされるんですか?
丹羽先生:本当に純粋に雑談ってあんまりなくて。今子どものことやってるから。それこそ、さっき言ってた昔の自分の高校時代の話とか少子化対策の話とか、「最近のあれだよね、あんなの全然役に立たないよな」って話とかね。そういう話の方が盛り上がります。だから、報告してもらうっていうのと、あとはもう基本的にはゼミ生がやりたいことをやるっていうことにしているので、ゼミ生の募集かける時に枠組みだけは決まっているので、そこから大きく外れなければ何やってもいい。
質問者:課外活動などはどのようなことをされていますか?
丹羽先生:本当、学生がなんか言ってくるまでは何もしないので。だから飲み会もしたいって言わないとしない。
質問者:過去には学生の方々はどのようなことを企画されていたんですか?
丹羽先生:いや、龍谷にきてからはほとんどやってない。
前任校ではいろんなことをやりました。最高裁判所も行きましたよ。普段、例えば地裁とか高裁って見学がすぐにできるんですね。でも最高裁ってやっぱハードルが高くて、大学として行くっていう感じになるんです。だから、申し込みもちゃんと事前申し込みが必要になります。で、その代わり向こうは全部付いてくれるんですよ。で、最高裁は法廷が開いている日は見学できないんです。その代わり、大法廷とか小法廷とか全部見れますよ。裁判官が並んでるあの席も見られますよ。写真は撮ってはいけないんですけどね。海外に行くと別に平気なんだけどね。韓国の憲法裁判所に行った時、みんなで裁判官の席に座って記念写真撮った。ヨーロッパ人権裁判所もみんなで横になって写真を撮りました。
質問者:ゼミの強みや魅力など、何か先生がこれだなって思うような所はありますか?
丹羽先生:問題設定から全部自分でやらせるので、基本的には。組み立てをしていくっていうことができるようにはなるかな。与えられたテーマではなくて、テーマそのものを自分で考えさせるから。
Q2.どのような学生にゼミに来てもらいたいと考えていらっしゃいますか。
また、学生にゼミでどのようなことを学び、習得してもらいたいと考えられていますか。
特にない。特にないんだけど、1時間ずっと黙ってる人は嫌だな。ずっと黙ってて一言も喋らない。報告をする時は喋るけれど、それ以外は一切喋らないっていうのだけはやめてほしい。あと、普段から物事を考えてない人も嫌だな。
それ以外だったら別に誰でも来てもらって大丈夫だけど、一応テーマ設定してあるので、 それに強い関心を持って積極的にそのことに取り組んでくれるっていうのが一般的には一番いいのかなって思いますね。
あと、僕のゼミは基本的に卒論書いてもらいたい。
3.学生に向けて
Q1.学生へのメッセージをお願いします。
難しいね、そういうのってね。うーん、常に現状に満足しないこと。現状に満足をしない学生になってほしいです。
40年か50年ぐらい前だったら「変革の主体になれ」っていうのかもしれないけど。現状に満足することは、進歩しないっていうことですから。本人だけじゃなくて、社会そのものも進歩しないので。今の学生ってそういうとこあるじゃない。なんか現状肯定的で。いくつか理由があると思うんですけど‥。今、経済的に厳しいって言うんだけど、例えば40年、50年前、もっと前から比較すれば圧倒的に経済的な条件って整ってるじゃないですか。確かに貧困層はいるけど、本当に生活できない人の絶対数はそのころと比べれば減ってるんですよ。要するに生き死にに関わるような貧困っていうのは減ってたりするし、住環境も昔に比べれば良くなってるので。文句言わなければそれなりの生活ができるという状況は、実はある程度作られてるんですよね。でも、結局それに満足していた結果、だんだんそういう生活ができなくなってる人が増え始めているわけで。だからなんでそうなるかって言ったら、何もしないからですよ。だから、現状に満足をしないっていうことは、心の中で腹立たしく思うだけではなくて、それをどうにかしようと思ってほしいという含意があるので、常に社会が進歩するような行動をしてほしい。
だから、そのために何をしなきゃいけないかって言ったら1つは勉強しろってことなんだ、やっぱり。勉強すれば課題も見えてくる。それといろんな経験した方がいいですよ。だから海外に行けばいいと思うんだけど、昔はなかなか行くの大変だった。僕だって学生時代に海外に行ってないんだよね。飛行機代高かったから。卒業旅行に海外に行くのもあんまりいなかった。僕、大学院に行くってことで卒業旅行もしなかった。
でも、知らないところに行くって良いかもしれない。皆さんも行ってください。留学までしなくていいので。
質問者:先生がパリなど海外に行かれる理由っていうのもこのような意図があるのでしょうか。
丹羽先生:まあ、研究材料を探しに行くっていうのが一応建前ではあるんだけど。だから、 わざわざ休みで行くっていうのも1つ兼ねていくんだけど。基本的には国外逃亡だね。だから「向こうに行ったらこっちのもんだ!!」っていうのがあるじゃない。普段とは違う時間の流れの中で生きていられるっていうので、のんびりできるっていうのがある。今から25年前かな、1年間いたんだけれど、その頃っていうのは、向こうに行ったら 基本的には連絡は来ない。国際電話も高いし、インターネットがそれほど普及してるわけでもないし、インターネットって言ったって、メールとかのやり取りができなくはないんだけど。電話回線でやってたからもう受信したらすぐ切るっていう、そういうようなことをやったんで、ほとんど向こうに行ったら何の連絡も来なくなるみたいな。国外逃亡っていうのはこういうところですね。
最近ダメだよね。オンラインで会議もできる、それはダメだと思う。時間軸が少し変わるので、 非日常を楽しめるよね。日本にいたら非日常っていってもやっぱり時間軸そんな変わんないし、携帯ですぐ電話かかってくるじゃない。
Q2.高校生へのメッセージお願いします。
昔だったらね、進路に迷ったらとりあえず法学部ってのがあった。でも今そういうわけじゃないから。法律って学んでて損はないんだよね。世の中を法というプリズムで見るということができるというのは非常に社会にとって重要。経済学部とか他のところってさ、そういうプリズムがないんだよね。プリズムがないっていうか、要するに枠組みがない。例えば、経済をどうやって見るかって、人によって、先生によって全部違う。なんでかって、枠組みがないから。法学部は法という枠組みがあって、その枠そのものを疑問に思うということができるっていうのと、枠組みがあるからその枠の中で物事を考えられるっていう2つのことができるっていうのは法学の特徴なので、社会をそういう2つの側面から眺めることができるというのは、将来のこと考えた時にも非常に役に立つ。元々は就職とか考えず気にせず学ぶというのが大学の役割なんで。最近、本読んでてさ、大学と学校は違うって述べてるんだよね。最近の大学は学校になってるから。学校って、要するに、ある知識を教えるところなんだよ。大学はそうじゃないはずなのに、所謂学校の部分がでっかくなってきているんだよね。
枠組みの中を議論するのが、昔の法学部、ヨーロッパの近世とかにできた医学、法学、神学とかのあれの中の1つはそういう枠組みを学ぶ。枠組みを学んで、法律の専門家になる。昔の法学部、狭い意味での法学部っていうのは昔はあった。専門家養成の為の法学部っていうのは、そういう側面があったから。法律の専門家を養成するところは法学部だから職業と直結している。
でも大学なんだから、大学としての法学部っていうのはそういう部分も確かにあるけれども、枠そのものをどう考えるかってことも含めて議論したり枠の作り方も含めて考えるっていうようなこともやれるのが大学だから。例えば、高校生なんかで、今の学校の校則っておかしいよねって思ってる人は法学部に来る素養がありますよ。校則っていう枠組みがあるじゃないですか。 校則という枠組みがあるから、それを前提に行動するじゃないですか。でも今ある校則そのものがおかしいと思ってるんだったら、このおかしいと思うこの枠組みを考え直そうということができるはずなので。そういうことしたい人には法学部はいいと思いますよ。こういう枠組みは色々ありますよ。例えば、なんで、歩行者は右側を歩かないといけないんだとかね。そういうことを今の時点で考えてる高校生とかはぜひ法学部に。
【インタビューを終えて】
お忙しいにも関わらずインタビューを喜んでお受けして下さり、心より御礼申し上げます。インタビュー当日はとても緊張しておりましたが、先生が優しく受け答えして下さったおかげで緊張も解れ、こちら側から事前にお送りさせて頂いた質問以外にも質問をする事ができ、とても楽しくインタビューをすることができました。また、先生の学部生時代のことや院生時代のことなど、普段講義を受けているだけでは知ることができない先生のことをこのインタビューを通して読者の皆様も知ることができたのではないでしょうか?
「憲法分野に興味がある」「子どもの権利について勉強してみたい」という方はぜひ丹羽ゼミへ!
自分の可能性は無限。You, Unlimited.次回のインタビューも、乞うご期待。
【取材・記事】
隅田知里 (法学部3回生)
井上詩緒里(法学部2回生)
山中いろは(法学部2回生)


