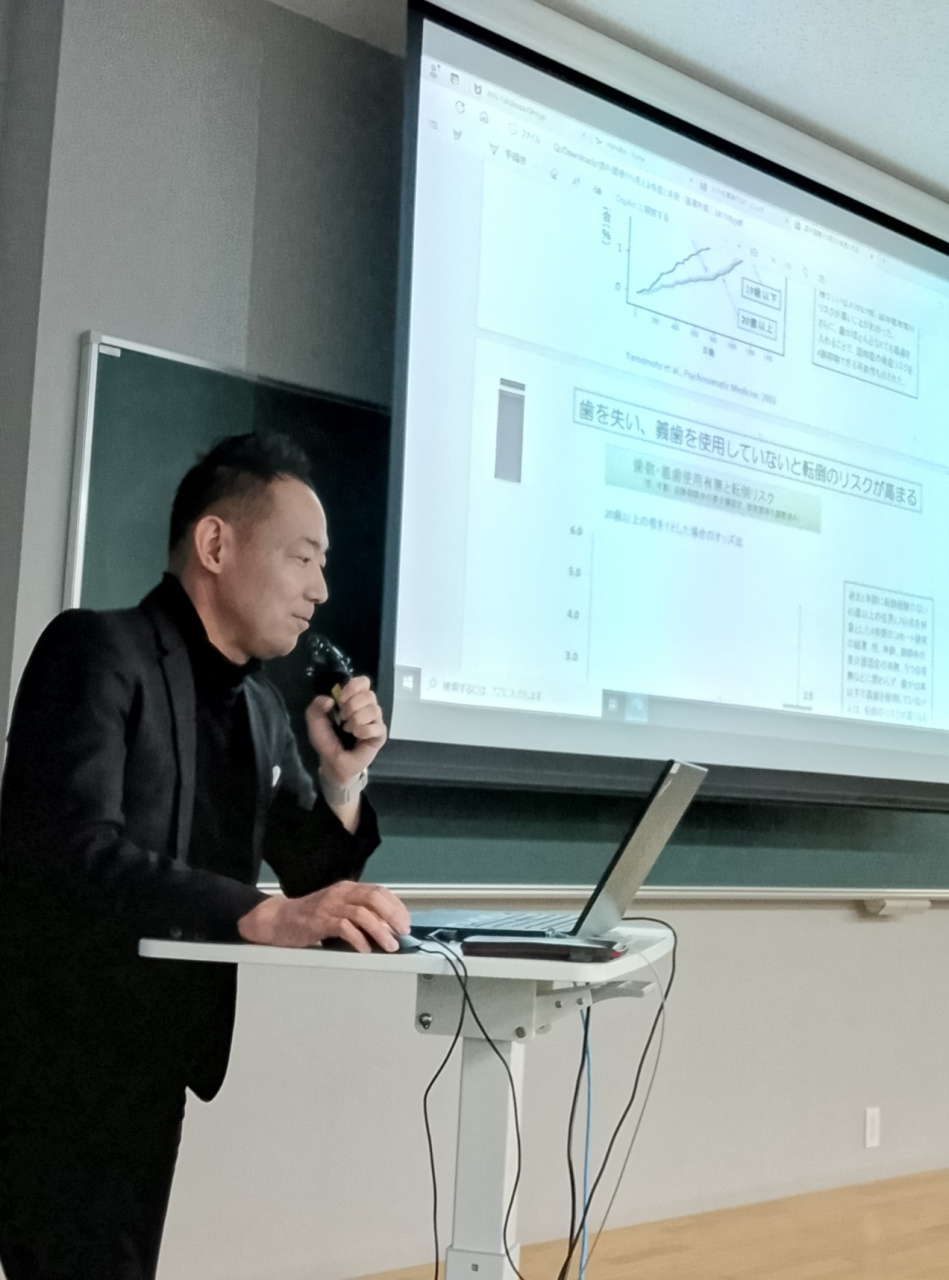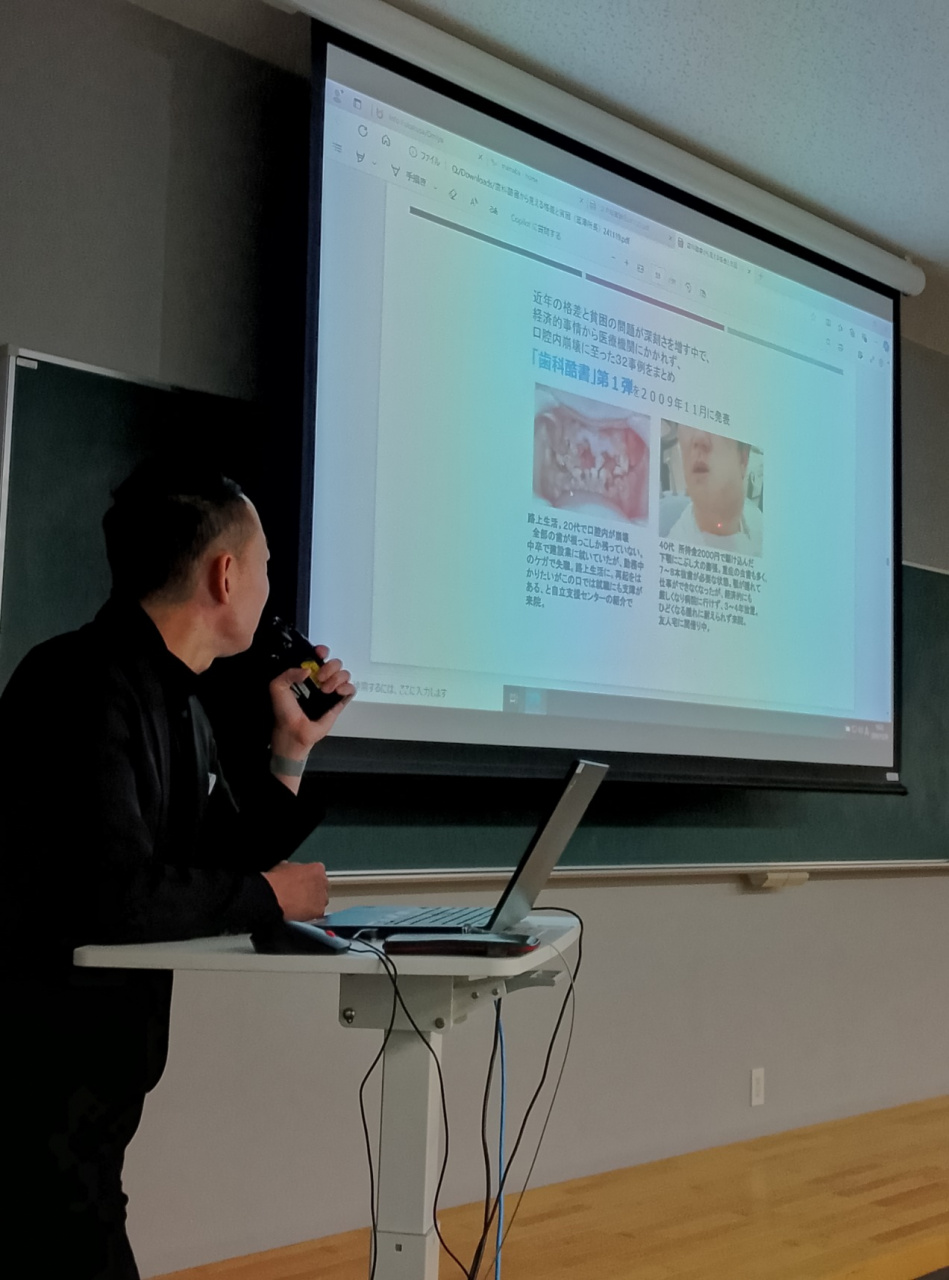2024.12.10
「公共経営論」で、冨澤洪基氏(尼崎医療生協・生協歯科所長)にご講演いただきました
経営学部開講科目である「公共経営論」では、昨年に引き続いて保健医療福祉の生活協同組合(医療福祉生協)について取り上げています。
11月29日、現役の歯科医師である冨澤洪基さん(尼崎医療生協・生協歯科所長)をお招きした講演がありました。
「総入れ歯ではファーストフードのハンバーガーが食べられるか?」
健常者の噛む力を「10」とすれば、総入れ歯の人の噛む力は「2」程度。だから80歳を超えてファーストフードでハンバーガーを食べている高齢者がいるとすれば、それはしっかり噛む力を持って食べているとか。
近年、お口をきれいにしておくことが、内科疾患や認知症にも関連するという研究報告があり、高齢になっても自分の歯でしっかり栄養が取れる人は健康状態も良く、「歯の本数が少ない人は友達も少ない」…などの最新の研究のお話もありました。
こうした最新の歯科・口腔衛生に関する知見の紹介をしながら、健康の社会的決定要因(SDH)についての詳しいお話となりました。その人の置かれる社会的背景をしっかり捉えることは、単に「甘いものばかり食べてはダメ」「もうちょっとしっかり歯磨きしないといけません」というだけの対応ではいけない。それよりもその人が「なぜ甘いものを食べなければならなくなったのか」「なぜ歯磨きすることができないのか」という社会的経済的背景を考える視点がないと解決の方向も見出せないこともお話でありました。
最後に、最大の健康の社会的決定要因は「平和」との指摘がありました。
1935年~1945年の平均寿命は男性が43歳、女性が44歳でした。これは戦争が寿命を短くさせてしまったものでした。戦後、高度経済成長を経て今日に至って、日本は戦争をすることなく男性81歳、女性88歳の平均寿命となりました。今日のウクライナやガザでの戦争は健康を害するものであるとの指摘は、平和は健康にもつながる大切なものであることがわかりました。
現役の歯科医師から医療のあり方、経営のあり方を聞く貴重な機会となりました。
(文責:岸本貴士)