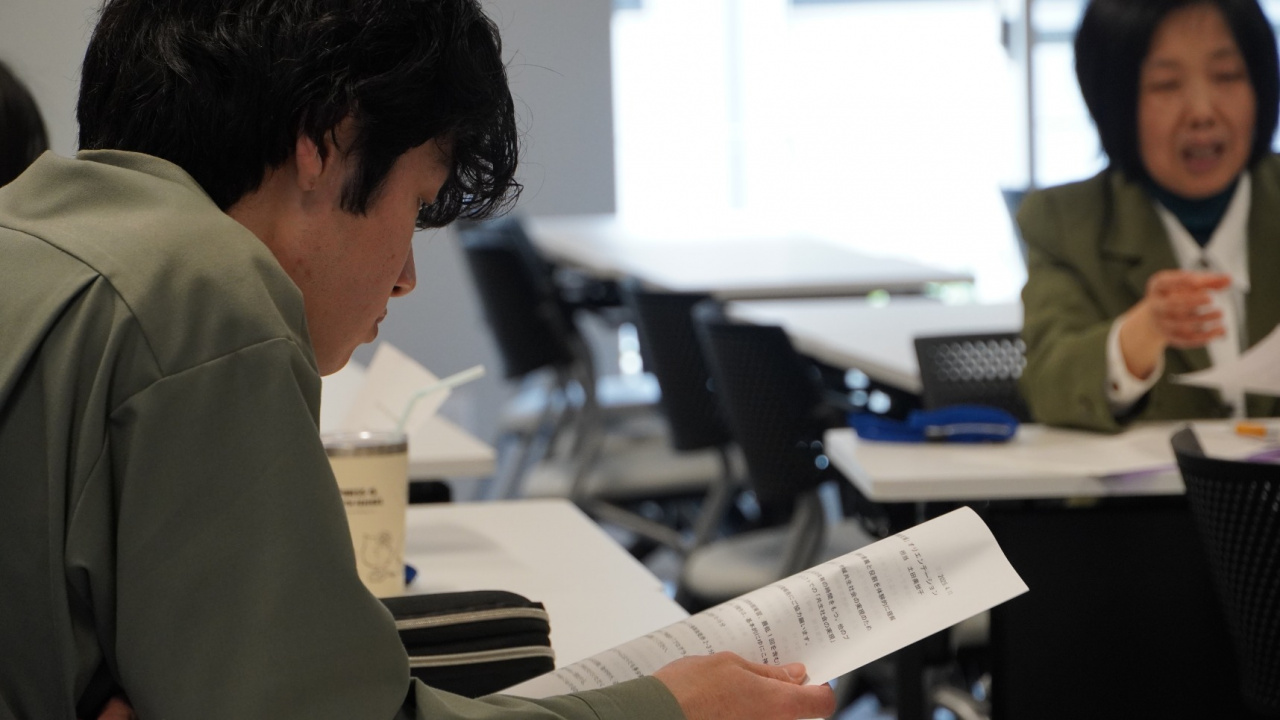2025.04.14
2025年度の【社会共生実習】が始動しました
「社会共生実習」とは、リアルな現場で考え、地域や世界の課題と向き合う社会学部の現場主義を体現する中核となる実習科目です。
本実習では、学生たちが学外のさまざまな連携機関と協働して、社会の諸問題に対する理解を現場の中で深めて行動していくことを重視し、教員がそれぞれの専門知識やフィールド、人的ネットワークを生かしたオリジナルのプロジェクトを提供します。
今年度は以下5つのプロジェクトが活動します。
1.地域エンパワねっと・大津中央(担当教員:脇田健一教授)
大津市の中心市街地にある中央学区の住民の皆さまとのコラボを通じて、地域活性化に取り組みます。課題を地域住民とともに学生自身が見つけ出し、その課題解決に向けて活動します。
2.農福連携で地域をつなぐー「地域で誰もがいきいきと暮らせる共生社会に向けて」(担当教員:坂本清彦教授)
障がい者、高齢者、生活困窮者らが農業と携わる「農福連携」を通じて、多様な人々が地域社会とつながり、いきいきと暮らせる社会の実現に向けた課題発見、解決のための企画・実践をめざします。

過去の活動の様子
3.お寺の可能性を引き出そう!―社会におけるお寺の役割を考えるー(担当教員:猪瀬優理教授・古莊匡義教授)
いまお寺では、仏教の関わりのない人も参画して、地域の居場所やつながりをつくる活動が行われています。そうしたお寺の社会活動に参加しながら、地域におけるお寺の役割と可能性を考えます。
4.障がいがある子どもたちの放課後支援(担当教員:土田美代子教授)
放課後等のデイサービスでの活動を通じて、障がいがある子どもとの具体的な関わり方、放課後支援の意義を学び、障がいがある人と共に生きる社会について考えます。
5.コミュニティの情報発信!レク龍プロジェクト(担当教員:久保和之教授)
滋賀県レクリエーション協会の広報活動について、広報誌の編集発行作業・ホームページの管理運営などの仕組みや内容を学ぶとともに、現状の問題点を探り、解決に向けて企画・運営していきます。
4/11(金)に行われた初回授業では、各プロジェクトで自己紹介やアイスブレイク、年間スケジュールの確認などがなされました。受講生らが活動する中で、お互いを尊重しつつより良い関係を構築してくれることを願っています。
次週からさっそく学外活動を予定しているプロジェクトもあるので、各プロジェクトの活動の様子を追っていこうと思います。
社会学部「社会共生実習」について、詳しくはこちらの【専用ページ】をご覧ください。