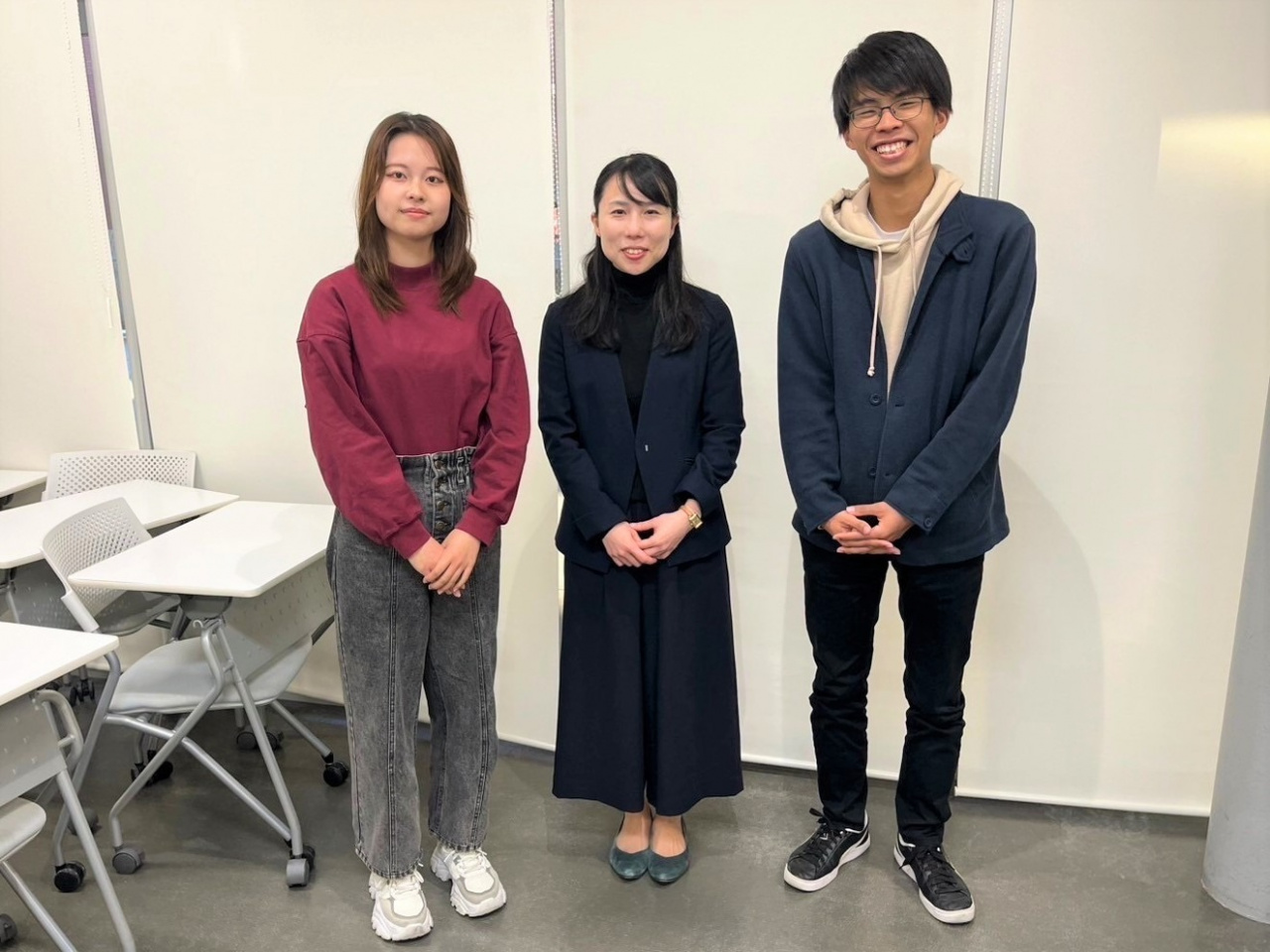2025.04.18
【法学部企画広報学生スタッフLeD’s】永岩 慧子先生インタビュー

Q1.どのような経緯で法学部に入学されたのでしょうか?
もともとは法曹になれたら良いなということをなんとなく考えていましたが、そこまで明確な将来の進路をイメージしていたわけではありません。法学部は色々な進路に開かれているので、入ってから考えても良いかなと思い、法学部を選びました。
Q2.民法を学ぶきっかけは何ですか。
法学部に入学後、あまりまだ法学のおもしろさが分からないなと思っていた頃に、民法の授業の中で、のちに指導教員となる先生が「民法は常識で考えればわかる」とおっしゃっていたことがとても印象的だったんです。この言葉をきっかけに法律を身近に感じられるようになり、3年次のゼミ選択の際に、民法ゼミを選びました。
また、法の社会での役割について考える機会となったのは、大学院生の頃、東日本大震災の被災地に民法ゼミの活動としてボランティアに行ったことです。現地の方々から法律に関わるさまざまな困りごとやトラブルについてお話を伺い、そこでも民法という法律の大切さを実感しました。
Q3.学生の頃行っていたバイトやサークルは何ですか。
法律を一緒に勉強するようなサークルに一応所属していました。ロースクール希望者が比較的多く集まっていて、私自身はあまり真面目に参加していませんでしたが、みんなで問題を解くなどといった活動をしていました。
アルバイトは、塾の講師や大学内の情報センターの受付業務などを行っていました。
Q4.先生のご趣味は何ですか。
趣味らしい趣味はありませんが、食べることが好きなので、出張先などの美味しいものやお酒を調べたりして、楽しみにしています。また、気分転換に散歩をするのも好きです。京都は歩いて楽しい場所が色々とあると思うのですが、今のところあまり出かけられていません。
Q5.先生が専攻されている民法の面白さや魅力を教えてください。
契約自由の原則や私的自治の原則という言葉を聞いたことがあると思いますが、私人間のルールである民法は、その基本的なスタンスとして、国家が作った法律で人々の社会生活関係までを規律しようとするのではなく、平等な個人と個人は、自由な意思でお互いの社会生活関係を自律的に作っていくべきだという考えをとっています。つまり、その取引を行う当事者が自分たちの意思でルールを作れば、そちらを優先させようということです。そのうえで、民法は、もしそこで合意がない場合にはどうなるかということや、自由といってもこれはダメですよ、といったふうに、みんなが納得できるルールを定めています。多様な価値観をもつ立場の人がともに暮らし、めまぐるしく変化する社会において、そこに妥当する望ましいルールは何かを探ることは容易ではありませんが、現実に生じている紛争解決だけではなく、将来の社会においてどうあるべきか、ということを考える過程におもしろさを感じます。民法に限らないお話ですが、歴史学、心理学などなど幅広い知見を総動員して考えることも必要です。そういった日々の生活でのあらゆることが学びにつながる点に魅力があると思っています。
Q6.学生が民法を学ぶ際に意識してほしいことや気を付けてほしいことはありますか。
こちらも民法に限らない答えになりますが、最近は、わからないことがあればすぐにインターネットや生成AIなどのツールを使って調べることができます。こういったもので調べると、一応の答えというのは入手できますが、思考停止に陥りがちな危険性もはらんでいると思います。学生の皆さんには、なぜこのような法律があるのか、どのような場面で役に立つのかということを、一度、自分自身で考えてみてほしいです。法律がこうなっている、ということをただ知るだけではなく、自分が納得できるかどうかということは、とても大事だと思います。最近では、誰かがこう言っている、ということについて、疑問なく受け入れてしまいがちな傾向があるような気がしています。他人の意見を受け入れることも大事だとは思いますが、自分の中の違和感を大切にしてほしいなとやはり思います。例えば、皆さんの世代の感覚として、「このルールっておかしくない?」と思うことは当然にあって良いことです。自分の思考を止めないことが重要で、それはおそらく、民法だとやりやすい場面もあるのではないかと思っています。
Q7.先生のゼミでは、今具体的にどのような活動をされていますか?
現在は演習Ⅰが始まったばかりなので、民法の主要な論点をいくつかピックアップして、それに関しての事例研究や判例研究ということを中心に行っています。判例研究については、まずは判例を読むために必要な基礎知識を調べましょう、ということをやっています。ゼミ生が先生役をやるようなイメージで、「ここに関しての知識はこういうものですよ」という説明をしてもらい、教員から説明を加えたうえで、それを踏まえて判例を読んでみるという形式です。
2年生の後期では、取り上げる論点について、すでに学んだ範囲からある程度ピックアップしていますが、今後は各自の興味関心があるものを選んでもらう予定です。あとは、最終的に論文を書くということで、調査報告や引用の仕方といったことも一緒に行っています。現在は少人数のゼミですが、もう少し人数が多ければ、ディベートなどの練習もやりたいなと思っています。今のところゼミのイベントとかは特に決めていないので、他のゼミと比べて特色はあまりないかと思いますが、ゼミ生の関心に応じて進めていこうと考えています。
Q8.先生のゼミの特徴や強みは何ですか?
今のところこれといった特徴を挙げることは難しいですが、とにかく学生主体で議論をしてもらいたいと考えています。時々、口を出したくなりますが、そこは控えて、まずは自由に議論してもらいたいと思っています。最近は、あまり人前で話すことが得意じゃないという学生さんが少なくありません。私自身も、法学部ではそういった議論の機会があると聞いて、大学入学前はとても嫌だなと思っていました。なので、話しやすい雰囲気づくりや環境づくりということは、常に心がけています。だから全然怖くないですよ(笑)。あとは、やはり民法は身近な法律ということで、皆さん自身がどう思うかということが大事なので、気づいたことを何でも言ってもらって、その視点おもしろいね、とみんなで色々考えてみたりとか、そういうことができたらいいなと思っています。
ゼミの強みについては、そういった議論をしたり、人の意見を聞く姿勢だったりとか自分の意見をちゃんと言えるというような力は、どんな世界でも役に立つと思うので、そういうものを身につけてもらえたらと考えています。
Q9.どのような学生にゼミに来てほしいですか、またどのような学生向けのゼミですか?
こちらから「このような学生に来てほしい」ということはありません。参加学生のこれまでの傾向として、民法が得意だから民法ゼミという人もいないわけではありませんが、むしろ「民法が苦手だから克服しようと思って民法ゼミを選んだ」という学生も少なくないです。民法に苦手意識を持っている人がいれば、そういった方にも来ていただけると、私としては嬉しいです。講義の中だと十分に伝えきれなかったことなどから、実際にこういう場面でこのルールが機能しているんだな、という実感がゼミを通じて湧いたらいいなと思っています。あとは、資格試験などで民法が必要なものも多いので、そういった具体的な進路との関係がある方にも、もちろんお勧めできると思います。
【インタビューを終えて】
お忙しい中快くインタビューを引き受けてくださり、ありがとうございました。インタビュー当日は、緊張していたのですが、優しく朗らかにお話ししてくださったおかげで、緊張も解け、楽しくインタビューをすることができました。
このインタビュー記事が皆さんのゼミ選択、学校選択のお役に立てれば幸いに思います。
自分の可能性は無限。You,Unlimited.次回のインタビューも、ご期待ください
【取材・記事】
法学部学生広報スタッフLeD’s
中川 波音(法学部2回生)
平ノ上 美羽(法学部1回生)
八木 菜摘(法学部1回生)