2025.10.02
低・未利用魚である雄の鮒から滋賀の新名物を ―鮒寿司メーカー・農学部学生らと共に考案した「フナズシクッキー」を国スポ・障スポで試食提供―
【本件のポイント】
- 従来は活用が限られていた琵琶湖のニゴロブナの雄を用い、滋賀県の伝統的な発酵食品である「鮒寿司」をアレンジ。地域資源を活かした新たな商品開発に挑戦中。
- 大学・企業・学生が協働し、世界農業遺産に認定された滋賀県独自の農林水産業の営み「琵琶湖システム」を次世代に継承する取り組みを実践。
- この秋、滋賀県で開催される国スポ・障スポ会場で来場者に試食提供を実施。フィードバックを受け、今後は食品の機能性についても研究を推進予定。
【本件の概要】
龍谷大学 発酵醸造食品機能性研究センター(1)の研究メンバー、農学部食品栄養学科の学生、鮒寿司メーカーの奥村佃煮が連携し、低・未利用魚であるニゴロブナの雄を活用した「フナズシクッキー」を新たに考案しました。本品は、2025年10月に滋賀県彦根市で開催される「第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会(愛称:わたSHIGA輝く国スポ・障スポ2025)」の各閉会式の会場内「おもてなSHIGAエリア」内のブースにて、来場者に試食提供します。
【参考イメージ】

写真左:研究で使用した雄のニゴロブナ

写真右:フナズシクッキーの試作品
【開発の背景】
滋賀県の郷土食「鮒寿司」は、琵琶湖の固有種・ニゴロブナを使った乳酸発酵食品で、特に卵を抱えた雌(子持ち鮒寿司)は珍味として有名です。一方、雄は価値が低く、利用される機会が限られてきました。また鮒寿司は、滋賀県の伝統的な発酵食品であるものの、若年層を中心に喫食率の低下が報告されています。
しかし、雄の鮒寿司は卵を持たない分、身に旨味が凝縮されており、噛むほどに滋味が広がる特長があることから、奥村佃煮ではこれまでもニゴロブナの雄を使った鮒寿司にチーズを加え長期の乳酸発酵を行った新商品開発などに挑戦してきました。
こうした低・未利用魚を「おいしく食べられる商品」に加工することで需要を創出し、琵琶湖の水産業や水産加工品業に新たな可能性をもたらせるのではないかと考え、本プロジェクトが始動しました。
【開発プロセス】
実施にあたって、奥村佃煮が滋賀県の令和7年度『世界農業遺産「琵琶湖システム」地域活動支援事業補助金』の助成を受け、2025年6月〜2026年3月にかけて企画・開発および試食を通じた市場調査を行い、製品化をめざします。
「フナズシクッキー」試作品の考案にあたっては、龍谷大学 発酵醸造食品機能性研究センターの田邊公一教授(本学農学部)と柿崎博美博士研究員、(株)奥村佃煮 代表取締役の奥村吉男氏が参画。また、本学農学部食品栄養学科(田邊ゼミ)において、学生の感性と柔軟な発想によるアイデアを募集。本学農学部食品栄養学科4年生の宿谷紗良さんが特別研究の一環としてレシピ検討を重ね、“おいしくて、若い方でも口にしやすい”普及性を考慮した「クッキー」の形にたどり着きました。
今回の国スポ・障スポでの試食提供をはじめ、2025年度中に試食・フィードバックを重ね、最終的には市販・流通を目標とします。滋賀ならではの食文化を手軽に楽しめる商品として、土産物やギフトなど幅広いシーンでの展開が期待されます。
【滋賀国スポ・障スポ2025での出店予定】
1. 国スポ・総合閉会式「おもてなSHIGAエリア」
日時:2025年10月8日(水)9:00〜14:00
会場:彦根総合スポーツ公園(滋賀県彦根市松原町3028)
2. 障スポ・閉会式「おもてなSHIGAエリア」
日時:2025年10月27日(月)9:00〜17:00
会場:同上
備考:
- 両日ともに「おもてなSHIGAエリア」内の「琵琶湖と共生する滋賀の農林推進協議会」(事務局:滋賀県 農政水産部 農政課)ブースにて出店。同ブースでは、「琵琶湖システム」(2)にかかる広報・啓発を行う予定。
- 各日ともに提供予定数に達ししだい終了する見込み。
【補足】
(1)龍谷大学 発酵醸造食品機能性研究センター
滋賀県の発酵醸造産業を支援することをめざして2021年度に開設。発酵醸造に有用な微生物の収集とデータベースの構築、およびそれらを活用した応用研究の展開を目的として研究活動を展開している。2021-2023年度は発酵醸造微生物リソース研究センターの名称で活動し、2024年度より現在の名称に改称。「微生物の有用機能を介した発酵醸造学とスポーツ栄養学の融合とマネジメントによる滋賀県域における応用展開」をテーマに、研究体制を拡充して、より学際的に研究を推進している。
https://hakko.ryukoku.ac.jp/
(2)琵琶湖システム

「琵琶湖システム」とは、日本最大の湖・琵琶湖とその周辺の森・川・水田・湖が有機的につながった農林水産業の営みを指す。湖魚が水田やヨシ帯に産卵する生態を活かした伝統漁法「エリ漁」や、森林や農業と共生する暮らしが千年以上続いてきた歴史のある滋賀県。こうした資源にやさしい循環型の仕組みは高く評価され、2022年にFAO(国連食糧農業機関)から世界農業遺産に認定。現在は漁業者・農業者・林業者に加え、消費者、NPO、研究機関、企業など多様な主体が保全活動に参画している。
https://www.pref.shiga.lg.jp/biwako-system/ (滋賀県 農政水産部 農政課)
【企画・開発担当者コメント】
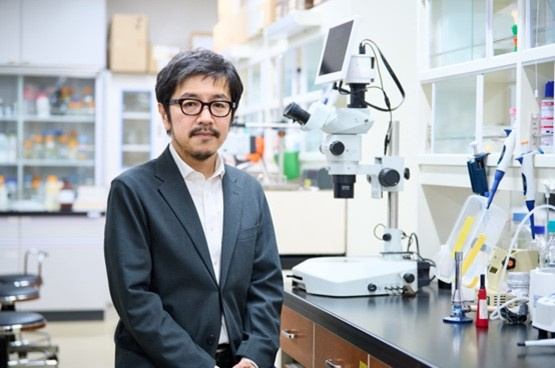
田邊 公一 教授(本学農学部・発酵醸造食品機能性研究センター兼任研究員)
/専門:応用微生物学
滋賀県の伝統的な発酵食品である鮒寿司は、琵琶湖固有種のニゴロブナをご飯と共に丸ごと漬け込み、乳酸発酵させて作られます。乳酸菌には腸内環境を整える作用があり、近年では、腸内環境を整えることが持久力の向上につながる可能性も報告されています。国スポ・障スポの会場で、鮒寿司の新しい食べ方をアスリートの皆さんに体験していただきたいと思います。
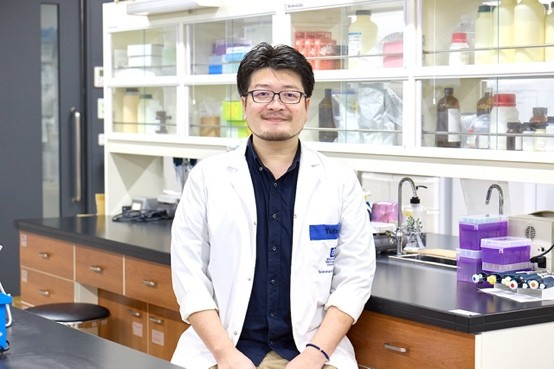
柿崎 博美 氏(本学発酵醸造食品機能性研究センター博士研究員)
/専門:生物資源学、食品利用学、食品機能性評価
滋賀の伝統食である鮒寿司は、長らく雄の活用が課題でした。今回、企業や学生と連携し、低・未利用だったニゴロブナの雄を使った「フナズシクッキー」を開発できたことは、持続可能な食資源利用やSDGsの観点からも大きな意義があります。今後は、発酵食品の健康機能やアスリートの栄養補給への応用も視野に、地域の食文化を未来につなぐ新しい提案を続けていきたいと考えています。

宿谷 紗良 さん(本学農学部食品栄養学科4回生)
相可高校食物調理科および本学食品栄養学科での実習経験を生かし、どなたにも食べやすい形をめざしました。鮒寿司の独特の風味を残しつつ、初めて口にする方にも手に取りやすい“お菓子”にすることは大きな挑戦でした。滋賀国スポ・障スポ2025「おもてなSHIGAエリア」ブースには、ゼミの仲間と共に参加予定で、皆さんの試食の反応を楽しみにしています。

奥村 吉男 氏(株式会社奥村佃煮 代表取締役)
鮒寿司は長い歴史を持つ滋賀の味覚ですが、雌に比べて雄はなかなか日の目を見る機会がありませんでした。研究者や学生の皆さんの発想力と研究を通じて、雄の鮒にも新しい可能性を見いだせたことをうれしく思います。地域の食文化を次世代につなげ、商品化に向けて実現性を高めていきたいと考えています。
本件の取材を希望される場合は、下記の問い合せ先までご連絡ください。
問い合わせ先:龍谷大学 研究部(発酵醸造食品機能性研究センター)
Tel 075-645-2154 E-mail hakko-rc@ad.ryukoku.ac.jp https://hakko.ryukoku.ac.jp/