2021.01.24
【新型コロナ現象について語る犯罪学者のフォーラム】12/28オンライン・フォーラム実施レポート
「コロナ禍と罪に問われた・罪をおかした高齢者・障がい者」をテーマにオンライン・フォーラムを実施
2020年12月28日、龍谷大学犯罪学研究センターは第25回「CrimRC(犯罪学研究センター)研究会」をオンライン上で開催し、約50名が参加した。
【イベント概要>>】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-6715.html
犯罪学研究センターは、2020年4月下旬より、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19、以下新型コロナ)の拡大によって浮き彫りとなった個人と国家の関係や、ウィズ・コロナ時代における社会の在り方について、犯罪学の視点から考えるフォーラムをWEB上で立ち上げ、情報発信を行ってきた。
https://sites.google.com/view/crimrc-covid19/
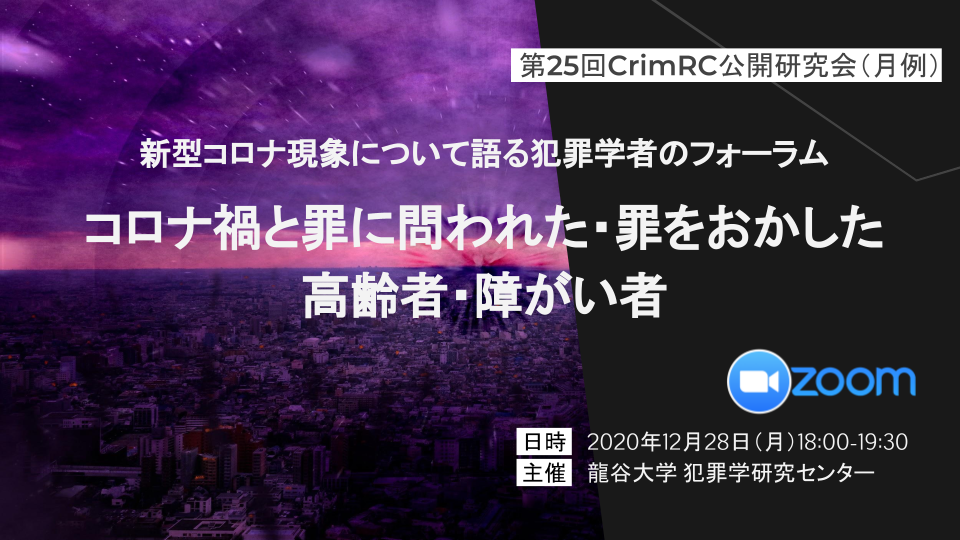
趣旨説明
石塚 伸一 教授(本学法学部・犯罪学研究センター長)
これまで犯罪学研究センターは、新型コロナを「犯罪学」の観点から検討してきた。with/after コロナの時代、学問に求められているものは何か。それは時代に即した問題に対して科学的に応答することであり、私たち研究者のタスクである。
今回の研究会には、福祉法人の職員(南口氏)、地域定着支援の現場で参与観察を行う司法福祉学を専門とする若手研究者(掛川氏)、矯正・保護の実務経験があり近年は地方自治体の地域再犯防止推進計画の立案に携わる犯罪学者(浜井教授)の3名を迎えた。いずれも社会的に弱い立場におかれている人たちに、犯罪学的知見を日々現場で実践しながら模索している。今日は個々の視点からお話いただきたい。
テーマに関する話題提供(立法・制度背景を中心に)
西本 成文(犯罪学研究センター・RA)
日本の犯罪学、刑事政策の領域で、現在大きなテーマとなっているのは「再犯防止」である。これは単に犯罪予防に焦点をあてるだけでなく、「司法と福祉の連携」が大きな課題となっている。実際に複数の調査によって「社会的に弱い立場におかれている障がい者・高齢者が、社会で適切なサポートを受けられないがために犯罪を繰り返して刑事収容施設に送られ、さらに近年その割合が増加傾向にある」ことが明らかになっている。
この問題をうけて、2011年までに各都道府県に「地域生活定着支援センター」が設置され、2016年に「再犯の防止などの推進に関する法律」が施行された。現在では地方自治体にも「 居場所(居住支援)」と「出番(就労支援等)」をキーワードに、様々な福祉的サポートを拡充させる取組みに着手することが義務づけられている。しかし、ことはそう単純ではない。地方自治体や福祉の現場には、従来の刑事司法制度の枠組みで行われていた処遇や対象者がどのようなものだったか、に関する情報が不足していたこと、そして、対応についてのノウハウがなかったがために多少の混乱がみられた。「司法に関わることは国の仕事ではないのか」、「再犯リスクを持った人が違反行為をしたら即、通報するべきなのか」等々、不安やとまどいの声がある。「司法と福祉の連携」は制度や立法が先立ったために、現在も試行錯誤の状態である。今回の研究会は、罪をおかしてしまう背景には何があるのか、どのような人がサポートを必要としているのかについて、事例を交えながら話題提供していただき、あるべき取り組みについて考えるきっかけにしたい。
パネリスト紹介

南口 芙美 氏(社会福祉法人南高愛隣会 法人法務・相談室、龍谷大学 矯正・保護総合センター嘱託研究員)
社会福祉法人 南高愛隣会(長崎県)の法人法務・相談室に勤務。
龍谷大学法学部から大学院、法科大学院へと進学し、刑事学について石塚教授・浜井教授より指導を受け、2013年より現職に就く。南高愛隣会は、「地域生活定着支援センター」創設のきっかけとなった*社会福祉法人であり、厚労省や法務省との共同研究事業やそれに関わるイベントの担当者になれることに魅力を感じて就職した。
南高愛隣会は、職員600人、利用者約1000人で、知的障がいを持つ方を中心に支援している。主な業務は法務部門として、各種規則・契約書の作成、事件・事故などのトラブル対応、相談部門として、職員や利用者の相談窓口(相談内容は職場の人間関係から相続問題までさまざま)である。今回お話しすることは法人を代表するものでも福祉業界を代表するものでもないことにご留意いただきたい。
*Link>> 田島良昭(研究代表者)『罪を犯した障がい者の地域生活支援に関する研究(2006年〜2008年)』厚生労働科学研究(2008年)

掛川 直之 氏(立命館大学 衣笠総合研究機構専門研究員、犯罪学研究センター嘱託研究員)
龍谷大学および同法科大学院を経て、出版社に就職。在職中から大阪市立大学の大学院で社会学・社会福祉学を専攻して博士号を取得。日本学術振興会の特別研究員を経て現職。
専門は司法福祉学で「司法と福祉」の連携をテーマに研究し、複数の大学で「司法福祉」の講義を担当している。法律と社会学・社会福祉学を学んだ者として双方の立場から刑事司法と福祉とを架橋するための理論と実践をを日々模索している。2021年度から、社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験科目でも、「刑事司法と福祉」が必須の科目になる。今後、福祉の分野でもその重要度が増すだろう。
また、大阪府の地域生活定着支援センターでの参与観察は今年で3年目になる。センターのソーシャルワーカーとして、コロナ禍でもさまざまな体験した。ただし、今回お話することは、大阪府や全国の地域生活定着支援センターを代表するものではないことにご留意いただきたい。

浜井 浩一 教授(本学法学部、犯罪学研究センター 国際部門長、矯正保護・総合センター長)
法務省にて刑務所、少年院、少年鑑別所などの矯正施設、保護観察所(保護観察官)や矯正局に勤務した他、南イリノイ大学大学院派遣留学、法務総合研究所研究官、在イタリア国連犯罪司法研究所研究員等を経て現職。
現在、地方公共団体と連携した法務省の「再犯防止推進計画」に関わる地方自治体(北海道・鹿児島県奄美市・奈良県・奈良市)の政策立案に協力している。たとえば、奈良県では、出所後の受刑者を受け入れるため、財団法人によるソーシャルファームを創設し、出所前の受刑者へ求人情報を提供することで、出所後にスムーズな就労支援をすることを狙いとしている。また奈良市には、元受刑者に対して福祉サービス(住宅提供、生活保護、障がい者支援など)を提供する仕組みを提案している。こうした政策・立案の段階で、犯罪学研究センターが日本版ライブラリーを運営している「キャンベル共同計画」による科学的エビデンスの提供を試みている。
【対談】 パネリスト:南口氏・掛川氏・浜井教授/司会:西本
「罪をおかした」ことが問題なのか?
西本:はじめに、今回のフォーラム・タイトルについて「罪をおかした」高齢者・障がい者の支援という部分はイメージが容易だったと思うが、「罪に問われた」という部分はあまり聞き慣れないのではないか。この部分について南口さんから問題提起をしていただいて進めていきたい。
南口:「罪に問われた」という表現は、就職した際に、司法と福祉の役割の違い、視点の違いを強く感じたので、そこをどうにか表すことができないかと考えて使うようになった。
2つ理由がある。
1つ目は、「罪をおかした」と決まるのは確定判決が出た時点だが、福祉の支援は確定判決を待って行うものではないからだ。司法について理解することが困難な人たち、対応できない人たちへのアプローチは判決が出る前、捜査中にも当然必要になる。
一般的には逮捕されれば「罪をおかした」人だと認識する。しかし、障がいがあろうとなかろうと、やっていないことで白い目でみられることは不愉快である。また、障がいのある方は一般の人以上に意思表示することや物事を整理して考えることが苦手だったりする。例えば窃盗の事案で「この3件はやったが、あとの2件はやってない」と自分で抗弁することができないことが多い。「罪をおかした」という言葉を簡単に使わない方がいい、という思いを込めている。
2つ目に、就職した8年前は「司法と福祉の連携」という言葉は広く知られるようになっていたが、「連携」とは何かという部分で、「連携」ではなく、司法の役割を福祉が担う、というような語られ方があったことに強い抵抗を感じた。現在は「司法福祉」が正式な教育科目として認知されるようになり、「連携」という言葉が何を意味するのかを、文脈を意識しながら注意深く使い、時には批判的に司法と福祉の関係について議論するところまでになった。司法と福祉が連携する上で大切なのは専門性の尊重であるが、双方の議論・視点がかみ合わない部分が多々あることは今も解決されていない。そのため、司法の側が関心を払っていることを、福祉の側も知る必要があると考え、思いを込めた。
司法と福祉の連携に向けて、定着支援対象者の現状
西本:今のお話を聞いて、司法と福祉の連携において、前提としているものをどこに置くかという部分で、「罪に問われた」という言葉の真意を今まで汲み取れていなかったように思う。そういった点も含めて理解を深めていきたい。まずは「障がい」という大きなくくりについて、どういう利用者がおられるのかを南口さん、掛川さんに伺いたい。
掛川:定着支援センターはそもそも入所施設ではないので、出所者の方々を一ところに集めて支援する機関ではない。基本的には出所の6~8ヶ月前から、刑務所内で受刑者との面談を始め、出所後の生活について一緒に考えている。この受刑中から支援を開始するところがこの制度の肝となる。出所日以降はフォローアップという形で、地域の支援者たちにバトンを繋いでいく。大まかには、受刑中に生活環境をコーディネートする業務と、出所後の地域での生活のフォローアップしていく業務の2つがある。
一般に障がいは、知的障がい・精神障がい・身体障がいの3つに区分される。地域生活定着促進事業における特別調整の対象となるクライエントも、基本的には知的障がい・精神障がい・身体障がいのいずれか、もしくは複数の障がいを持たれている方である(高齢を要件とされる方もいらっしゃる)。障害者手帳を持っているか否かに関わらず、障がいが疑われるような方も支援の対象となる。量的なところでは、知的>精神>身体の順で多く、身体障がいを持つ方はあまりいない。知的障がいは(障害者手帳を持っていない人を含め)、IQでいうと知的障がいのボーダー域以下の方々が多く、高齢者も含めるとその多くに知的な課題がある。
南口:当法人は知的障がいの方への支援を中心とする法人。入所施設以外の障害福祉サービスを提供している。発達障がいや精神疾患の方が利用される事業所も運営している。障がいを併発されている方も、身体障がいの方もいる。福祉サービスを提供しているため、基本的な対象者は障害者手帳を持っている方になるが、更生保護施設には障害者手帳を持たない方もいる。
このフォーラムには法律関係の方が多いので、知的障がいについて具体的にイメージを描けないかもしれないが、単純に言えば、未来の見通しをたてること、仮説をたてることや、他人と自分の立場を置き換えて理解することが苦手な方々である。さらに感覚過敏といって、周囲の雑音と自分が聞くべき会話の音が同じ音量で聞こえてしまったり、今見るべき目の前のものと背景の壁の柄が同じ強さで見えてしまったりする方もおられる。
利用者が当法人へ来るまでの過程を簡潔にまとめると、罪に問われた方々については掛川さんのような定着支援のコーディネーターを通して来るというルートがある。もう1つのルートとして、当法人の各地区の別事業所や他の法人の利用者が、警察に捕まる等のトラブル時に利用するケースがある。これは元々いた施設側の受け入れ準備(リセット)のためだ。
コロナ禍が支援におよぼす影響 変わったこと/変わらないこと
西本:支援対象者は、昨今のコロナ禍の状況に応じた新しい生活様式に対応できているのか。「特措法を改定して外出制限などを強制せよ」という意見もあるが、現場感覚として、そのようなことは可能だと感じるか?
南口:知的障がいのある方々で考えると、「出ないようにしましょう」が理解できて行動を変えることができる方は、特措法がなくても外出しないし、理解できない方、行動を変えることができない方は、法律ができても行動を変えられないと思う。(2020年春の)緊急事態宣言発令時、理解したことで行動を変えることができる方には説明をして、変化に対応してもらった。ただ、障がいの特性として見通しを立てることが苦手な方は、スケジュールの変更を受け入れられない場合がある。本来、変更がある時には、かなり早期から計画を崩して組み立て直すということをするが、それで対応できる人もいれば、できない人もいる。そのため時間をかけて話し、絵で示したりプレゼン資料を使ったりして繰り返し説明をしている。長崎県はあまり切迫していなかったが、年末になって急激に感染者が出ているため、年末の予定を立てていた方々に変更を提案している状況。法人としては早い段階でBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)をたて、その通りに進めている。法人内に発症者が出ていないので、今のところ大きな混乱はない。
掛川:支援内容について、コロナ禍で変わったことはない。ただし、(2020年4月の)緊急事態宣言の発令時には、刑務所での面接が制限されたり、できなかったりしたこともあった。テレビ会議システムも刑務所とつなぐ場合は、法務省のシステムを使わないといけないため、テレビ会議システムが非常に混み合い、面談の機会を確保できないこともあった。また府県をまたいで移動することができないケースもあって調整が難航した。コロナの流行初期には、出所者を受け入れ拒否する福祉施設や地域が出てくるのではとの懸念があったが、刑務所の方が一般社会よりも感染リスクが少ないということが理解されたことにより、大きな混乱はなかったと感じた。(2020年5月の)宣言解除後も、刑務所での面会は制限され、取調室のようなアクリル板があるところでの面談という形になった。アクリル板に開いた穴さえふさがれていたので、声の小さな受刑者の話を聞き取らなければならなかったり、こちらも大声を出す必要があったりと、コミュニケーションに困難が生じた。後に、飛沫防止のための簡易的なアクリル板は置かれはしたがいつもの面談室になったので、今は大きな問題は起きていない。
支援について、手帳の有無に関わらず障がいを持っている方が特別調整の対象者に多いので、できる限り具体的なイメージを持っていただけるように、図やイラストの使用等、視覚的な工夫が求められていると考えている。特に出所者支援やソーシャルワークの領域では、これまで自分の生活に、選択肢がなかった人たちが非常に多い。そのため、1つでも多くの選択肢を提示することがソーシャルワーカーの腕の見せ所ではないかと考えている。選択肢をできるだけ多く準備できるように、また対象者と受け入れ先とのマッチングがうまくいくように考えながら、日々業務にあたっている。さらに、他者から大切にされてきた経験が乏しい人に、大切にされていることを実感してもらえるように同じ視点に立って接することを心がけている。
このように地域生活定着支援センターの業務は、地域の支援者にバトンを繋ぐことが目的になる。出所後、地域支援者や施設の世話人の方々においても、コロナに関する大きな問題は特になく、対象者の側にもコロナに関わる大きな問題はなかった。ただし、施設入所者たちは例年よりも行動を制約される場面が多くなっている。この点が、社会生活にどう影響したかについてはしっかりと考えていかなければならない。また、受刑者にも等しく給付された特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)について、出所後の方々は「大金を得た」という感覚に陥ってしまい、気が大きくなって「施設を出て自活する」と言い始めるなどするケースもあった。所持金10万円だけでは出所後の生活がままならないにも関わらず、受刑中に給付金を受給したがために、生活保護をすぐに受けられない事態に陥ったというケースもあった。
地域につなげる支援について 都市部と地方での違い
西本:南口さんは長崎、掛川さんは大阪で支援活動をされているが、都市部と地方で色々な違いや特色があると思う。双方の視点からどのようなことが問題になるのか伺いたい。
南口:長崎県の犯罪発生率は、全国で下から5番目以内に入るくらいに少ない。人が少ない分、社会資源の種類が少ないかもしれない。最も感じている点として、公共交通機関が少ないことがある。地方都市では、生活する上で車が必須になる。知的障がいに限らず、視力や聴覚に障がいがある方にとっても免許取得は様々な困難・課題が多く、それゆえ地方では彼らの生活圏は一気に狭くなる。当法人の利用者の中には、福祉タクシーの予約や電車の乗り換えに苦労するという方がいる。車の運転ができる方は多少不便でも暮らしていけるが、障がいがある方は移動手段が減ってしまう。家族と会える距離に住みたいと思っても、車で移動するのと倍くらいかかる時間が違うということが起きてしまう。このような不便さが地方にはあると考えている。
もう1つは、住人全員が顔見知りのような関係だからこそ、馴染めば良い面が沢山ある一方で、生きづらさを感じている人もいるという、地方独特の空気感があると思う。
掛川:私は大阪のほかに研究対象として名古屋でも活動しており、地方と比べると社会資源は豊富なところをみてきている。実際に地方ではクライエントが「施設に入りたい」と希望しても、入所可能な施設がないためにかなわず、結果的にハウジングファーストの形でアパートに繋いで支援していくというケースも聞く。しかし、都市部であっても、出所後に施設ではなくいきなりアパートで生活できる方は少ない。ハウジングファースト型の支援を実践していくためには、日々日々の生活支援を担うソーシャルワーカーの存在が不可欠になる。ただ大阪の地域特性として、受刑者の中には釜ヶ崎*で日雇い労働をしていた方、ホームレス生活をしていた方も多いことから、「釜ヶ崎に行けば仕事にありつける」というイメージを持つ方が多く、「釜ヶ崎に帰りたい」という方がいる。釜ヶ崎信仰といってもいいかもしれない。釜ヶ崎だからダメということではないが、現在の釜ヶ崎はすでにかつての労働者の街ではなく、福祉の街に様変わりしているところも多い(コロナ禍に見舞われる直前までは海外からの旅行者であふれていた)。また、昔の経験から犯罪につながるものがどこで手に入るかを知っていたりもするし、飲酒や違法薬物の使用など、控えたほうが良い嗜癖行動を再びしてしまう環境にも陥りやすい。そのため、その人が持っている課題によっては、他の地域に繋ぐような選択肢を提示することも必要になってくる。
なお、大阪は特別調整の件数が全国的に多い地域である。出所者の多くが生活保護に繋がるため、そもそも申請が多い西成(大阪市西成区)に集中してしまわないように、大阪府下に分散することを意識している。
*釜ヶ崎:JR新今宮駅の南側に位置する簡易宿所・寄せ場が集中する地区。釜ヶ崎は旧来からの地名で、あいりん地区とも呼ばれる。
【フリーディスカッション】
<地域定着支援を受けている方の実情について>
Q. 地域定着支援は、高齢者や障がいのある方の中で「希望する人」を対象としていると思うが、本来支援があればより円滑に地域に戻れる、支援が必要だと思われる人の中で、実際に支援を受けている人はどの位の割合になっているのか?
(裁判を傍聴していると、家族や地域での支援がないままに法廷に立っていると感じる方が多いように思う)
掛川:割合は分からない。注意すべきは、そもそも多くの方が福祉の支援というものを理解した上で制度にのっているかというと、そうではないことだ。刑務所では客観的なデータから支援を必要としている人をピックアップし、支援を促しているので、福祉専門官の目に留まらなければ支援を受けられない。また受刑者のなかは福祉に良い印象を持っていない人も多い。福祉専門官による支援を受けるにあたって動機づけがどれだけできるかによって変わってくるのではないか。
浜井:刑務所によって福祉専門官の常勤・非常勤の配置人数が異なるが、福祉専門官らの受刑者に対する考え方や支援の在り方、ニーズの把握、情報提供がうまくいっているかどうか、ということが非常に大きな影響を及ぼす。通常のやり方で受刑者に話を聞いてしまうと、軽度知的障がいの人の多くが見逃されてしまう。普通の人と比べて時間間隔がずれているので、若い頃にできたことが年老いた今もできると思っており、やりたいという希望と現実の区別がつかなくなっている場合もある。
また、そもそも福祉の支援・生活保護を受けることに対して抵抗感がある人が多く、そういう人たちは福祉に対してあまり良い印象を持っていないことが分かる。それは、生活保護の申請窓口であったり、福祉施設での暮らしなど色々なところで嫌な思いをしたことがあったりするからだ。職員側の意識変化が必要であって、受刑者にどれだけ正しい情報を提供できるか、動機づけをすることができるか、その上で受け入れるかどうかの話になるので、実態としてどれ位の人がフォローされているのかというのは見えにくい部分である。今はそれを掘り起こしている段階ではないか。
<コロナ禍の出所に関して>
Q. コロナ禍によって、出所後の環境調整や仮釈放の判定に影響があるのか?
障がい認定がされておらず、高齢でもない出所者の支援については、地域ごとに定着支援の対応が違うように感じるが、どうだろうか?
掛川:各地の定着支援センターによって、運用の仕方が異なる。障害者手帳を持たず、介護の申請等もできない方は、極端に行き場が少ない状況にある。施設の中には生活保護のお金だけで受け入れてくれるところもあるので、そういう方を受け入れてくれるところに繋がざるを得ない。更生保護施設や自立準備ホームへの入所には保護観察所の判断となるので、定着支援センターのだけの判断では繋ぎようがない。行き場のない人というのは現在の制度でも一定数いるのは確かである。
<刑務所内での障害認定>
Q. 厚労省は薬物依存症も障がいの一つだと認定しているが、刑務所で障害者手帳の有効期限が切れている人やそもそも認定されない人が多くいるように思う。刑務所内での障がい認定の業務が円滑に進む方法はないものか?
浜井:この10年で刑務所の中にも社会福祉士を入れるようになってきているので、障がいが明確な場合、障害者手帳取得のために動くこともある。しかし、障がいが曖昧なケース(刑務所内では特に困った様子がない等)では、その方が社会復帰した際の想像力が必要となる。刑務所では困らなくても社会に出たら適応できない人というのはたくさんいるからだ。
受刑中に障害者手帳を取得するには、様々な行政機関との調整が必要となる。そのようなノウハウを持った専門官がいれば上手く繋げられるが、ノウハウやコネクションがないと、見て見ぬふりをする場合があるかもしれない。その点は法務省職員も刑事施設職員も全員が、障がいを持つ方たちが社会復帰した時にどのような場面で苦労をするのか、について想像力を持つべきである。刑務所は非常に構造化した社会なので、軽度の障がいでは困らないことが多いが、社会に出た途端に生活が困難になるということを理解し、対応や方針を検討することが必要ではないか。
西本:さいごに、今回のフォーラム全体を通して伝えたいこと。また、社会における福祉の役割や今後の展望についてお話いただきたい。
掛川:定着支援センターの業務は、将来的になくなるのが一番だと考えている。厚労省は「地域共生社会」を掲げているが、共生の対象として、「罪に問われた人たち」という存在が、現段階で人びとの考えのなかに、その射程に入っているのか怪しいところがある。地域の中でいかにこの問題を考えていけるのかという点を意識しながら、これからも研究や実践を続けていきたい。目指すべきは出所者支援を必要としない社会である。再犯防止のためではなく、支援を必要とする方が、一人の困窮者として、障がい者として、高齢者として、必要な支援につなげられるような社会を作っていけるように頑張っていきたい。
南口:掛川さんの「定着支援がなくなればいい」という点に繋がるが、刑務所内で障がいの有無に気づいてもらうことをあまり重視するのは酷なのではないかと感じる。浜井先生は刑務所の持つ構造化の弊害について触れておられたが、福祉の現場でも、意図的に構造化をする。つまり、何をする場所かがはっきりするだけで、落ち着いて暮らすことができる方がいる。刑務所だと適応できる方、閉じられた世界で決まったことだけをやる分には困らない方というのはたくさんいる。障害者手帳も刑務所内で取れると良いかもしれないが、更生保護施設に行っている間に、福祉施設の見学に行く方がハードルが低かったり、選択肢が多い場合もある。刑務所だけで完結させようとするより、出てきてから、複数の選択肢の中から選んでいけるようになるといいと思っている。「相談支援と定着が協働する場面があるのか?」という質問をいただいたが、福祉サービスを利用する場合は相談支援が窓口になる。当法人では、定着支援センターと相談支援の担当者が連携している。色々な立場の方が少しずつ関わって支援するという体制は地域だからこそできる。社会に出て「この町で生きていく」という感覚を、多様な人との関わりを通して持ってもらえるようになるといいと思う。
今後取り組みたいこととして、法律の知識が役に立つ場面が思いのほか多かったので、社会福祉法人や福祉に関わる方たちと、法律に携わる職についている方々との橋渡しをするために、知見の共有をはじめ何ができるかを考えていきたい。
総括
浜井:今回のフォーラムで色々な問題点が指摘されたが、近年改善されてきた部分もある。今年度の厚生労働省の予算では、入口支援のための資金として、定着支援センターに10億円以上が計上されている。今後は出口支援だけでなく積極的に入口支援に取り組めるようになるだろう。掛川さんや南口さんが言ったように、受刑者が最後に戻っていくところは地域社会なので、ノルウェーのように司法と福祉がきちんと連携しているのが理想であると思う。最終的には定着支援センターに頼る必要のない社会にしなければならない。刑務所にいるがために、刑務所の外にいる地域の方と同じように、様々な福祉的なサポートを受けられず、出所前後に調整するという運用で良いのか、ということだ。
現在、再犯防止推進法に基づいて地方自治体では様々な取り組みが行われている。地方自治体のレベルで出所後に困っている方が当たり前の支援が受けられるようにしなければならないし、日常的に困っている方に支援がゆきとどく体制が全国に広まることを願う。福祉を必要とすることについて受刑者と地域住民に差はない。なぜならどちらも同じ人間であるからだ。
石塚:江戸時代に極悪犯を捕まえる「火付盗賊改方(ひつけとうぞくあらためかた)」という仕事があった。鬼平犯科帳の長谷川平蔵が有名だ。その長谷川がやったことで重要なのは、当時、地方で食いはぐれて都会に出てきて江戸の街でも仕事がなく悪いことをせざるを得なかった人たちのために、日本で最初の刑務所といわれる「人足寄場(にんそくよせば)」を作ったことだ。これは悪人を懲らしめるためではなく福祉的なサポートのためであった。また、日本の「監獄学の父」と言われた小河滋次郎は、官職を辞した後、大阪で方面委員(現在の民生委員)制度を作った。刑務所の中にいる人たちが社会復帰するため、また刑務所に入らないようにするために、やるべきことがあるのではないかということに気が付いていたからだろう。小河は、刑務所ではできないことを、社会の中での福祉に求めたのではないか。

石塚 伸一 教授(本学法学部・犯罪学研究センター長)
今回、パネリストの皆さんがやっていることは、刑事政策を学んだ人の行くべき究極のところである。日本の刑事政策の基礎とされている「無刑録」を著した儒学者の蘆野東山は、その著作で「刑は刑無きを期す(刑罰は刑罰がなくなるためにあるものだ)」と記している。自己矛盾のようだが、このことを自覚している人たちによってこそ制度は運用されるべきだと主張していた。
人間というものは頑張っていると、どうしても「ここまでやっている、やってあげているのに…」となってくる。だからあまり気張らないで、これからも南口さんと掛川さんには楽しくやってほしい。
