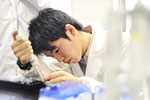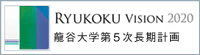- HOME
- > 大学紹介
- > 学長紹介
- > 学長メッセージ・対談等
- > 第37回龍谷大学成人のつどい学長祝辞
2012.01.07 顕真館
皆さん、ご成人おめでとうございます。
この「成人のつどい」は、皆さんにとって大きな節目となる行事です。私たちは、文章に読点を打つように、さまざまな「通過儀礼」によって、人生における区切りを象徴的に経験します。なかでも、「成人儀礼」は子供から大人への成長という、最も跳躍力のいる特別な時期に行われる、大事なイニシエーションであり、人生最大のターンだと言えるでしょう。
誰の人生にも、必ずいくつもの転機があります。そうした時期を乗り越えることで、人は新たなステージへ踏み出し、成長することができます。しかし、うまく通過できないと、その後(ご)の歩みは非常に困難なものになってしまいます。まさに人生の“岐路”です。
分かれ道に立ったとき、子供であれば、大人に導かれて迷うことなく、進むべき方向を見つけることができるでしょう。しかし、大人は、みずからの決断によって道を選び、あるいは開拓しなければなりません。
もちろん、人は一人で生きているのではありません。お互いに支え支えられ、抱(いだ)き抱(いだ)かれながら、ともに生きていく存在です。その上で、なお、自分の判断に基づいて、みずからの人生を築きあげ、同時に社会に貢献していかなければならないのが、「成人」なのではないでしょうか。
とはいえ、皆さんは闇夜の大海(たいかい)に、ただひとり、何も持たずに漕ぎ出すわけではありません。龍谷大学での学びを通じて、皆さんは確かな知性と潤いのある人間性を着実に身につけてきています。私たちは今、先の見通しにくい時代を生きています。あらゆることが揺れ動き、急激に変化し、混迷が深まっているかに見えます。まさに、激動の時代であり、危機の時代です。しかし、本学で培ってきた豊かな“人間力”、実践を伴う“ハイブリッドな知性”があれば、必ずや自らの進むべき道を切り開きつつ、直面する課題に真摯に取り組み、解決することができるはずです。皆さんならば、さきほどの「誓いのことば」をきっと実現できると、私は確信しています。
ところで、皆さんは『インパラの朝』という本をご存じでしょうか。皆さんよりも一回りほど年上の中村安希(あき)さんが、26歳の時に、各地の生活に根ざした“小さな声”を求めて、世界47カ国をめぐる旅に出かけました。この本は、その2年間にわたる旅のドキュメンタリーです。
さて、その冒頭に、旅のきっかけになった印象深いエピソードが語られています。そのころ、アメリカの大学で学んでいた中村さんは、「無口でパッとしないうえに自信を失っていた」そうです。彼女なりに危機的な状況にあったのでしょう。そんなある時、一人の先生が次のような励ましの言葉をくれたのだそうです。「大きな声で話すばかりがコミュニケーションではないんだね。小さな声にそっと耳を傾けること。むしろ、それこそがコミュニケーションの核ではないかと、僕は考えている」と。さらにその先生は、「大きな声には力があるし、発言力を持つ者は脚光を浴びる」けれども、「話すことにばかり夢中になると、周りの声がまるで聞こえなくなってしまう」と言って、無口な中村さんに「たぶん君は、他の誰かの話をじっと聴いているのではないだろうか」と声をかけてくれたといいます。中村さんの心に刻まされたこの言葉が、数年後に彼女を「小さな声の限りない広がりと、そこに示される意味の深遠さ」を求めての旅へと誘(いざな)い、優れたノンフィクション作家を誕生させたことになります。
このエピソードは、人生の真の転機とは思いがけず、何気なく訪れることがあることを教えてくれます。皆さんも、前途洋々たる人生において、そのような経験をすることでしょう。それは一見すると、ささやかなことに思えるかもしれません。ですから、うっかりすると見過ごし、聞き逃して、未来への扉を叩くことなく素通りしてしまいかねません。
その意味でも、「小さな声にそっと耳を傾けること」こそが「コミュニケーションの核ではないか」という、その先生の一言を、ぜひ皆さんの心にも深く刻んでほしいと願っています。自分自身の人生のためだけではなく、人のため、社会のためにも大切にしたい言葉であり、本学の建学の精神にも通じるところのあるメッセージを有していると考えるからです。
皆さんが、龍谷大学の建学の精神を体現して、「生かされているいのち」を深く受けとめ、そして昨年3月11日の東日本大震災がもたらした現実に目をそらすことなく、その文明論的課題をも実践的に担う人間として、これから輝かしい未来を切り開き、実り豊かな人生を歩んでいかれることを、心より念じ申しあげます。
本日はまことにおめでとうございます。
2012年1月7日
龍谷大学学長 赤松 徹眞