2022.05.12
第4回ECCRN(犯罪・非行を研究する若手研究者ネットワーク)公開研究会開催レポート【犯罪学研究センター協力】
若手研究者による学際的交流の試み
2022年3月6日、「第4回ECCRN(犯罪・非行を研究する若手研究者ネットワーク)公開研究会」が本学深草キャンパス至心館とZoomのハイブリッド形式で開催され、当日は約50名が参加しました(犯罪学研究センター協力)。
【EVENT概要】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-9991.html
ECCRN(The Early Career Criminology Research Network of Japan)は、2018年にデイビッド・ブルースター氏と相澤育郎氏によって創設された、犯罪や逸脱、犯罪統制を研究している若手研究者のための学際的なネットワークです。ECCRNには、犯罪学研究センターの嘱託研究員をはじめとした若手研究者が数多く加入していることから、これまで犯罪学研究センターと協同でイベントを開催してきました*1。
今回の公開研究会では、ECCRNメンバーより各研究の進捗や成果が参加者に共有されました。
当日の司会は相良翔氏(埼玉県立大学・保健医療福祉学部・助教)が務めました。

相良 翔氏(埼玉県立大学・保健医療福祉学部・助教)
報告1.【共同研究*2】心理学的知見に対する裁判官の評価:刑事裁判判決文の計量的研究
研究メンバーを代表して、福島由衣氏(日本大学・文理学部人文科学研究所・研究員)より共同研究の成果が報告がされました*3。近年、心理学者による「証⼈の供述の信⽤性」や「被疑者の虚偽⾃⽩」に関する実験や調査で得られた知見が、再審請求事件などの場合に裁判所に証拠として提出されることが増えています。しかし、いくつかの有名事件の裁判*4で、証拠価値が認められませんでした。そこで、本研究では、①「裁判所は心理学的知見の使用に消極的か」、②「心理学的知見に対してどのような理由付けで肯定・否定するのか」を検討するために、⼼理学的知⾒が利⽤された過去55件の刑事事件の判例を対象に、計量的な調査を実施。調査の結果、「⼼理学的知⾒に対する裁判所の判断は、その大半が否定的である(肯定的評価5件、否定的評価50件)」こと、そして「否定的判断をくだした理由の大半は、⼼理学的知⾒を導くために⽤いられた⽅法論、およびその知見を支える理論的背景に問題があると指摘している」ことが明らかになりました。
福島氏は今後の課題として「裁判では、心理学の科学性についてより明確にし、心理学者ではない人にも理解されるような証拠を提出する必要がある」と述べました。報告の後、「公判において弁護士・検察官双方が、どのような意図をもって鑑定を請求するのか」や「海外の司法における心理学的知見の利用」、そして「心理鑑定と他の鑑定(自然科学や医学鑑定)との差異」について、参加者と意見交換が行われました。

福島 由衣氏(日本大学・文理学部人文科学研究所・研究員)
福島氏は、「科学的分析をめぐって心理学者同士でも対立がある。鑑定結果を証拠として採用するかどうかを判断する裁判官が、心理学的知見に対して実際にどのような認識を持っているのかを調査したい」と述べ、報告を締めくくりました。
報告2.【共同研究*5】犯罪からの離脱をめぐる文献レビュー研究
研究メンバーを代表して、竹中祐二氏(北陸学院大学・人間総合学部・社会学科・准教授)より、活動報告がされました。はじめに、竹中氏は「離脱(Desistance)は、犯罪学では伝統的であると同時に、近年注⽬を集めているテーマだ。しかし、離脱(Desistance)概念は、研究者によりさまざまで、その内実は必ずしも明らかにされてこなかった」と述べました。そこで、本プロジェクトでは、先⾏研究の傾向やそれぞれの差異を特定することを通して、『離脱』についてメタ的な知⾒を提供することを⽬的としており、、“SQLR”(Systematic Qualitative Literature Review) を実施しました。
具体的には、研究メンバーは、2011年から2020年の期間に出版・投稿された英語文献を収集(5,989件)し、プロトコルをもとに選別を2度実施して、199件にまで絞り込んだうえで、データベースを作成しました。それを元に分析・検討した成果は、共同研究のメンバーと共に、ヨーロッパ犯罪学会のポスターセッションで発表*6しました。また、今後さらなる文献レビュー研究として“Metasynthesis”および“Scoping review” を実施予定であることが報告されました。
竹中氏は、コロナ禍における研究活動を模索する中、ECCRNに所属する他分野の若手研究者とオンラインで共同研究を行った意義について言及すると同時に、研究活動の基盤となる助成金獲得の困難さについても参加者と共有しました。そして、海外ジャーナルへの投稿計画を述べ報告を終えました。参加者からは、離脱研究をめぐる海外と日本の状況との比較や、研究手法について意見が交換されました。

竹中 祐二氏(北陸学院大学・人間総合学部・社会学科・准教授)
つづけて、博士後期課程に在籍する2人のメンバーより、研究構想について報告がなされました。
報告3.【個人研究】Research notes:regarding interviews made to public officials working with post-carceral institutions in Costa Rica(研究ノート:コスタリカの社会内処遇施設や保護観察機関における公務員へのインタビュー)
コスタリカから日本に留学したDaniel GARCIA氏(広島大学大学院・人間社会科学研究科・博士後期課程)は、“Post-Carceral”をテーマにしたコスタリカにおける社会内処遇施設と保護観察機関について報告しました。ガルシア氏は、コスタリカのプンタレナス州の実務家に対して行ったインタビューをもとに、コスタリカでおこなわれている治療プログラムを紹介。プンタレナス州はコスタリカで最も貧困指数が高く、住民の主な関心事として、教育や就労機会の不足、犯罪や麻薬使用の増加、公共交通機関や道路整備の質の低下などがあげられます。
同州の社会内処遇施設は、3人のソーシャルワーカーと1人の犯罪学者によって、保護観察機関は、心理学者、ソーシャルワーカー、法律の専門家、そして2人のフォローアップスタッフで構成されています。ガルシア氏は両機関の業務の違いを説明した上で、「両機関ともに、なるべく刑務所への再収容を避けるために、さまざまなプログラムやサポートの提供が試みられている。その結果として再犯防止に一定の効果が認められる。しかし、予算が乏しく、人的資源や事務設備等の補充に苦慮している状況だ。また、業務で得た知見を全国的に共有する制度的基盤が整備されておらず今後の課題である」と述べました。参加者からは日本の更生保護および保護観察制度との比較を通した質問がなされました。

Daniel GARCIA氏(広島大学大学院・人間社会科学研究科・博士後期課程)
ガルシア氏は今後の研究課題として「調査対象の拡大と実態の精査、そして日本の保護観察や更生保護制度との比較」をあげ、報告を終えました。
報告4.【個人研究】「Carceral Aesthetics(監獄の感性学)に関する検討」
風間勇助氏(東京大学大学院・人文社会系研究科・博士課程)は、2020年9 ⽉ 17 ⽇から2021年4 ⽉ 5 ⽇までアメリカの MoMA PS1*7で開催された⼤規模な刑務所アート展《Marking Time: Art in the Age of Mass Incarceration》*8と、同展示のキュレーターを務めたニコル・R・フリートウッド氏の「Carceral Aesthetics(監獄の感性学)」概念を紹介し、⽇本の刑務所における芸術活動への応⽤可能性について参加者と意見交換を行いました。
風間氏はアートマネジメントを専門としています。これまで、受刑者・出所者の支援活動をしているNPO法人マザーハウスと協働しながら、日本の矯正施設(特に刑務所)における芸術・文化活動について、出所者や矯正職員にヒアリング等を行い、矯正施設の文化環境を調査しながら、刑務所でのアートプロジェクトを目指してきました*9。
風間氏は、フリートウッド氏の取り組みについて説明したのち、日本の状況についてもエピソードを交えながら紹介。プリズンアートを巡って、アメリカと日本の背景の違いに注意を促しました。参加者からは、日本における芸術の取り上げられ方、受刑者はいかにして芸術に関心を持つのか等について質問が寄せられました。
風間氏は、「刑務所では表現の機会はあるものの、コミュニケーションや学習の機会が奪われている。」として、芸術制作(文芸表現)や展示が、受刑者にどのように影響するのか、他者との関係性やコミュニケーションに着目する意義について述べ報告を終えました。
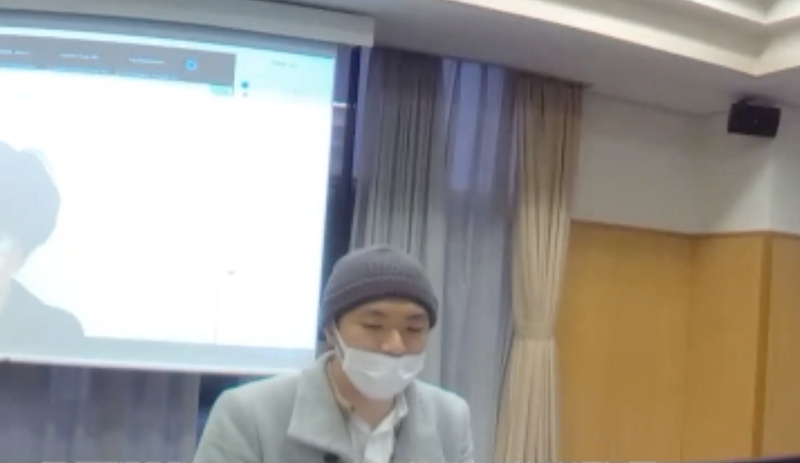
風間 勇助氏(東京大学大学院・人文社会系研究科・博士課程)
報告5.【共同研究*10】「テキストマイニングを用いた都道府県再犯防止推進計画の検討」
研究メンバーを代表して、向井智哉氏(東京大学大学院・法学政治学研究科・専門職学位課程法曹養成)より報告がされました。2016年に再犯防⽌推進法が施⾏され、再犯防⽌施策を実施する責務が、国だけでなく、地⽅⾃治体も担うこととなりました。再犯防止政策は、各自治体の特色にあわせて策定されているのかという疑問について、本共同研究は、2021年8月時点で策定された42都道府県の再犯防⽌推進計画の計量的な分析がこれまで⾏われていないことに着目し、分析手法にテキストマイニングを⽤いて検討しました。
今回の報告では、向井氏より、テキストマイニングの方法論や調査の実施手法についての説明がなされました。研究メンバーは、国が策定した再犯防⽌推進計画を基にコードを作成し、各都道府県の再犯防⽌推進計画に各コードがどの程度出現しているのか、各都道府県間で大きな相違があるのかを検証。調査の結果、①「出所者の特性に配慮した政策」を重視する「特性コード」および「機関相互間の連携推進」を重視する「連携コード」の出現頻度が⾼いこと、②京都・兵庫を例外として、その他の都道府県は概ね等質であったことが明らかにされました。
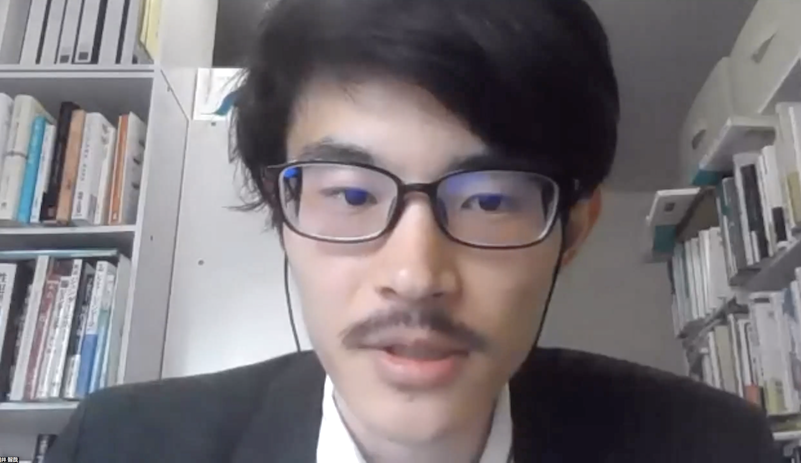
向井 智哉氏(東京大学大学院・法学政治学研究科・専門職学位課程法曹養成)
参加者からは、テキストマイニングの手法についての質問や、再犯防止政策の策定に関する地方の実情についての意見が出されたほか、地域の特色がどのように生まれるのか、また地域ごとに違って良いのか等をめぐって意見が交わされました。
最後に、ECCRNを代表してDavid BREWSTER 氏より閉会の挨拶が行われ、当日の研究会は盛況のうち終了しました。
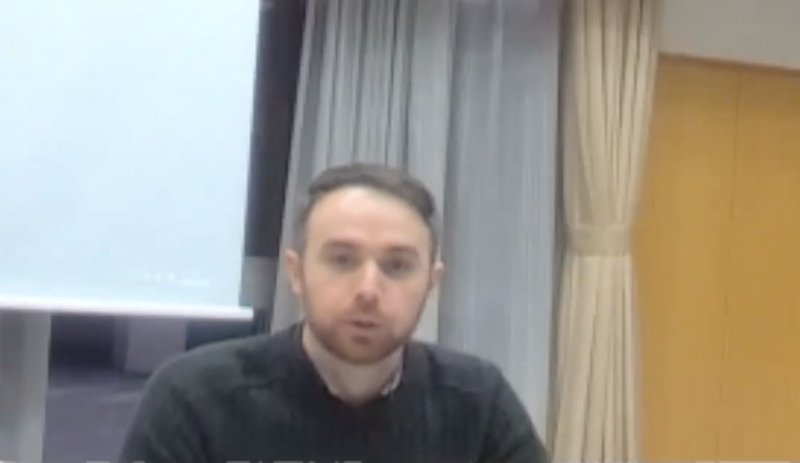
David BREWSTER氏(金沢美術工芸大学・講師)
ECCRNは、随時、新規会員・サポーターの募集をしています。
入会希望の方は、ECCRNのHPにアクセスし、登録フォームからお申し込みください。
ECCRNのHP:https://www.hanzaigaku.com/
───────────────────
[脚註]
*1 参考記事
>> 2019.02.15 ディビッド・ブルースター × 相澤 育郎 対談「日本における犯罪学教育と若手研究者の現状」【犯罪学研究センター】
>> 2021.01.08 アジア犯罪学会 第12回年次大会 オンライン・プレイベントを実施【犯罪学研究センター】
*2 研究メンバー
福島由衣(日本大学・文理学部人文科学研究所・研究員)
向井智哉(東京大学大学院・法学政治学研究科・専門職学位課程法曹養成)
相澤育郎(立正大学・法学部法学科 助教)
入山茂(東洋大学・大学院社会学研究科・社会心理学専攻・博士後期課程)
*3 研究成果の詳細については、以下の論文を参照のこと。
福島 由衣、向井 智哉、相澤 育郎、入山 茂「心理学的知見に対する裁判官の評価 ──刑事裁判判決文の計量的研究──」『心理学研究』92 巻4号(2021年)278頁〜286頁
*4 例示された事件として、「飯塚事件」では、現実に起きたとされる事態を実験によって再現した検証を行い(再現実験)、目撃供述の信用性評価がおこなわれた。「大崎事件」では、関係者の供述の信用性判断に、供述者の言語的特徴に着目して信用性評価をおこなう供述分析が使用された。
*5 研究メンバー
鈴木政広(Central Queensland University College of Law, Criminology and Justice Lecturer in Criminology)
相良翔(埼玉県立大学・保健医療福祉学部・助教)
橋場典子(成蹊大学・法学部・法律学科・助教)
山脇望美(人間環境大学・心理学部・犯罪心理学科・講師)
竹中祐二(北陸学院大学・人間総合学部・社会学科・准教授)
*6 Trends in Desistance Research in the Last 10 Years:2011-2020
(21th Annual Conference of the European Society of Criminology)
Yuji TAKENAKA, Sho SAGARA, Masahiro SUZUKI, Noriko HASHIBA, Nozomi YAMAWAKI
*7 MoMA(The Museum of Modern Art, New York)は、ニューヨーク近代美術館の略称。MoMA PS1は、1971年にAlannaHeissによって設立されたInstitutefor Art and Urban Resources Inc.によって、 ニューヨーク市で放棄され活用されていない建物(Public school 1)をアーティストスタジオや展示スペースにしたもの。2001年からMoMAと提携し、同美術館の分館として現在に至る。
https://www.moma.org/ (MoMA)
参照:
塩津友里「アートが地域を変えるP.S.1」『公共R不動産のプロジェクトスタディ』(2015.04.23)
Wikipedia(EN)「MoMA PS1」
*8 Marking Time: Art in the Age of Mass Incarceration
*9 当センター協力のもと、2021年度に全3回の研究会を主催。
参照>>「第1回 刑務所と芸術研究会」開催レポート【犯罪学研究センター】
日本の矯正施設における芸術活動を阻む壁は何か
*10 研究メンバー
向井智哉(東京大学大学院・法学政治学研究科・専門職学位課程法曹養成)
David BREWSTER(金沢美術工芸大学・講師)
高橋有紀(福島大学・人文社会学群・行政政策学類・地域政策と法コース・准教授)
竹中祐二(北陸学院大学・人間総合学部・社会学科・准教授)
鈴木政広(Central Queensland University College of Law, Criminology and Justice Lecturer in Criminology)
相良翔(埼玉県立大学・保健医療福祉学部・助教)
相澤育郎(立正大学・法学部法学科 助教)