2021.07.02
アジア犯罪学会(ACS2020)全体講演レポート_Prof. Natti Ronel【犯罪学研究センター】
スピリチュアル犯罪学とポジティブ犯罪学:既存の知識の現代的応用
龍谷大学がホスト校となり、2021年6月18日(金)〜21日(月)の4日間にわたり国際学会「アジア犯罪学会 第12回年次大会(Asian Criminological Society 12th Annual Conference, 通称: ACS2020)」*をオンラインで開催しました。2014年の大阪大会に次いで国内では2回目の開催となる今大会では、アジア・オセアニア地域における犯罪学の興隆と、米国・欧州などの犯罪学の先進地域との学術交流を目的としています。
大会の全体テーマには『アジア文化における罪と罰:犯罪学における伝統と進取の精神(Crime and Punishment under Asian Cultures: Tradition and Innovation in Criminology)』を掲げ、「世界で最も犯罪の少ない国」といわれる日本の犯罪・非行対策と社会制度・文化に対する理解を広めることを目指しました。
【>>関連ニュース】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-8690.html
LIVEで行われた本大会の全体講演(Plenary Session with Q&A Session)の概要を紹介します。
(Spiritual and Positive Criminology - contemporary applications of established knowledge)
〔講演者〕ナッティ・ローネル(バル=イラン大学 社会科学部 教授,イスラエル)
Natti Ronel (Professor, Faculty of Social Sciences, Bar-Ilan University, Israel)
〔司 会〕津富 宏(静岡県立大学 国際関係学部 教授)
Hiroshi Tsutomi (Professor, the school of International Relations, University of Shizuoka, Japan)
〔日 時〕2021年6月20日(日) 16:30-18:00
〔キーワード〕ポジティブ犯罪学、スピリチュアル犯罪学、スピリチュアリティ
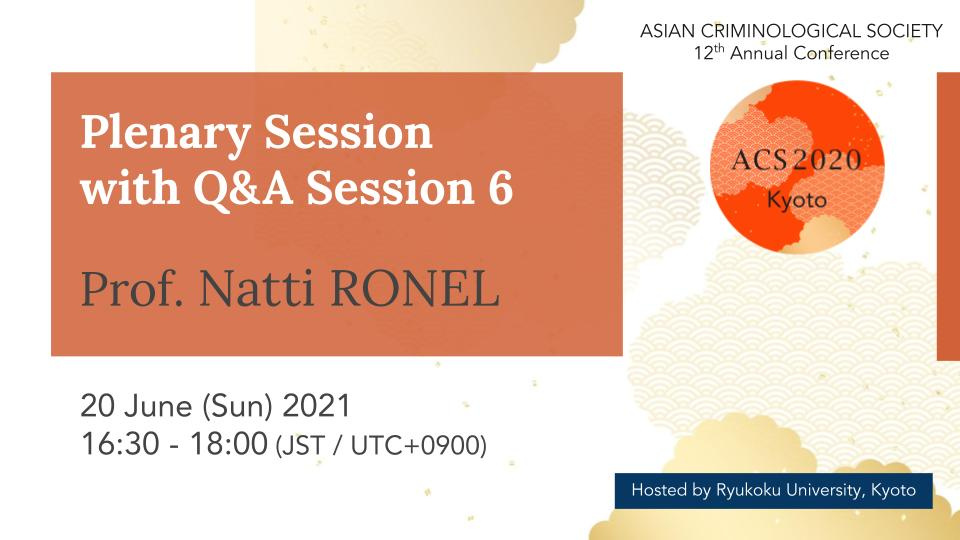

ナッティ・ローネル(バル=イラン大学 社会科学部 教授,イスラエル)
犯罪行為の抽出された要素はなにを具現化しているのだろうか?ポジティブ犯罪学は,否応なく分解と分離のプロセスを伴う犯罪行為のあらゆる形式を一般的に示している。ポジティブ犯罪には,個人間,個人内,スピリチュアルという関連する3つのレベルがあることが明らかになっている。それゆえ,ポジティブ犯罪学は,犯罪からの離脱(desistance)と出所者の社会復帰の主要な手段として成功した統合であるということを繰り返し強調している。スピリチュアル犯罪学は,スピリチュアルに関する統合的な知識の普遍的な要素をまとめる意識的な試みを,ポジティブ犯罪学に結び付けている。こうした試みはアジアの様々な文化のなかで集中的に展開された(たとえば生活の宗教)。様々な文化は伝統的にスピリチュアリティに関する異なる見解を維持しているものの,そうした文化はすべて,スピリチュアリティの根幹に共通して存在する特徴を共有しており,スピリチュアル犯罪学に応用されている。
その結果,犯罪行為のあらゆる形式は一般的に,犯罪行為に関与した人たちの過度な自己中心性を伴う。自己中心性は個人の欲求,リスク,欲望,期待の過剰な占拠と関連がある。また自己中心性は,無知であることに関するその人の個人的なレベル,その人のエゴに関する自己認識の程度,もしくは神とその人との距離を示す。自己中心性は時折,特定の集団に所属させることもあり,それによって集団的に自己中心的になることもある。自己中心性とは,スピリチュアルのレベルで根本的な分離のことを指し,通常は,その人の個人間レベルと個人内レベルによって表現され,影響をされる。犯罪からの離脱(desistance)と出所者の社会復帰は,手段の統合の採用に加え,自己中心性の減少を促進することによって着実に達成される。このことは,COVID-19(新型コロナウイルス)パンデミックと権力者の世界的規模の公的な反応によって実証された。そしてそれによって不幸なことにソーシャル・ディスタンスと個人の恐怖心は増大した。それゆえ,自己中心性が増加すると,結果として,薬物乱用や薬物依存,家庭内暴力,自殺というような関連する現象が増加することになる。ポジティブ犯罪学とスピリチュアル犯罪学はどちらも,信仰と希望を増加させ,統合を促進するための社会的機会を割り当てる試みによってこのプロセスが逆転することを予測している。そうした手段は公衆衛生のポジティブな結果を得ることによって推定される。
【質疑応答(Q&A)要旨】
(問1) スピリチュアル犯罪学とポジティブ犯罪学の関係はどのようなものか
(答1) スピリチュアル犯罪学は、ポジティブとネガティブ、善と悪といった通常の区別を超えたものである。
(問2) 今日の話は、世俗的なものの場面にも応用可能ですか。
(答2) 今日は、スピリチュアリティの話はしたが、宗教の話をしたわけではない。世俗の人であっても、善を行っており、同じである。
(問3) ボランティアであることが重要であるということは専門家の意義はどこにあるのか。
(答3) 専門家である場合、まず、無条件に人を助けたいというボランティアであり、それに付け加えて、専門家としての付加価値をもっている。
(問4) スピリチュアル犯罪学と、宗教の関係について教えてもらいたい。政治問題としての宗教に関心がある。どのような形の宗教やスピリチュアリティが社会にとって有益なのか。それは誰がどうやって決めるのか。刑務所の中で反社会的な宗教を信仰している受刑者がいる場合、信仰を認めるべきか。
(答4) 宗教とは、お参りをしたり儀式をしたりといった行為であるが、一方、スピリチュアリティは行為をする際に本人の心の中に何があるかである。離脱とは、自己中心性から、他者中心性、そして、神を中心にする方向へと変わることである。宗教集団もギャングも、社会から切り離されていれば、自己中心的なものとなる。何が、自己中心的でそうでないかを判断するのは難しい。むしろ、その自己中心性からの成長を望むとしか言いようがない。
(問5) (問4に引き続き)私は、オウム真理教の研究をしている。刑務所内の教誨師ともたくさん会ったが、オウム真理教の教誨師はいなかった。ある宗教をよいもの、あるいは、悪いものと定義することは、政府にどの宗教が良いか悪いかを定義する権限を与えることになる。この点について、共通の関心があると思う。
(答5) どんな権力も乱用の原因となる。犯罪も権力の乱用であり、刑務所も権力の乱用の場である。宗教の名において、虐殺も行われてきた。だからこそ、スピリチュアル犯罪学においては、善と悪の区別を超えて、自己中心性との戦いに焦点を当てた考えを提供しようとしている。
(問6) 自己中心性という概念が主張の中心にあるが、なぜ、自分を殺してしまう自殺が、自己中心性の表れなのか。
(答6) 自己中心性とは、自分のことで頭がいっぱいな状況を指す。自殺や自傷は、自分が自分をコントロールできる証明のようなものである。自殺とは痛みを終わらせるということで、自己中心性の表れである。
(問7) ご自身のなさっている心理治療について教えてほしい。
(答7) 心理治療についてはTwelve toolsという本を出版している。12ステップとも似ている。豊かな人から貧しい人まで、様々な人を治療している。薬物依存、性的依存、暴力、性暴力の人もいる。患者には、正統派ユダヤ教徒の人たちもいる。彼らは信仰心は厚いが、性依存症の人が多い。セックスは合法なので性犯罪者ではないが、そこに、スピリチュアリティはない。初回面接では、信念体系と宗教を尋ねる。これがきっかけになる。性依存の人は絶えず、セックスのことばかり考えていて捉われている。この治療は難しいが可能である。
(問8) 日本では、薬物依存症者の支援に、国が関与するようになり、依存症者を治療の対象にし始めているが、どうしたらよいか。
(答8) 国は、AAやNAとは本来は無関係である。私は、大学で12ステップについて教え、学生たちの教育の一環としてAAやNAなどのプログラムに送り込んでいる。イスラエルでは、NAを助けるために、政府が施設を提供し、いろいろなまちにNAができた。グループの側から、協力関係を引き出してほしい。
(問9) 日本では高齢者が孤立して、多くの高齢者が犯罪を犯して刑務所に入っている。どうしたらよいか。
(答9) 再定住センターをつくるのでは、もう一つ刑務所をつくることになってしまう。そうではなく、地域に家を借りて、コミュニティをつくるのが大事。そのほうが政府にとっても安上がりである。AAやNAなども、こうしたコミュニティとして、社会の外と社会の橋渡しになる。
(問10) あなたのスピリチュアル犯罪学の背景にある、哲学について知りたい。
(答10) 私の根本は、12ステップであり、私の中にスピリチュアリティを探し求めて旅をしてきた。日本に来て禅をしたこともあれば、インドにも行った。この共通なもの、自分より偉大なものが根底にある。
◎本大会の成果については、犯罪学研究センターHPにおいて順次公開する予定です。
なお、ゲスト・スピーカーのAbstract(英語演題)はオフィシャルサイト内のPDFリンクを参照のこと。
ACS2020 Program https://acs2020.org/program.html
*アジア犯罪学会(Asian Criminological Society)
マカオに拠点をおくアジア犯罪学会(Asian Criminological Society)は、2009年にマカオ大学のジアンホン・リュウ (Liu, Jianhong) 教授が、中国本土、香港、台湾、オーストラリアなどの主要犯罪学・刑事政策研究者に呼びかけることによって発足しました。その使命は下記の事柄です。
① アジア全域における犯罪学と刑事司法の研究を推進すること
② 犯罪学と刑事司法の諸分野において、研究者と実務家の協力を拡大すること
③ 出版と会合により、アジアと世界の犯罪学者と刑事司法実務家のコミュニケーションを奨励すること
④ 学術機関と刑事司法機関において、犯罪学と刑事司法に関する訓練と研究を促進すること
このような使命をもつアジア犯罪学会は、現在、中国・香港・マカオ・台湾・韓国・日本・オーストラリア・マレーシア・フィリピン・シンガポール・アメリカ・スイス・パキスタン・インド・スリランカなどの国・地域の会員が約300名所属しており、日本からは会長(宮澤節生・本学犯罪学研究センター客員研究員)と、理事(石塚伸一・本学法学部教授・犯罪学研究センター長)の2名が選出されています。