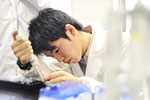6月の法話 2013年6月11日(火)/大宮学舎
おはようございます。6月に入りまして気象庁も早く梅雨入り宣言をしたため、この間多くのクレームの電話が入ったようでありますが、ようやく今週になって梅雨の本格的な雨が降ってきそうです。ちょうど台風も南の方から押し上げているようですので、一方では集中的な雨の危惧というものが生ずるかもわかりません。そういった中で、6月の今日大宮学舎での法話という機会を得ることができました。
最近よく語られる言葉で、大学でもそうですけれども政府のかかえるいろいろなところで”グローバル人材の育成”ということがよく語られています。皆さんもご承知のことだと思います。グローバルという言語は球・球体とかあるいは地球のとか丸いということを表しているのですが、それは同時に国境、あるいは地域のいわゆる縦割りの境界を越えて地球が一つの単位となるといったものを意味している動向過程を示しています。それはちょうど1970年代に地球環境という問題が大きくクローズアップされる中で、地球環境の問題を解決することが人類の生存にとって欠かせない課題となってきた、こういうことを背景にして、このグローバルということが浮上してきたことでもあります。またその後は1989年のいわゆるベルリンの壁が崩壊し、1991年にソ連邦の社会主義圏が崩壊して、いわゆる冷戦構造が解体をしていくわけですが、そうすると東西の分断を超えていくような人類的な視点というものをどう考えるのかということにあたって、グローバルという名称を使って世界平和というものを指向するという言葉で語られた傾向があります。しかしながらその後はご承知のように1990年代、日本においてもバブル崩壊の中でいわゆる規制緩和という傾向が出現し、経済関係もいわゆる自由競争、よく言われる新自由主義という言い方もしますが、そういった中でこのグローバリズム、あるいはグローバルということが経済領域で特に強調して言われつつあります。言葉というのはそれぞれの時期によって当初語られている言葉の意味文脈も少しずつ変化をしながら使っているということです。
大学でも文科省の大学改革の実行プランの中においても、グローバル人材の育成というものが求められているということをよく言われるのは、日本の社会もあるいは世界的な国境線あるいは経済関係の垣根が低くなっていくという中で、日本の企業が国内だけにとどまらず世界各地で展開していく上においての企業を担っていく人材を育成するという方向からグローバル人材というものが言われるのかも知れません。その言葉だけで見ますと、いわゆる人材ということの中での位置づけは人材ですので仕事の目的に従属するような材としての人の存在という位置づけで、どれだけの役割・機能を果たしうる人を育てていくのかと語られるのです。
しかし私たちはグローバルという形での社会変化・状況の中で、本学が浄土真宗の精神・親鸞聖人の精神をあるいは浄土真宗のみ教えを建学の精神としていることにおいて、この時代とどのように向き合いながら教育展開をするのか、あるいは研究を展開していくのかということにおいては、政府とか企業が語られる文脈とは違った観点からの洞察なり位置づけなり意義づけを作り上げていかなければならないと思います。そういう意味ではそもそも論というものが私たちの大学にとってはどうしても欠かせないこととしてあります。それは仏教の思惟、あるいは仏教的な人間観というのはそもそもどういうものなのか、仏教とは何なのかということの出発点、広く言うと宗教とはどう考えるのかということにも関わります。
グローバリズムという中での中心はやはり欧米を中心にした経済社会が振興していくわけですが、そこでの躓きなり問題点の指摘はいくつか明確に出されています。たとえばそれはどういう言い方かといいますと、それは物事を分析していく手法としての二分的な見方あるいは二値的な基軸の中で物事を分析・分類して、そのことに伴う言語表現をして態度決定していくという二分的な思考方法を政治経済でも貫いていくというのが基本的な傾向だと指摘されます。それはそのことによって言葉も対極する言葉で、一見たしかに二分すれば明確で多くの人たちが理解しやすいのですが、そのことによって漏れ落ちるような世界というのがあります。そのことを1970年代にも議論としてファジィ論理というのが定義されたのがそういう領域です。ファジィというのは曖昧性があるというきわめて重要な理論として、二分法の世界だけではないものとしてファジィ論理というものが出される意義がでてきたわけです。
そうすると仏教なども物事を分けていく、洞察していくような言語というようなものも、親鸞聖人の著作の中では、晩年、たしか83歳だったと思いますが『愚禿鈔』という書物を上下2巻出されております。それは一般には教相判釈(きょうそうはんじゃく)という少し専門的な言葉かも知れませんが、なぜ浄土真宗でなければ私たちは救われる道がないのかということを、さまざまな仏教経典を駆使しながら明確に分析をして徹底した分析知を駆使し、表現しながら、なおかつそのことを超えるものとして阿弥陀仏の本願のはたらきがなければ私たちは仏に成ることはできないということを知らしめられていく教えであります。そういう著書でも論理をもって対置する言語を駆使しながら著述をされていますが、その言語を使いながらもなお今申し上げたように阿弥陀仏の本願力・あるいは他力ということを申されているのは、そういう対極言語の世界を超えた仏教の智慧、ほとけさまの智慧というものに目覚めていくということをそこで語られているのです。そういった考え方というのは、現代社会の動向というものにどのように向き合いながら仏教的な意味、あるいは仏教的な思惟、あるいはスタイルというものを示していけるのかというのが私たちの大学にとっても大切なことではないだろうかと思います。
先日、本棚で手にした随分前に発行されている西田幾多郎の『場所的論理と宗教的世界』という文章の一端に、宗教心というということについてこういう文章があります。「宗教心というのは多くの人の考えるように有限と無限とか、相対と絶対というごとき仮定的関係において生ずるものではなく、我々の自己自身の存在が問われるとき、自己自身が問題となるとき、はじめて意識せられるのである」。宗教心というのは有限とか無限とか、相対とか絶対といった関係のところではなくて、我々自身の存在が問われたりあるいは自分自身が問題となるとき初めて意識されるものだとこういうことを指摘されています。私もその通りだと思います。つまり仏教的な思惟は私と向こう側にある仏というものとの対置的な関係ではなく、私自身の存在が問われるときにそこに目覚められる世界、気づかしめられる世界というのが顕在化する、あるいはそういう私の存在を問い直すときにすでに阿弥陀仏がこの私に向かって救わずにはおけないというはたらきがすでにされている、これを対置的な関係ではただちに領解できるものではないだろうと思います。西田幾多郎という方はそのような文章を書かれたり、他にも西谷啓治さんという哲学者がおられ、その方の『根源的主体性の哲学』という戦前に発行された書物ですが、そこでは西谷さん自身は「根源的主体性」という言葉でそのことを語っております。どういう表現かというと「我ありということの究極の根底は底なきものである。我々の生の根源には足をつけるべき何物もないというところがある。むしろ立脚すべき何物もないところに立脚するゆえに生も生なのである。」立脚するところがないということをもってむしろ無いところに立脚するがゆえに生がある。つまり立脚することがないということは逆に言うとその立脚するはたらきというものがそもそもあるんだ、そういうことの気づきがあるんだというところが『根源的な主体性の哲学』の中で述べられています。
私たちが浄土真宗のみ教えという中で受け止めていくに際しては、親鸞聖人の語られている言葉あるいはそういうことから言うならば「他力」という表現がありますが、随所に親鸞聖人も「他力というは如来の本願力なり」(顕浄土真実教行証文類 註釈版聖典190頁)、あるいは「他力と申すことは、弥陀如来の御ちかひのなかに、選択摂取したまへる第十八の念仏往生の本願を信楽するを他力と申すなり。」(親鸞聖人御消息 註釈版聖典746頁)等と示されています。だから他力ということも言葉でいうと自力・他力という相対する局の言語かもしれませんけれども、浄土真宗なり、仏教の基礎をふまえて考えるならば他力というのは私たちをして生たらしめている、とりわけ阿弥陀仏の私たちをして必ず浄土に生まれせしめたいというはたらきが他力なのだと、このことは仏教的な思惟、考え方の道筋というものに気づかなければなかなか領解しにくい、あるいは頷けないというところがあろうかと思いますけれども本学にとってはそういった教えに出会っていくことではないかと思います。
親鸞聖人はたくさんのご和讃(和語で三宝を讃嘆する七五調の詩歌)を書かれています。その中に私たちが日常的に大学の行事でも歌っている「恩徳讃」があります。
身を粉にしても報ずべし
師主知識の恩徳も
ほねをくだきても謝すべし
(『正像末和讃』註釈版聖典610頁)
私たちはなぜ仏になれるのか、あるいは浄土に生まれることができるのかということは、如来大悲のはたらき無くしてはそういうことはあり得ない。そういうことを気づかしめられることがないので、そのことに気づきさえすればそのことの恩徳というのは、この私にとっては身を粉にしても報ずべきことである。またそういう教えに出会うことについても師主知識ですので親鸞聖人にとっては七高僧であってみたり、一番の近いところでは法然聖人がそうですが、私たちにすれば皆さん方もそれぞれどこかの人との出会いというものが必ずあります。この人に出会えばこそ浄土真宗の教えの道に入ることができた、あるいは仏教の教えの出会いに近づくことができた。そういうことの恩徳というものもあろうかと思うのですが、そういう意味ではそういう人との出会いあるいは恩師と称してみても師主と称してみてもそういう方々の恩徳も、やはり私が何らかの求道の中で自分の力で見いだしたものではなくて恩徳として受け止めて、そのことをほねを砕きても謝すべし、とこのように歌われているのが「恩徳讃」というものだと思います。私たちも個人的なこととして振り返ってみればそういった恩師とも言うべき方々との出会いによって浄土真宗のみ教えに近づき、またその教えを旨として生き抜いていきたいという思いを育てていただいた恩というものがあります。
私も田舎のお寺の住職をしておりますが、若くして40代50代の親を亡くした息子さんなどに出会いますが、その場はその場で深い悲しみに泣き崩れていくのですが、その後、我が身というものの育てるところにどれだけ親のはたらきを感じ、その後の人生を歩むのかということについては、なかなか容易なことではないのです。言ってみれば親が亡くなってもその後は日々の中でお礼をする、あるいは手を合わすことさえも欠いていくというような日常を送りがちなところがあります。しかし、よくよく振り返って我が身、あるいは私の存在を問い直してみた場合に、私というものの中ですでに親の願いあるいは親のはたらきというものが私の体の中に命の中にはたらいているのだということを気づかしめられた身であるならば、日々の中で一時たりともと厳しく言わなくとも、一分間であっても30秒であってもわずかな時間でも、手を合わせて念仏を申すというところに、我が身に仏さまのはたらき感じて、いただいたいのちを精一杯歩まさせていただこうとこういう人生が開かれてくるのではないだろうかということに気づかされていることであります。
今日は、大宮学舎本館講堂でお話しさせていただきました。