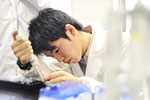11月の法話 2014年11月7日(金)/大宮本館
お早うございます。ようこそお参りいただきました。
11月に入りまして、今日は天候にも恵まれて、大宮キャンパスに古くからある公孫樹の木が、徐々に黄色が鮮やかになっています。時に風があると、構内に公孫樹の葉が散らばります。それも早朝のうちは見られるのですけれども、講義前から早々に箒で落ち葉を掃き集めてくださり、きれいにしてくださいますので、昼前には公孫樹の葉をゆっくりと見ながら過ごすということも少なくなっているようなことがあろうかと思います。
社会がいろいろと変動しつつあるなかで、私たちは大学におります。その社会の変動をいろいろな方々が、例えば歴史的にも、また、さまざまな形で「今の世の中は、地殻変動の真っただ中だ」と指摘されることもあります。新聞を見ますと、日本銀行の金融緩和で株価もずいぶん高くなっていると言われます。社会はさまざまに変化し、この20年あるいは30年の間に日本の社会も大きく移り変わっております。
大学も、さまざまに抱える課題について、その対応を迫られているところがあります。
その一つは、大学で学んでいる事柄が、広い意味での社会から期待されていることに応えているか、ということです。大学が取り組んでいることについて、どのような対話を重ねて、社会の期待に応えているか――。それが大きな問題としてあります。そういう意味では、大学に在籍している学生自身が4年間の学びを通して自ら成長しながら、社会人として貢献していくか――。
かつて大学への進学者も少ない時代には、大学を出れば「インテリゲンチャ(知識階層)」と言われました。そもそも「インテリジェンス」の意味は、「分析する知性」を持つということです。今の社会でもそれは、一般的には一つの素養としての、「物事を分析する能力」あるいは「物事を論理的に表現する力」であり、それをもって多くの人々と対話をしたり、議論をしたりする力を身につけていく、そういうことだと思います。
その際に、時代の大きな反省も同時にあります。それは、ものごとを対象として見て、そのことについての詳細な分析をすることは確かに近代的な、あるいは科学的な知性だと言われるし、そのように理解してよいわけですけれども、やはり分析を中心とする論理的合理的な知性の高度性、専門性を身につければそれでいいのかというと、必ずしもそうではない。そのことによって、見逃していってしまっているもの、陥穽がある。このように言ってもいい本質、根源的なものがあります。
「詳細な分析」と言っても、いろいろな分野があります。私は先日、3時間ほどの人間ドックに入りました。大学で行なわれる年1回の健康診断があります。その時に血液検査から示される数値があります。最近は、かつてのような血液検査ではなくて、いろいろな項目について、かなり詳細な数値が出てきます。人間ドックに入りますと、大学で検査する血液検査の項目以上に、より詳細な項目があげられて、それが数値として示されます。平均的な数値からいうと、多い、少ない、というなかで、基準値の枠のなかに入れば、ひとまず良好であるという判断が下されるわけです。数値として表わされる分析は確かに進んできています。人間ドックの決まった項目以上に、オプション項目の検査を求めれば、さらに高度な分析機器を使った血液検査が受けられます。血液中のガンの要素になり得るものを抽出できるような検査項目もあります。
数値で表わされるということは、そのような医療の分野だけでなく、さまざまな分野で行なわれています。先日も日本シリーズがありました。それぞれのチームが相手チームを数値で分析しています。ピッチャーもキャッチャーとのサインの交換で、投げるたびに球種を決めるにしても、パターン化できるならばそのパターン、傾向を抽出していく――。そういった分析の仕方があるわけです。他のスポーツでも、試合に臨む時には相手チームを分析する。誰がメインの選手なのか、誰にボールが集まるのかという、そういった分析をして、対応の仕方を考えるのだろうと思います。大学での諸分野にも数値化が進行しています。
ところが、大切なことは必ずしもそれだけではありません。それと合わせて、私たちの建学の精神にあるような、数値の世界とは違った側面――そういう根源的なものがあるだろうと考えるわけです。
それは本学の建学の精神でもありますし、多くの日本の哲学者といわれるような人たちが、ヨーロッパの近代科学あるいは哲学を学びながらも、日本の哲学あるいは東洋の思想、あるいは仏教の思想のなかから見出したものであり、それが言葉として表現されているものがあります。例えば、金子大栄(かねこだいえい)とか鈴木大拙(すずきだいせつ)、あるいは西田幾多郎(にしだきたろう)という人たちも深く、人間の根源的なものを考えています。西田のキーワードに「絶対矛盾の自己同一」という言葉があります。
例えば、鈴木大拙は、「東洋的一(いつ)」という言葉をキーワードにしました。一つの多元的なことがあるけれども、その中の基本としての根本は「一(いつ)」であるという原理をもって顕れているものが、多元的なものとしてある――こういう表現の仕方をしています。
あるいは、柳宗悦(やなぎそうえつ)という民芸運動の中心人物でもあった人は、「東洋的不二(ふに)」という言葉を遣って、根源的なはたらき、根源的な世界を表現しました。あるいはそれを「無」の世界といい、「絶対無」という言葉を遣ったりしました。言葉は若干違うのですけれども、言わんとするところは同じです。
その言わんとするところは何かというと、仏教的表現をすると、〈私〉あるいは自我というものに実体を置かない、という見方、考え方に達する。〈私〉と〈他者〉、いま二項対立的に向かい合う関係でものごとを見てしまうのですけれども、徹底して〈私〉というものを問いかけて、考え抜いていけば、そこには〈私〉とひとまずは言っているけれども、その〈私〉は〈私〉というものによって成立して、働いているものではない。それでは、それは何なのかと言えば、その「何なのか」という部分をどう表現するかと言えば、それは表現する人によって異なるわけですけれども、仏教の伝統的な言葉でいえば、我にあらざるはたらきという意味で、「無我」あるいは「非我」という言葉を遣います。あるいは、浄土教であれば、それは(仏の)「不可思議なはたらき」――思議を超えたはたらき、そういう言葉で表現しています。
要するに、〈私〉というものを実体化してみたり、その実体化することによって、〈私〉のエゴイズム、あるいは〈私〉と〈私〉自身の驕りやうぬぼれを醸成してしまうものがある。だから、無我とか非我というはたらきによって初めて〈私〉が成り立っていると受けとめることによって、より謙虚に、より柔軟に、あるいは自分のありのままの姿、本当のあり方を見て自分自身の罪深さを自覚してみる――。
そういうふうにどこかで、向こう側にいる、向こう側の対照としてあるものから知らされている。徹底的に自己を問うことによって、そういうはたらきの中に〈私〉がある、と考えます。
同時にまた生死(しょうじ)といった事柄も、科学的に、ミクロ的に細胞レベルで考えれば、私たちのこの体は日々、生活をしながらも、その中で、死んでいく細胞もあるし、新たに造くられていく細胞もある。そういう意味では、生と死ということは私たちの日常の中にも確実にあるわけです。ところがやはり、私たち自身の日常の中で、死んでいく細胞があるなんてことが意識として浮上することは、なかなか難しい。
ミクロとしては生死(しょうじ)――生と死の間を、できるだけ隙間を近づけて考えてみる。そういうふうに考えていくと、いのちに恵まれていることと、いのちを終えることとの間には〈私〉自身のことも考えれば、それは本当に一瞬、一瞬でしかないわけですから、そのように考えれば、「死」は決して遠いものでもない。遠いものでないことを、どこか頭の片隅において生活すると、いのち恵まれていることのありがたさ、尊さ、あるいは家族であっても友人であっても、今日出会っていることが素晴らしい出会いではないだろうか、そのように受けとめることが、縁としては生まれてくるのではないか――。
それをいつでも、「死」がない状態が恒常的に変わらないものとして、あり続けるのではないかと思ってしまうと、思ってしまう側の方に、大きなうぬぼれ、驕りがあったりして、「生」はいつでもあり続けるもの、どこまでも続くものだという思い込みに胡坐をかいて生活をしてしまう。いのちの儚さとか、虚しさも感じないままに歩んでしまう――。このことは、自らの体験をより深く尋ねることによってしか、意識することはできないのではないだろうかと思ったりもいたします。
そのことを西田幾多郎はどう言ったか――。「西田哲学」といわれます。私たちは「私がいろいろなことを経験する」と言うのですが、西田哲学の中で言われる一つのフレーズとしては「経験のなかから私が造られていく」という道筋でものごとを考えてみようということです。私が何をしていくというよりも、経験する中で私というものが形成されていく――このような発想です。
それは、かつて仏像を彫る仏師が、西洋的に考えれば、木彫にしても石にしても、私がデザインをして、デザインに沿って素材を削って、そうしてデザインしたものを形あるものとして作りあげていく――。こういう発想でデザインを繰り返しながら、自分が作りあげようとするものを刻んでいく。素材が木であっても石であっても、それをデザインし、刻んでいくのは私――こういう発想があるわけです。
けれども、日本の仏師が木を素材にして仏像を彫る際には、その人たちの表現としては、「木の中から仏像が顕れてくる」と言います。自分は確かに木を彫って、仏像を造ろうとする。ところが仏像を彫りながら、木の中から仏像が顕れてくる――。このような発想はある意味、極めて東洋的な発想だと思います。それは、必ずしも全てが計画通りに、計算通りにいくものとして顕れてくるものではない――。そういう事柄として表現されるのではないかと思ったりもします。
私たちは、こういった時代に、ほとんどよく似た思考パターンで、計画どおりに、予定どおりに、ということを最優先しながら、物事を判断したり、決定したり、受けとめたりすることが多い。そういうことが常識化しているかも分かりません。しかしもう少し、ものごとの本質、根源を掘り起こして考えたい。とりわけ仏教的な思惟、仏教的な考え方とはどういう考え方なのか、あるいは本学が建学の精神とする浄土真宗のみ教えからいうと、どういういのちの受けとめ方をしていくことが、最も教えに忠実なのか――。
同時に、自分たちの人生をこれから歩んでいくについては、自らを問うことなくして、横に置いておいて、人生を問うことなどあり得ないわけです。先ほど言いましたように、阿弥陀仏のはたらきという事柄も、自分が誰かに代わってそのはたらきを感じ取ることはできないわけです。自分自身に問いかけて、自分というものの中身、内容として、問いかけてみた場合に、私自身のいろいろな事柄は、さまざまな個別的な経験をしながら、この間、今の〈私〉を造りあげてきた。
その造りあげてきたものの中にある一番の根本は、自分の操作あるいは意思でいのちを動かしているものではない、ということです。その事柄が重要であり、そのいのちは、無量のいのち、量ることのできないいのちだと受けとめることだと思うのです。それを数量として、有量なものとしていのちを数値化していくと、やはりそこに虚しさとか、悲しさも同時に生ずるところでもあるわけです。
そこのところを私たちはよくよく考えながら、大学生活を送り、日常生活を送らせていただこうと、このような思いをさせていただくところでもございます。
今日、皆さんと共にお参りさせていただきました。私は普段、忙しい生活をしています。今朝は4時半頃に起きてラジオを聴いていたのですが、最近の経済関係の人たちのよく使われる言葉が紹介されていました――。
「今だけ、金だけ、自分だけ」。これが、今の経済アナリストの一般の、とくに先端をいっている人たちの合言葉だそうです。しかし「今だけ、金だけ、自分だけ」と言って、経済を操作し、活動している人たちが、果たして幸せな社会、望ましい社会を作りあげる働きをしているだろうかというと、そんなことはない。「今だけ、金だけ、自分だけ」というあり方で、果たして人間社会が豊かな社会、望ましい社会になっていくのだろうか、と思ったりもします。そういうことがまかり通っていく面も、今の社会にはありますので、私たちは、そうではない道をしっかりと歩まなければいけないと思います。