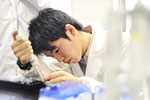10月の法話 2014年10月29日(水)/深草顕真館
お早うございます。ようこそお参りいただきました。
10月下旬になりまして、落葉樹のあるこの深草キャンパスも紅葉の季節を迎えています。木々の葉がパラパラと落ちるようなことでもあります。
私の研究室は大宮学舎にあります。2階の研究室の窓越しに樹齢100年を超える大きな公孫樹の木が見えます。色づいた公孫樹の葉を見ながら季節の移ろいを感じています。
日本には四季があり、季節の移り変わりがありますので、皆さんもそれぞれの場所で、そういった自然環境を見ながら、季節の巡りを感じられると思います。あるいは食事の時には、秋には秋の味覚を味わう、そういったことがあると思います。
先日、ニュースで報じられていたのですが、最近は小学生の五感、あるいは味覚がずいぶんと変化しているそうです。3割近くの小学生は、甘いとか苦いという味覚は感じるにしても、特に酸味とか塩味に対する感覚がずいぶんと失われている。そういう子どもたちが3割を超えるぐらいになっていると報道されていました。
たぶん、普段からの食事のあり方が、その背景にあるのではないかと思います。皆さんにおかれては、いかがでしょうか。
笑い話のようなことになりますが、最近は食も、単純に言えばそれぞれの好みだけを優先して口に入れてしまいますので、味に多様性があるにも拘わらず、ついつい画一的な味を求めてしまい、味覚が偏り過ぎているのではないか。このようなことも言われます。
家庭の味といったものを口にする機会も少なくなっているという指摘があります。事例としてよく語られるのは、家庭でも手作りの食事が少なくなって、出来合いの食材をスーパーなどで買い求めることが増えている。あるいは、24時間営業のコンビニエンスストアがたくさんありますので、今日はコンビニA店、明日はコンビニB店というふうに、買う店を変えていけば週に4日くらいは味の違うものを食べられる。あるいはデパートも多くありますので、髙島屋、伊勢丹、大丸などの地下の食品売場へ行けば出来合いの食材を買い求めることもできます。とりわけ、夜遅くに帰る時などは、家の食卓には食べるものがないから、帰り途にあるコンビニに寄って、買い求めたものを口に入れる。小さい頃から、そういうことが背景としてあると、味覚がなかなか育たない。味覚を感じられなくなっている――。こういうことが、よく指摘されます。
「豊かな日本の社会」とひと言でいうのですけれども、それは、いろいろな意味での豊かさを損ねるようなこともあろうかと思います。食材についても、エネルギーのカロリー数だけを計算していくと、カロリーに関しては満たしていても、食材の多様性が失われる面もある。スポーツをしている人などはカロリー計算をして、分析をして、こういう栄養素が足りないとなれば、サプリメントで補う。
そういうことが対症的にはあるにしても、それはあくまでも対症的です。日常的に私たちの体全体をはたらき支えていくうえで、さらに日常の生活の基本的な要素として、食事は極めて重要です。このことが現代社会において、より一層、関心をもたれつつある。このように言ってもよいのだろうと思います。
本学でいつも申しあげている建学の精神、あるいは親鸞聖人の精神、浄土真宗のみ教えの言葉の中で、阿弥陀さまという仏さまについて、私たちが勘違いをしてはいけないことがあります。
〈私〉がここにいて、向こう側に阿弥陀仏という仏さまが対照としてある――このように向かい合って見るような受けとめ方は違いますよと、一つは考えておかないといけないと思います。〈私〉がここにいて、阿弥陀さまという仏さまを向こう側に置いてしまうと、どうしても〈私〉というものを自明の前提としてしまうからです。
それゆえに、〈私〉がさまざまな事柄にぶつかったり、悩んだりした際に、自分の思いを、向こう側にいる阿弥陀仏の方に、言うならば“願い奉っていく”ような向かい合い方をする。それは、自分たちの現世利益あるいは祈祷という内容をもって阿弥陀仏に向かい合っていくことになってしまう向きがあります。
ですから、阿弥陀仏という仏さまの絵像(えぞう=絵に描いた仏像)であってみても、それは何を示すものかというと、それは働きを示しているものとして、阿弥陀仏というふうに名乗っているものだ、と。阿弥陀さまという仏さまの名乗りを、親鸞聖人はお手紙の中で「弥陀仏は自然のやうをしらせん料なり(阿弥陀仏とは自づから然らしめるはたらきを知らせるためのものだ)」と述べておられます。
「自づから然らしむる」とは、私たちが、自分の意思、気持ちで、いのちを左右しているものではなくて、「自づから然らしむる」という、智慧と慈悲のはたらきの中にある、そのはたらきがあることを知らせるがために、阿弥陀仏と名乗られたものだということです。この名乗りというものがなければ、その智慧と慈悲のはたらきに気づくことができない、ということです。ですから、阿弥陀仏のご絵像が向こう側にあったとしても、それは私たちに「自づから然らしむるはたらき」を知らせていただくための方便――手立てとしての絵像を見ている。
だから親鸞聖人も鎌倉時代に――当時も大きな仏像がどんどん造られていましたが――、ご本尊としてこの顕真館正面に掲げてあるような「南無阿弥陀仏」という名号を書かれた。名号は、私たちに仏のはたらきを示していただくものとしての「南無阿弥陀仏」という意味があるわけです。
なかなか難しくて、了解しにくいところがあろうかと思います。しかし、私たち一人ひとりが、〈私〉にはたらいている。自分の思いや力によって動かしたり、はたらかせているのではない、ということです。言葉を換えると、思議――自分たちの考え、分析――を超えたはたらきなのだ、と言えます。このような大いなるはたらきに目覚める、気づくことに大きな意味があります。
どうして意味があるのか――。私たちが現実に、さまざまな出来事に出会ってみたり、人間関係とか、いろいろなところで悩みを生じた場合、どうしても〈私〉の思いとの間の対立とか、軋轢とか、葛藤とか、あるいは思い通りにいかないことに応じて、悩み、苦悩が生ずるわけですけれども、その際に、その直面している悩みは、〈私〉との関係で生じていることです。
そうすると、〈私〉の思いだけでそれを動かしていった際にどうなるか――。必ずしも思い通りにならない出来事、事態が生じた時に、そういう形だけで考えてしまうと、自分たち自身の生きる意味を失っていくような事態になりかねません。その際には、私の人生だから、私の体だから、私のいのちだから、と思い込んで、〈私〉という思いの中で、自分の身を傷めてみたり、自分自身のいのちを傷つけてみたりする要素も、私たちの心の中に生ずるかもしれない。
その際に、もう少し深く考える立場を、私たちは本学の学びの中で気づかせていただこう、ということなのです。先ほど言ったように、〈私〉の思いとか、そういうものを超えて、いのちとしては、「自づから然らしむる」「いのちをいのちたらしめていく」というはたらきが、この〈私〉の中にはすでにはたらいています。これを自分の思いとか意思で左右してみたり、傷つけてみたり、操作するものではない――。
このように考えておくというか、深く考え抜いていく。先にそういうはたらきに気づいていけば、現実の中での事態がどうあろうとも、その条件それ自体については、私たちは変えられる努力、あるいはそれを乗り越えていく歩みが開かれていく。このように考えて歩んでいってこそ、私たちの人生を、実のある人生として生き抜いていくことができる。こういうことだと思ったりもいたします。
私たちにはそれぞれ、年齢があります。それぞれの齢を重ねていきながら、他者の中で自分よりも年老いた人、あるいは生まれて間もない赤ちゃんを見た時には、そういう方を、自分の外にある人だと考えずに、そこに〈私〉を重ね描くことを営みとして持っておくことがまた大切です。そのことによって、いくつかの大きな意味に気づかせてもらえるのです。1歳や生後数カ月の小さな赤ちゃんの姿を見た時に、かつてこの私がその時期を過ごしたことがある姿として、その赤ちゃんと〈私〉とを重ね合わせて描いてみる――。
そうするならばたぶん、現代社会にある、大きな、悲しい、痛ましい事件、親子・夫婦の暴力的な行為とか、子育ての中で子どもに食事を与えないような悲しい出来事は起こらないでしょう。
縁あって生まれた赤ちゃんを、親として食事も与えないまま、餓死させてしまうような悲しい事件、痛ましい事件がときどきあります。その親が赤ちゃんを見た時に、かつてこの私が1歳、あるいは生後数カ月の赤ちゃんであった時期には、その赤ちゃんであった私に向かって、親が食を口に入れてくださったのだと重ね描くことができるならば、そういう痛ましい、悲しい事件はたぶん生じないだろうと思ったりもいたします。
また、年老いて認知症になったり、身体が衰弱り傷む姿を見た時には、この私もいずれ、縁あって、80歳あるいは90歳という齢を重ねる時があったならば、もしかしたらその姿が〈私〉の姿としてあるのではないか――。
そのように、自分自身を重ね描く営みを自分の中に持ち続けていたならば、そういう人たちとの出会いの中で、自分が今、なし得ること、できること、手を差し伸べてみたりする行為もできるのではないだろうか。これも、〈私〉と〈他者〉という対立関係の中で見てしまうと、よそ事になってしまいます。そこに自分自身を重ね描くという営みを、自分の中に内在させていくことによって、そういうあり方を開いていけるものだと、このように思ったりいたします。
秋になると、私たちはいろいろなサークルから試合の成果などの報告を得ることが多いのですけれども、そこでもやはり、一人ひとりの役割は役割として担いながら、それぞれ違ったものを持った者同士がパートナーとして、一緒に活動やプレーをしています。お互いの良さを活かし、役割を担いながら、一方でネットワークをつなげてこそ、よいチームづくりができると思います。
「私だけが」という世界ではなくて、それぞれの出会いがあって、それぞれの能力を十分に発揮できるチームづくりが尊重されながら、試合ができる。またそこには、試合の場面だけではなくて、人の出会い、友人との出会いもあるのではないか。このように気づかせていただく場所であることが、本学の大きな意味だと思ったりもいたします。
先週の土曜日(2014年10月25日)、校友会の結成式があって私は仙台へ出張していました。たまたまその日には西京極のわかさスタジアムで、私が名誉顧問をしているアメリカンフットボール部の同志社大学との試合が行われました。その試合中、前半には、部長である文学部の越前谷宏先生から「危ない、危ない」とメールが入ってきていました。前半は0対0でしたが、試合としてはかなり押され気味だったようです。後半の3クォーターには9対7で推移して、第4クォーターで龍大が7点を入れて、14対9で勝った。試合の推移は、私も帰ってからインターネットのYouTube、USTREAMで見ました。非常にどきどきする試合でした。やはりチームの者同士のそれぞれの連携が非常に大きな役割をしているのだなと、改めて感じ入りました。
今日、皆さま方とお参りをさせていただいて、改めて思います。私たちは根底のところでは、恵まれたいのち、あるいは量ることのできないいのちをわが身にいただいて、そのいのちは誕生以来、さまざまな形で育てていただいた親と名乗ってくださった方々によって、一人ひとり、育てられてきたものであるのです。今は20歳、22歳であろうとも、その後、さまざまご縁があって、70歳、80歳という齢を重ねることもあろうかと思います。その時、私の人生には、このいのちを育てていただいたはたらきがある。あるいは、不可思議なはたらきの中で、いのちというものは恵まれているものだ、ということに深く感じ入って、お礼を申させていただく気持ち、謙虚さを持ち続けたい――。このように思います。
たくさんの方々とお参りさせていただいたことに感謝を申しあげ、法話を終えたいと思います。