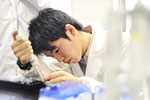4月の法話 2015年4月30日(木)/深草顕真館
お早うございます。新学期が始まりまして、ほぼ1カ月が過ぎました。桜が咲いた頃に入学式をさせていただいて、すでに新緑の季節を迎えました。私にとっては疾風のような1カ月であったと思います。
私は、奈良県宇陀市の山間地域、山里での生活がありますので、近所の方が旬のものを届けて下さることがままあります。最近は筍が土を突き上げてきて、近所から届けられますと、湯がいて、味噌和えやおすましなどしていただきます。しばくすると蕨が伸びてきますので、近所から「持って帰って下さい」と頂くことが多くあります。地域の共同性がそういった旬の山菜など通して感じられます。商品化の次元ではない山菜、自然環境からの冥加としての山菜です。また春先には鶯の声がします。春先の鳴き声はかすれていたりするので、何の囀りかなと訝しむ時があるのですが、さすがに昨日くらいになると、鶯のきれいな囀りがあちこちから聞こえていました。私の山里で聞きづらい声がキジの鳴き声だと思います。キジは、羽を見るときれいですけれども、声はガーガーと軋んだ感じで聞きづらい。そういう声が聞こえるような環境での暮らしをしています。
ところで、先日ある新聞を拝見していますと、東京大学大学院に藤原帰一(ふじわらきいち)という国際政治学の先生がおられますが、その先生が朝日新聞(夕刊)に、「時事小言」という題で1カ月に1回ほど執筆している文章に出会いました。
どういう文章かと言いますと、いつの頃からか、書店の店頭や新聞記事とか、テレビ番組で、日本のよさを伝えるものが目立つようになってきたと、指摘されていました。その前には、特に日本への批判を「自虐」という言葉で拒むような態度があった、と。
これは過去の歴史に対する見方についての「自虐史観」という形で、その批判を封ずるような動きがみられるわけです。しかし、その社会の抱える問題に対しての批判を「自虐」という言葉によって拒んでいくような態度をしていくと、それは無反省に現実を肯定するだけに終わってしまって、悪くすれば、無為無策を招いてしまう。
日本の歩んできた歴史の中で、より望ましい社会を実現し、あるいは変革を実現していったのは、現実に対する単なる美化ではなくて、そこに抱える問題に目を向けた態度があったからではないか――。
このような指摘をされていました。あるいは「自尊」という言葉があります。自尊という言葉は自分で自分を偉いと思い込む態度のことです。「自虐」という言葉によって批判を拒む一方で、「自尊」という言葉に表現されるように、自分を偉いと思い込むような社会風潮が目立つようになってきた。このような指摘をされている文章に出会いました。このご指摘には頷けるところもあります。
別の、アメリカの社会学者のジーン・M・トウエンギ、W・キース・キャンベルが著した『自己愛過剰社会』という本があります。成熟した社会では、自分ほど可愛い存在はないのではないかと思っていくような人々が非常に増えているという指摘がありました。こういった社会傾向は、豊かな先進国に共通に見られる現象だと思います。
顕真館の正面には「南無阿弥陀仏」と親鸞聖人がしたためられた、お名号を刻まれているわけですけれども、私たちは日々、阿弥陀仏のはたらき、光に出遇わせていただく。あるいは阿弥陀仏の光に照らされた〈私〉であると、このように見つめ直してみた時には、そこには単に今の社会の傾向としてあるような、自分を偉いと思い込むような態度から改められていく、あるいはむしろ自分のあり方を厳しく問い直していく――。そこに、私たちの建学の精神の大切さがあろうかと思います。
皆さんもご存知かもわかりませんけれども、家永三郎(いえながさぶろう)という東京教育大学の名誉教授がいました。三省堂発行の『新日本史』という高校の教科書や、古代から近代に至る思想史、文化史などの著書を多く執筆されている歴史学の大家でした。
その家永先生が戦争中に『日本思想史に於ける否定の論理の発達』(1940)という本を出されています。否定の論理とはどういうことか――。日本の古代から近代に至る歴史の中で、人間を見つめ、見直していくための仏教というものを見出して、その仏教の持つ思想史的な意義を明確にした論考であるわけです。
仏教とは、自己とは何かという問いかけをして、そしてまた〈私〉というものの一方的な思い上がりを砕いていくところに、むしろ生かされたいのち、恵まれたいのちを深く受けとめて、自己を中心とした見方を修正していく。そうして、より多くの人々と共に歩んでいくような人生、あるいは多くの人々と共にあるような社会が、いつの時代においても求められていく社会ではないか。だから、仏教徒ならば、自己中心性から離れる、否定する智慧をもって、多くの人々と共に歩む社会を常に求め続けていくことが、いかなる時代であっても、普遍的に重要なテーマ、課題であると――。その意義を見出したものが『日本思想史に於ける否定の論理の発達』という著書でもありました。
その著書で家永先生も、親鸞という方を大切にされています。親鸞という方の中に「悪人正機」という教えがあろうと思いますし、親鸞聖人ご自身も自らを「煩悩具足の凡夫(ぼんぶ)」、煩悩に満ちあふれた〈私〉である、あるいは「罪悪深重(ざいあくじんじゅう)の凡夫」である、と言いました。〈私〉でありながらも、自らの自覚に伴わなくても、私以外の人々を踏みつけること、傷つけることがある〈私〉である。そういうものとして、自分のなかに罪悪性、罪というものを明確に意識したところに、深い人間観が育てられてきたと、このように見出した論考であります。
私たちも日常の生活の中で、日常性としてありながらも、人間関係の中においては、共に上手く歩める面もあろうかと思います。しかしながら、私たち自身が自分たちの行為――仏教の中では、分類的には「身口意(しんくい)の三業(さんごう)」といいますが――、身体的な行ない、あるいは言葉として口に出す行為、あるいは心の働きという行為を、それぞれ明確に、深く問いただしていくと、そういう自分の身に起こす三業という行ないの中に、他者を傷つけてしまっているような、あるいは踏みつけてしまっているような行為が伴っているのではないか――。
そう問いかけるところに、私たちの罪悪性を意識させていただく。その意識させていただくところにはやはり、阿弥陀仏の光というはたらきが意識されていくということであるわけです。ですから、現代の社会がいわゆる自己愛過剰社会であるという傾向に対しての、私たちのあり方というもののもつ大きな意味があろうかと思います。
社会の動きは激しい。しかしながら私たちは、今の日本の社会、あるいは世界の情況を見ましても、人間として何をしていくべき役割・使命があるのかということを意識しながら、大学という場所でより深く学び、研究し、そしてまた社会へ貢献をしていく。このような道として歩んでいければ、と思うことでもあります。
4月は今日で終わり、明日から5月になります。ゴールデンウィークもありますが、やはり私たちは龍谷大学という大学に身を置いて、いろいろな領域で活動をしていく際には、常に「南無阿弥陀仏」というはたらき、つまり量ることのできない光といのちがいつも、どこであっても、〈私〉のところに到り届いて、光として照らして下さる、そういう仏である。そうするならば、まざまざと〈私〉の姿が明らかになった時には、そういう自己愛、自尊、思いあがりの態度、あるいは考えは砕かれる――。繰り返し申しあげておりますように、他者とのどういうあり方が開かれてくるのか、こういう課題を常に意識しながら、仕事をさせていただこうと、このように思います。
今日も、8時半からの学長法話に伴う勤行でありますけれども、皆さん方も今日はいつもの時間より30分以上は早く出られたと思います。私たちの日常も、日常としての時間がただ流れているわけではなくて、日常の中に非日常という要素が含まれている。だから日常の中でもやはり、その時々において決断をして、態度を明らかにしていく――。そういった契機、きっかけが含まれておるものだと思います。
そこにはやはり、日常に流されない、あるいは日常の私たちの感情、心情のみに流されないで、そこを問い質していく契機、あるいは日常を根本的に照らし出されるような光によって、むしろ私たちの決断、私たちの新たな踏み出す発心(ほっしん)というか、心を起こしていく決断が促される――このようなことだと思ったりもいたします。
大学も今日において、高等教育機関としての使命というものが、より一層求められております。龍谷大学もそういう役割を積極的に果たす大学であり続けたいと考えるところでもあります。
季節は移り変わり、これからしばらくは、目にも鮮やかな新緑の季節でありましょう。季節を愛でることも大切でしょうけれども、一方では季節を愛でながら、私たち自身のありようを問い質す。そういう者の学ぶ場所として、龍谷大学はより一層、その役割を果たしていきたいと思います、皆さんと共々に。それは簡潔に言えば、私の口から「南無阿弥陀仏」という念仏が称えられる身になっていく。阿弥陀仏と〈私〉とが、決して対立的な関係ではなくて、すでに願いは到り届いている。すでに光は届いている。
そう「すでに」と考えてみた時に、先にいのちを終えた人は、皆さんにとってもご縁あっていのちを終えた方々との経験も関係もあっただろうと思いますけれども、いのちを終えた方は、いのちを終えた方として私たちと別世界の、あるいは〈私〉と別の形で、他者が存在するのではなくて、仏としていつも〈私〉のところにはたらいている。このように重ね合わせて、深く受けとめるところに、仏教の持つ意味があろうかと思ったりもいたします。
今日は皆さんと共に、朝の勤行を務めさせていただいたことを慶ばせていただいて、法話とさせていただきます。