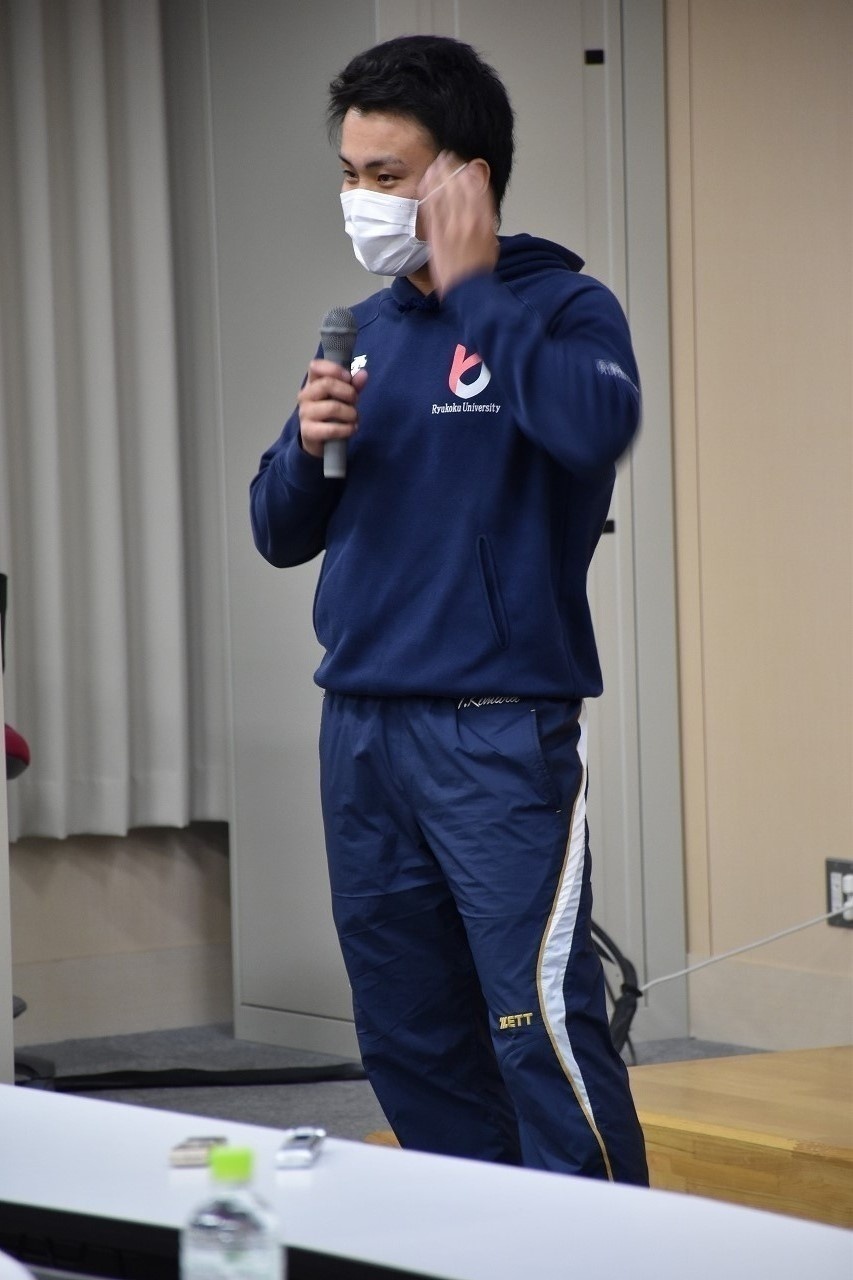2018年度より龍谷グローバル登龍門プロジェクトが始動しました
本取組は、国際展開している日本企業や地域コミュニティーと連携して、英語の「語学力」と「コミュニケーション力」を活かしてグローバルに活躍できる人材を育成する正課外プログラムとして位置付けられ、本学の教育の質保証およびキャリア形成を強化することを目的としています。
具体的なプロジェクトの内容は以下の3部構成となっています。
①「語学力」と「コミュニケーション力」を並行して効率的に向上させる語学講座実施(全10回の授業):
この語学講座は、Beginner、Intermediate、Advanceの3つのレベルにクラスを分けて実施され、講座のテーマは「TOEIC対策」、「ビジネスシーンにおけるコミュニケーションスキル」などです。※AdvancedレベルはTOEIC®830点以上
②実践活動:Advancedレベル以上の学生を対象に、国際展開している日本企業において、英語を使用しての国内インターンシップを実施しました。
③事後学修:TOEIC IPテスト実施と、プロジェクト終了後の語学力の伸長を測るためのコミュニケーション力確認テストを実施しました。
本プロジェクトは、8月7日(火)~9月上旬の期間に実施されました。
実施の結果、TOEICスコア向上者は、55%と半数以上の学生が短期間で成果を出すことができました。
また、インターンシップに派遣した学生は7名おり、その実習内容も英語を使用し、ビジネスシーンにおいて必要なコミュニケーションスキルを身につけることができました。
受け入れ企業側のコメントでは、実際、職場でのコミュニケーションにて十分な英語力を有すると評価され、限られた期間の中で、より実務に近い経験をさせたいという前向きな意見もありました。
次回のプロジェクト実施は2月~3月を予定しております。
多くの学生が受講し、語学スキルおよび、コミュニケーションスキルを身につけ、社会にでる準備になればと期待しています。