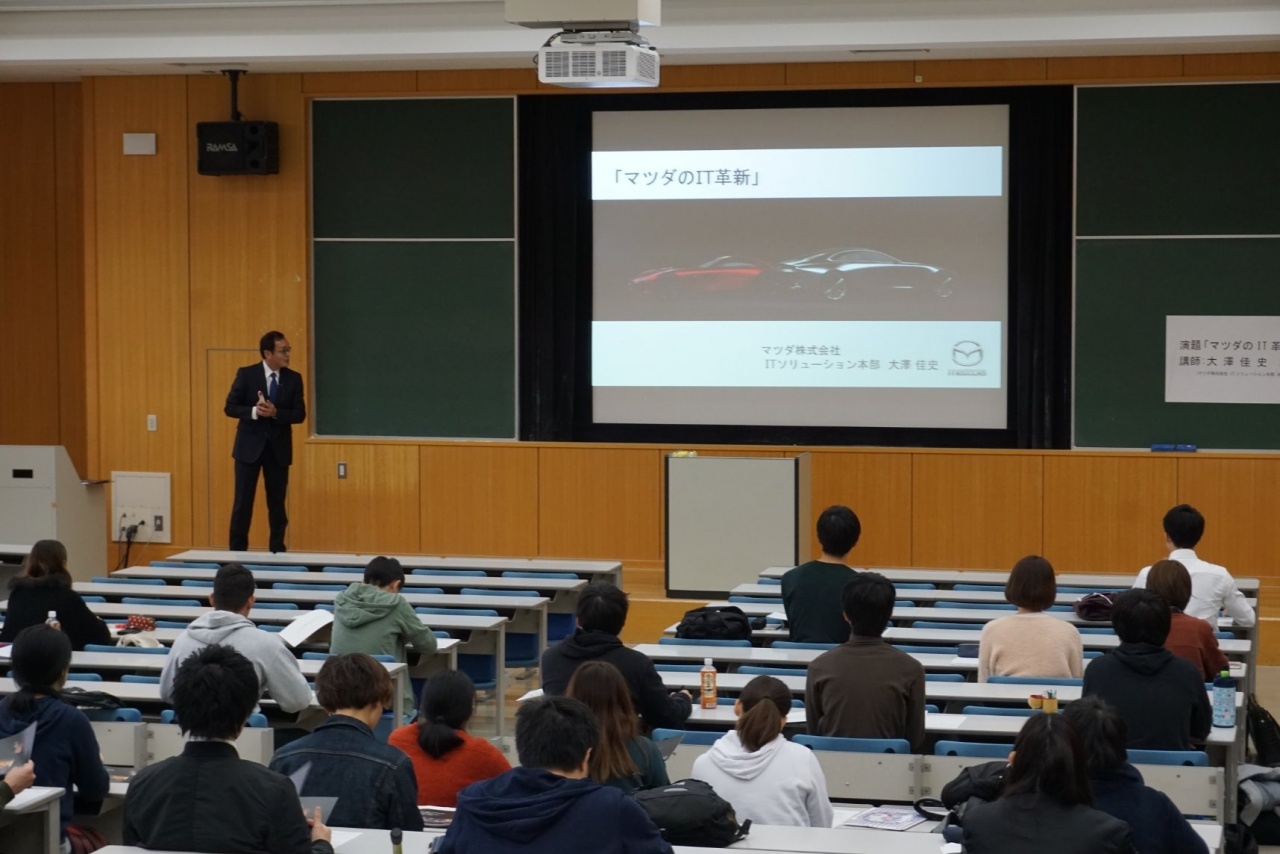【教員の活躍】講義「環境フィールドワーク」にて実習を行いました。(教養教育 丹野研一 先生)【文学部】
文学部教員の講義では、学内外で様々な活動を行っています。その活動とはどのようなものなのか、その一端を紹介するために、文学部にて教養教育科目を担当している丹野研一先生が実施した内容を報告いたします。
講義名「環境フィールドワーク」の実習は、文系コースのなかではやや異質感があるかもしれません。この実習は、私たちの暮らしと環境について、フィールドに出て考えようというものです。滋賀県日野町で、10月20日(土)に農作業を体験しました。予定では前週にも実習するはずでしたが、降雨の影響でトラクターが入れずに、今回だけの実習となりました。天気に左右されて人間の都合通りにはゆかない仕事もあるとわかりました。当日は、NHK滋賀が種まきの様子を撮影にきておりました。