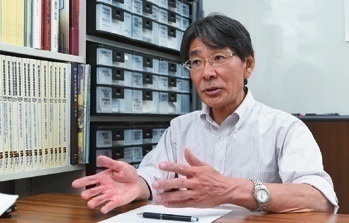国際福祉実習についての展示発表のお知らせ
短期大学部社会福祉学科阪口ゼミの2回生は、フィリピンの貧困や人々の暮らしを多面的に学ぶスタディツアー、インドネシアでの日本語教育や異文化交流等を行う実習、京都市内での在日コリアン等の支援を行う実習を夏休みに実施しました。
これらの実習に関する学修成果についての展示発表を行います。
どなたでも自由に展示をご覧いただけますので、みなさまのご来場をお待ちしております。
《展示期間》
2018年12月6日(木)14:30~2018年12月13日(木)14:00
※ 2018年12月13日(木)の13:20~14:00にご来場いただいた方には実習に参加した学生が展示内容について説明させていただきます。
《展示場所》
龍谷大学 深草キャンパス 和顏館1階 スチューデント・コモンズ「ギャラリー」
〒612-8577 京都市伏見区深草塚本町67
https://www.ryukoku.ac.jp/about/campus_traffic/traffic/t_fukakusa.html