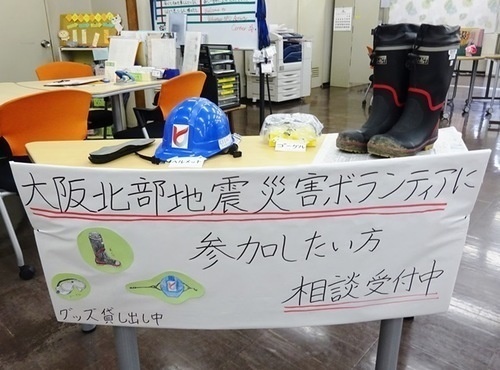【本件のポイント】
・ 日本で年間646万トンにものぼる「食品ロス」の課題に、大学生が地域を巻き込んで取り組みます。
・ 今春、関西で初めて(全国で3番目)開催された「無料スーパー」の取り組みで、今回で2回目の実施。
・ 第1回目の開催では、大学近隣の地域住民100人近くの方が来場し、165種類241品が3時間で完売。約7万kcalのエネルギー、約31kgの食品を循環。 今回は、大学周辺の近隣住民だけでなく、さらに深草区域外の地域住民にもアプローチ範囲を広げ、チラシ掲示やポスティング、ラジオ放送、SNSなどで呼びかけを実施。
龍谷大学政策学部深尾ゼミナールでは、京都市の生ゴミの現状を研究し、将来的に生ゴミをなくすことを目標に活動しています。今回のイベントで行う「無料スーパー」とは、このままだと捨てられてしまうような賞味期限前の食品を寄付で集め、来場者に無料で提供し、食品が手付かずのままゴミになるのは「もったいない」という想いを伝える啓発イベントです。
1.第2回Kyo 0 market(「無料スーパー」)概要
日時 :2018年6月23日(土) 13時~ (商品が無くなり次第、終了)
場所 :龍谷大学深草町家キャンパス (京都市伏見区深草直違橋6丁目303番地)
背景 :日本国内における年間の食品廃棄量は、食料消費全体の3割にあたる約2,800万トン。このうち、売れ残りや期限を超えた食品、食べ残しなど、本来食べられたはずの、いわゆる「食品ロス」は約632万トンとされています。これは、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料援助量を大きく上回る量です。これらの現状を踏まえ、ゼミ活動の一環で京都府の生ごみリサイクル施設「エコの森」へ視察に行った際、 食べられる食品が大量に捨てられている現状を目の当たりにし、深尾ゼミで生ごみの循環、食品ロスの現状についてテーマ研究を行うことになりました。東京都多摩市のNPO法人「シェア・マインド」が行っている「無料スーパー」の取り組み等を参考に調査・研究を進め、食品ロス削減の啓発に焦点を当てた「Kyo 0 market」を開催することに至りました。
2.実施内容詳細:
①もったいない(無料)スーパー
東京都などで既に行われている「無料スーパー」を参考にし、個人(一部企業)から食
品を寄付で集め、来場者に無料で配布するというものです。
②リサイクルかるた
小学生向けに作成したクイズ形式のカルタゲーム。リサイクルした後のものがカルタ
に描かれており、リサイクルされる前の素材が読み上げられます。
③水切りゲーム
生ごみは80%の水分が含まれていることから水切りを体験してもらって、水切りを
行う前と後でどれだけ重さが変わるかというのを体感してもらうゲームです。
④エコカフェ
食品ロスで出たお茶等を活用しそれを飲みながら余った食材の活用レシピを紹介した
り、来場者と大学生が生ごみの現状を一緒に考える会です。
⑤賞味期限カレンダー
来場者に配布するカレンダーで、食品の賞味期限を書き込んでもらうことによって食
品の期限を把握してもらうことを狙いとしています。また、家庭で簡単にできる余っ
た食品を活用したレシピと、今日からできる簡単な意識改革をチェックリストかした
ものを一緒に掲載しています。
3.参考
■第1回kyo 0 market(「無料スーパー」) の様子
深尾ゼミでは、2018年4月に第1回無料スーパーイベント(Kyo 0 market)を開催し、165種類241品の食品が集まり、食品エネルギー約70000kcal、重さ約31kgもの食品を廃棄せずに循環させることが出来ました。今回は、前回よりも更に食品廃棄予定の食品を集め、多くの方に食品廃棄のことについて、考えてもらえるようなイベントといたします。
■深尾ゼミ FMラジオ番組情報
深尾ゼミでは、毎月第1・3土曜日19時7分から30分間 FM79.7「Pick Upper~明日を考える30分~」にて、ラジオ放送を行っております。当ラジオ放送においても、日々のゼミ活動や当イベントに関する告知を行いますので、是非ご聴取ください。
問い合わせ先…龍谷大学 政策学部教務課 担当:奥村・石倉 Tel 075-645-2285