ブラウザからレイアウト自由自在
Layout Module
ここにメッセージを入れることができます。

2020年(令和2年)7月豪雨について Ver.2(一部情報更新)
この度の2020年7月豪雨で被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げ...

一人暮らしの学生への食材支援に京都生活協同組合が協力【学生支援特別推進室】
新型コロナウイルス感染拡大によってアルバイトができなくなるなどの理...
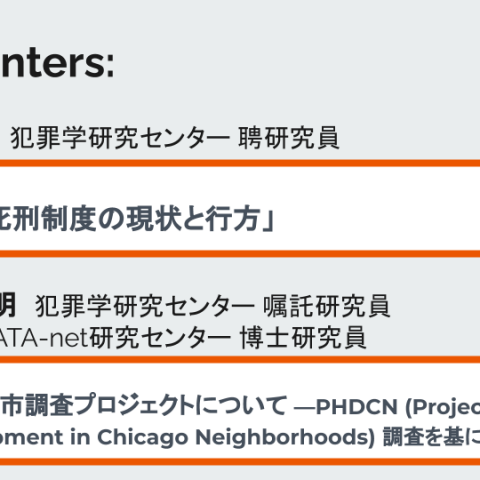
第20回「CrimRC(犯罪学研究センター)公開研究会」開催レポート・前編【犯罪学研究センター】
2020年6月11日、犯罪学研究センターは、第20回「CrimRC(犯罪学研究セン...



2019年度海外留学支援制度(協定派遣)による海外留学の実施について
本学グローバルスタディーズ学科では、グローバルな視点からの知識と思...