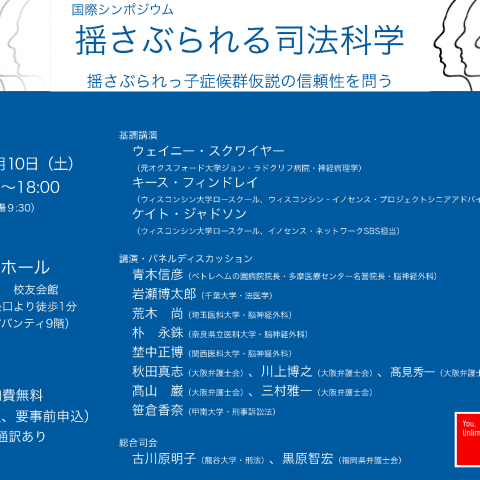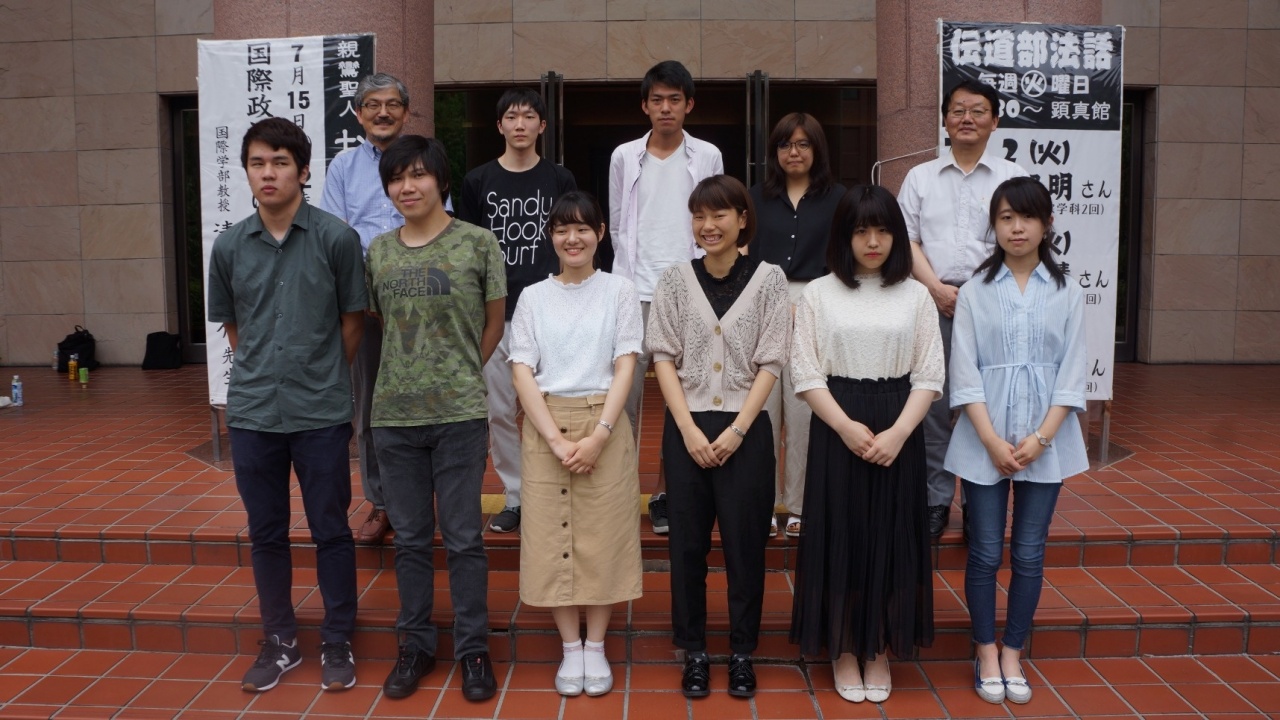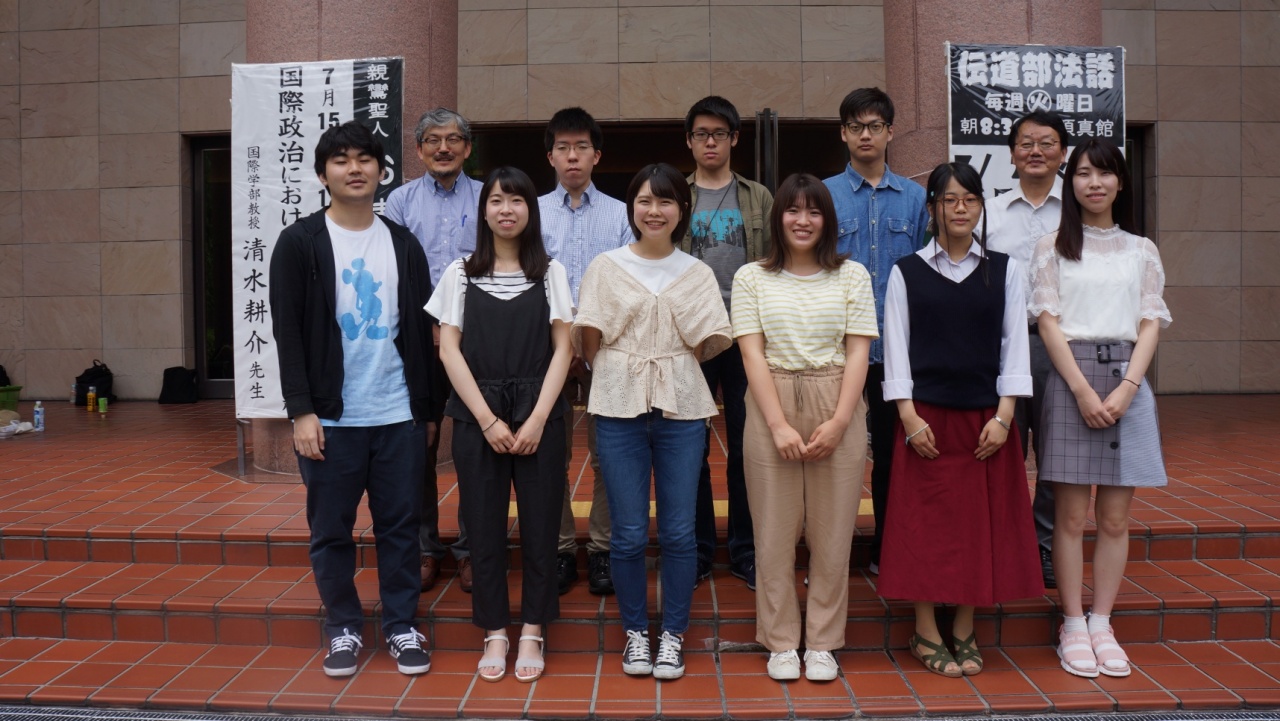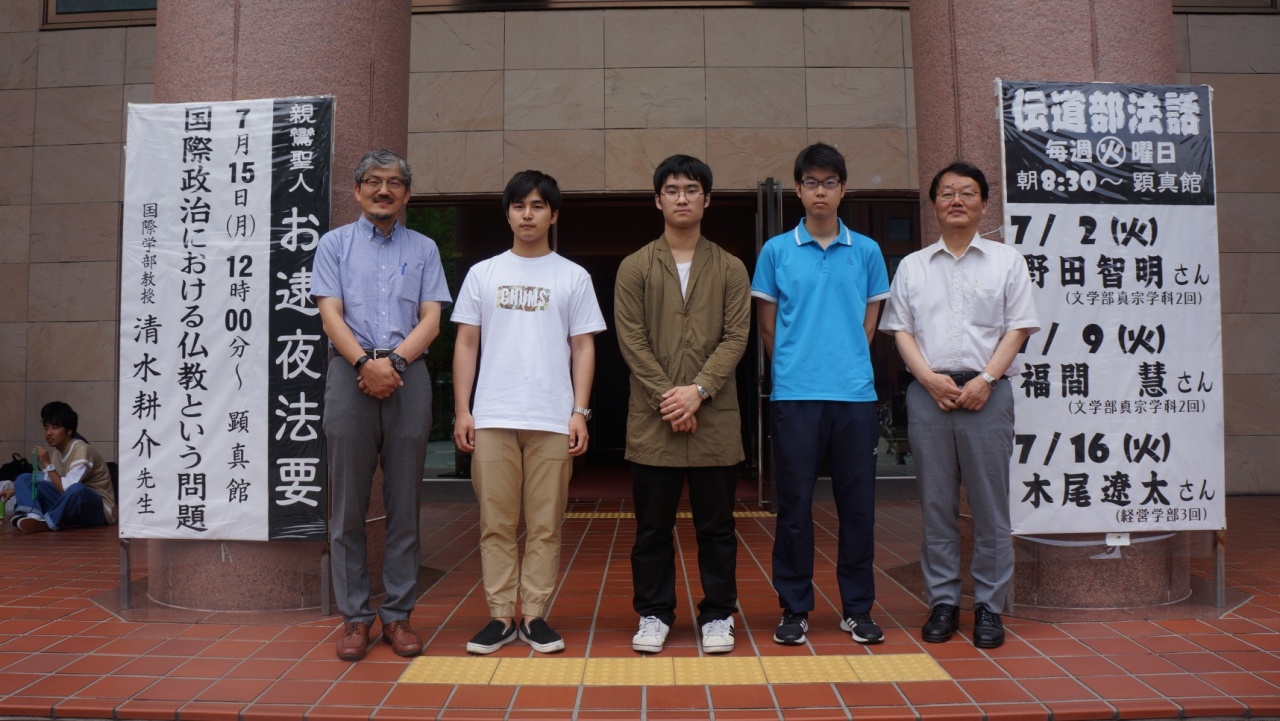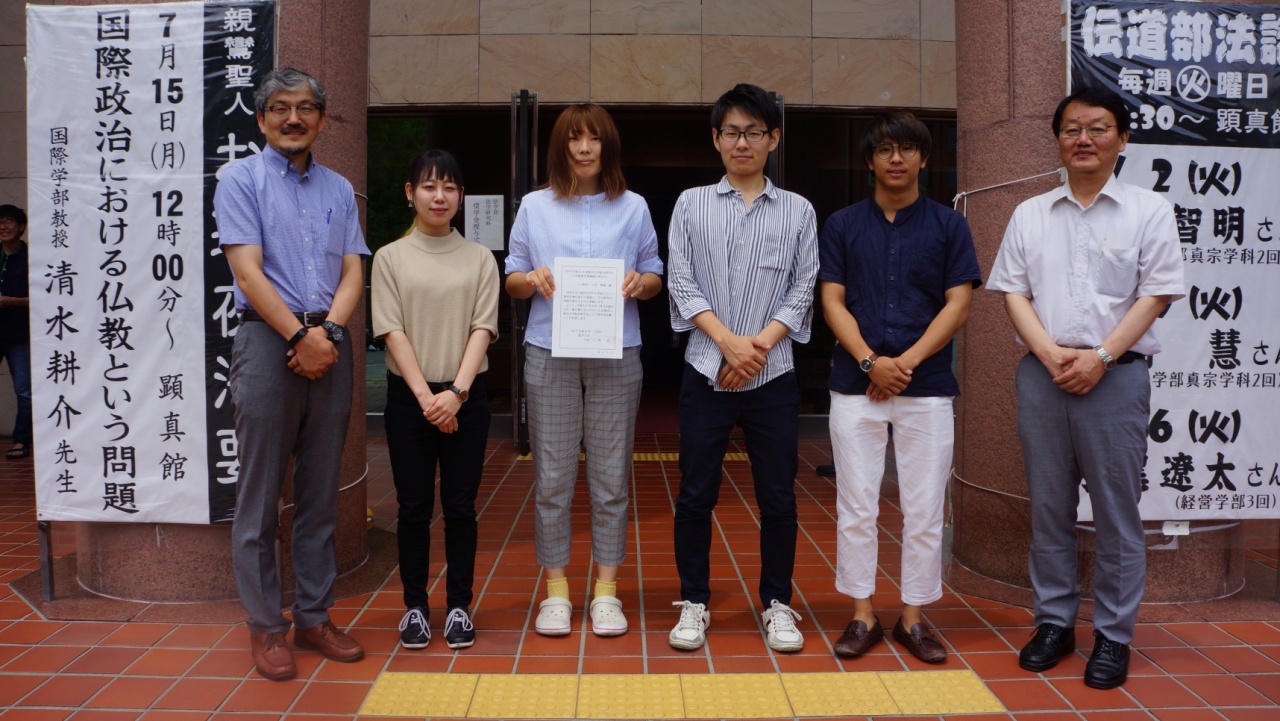【募集】サマーフェスティバル2019ボランティア
『サマーフェスティバル』(通称サマフェス)は、深草児童館で学生スタッフがボランティアをする中で生まれた子どもたちと遊ぶイベントです。児童館に通う子どもたちに夏休みの最高の思い出をつくってもらおうという目的で始まり、今年で6年目になります。また、龍大生にボランティアの楽しさや児童館の存在を知ってもらうことをもう一つの目的として掲げ、現在ボランティア参加を呼びかけています。
サマフェス当日は数種類の遊びを用意します。当日に向けてのおもちゃ作り、リハーサルなども可能であれば参加していただくと、充実感がよりアップすると思います!
あなたもこの夏休みにサマフェスに参加し、ボランティアの一歩を踏み出し子どもたちと最高の思い出をつくってみませんか?
■活動日時・場所
①竹切り@深草地域の竹林 2019年8月3日(土)7:30~午前中
②竹水鉄砲作り@センター 8月7日(水)14:00~
③リハーサル@深草児童館 8月20日(火)12:30~16:00
④サマフェス当日@深草児童館 8月21日(水)10:00~16:00
※雨天の場合は22日(木)
■申し込み方法:
チラシの参加申し込み用紙部分をセンターに持参いただくか、チラシの担当者LINEにアクセスし、氏名・学籍番号・電話番号・メールアドレス・上記①②の参加可否について連絡ください。
■問い合わせ:ボランティア・NPO活動センター(深草)
【TEL】075-645-2047 【Email】ryuvnc@ad.ryukoku.ac.jp

竹水鉄砲遊びの様子(昨年)

室内遊びの様子(昨年)

箱の中身あてゲーム(昨年)

ピンポンカップインゲーム(昨年)