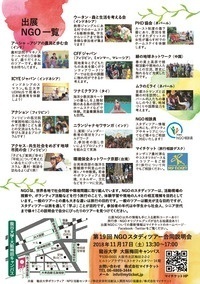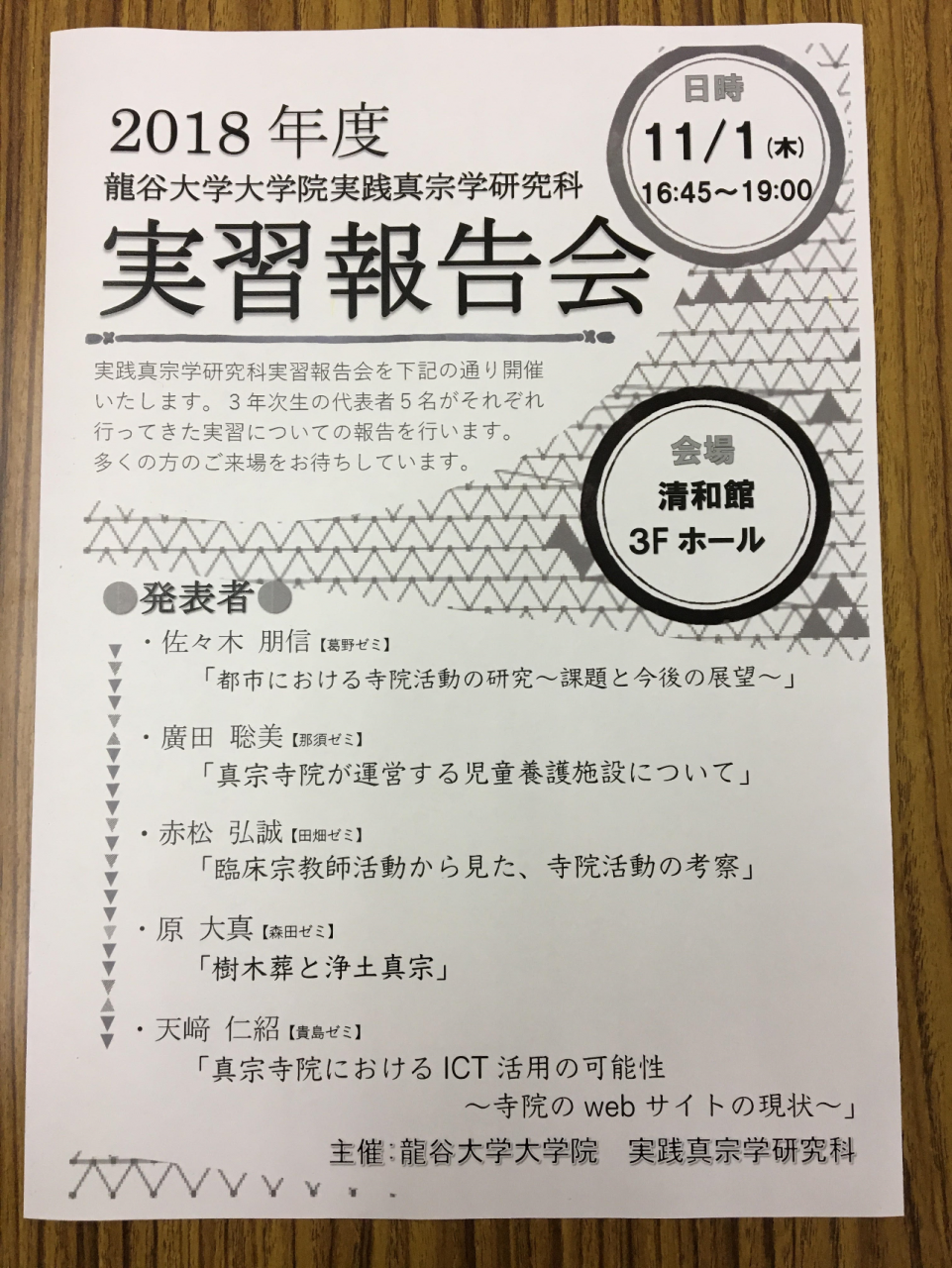【ご案内】NGOスタディツアー合同説明会
来年(2019年)の春休みに海外でのスタディツアー、ワークキャンプを企画しているNGO団体が集まり合同説明会を実施します。
「ツアーの具体的な内容を聞きたい」
「初めてでも、一人でも参加できるの?」
そんな疑問をNGOのスタッフから詳しく聞くことができます。
国際協力やNGO、ボランティア活動に関心がある、スタディツアーへの参加を迷っている人にぴったりな説明会です。
■日時:2018年11月17日(土)13:30~17:00
■会場:龍谷大学大阪梅田キャンパス(JR大阪駅桜橋出口から徒歩4分)
■内容:NGO団体による合同説明会
出展NGO団体についての詳細情報はこちら→
http://myticket.jp/guidance/study-tour-guidance
■参加費:無料
■申し込み:不要
■入退場自由
■抽選会も実施します。時間は16:00以降です。
■共催:龍谷大学ボランティア・NPO活動センター
特定非営利活動法人関西NGO協議会
株式会社マイチケット
■問合せ:ボランティア・NPO活動センター
【TEL】深草キャンパス 075-645-2047
瀬田キャンパス 077-544-7252
【E-mail】ryuvnc@ad.ryukoku.ac.jp