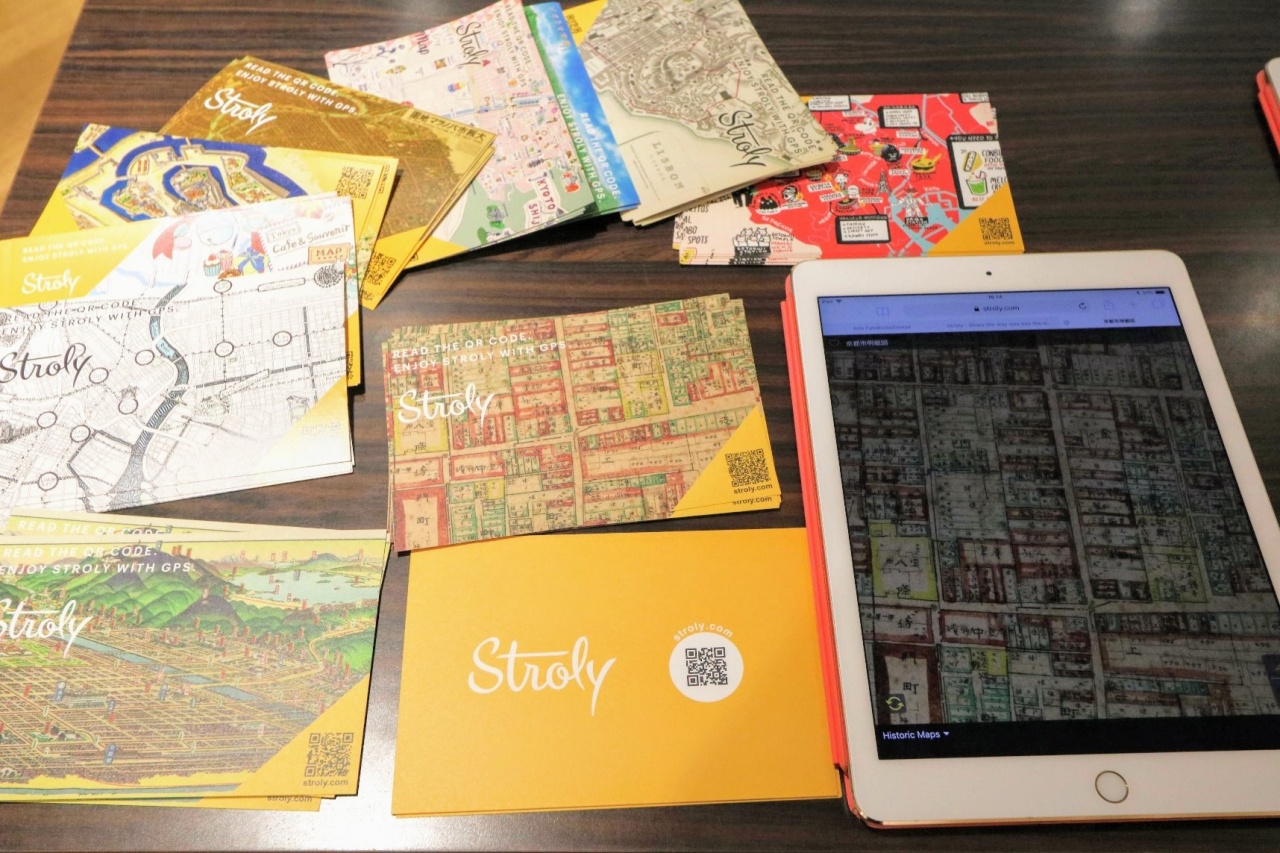第4回公開研究会「性暴力・セクシュアルハラスメントを考えるために――性暴力の顕在化・概念化・犯罪化」を開催【犯罪学研究センター】
2018年10月6日、第4回公開研究会「性暴力・セクシュアルハラスメントを考えるために――性暴力の顕在化・概念化・犯罪化」を、本学深草学舎 紫光館で開催しました。
企画者である牧野雅子(犯罪学研究センター博士研究員)がモデレーターを務め、今回は報道の現場におけるセクシュアル・ハラスメントをテーマに、フリーランスジャーナリストの林美子氏をゲストに迎えました。

ジャーナリスト 林美子氏
林氏は、長らく新聞記者として勤めた後、現在はジャーナリストとして、ジェンダーや労働問題を中心に取材・執筆活動を行っています。本年4月の財務省事務次官による女性記者に対するセクシュアル・ハラスメント問題が表出した際には、メディアで働く女性を代表して発言を行い、「メディアで働く女性ネットワーク Women in Media Network Japan(WiMN)」を立ち上げました。
林氏からは、財務省のセクシュアル・ハラスメント問題の経緯や、それに対するメディアで働く女性たちの反応、WiMNの活動や報道のあり方について、自身の経験や調査結果を交えて、報告がありました。
メディアは、24時間働くことの出来る男性をモデルにした「男社会」であり、女性記者は「二流」の存在と見なされています。このことは、職場内部のセクシュアル・ハラスメントを生み、被害の告発を困難にしてきました。
これまで、取材現場におけるセクシュアル・ハラスメントが表面化されることがなかった背景には、性被害の告発の困難さ、記者の取材源を失うことへの恐れ、セクシュアル・ハラスメントを「問題」にすることができない職場の認識の低さ、自分たちに起きた被害を報道することを躊躇う報道の中立性や客観性にまつわる問題、という、異なる水準の問題があることが指摘されました。WiMNに参加する女性記者の多くは、参加事実を公表していない「匿名」の記者たちです。そのことが、現在のメディアの――そして、社会の――状況を表していると言えます。
質疑応答では、耳目を集めた性暴力事件や、他の職場のセクシュアル・ハラスメント事例、事件報道のあり方にも、議論が及びました。
----------
本公開研究会は、犯罪予防と対人支援を基軸とする「龍谷・犯罪学」の構築を目指す、龍谷大学 犯罪学研究センターの共催で開催しています。
いずれも参加費無料・事前申込不要。どなたでも参加いただけます。
次回は10月27日(土)14:00-16:00開催予定です。 【>>詳細】
・テーマ:「セクハラ:誕生から現在まで」
・登壇者:牟田和恵 大阪大学大学院人間科学研究科教授
※この企画は、JSPS科研費 平成28ー32年度 基盤研究(C) 16K02033<研究課題「近代日本における『性犯罪』抑止政策と法の批判的検討」、研究代表者 牧野雅子(犯罪学研究センター博士研究員)>の一環として実施しています。