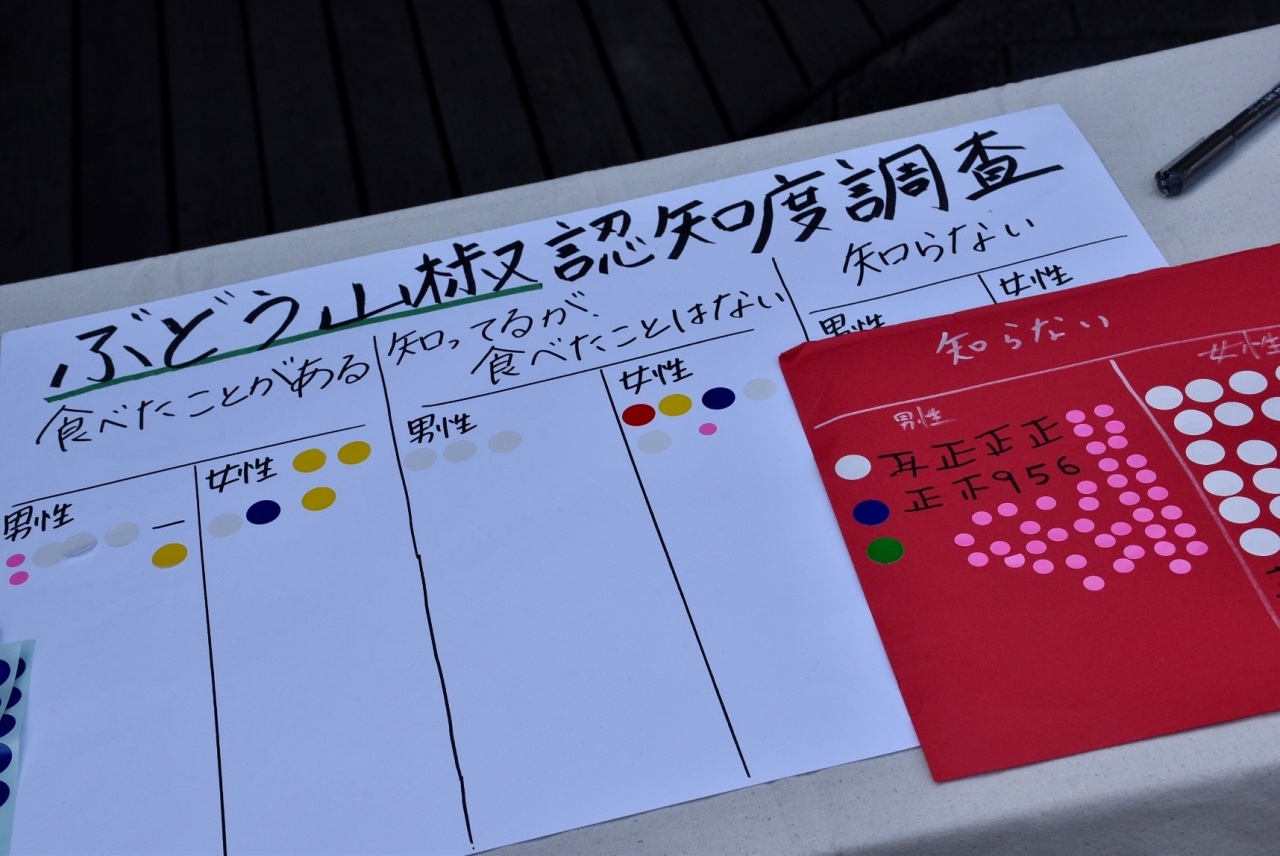龍谷大学臨床心理学会第9回学術講演会の開催【文学部】【文学研究科】
龍谷大学臨床心理学会第9回学術講演会
講題: 刑事司法における臨床心理の可能性 ~認知行動療法は、依存症を回復させることができるのか?~
講師: 石塚伸一先生
(龍谷大学法学部教授、龍谷大学犯罪学研究センター・センター長)
内容: 規範学である刑法学は、事実学である心理学をつまみ食いしてきた」これは、刑事法学者としての偽らざる心境です。その最たるものは、自由意志論です。刑法学者、「人間は、自由な意思決定の下に行為を選択し、それに従って行動し、意図した結果を惹起する。これは、心理学の実証した否定することのできない真実であると語ってきました。しかし、最近、人間は、反射的に行動し、その行動に理由を後付けして、次の行動を追構成している。という報告がなされ、自由意志をめぐる議論が活性しています。しかしながら、刑法学者は、それでもなお、規範論としては自由意志を前提に刑法理論を維持できると強弁しています。あるときは、心理学の裏付けがあるといい、あるときは、心理学に依拠することなく規範論は維持できるという。刑法学とはなんと自分勝手な学問でしょう。今回は、そんな刑事法学者の目から見た心理学への「憧憬と期待」についてお話させていただきます。
石塚伸一先生ご略歴:
1954年東京生まれ。法学博士、弁護士、日本犯罪社会学会会長、アジア犯罪学会理事、日本更生保護学会理事、著書に「刑事政策のパラダイム転換-市民の、市民による、市民のための刑事政策-」(1996年、現代人文社)、「社会的法治国家と刑事立法政策-ドイツ統一と刑事政策学のゆくえ-」(1997年、信山社)、編著「日本版ドラッグ・コート~処罰から治療へ~(DRUGCOURT:from Punishment to Treatment)(2007年、日本評論社)など多数。