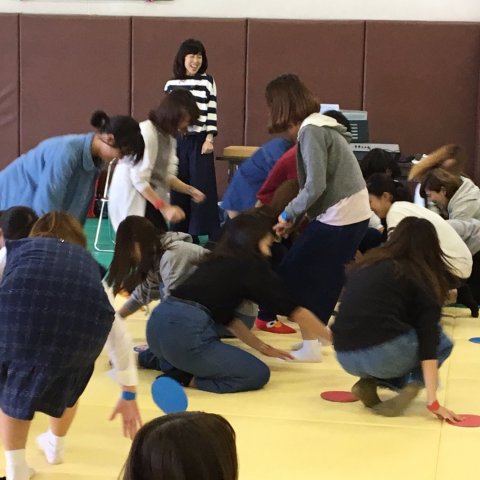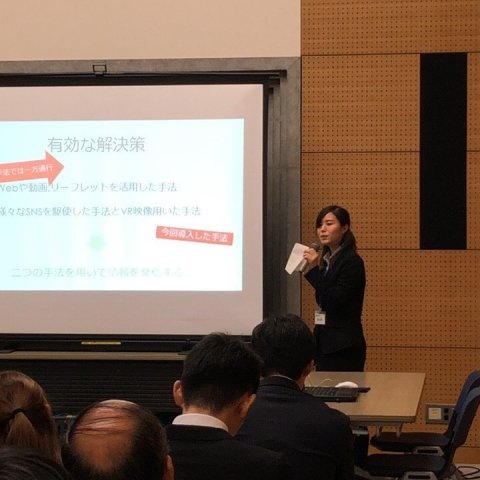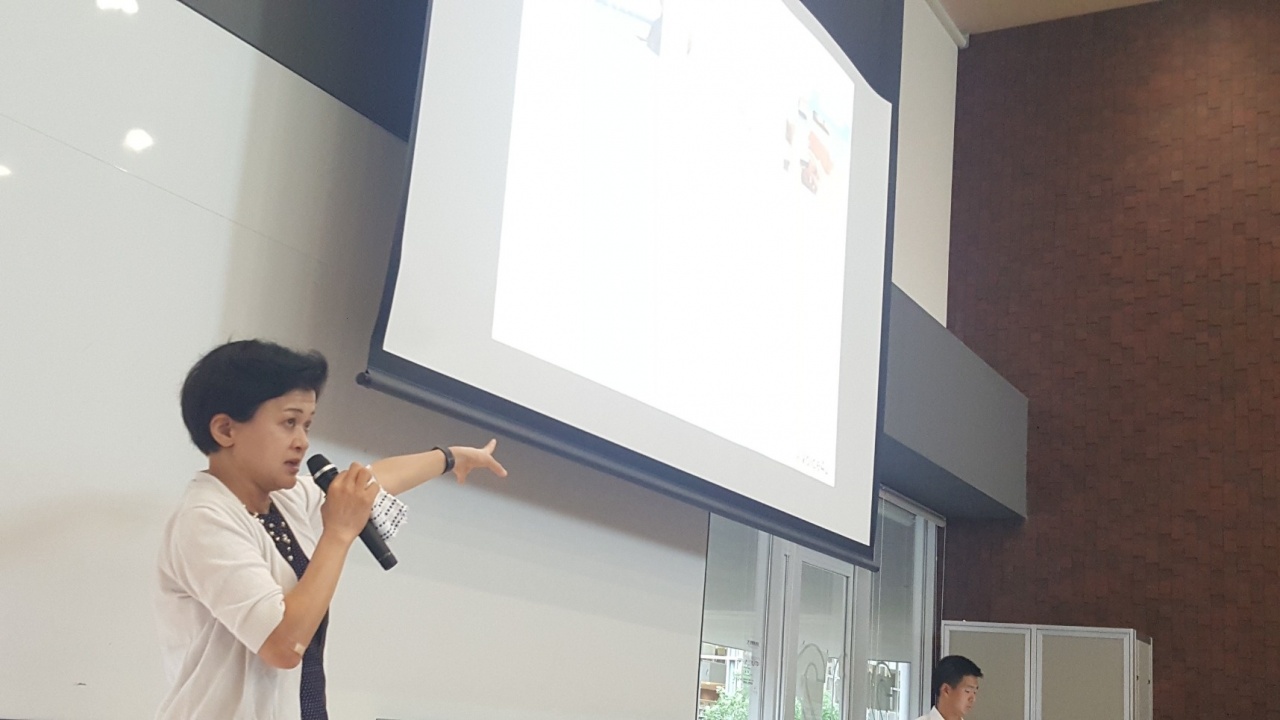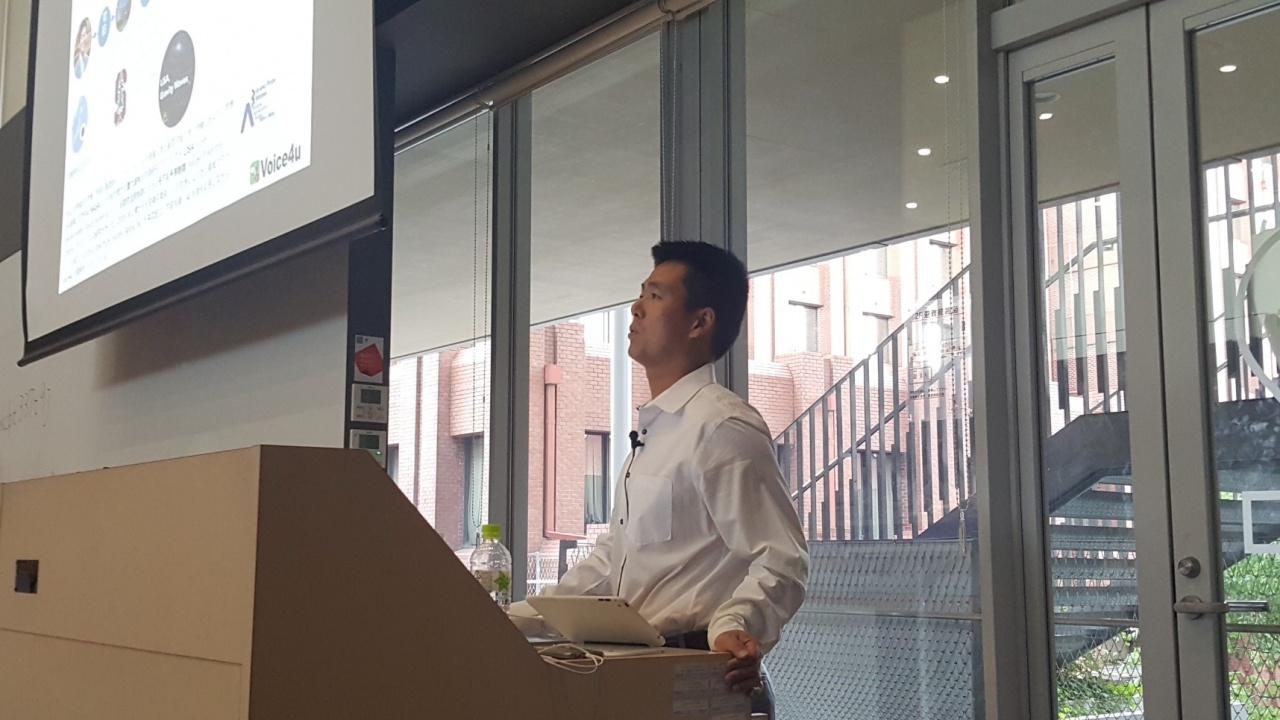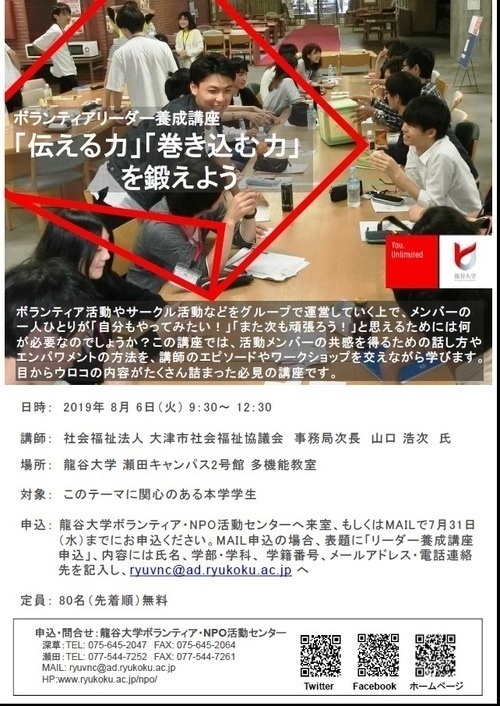2020年4月 「先端理工学部」開設予定(設置届出書類提出中)
学校法人龍谷大学 (本部:京都市伏見区) は、現在の理工学部 (所在地:瀬田キャンパス(滋賀県大津市)) を改組し、2020年4月、「先端理工学部」を開設いたします(2019年6月 文部科学省へ設置届出書類提出中)。
1989年、国内の仏教系総合大学で初めて設置された理工学部は、自然、社会と科学が調和する豊かな未来に向け、倫理観を携えた技術者、研究者の育成に努めてまいりました。
先端理工学部は、これらの取り組みをさらに発展させ、国連が定めた17の持続可能な開発目標「SDGs」や、日本政府が提唱する未来社会のコンセプト「Society5.0」など、社会の変化に対応できる理工系人材育成を目的に、学生や社会のニーズから逆算した教育制度の改革、カリキュラムの充実、教育環境の整備を行います。
また、本改組においては、2018年6月29日に公布・施行された「大学設置基準及び大学院設置基準の一部を改正する省令(平成30年文部科学省令第22号)」にて、新たに設けられた「課程」制度を、国内の理工系学部として初めて導入します。同制度は、理工系学部の課題であった「タコ壺型の専門教育」から、多様な学習ニーズに対応した「分野横断型の専門教育」の実現を可能としました。
なお、「先端理工学部」の教育理念や特徴および概要は、先端理工学部特設サイトや、1月16日に発表を行ったプレスリリースから確認いただけます。