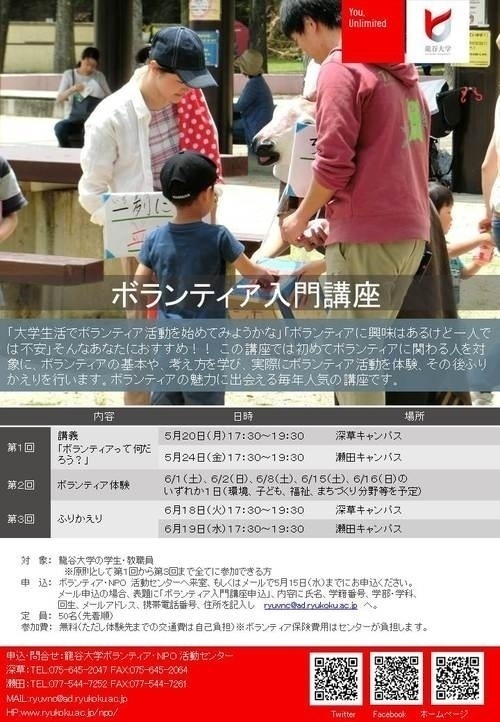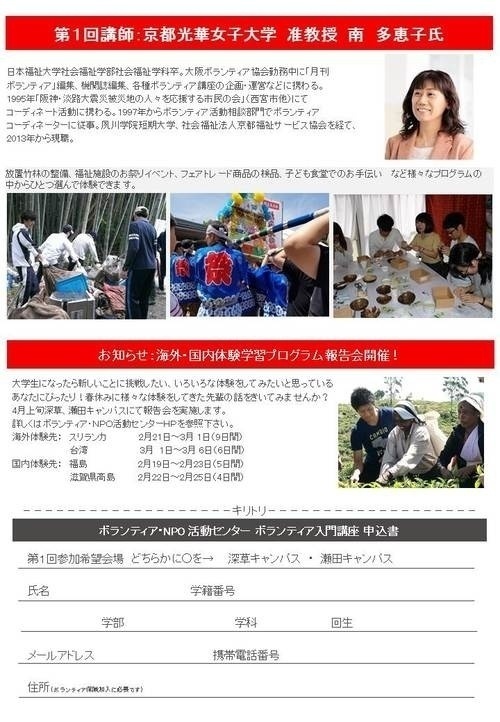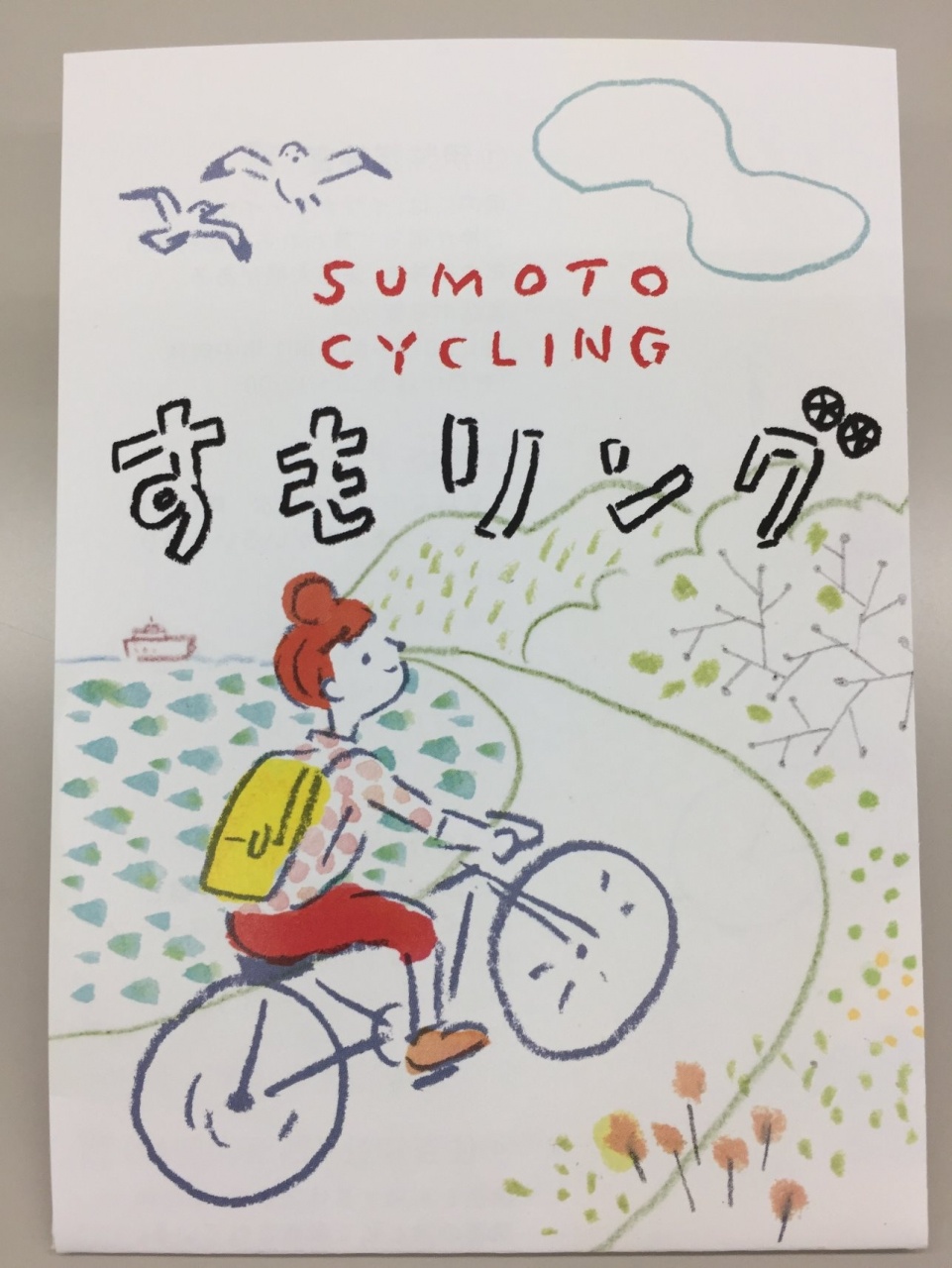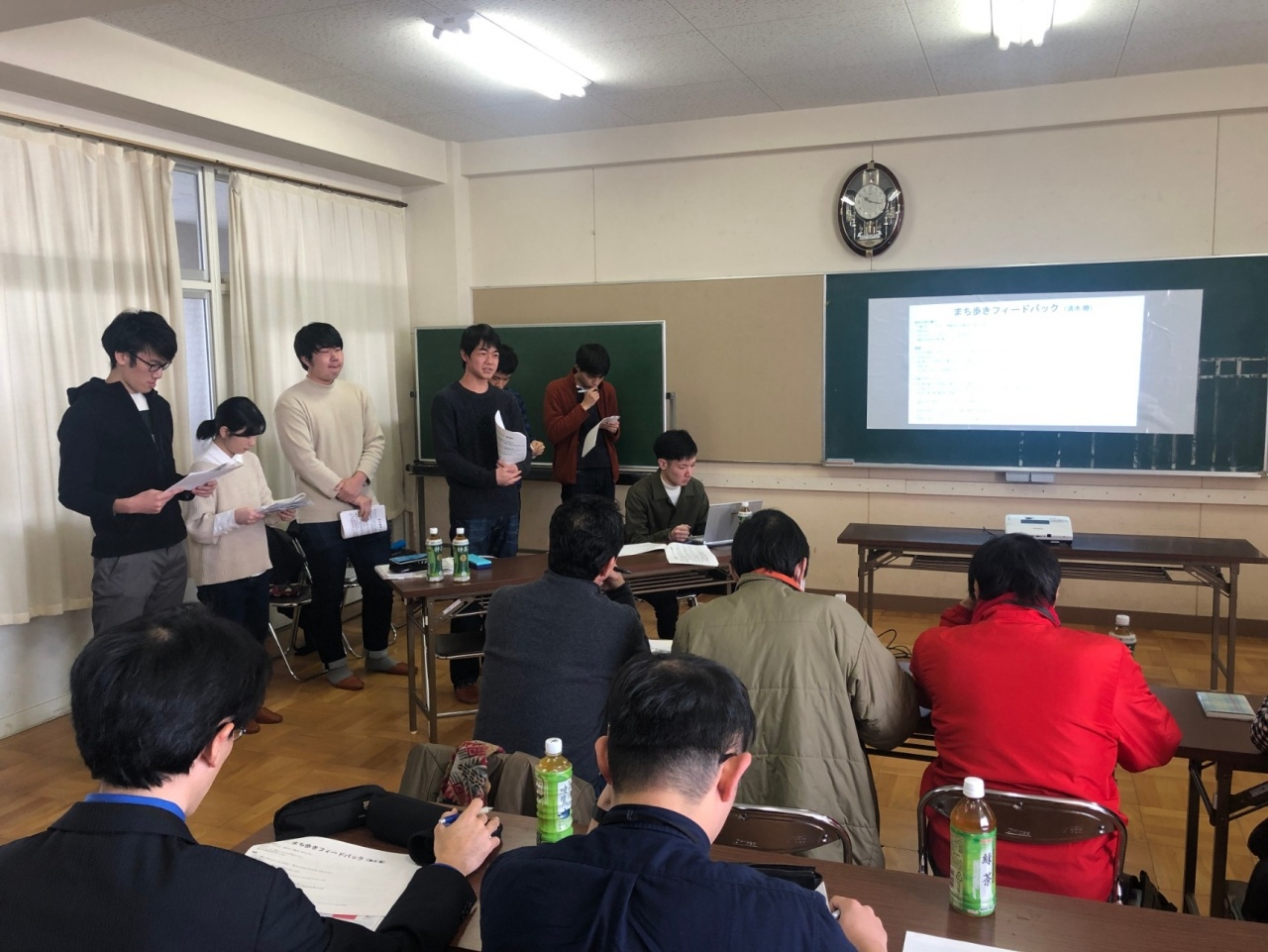【募集】ボランティア入門講座 参加者募集!
「大学生活でボランティア活動を始めてみようかな」「ボランティアに興味はあるけど一人では不安」そんなあなたにおすすめ!!
この講座では初めてボランティアに関わる人を対象に、ボランティアの基本や考え方を学び、実際にボランティア活動を体験、その後ふりかえりを行います。ボランティアの魅力に出会える毎年人気の講座です。
2018年度の様子はこちら
2019年度の内容:
【第1回】講義「ボランティアって何だろう?」
講師 南 多恵子 氏(京都光華女子大学 准教授)
5月20日(月)17:30~19:30 深草キャンパス 和顔館B106教室
5月24日(金)17:30~19:30 瀬田キャンパス 2号館多機能教室
【第2回】ボランティア体験
6月1日(土)、6月2日(日)、6月8日(土)、6月15日(土)、
6月16日(日)のいずれか1日体験 ※6/8は調整中
(環境、子ども、福祉、国際、まちづくり分野等を予定)
【第3回】活動のふりかえり
6月18日(火)17:30~19:30 深草キャンパス 和顔館B106教室
6月19日(水)17:30~19:30 瀬田キャンパス 2号館多機能教室
■募集対象:龍谷大学の学生・教職員
※原則として第1回から第3回まで全てに参加できる方
■募集人数:50名(先着)
■参加費:無料 ※第2回の体験先へ向かう交通費は自己負担です。
※ボランティア保険はセンターが負担します。
■申込方法:
・ボランティア・NPO 活動センターへ来室、もしくはメールで5月15日(水)までに
お申込ください。
・メール申込の場合、表題に「ボランティア入門講座申込」、内容に
第1回参加希望会場(深草OR瀬田)、氏名、学籍番号、学部・学科、回生、メールアドレス、
携帯電話番号、住所を記入し、ryuvnc@ad.ryukoku.ac.jpへ
・申込後の連絡はメールでやりとりすることが多いため、@ad.ryukoku.ac.jpが
受信できるように設定しておいてください。
■申込・問合せ:ボランティア・NPO活動センター
【TEL】深草キャンパス 075-645-2047/瀬田キャンパス 077-544-7252
【E-mail】ryuvnc@ad.ryukoku.ac.jp