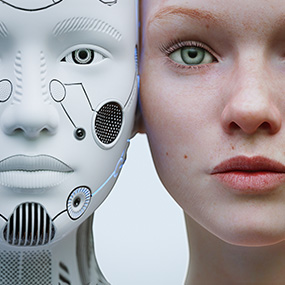監修 浜井 浩一 / 龍谷大学法学部・教授
1. 「反省=更生」という誤解
「しっかり反省しているのか?」
犯罪加害者に向けられる社会からの視線には、しばしばそんな問いが含まれる。しかし、浜井浩一教授(龍谷大学法学部)が指摘するのは「反省=更生」ではないということだ。「反省とはあくまで内面的なプロセスに過ぎず、更生には社会的な環境整備が不可欠」と浜井教授は語る。
たとえば少年院では近年、「反省を促す」だけではなく、再非行を防ぐための教育や環境づくりにも力が注がれるようになっている。支援の現場では、加害に至る背景として「生きづらさ」が注目されているためだ。学力の不足、人間関係を築くソーシャルスキルの未熟さ、自尊感情の低さ、他人を信じられない心の壁──こうした課題に対し、教育や心理的サポートによって改善を図る取り組みが進んでいる。
「幸せな状態で犯罪をする人は、ほとんどいません。だからこそ『幸せに生きられる状態』を整えること。これが更生支援の前提となります」と浜井教授。本人が社会の中で幸せに生きていける力を身につけるためには、学び直しや支え合える人間関係の再構築、自信の回復といった環境的支援が欠かせない。反省しているかどうかだけに着目すると、そうした立ち直りのチャンスを見失いかねない。
2025年6月に施行された改正刑法では、「懲役刑」と「禁錮刑」の区分が撤廃され、新たに「拘禁刑」が導入された。この制度においても、従来のように労務を課す「懲らしめ」ではなく、受刑者の背景に応じた教育や就労支援を行い、「立ち直りを支える」ことを刑の目的として正式に位置づけている。一方で、こうした加害者の立ち直りを促す施策に対しては、被害者や遺族の心情を軽視しているという批判が懸念されるのも事実だ。そのため、拘禁刑導入に先立ち、被害者や遺族が加害者に直接心情を伝えられる仕組みとして、「被害者の心情伝達制度」が設けられた。これは、加害者に被害者の立場への想像力を持たせるだけでなく、被害者自身が『加害者に思いを伝える機会』を通じて心情の整理を図り、回復への一歩を踏み出すことも目的としている。被害者を置き去りにしない、被害者も含めた社会全体の「回復」を目指す取り組みだ。
少年院などでは、以前から被害者の思いを伝える教育が行われてきた。しかしなかには、被害者やその遺族からの「あなたには一生不幸でいてほしい」といった言葉を受けて、立ち直りが困難になる事例もある。自尊感情の低さが再非行のリスクを高めることがわかっている今、支援者たちは「被害者の思いに向き合うこと」と「社会で生きる力を取り戻すこと」のはざまで、葛藤を抱えながら、加害者支援と被害者支援の両立を模索している。
2. 「被害者支援vs加害者支援」の二項対立を抜け出す
被害者への手厚い支援を強化すれば加害者が放置される、一方で加害者支援を充実させれば「被害者の感情を無視している」といった具合に、犯罪加害者と被害者をめぐる支援はどちらか一方の支援に偏らざるを得ないかのような発想に陥りがちだ。だが浜井教授は、その対立を抜け出す視点こそが、現在の社会に必要だと話す。
「立ち直り支援とは、対象が誰であれ、どちらも『回復支援』なのです。加害者だけではない。被害者も、そしてその家族も、何かによって壊された日常を取り戻していく必要がある。その意味では本質的に、加害者支援も被害者支援も、目的は『日々の回復』という点で共通しています」。
ノルウェーでは、加害者に対する支援が充実していることが知られているが、実はそれ以上に、被害者への支援が手厚く設計されている。刑罰の目的も「償い」にとどまらず、加害者の更生と被害者の回復を両立させる「修復的司法」の考え方が社会に根づいており、その結果、再犯率も低下傾向にあるという。
一方で、日本の支援制度は縦割りのままだ。障害者、高齢者、生活困窮者、犯罪加害者、犯罪被害者――それぞれへの支援が別の制度、別の担い手によって運用され、担当領域間の利害対立も生じやすい。
だが本来、支援が必要な人びとにとっての課題の根っこは共通している。たとえば、少年院にはいわゆる “ニート”状態の若者が多く、刑務所には職や家がないことから犯罪へと走った受刑者が多い。そこには、「孤立」や「居場所のなさ」といった、生きづらさの共通項が横たわっているのだ。実際、刑務所内に高齢者や障害者が多くいることが明らかになるにつれ、「福祉的支援があれば犯罪に至らなかったのではないか」という認識が社会に広がりつつある。
「必要なのは『普通の生活』を取り戻す支援。孤立を防ぐ支援を社会全体でどう担保していくのか。つまり、社会がどれだけ包摂的であるかが問われているのです」。
福祉と司法、縦割りを超えた支援体制を構築し、誰もが『普通の生活』を取り戻せる社会への具体的な連携を進めていく必要がある。「被害者か加害者か」という二項対立ではなく、誰もが孤立せず、包摂される社会を目指すこと。その視点の転換こそが、支援を「お互い様」のものとして捉えるための重要な一歩となる。
3. 支援の持続性を担保する「仕組み」と「人」
立ち直りの支援を単発的な対応にとどめず、持続可能な形で続けていくにはどうすればよいのか。浜井教授は、制度としての裏付けと、当事者に伴走し続ける支援者の存在、その両方が不可欠だと語る。
更生支援を大きく前進させる「立ち上げ時の熱量」は、担当者の交代や立ち上げメンバーの離脱によって徐々に薄れていくことが多く、継続可能な状態をどうつくるかが問われる。そこで注目されているのが、支援を「仕組み化」し、制度として根づかせていくアプローチだ。たとえば奈良県では、イタリアの「ソーシャルファーム法」を手本に、受刑者を雇用する会社を財団法人として設立、社会的に弱い立場にある人々の社会参加を後押しする取り組みが行われた。条例による制度面の支援と、伴走する委員会の存在が、取り組みを継続的に支える仕組みとなっている。
もうひとつの要となるのが、当事者に向き合い続ける「熱意ある支援者」の存在だ。たとえば、2006年に発生した下関駅放火事件は、支援のはざまに取り残された受刑者の姿を浮き彫りにした事例と言えるだろう。重要文化財である下関駅舎に放火した受刑者は、当時74歳。20代から放火を繰り返し、10回にわたり刑務所を出入りしていた。彼は出所のたびに家も身寄りもない状態で、行き場を失い続けた。74歳で迎えた10回目の出所後、「住民票がない」という理由で支援を求めて訪れた複数の自治体に門前払いされた末、下関駅に辿り着く。深夜という時間帯もあり、人的被害はなかったものの、火をつけた駅舎は全焼。「彼にとって『火をつけること』は刑務所に戻るための手段。それ以外の選択肢を知らなかったという点で、孤立が招いた結果だったと言えるでしょう」。
この事件を知り、支援を決意したのが、九州でホームレス支援に取り組んでいた奥田知志さんだ。「自分たちの支援が届かなかった責任でもある」と捉え、彼との面会を重ね、検察への嘆願書提出や控訴回避などを経て、彼の出所後の身元引受人になる。結果、彼は初めて「迎えに来てくれる人」がいる出所を経験することとなった。出所後は奥田さんの運営するNPO法人の施設で支援を受けている。80代半ばで出所して、今年で94歳。一度も再犯することなく、今日に至っている。
こうした支援者の存在は、制度ではカバーしきれない空白を埋める重要な役割を果たす。浜井教授は、「この人に頼まれたら断れない」と思わせるような人物が中心となり、つくられていく関係性が、支援を支える推進力になると語る。とはいえ、そうした支援者をプログラムなどを用いて「育成する」ことは難しいと、浜井教授は考えている。「現場での経験や偶発的な関わりの中から『目覚めていく』という感じに近い。最初は頼まれて断れず、気づけばのめり込み、頼られる存在になる。そんな流れで自然と『熱意ある支援者』になっていく人がいるんです」。
だが一方で、いくら熱意があっても、支援者が孤立するような状況では、支援そのものが崩れてしまう懸念がある。持続可能な支援のためには「熱意ある個人」の熱量を活かしながらも、一人に過度に依存しない仕組みづくりが必要だ。支援者を孤立させないためにも、浜井教授は、支援者になる可能性がある人を、積極的に巻き込んでいくことが重要だと強調する。「この人ならできるかもしれない」と誰かが声をかけ、実際に引き受けた人が、結果として重要な担い手になることがある。熱意のある個人と、それを持続させ、孤立させない制度とネットワーク。その両輪があって初めて、立ち直りの支援は持続可能なものとなる。
4. 「助けて」と言える社会に向けて
浜井教授は、「犯罪者には特別な人格的欠陥がある」という見方を明確に否定する。犯罪とは、もともと社会の周縁に追いやられ、困難を抱えた人々が、その生きづらさを行動として表出させた結果であることが多く、その困難は決して他人事ではないという。
迷惑を「かける人」と「かけられる人」に分けるのではなく、「自分もいつか誰かに迷惑をかけるかもしれない」という想像力をもったうえで、お互いに支え合うことを前提として社会を捉えること。その視点こそが、「お互い様」に基づく社会設計の出発点となる。
こうした視点を実践するヒントが、イタリアの制度にある。イタリアの「ソーシャルファーム法」では、障害者、薬物依存者、外国人、元受刑者といった属性で被支援者を区分するのではなく、「困難を抱える人々」として包括的に支援する仕組みを採用している。ラベルで人々を分類して「誰を助けるべきか」を天秤にかけるのではなく、どうすれば多様な属性や状況を包摂できるかという視点から社会設計を進めることで、結果として誰にとっても生きやすい社会がつくられるのである。
困難を抱えるすべての人が、支援を必要とするタイミングで安心して声を上げられること。そして、その声に社会がきちんと応える仕組みが整っていること。浜井教授は、日本社会に根づく「迷惑をかけてはいけない」という強い規範意識が、こうした社会をつくる動きを抑え込んできたと指摘する。精神障害者の長期入院率が他国より高いことなどに象徴されるのは、「『迷惑をかける人』については家族が責任を取るべきだ」という価値観の根強さだ。「迷惑をかける人は家族が責任をもって社会から隔離する」と考えると、家族はその人を閉じ込めるか施設に強制的に入れるしかなくなってしまう。これは地域や社会全体で支え合うことを目指す、「お互い様」の精神とは真逆の結果を生み出しかねない。
実際、老いや病気、失業や事故など、人生の中で立場が一変する出来事は誰にでも起こりうる。どれほど健康で順調な人生を送っていても、ある日を境に「助ける側」から「助けられる側」へと変わる可能性がある。そして多くの人が、実はその両方を同時に経験している。
だからこそ、「明日は我が身」という意識を一人ひとりが持ちながら、困難を抱えた人が、「助けて」と声を上げられる社会、そしてその声を社会全体で受け止める仕組みづくりを、領域を横断して進めていくこと。それが誰もが安心して暮らせる未来への一歩になるだろう。