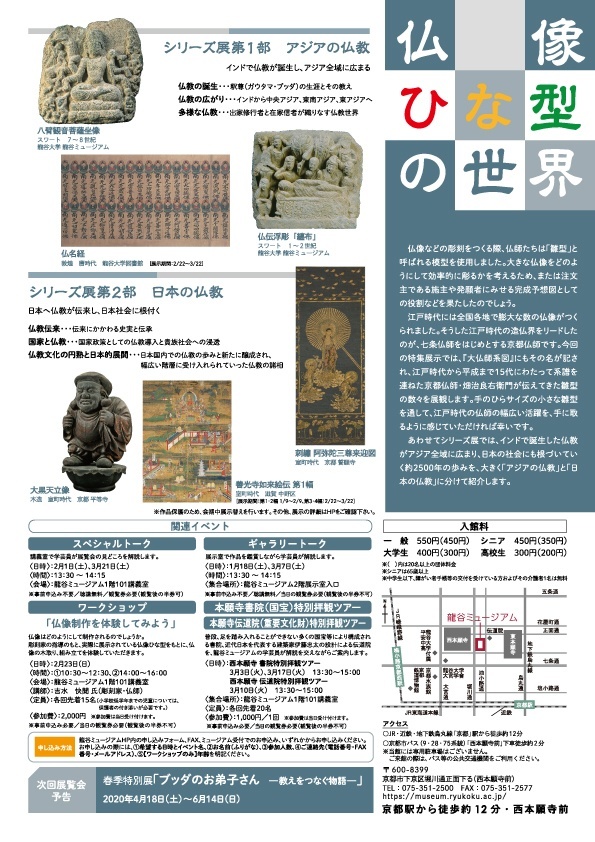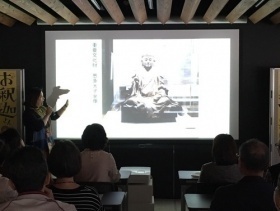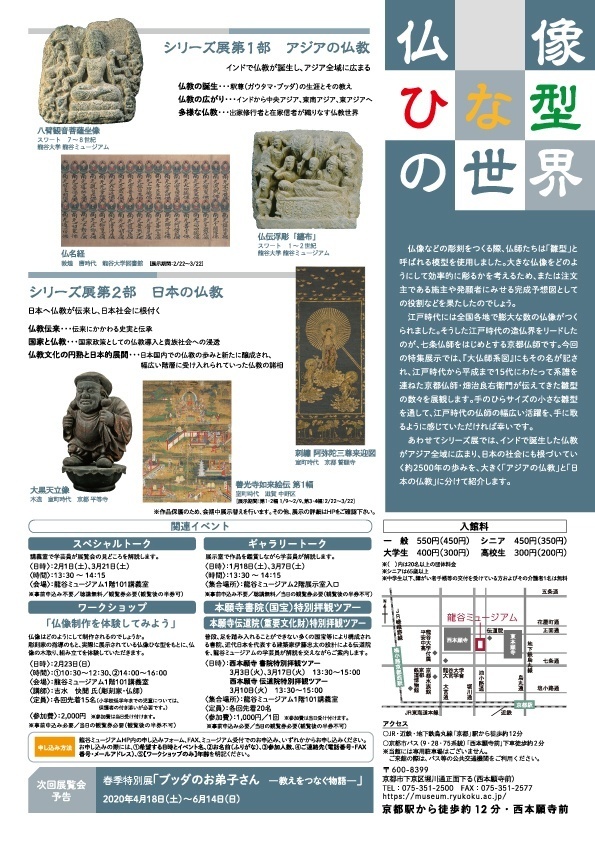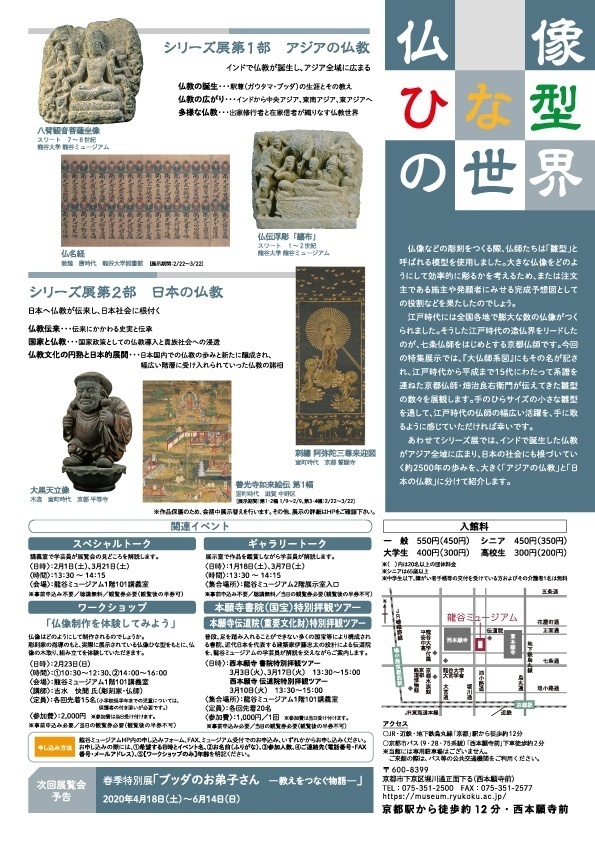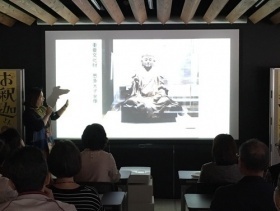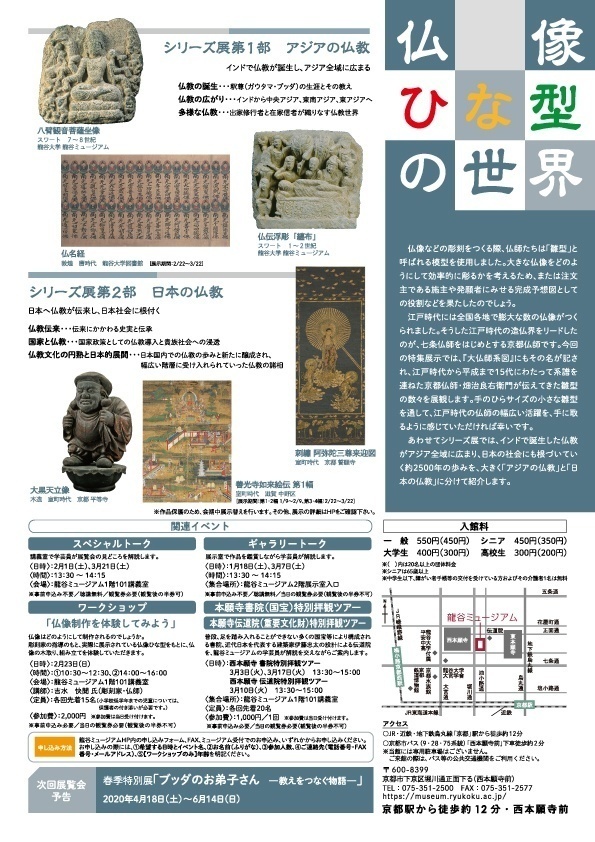「第78回公開研究会」の開催について
龍谷大学矯正・保護総合センターでは、本学犯罪学研究センターと共催し、第78回公開研究会を下記のとおり開催します。
つきましては、興味・関心のある方は奮ってご参加ください。多くの方の参加を心よりお待ちしております。
記
日 時:2020年1月30日(木) 17時00分~(2時間程度)
場 所:龍谷大学深草学舎至心館1階フリースペース
報告者1:龍谷大学深草BBS会の活動(NPO法人OMOIYARIプロジェクト主催の
イベントへの参加報告)
報告者2:京都コングレスユースフォーラム参加チームの活動(法務省主催の
政策提案ワークショップへの参加報告)
報告者3:日本刑事政策研究会・日本BBS連盟主催「わかものシンポジウム」
への参加報告 (法学部4回生松井翼)
【公開研究会事務局】
龍谷大学 矯正・保護総合センター 〒612-8577 京都市伏見区深草塚本町67 至心館1階
TEL: 075-645-2040/FAX: 075-645-2632