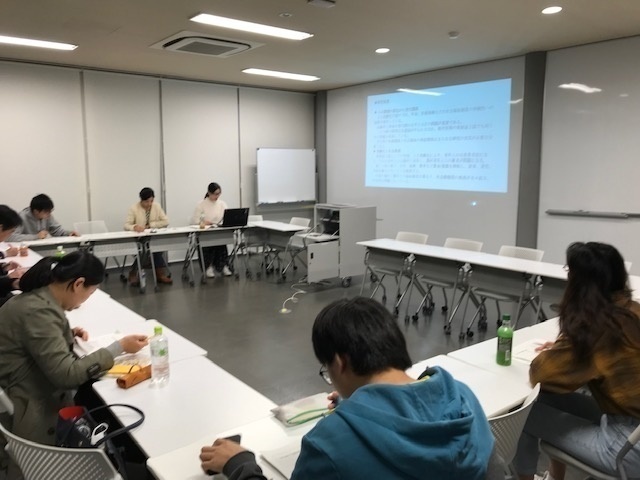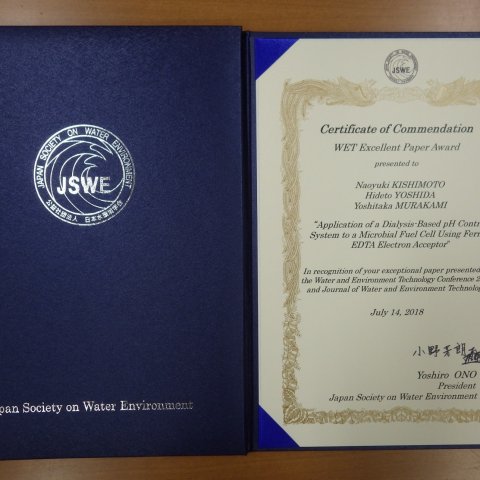2020年4月13日~15日、国立京都国際会館において、京都コングレス・ユースフォーラム(以下、ユースフォーラム)が開催されます。それに伴い、参加予定の学生に日本の刑事司法制度に関する理解を深め、ユースフォーラムにおける活発な議論につなげるため、事前準備の一環として、京都所在の法務省関係機関における業務説明会が行われました。
犯罪学研究センターでは「京都コングレス・ユースフォーラムへの道のり」と題して、参加学生の皆さんの活動の様子をシリーズで紹介しています。今回は、京都地方法務局の業務説明会に参加した、山下敦史さん(龍谷大学法学部法律学科2回生・石塚ゼミ)の参観レポートを紹介します。

山下敦史さん(龍谷大学法学部法律学科2回生・石塚ゼミ)
________________________________________________________________
京都地方法務局を訪問して
2019年10月31日、京都地方法務局人権擁護課の業務説明会に参加してきました。内容は①人権の擁護②インターネットの人権について③子供の人権SOSミニレター事業について各20分ずつで主に人権のことを中心にお話をお伺いしました。人権擁護課が掲げる主な人権課題は多様でしたが、本日はインターネットと子供の人権について主にお話しをお伺いしました。
法務省の人権擁護活動は、人権啓発活動、人権相談、人権侵犯事件の調査・処理を行っているそうです。人権相談では、人権擁護委員の方々が対応しているそうで、弱い人々の立場に寄り添っているという印象を感じました。また、NTTドコモと連携してスマホ・ケータイ人権教室を開催しているそうです。対象は中学生で、インターネットのリテラシー向上に取り組んでいるそうです。
インターネットについての法務局人権擁護課の取り組みについては①相談②助言③削除依頼⓸削除要請という形態で行っていました。法務局自体は削除をすることができないため、相談を受け助言をしているそうです。相談者に削除依頼の仕方を教え、削除依頼ができない場合には、法務局が代行して削除要請を行っています。
子どもの人権SOSミニレターについて、相談しにくいことを手紙で送るという形式で、1万件ほど相談件数はあるそうです。内容の一部を見せていただいたのですが、子供の抱える深い闇や悲痛な叫びを感じました。
今回地方法務局訪問を通して、京都地方法務局が人権問題に対してどのような取り組みをおこなっているのかということを知ることができました。ユースフォーラムを前に一部ではありますが、日本の人権問題への取り組みを知れてとてもよかったです。人権問題は弱い立場やマイノリティの人々に起こりやすい問題で、誰でも被害者にも加害者にもなることがあると感じました。
山下敦史