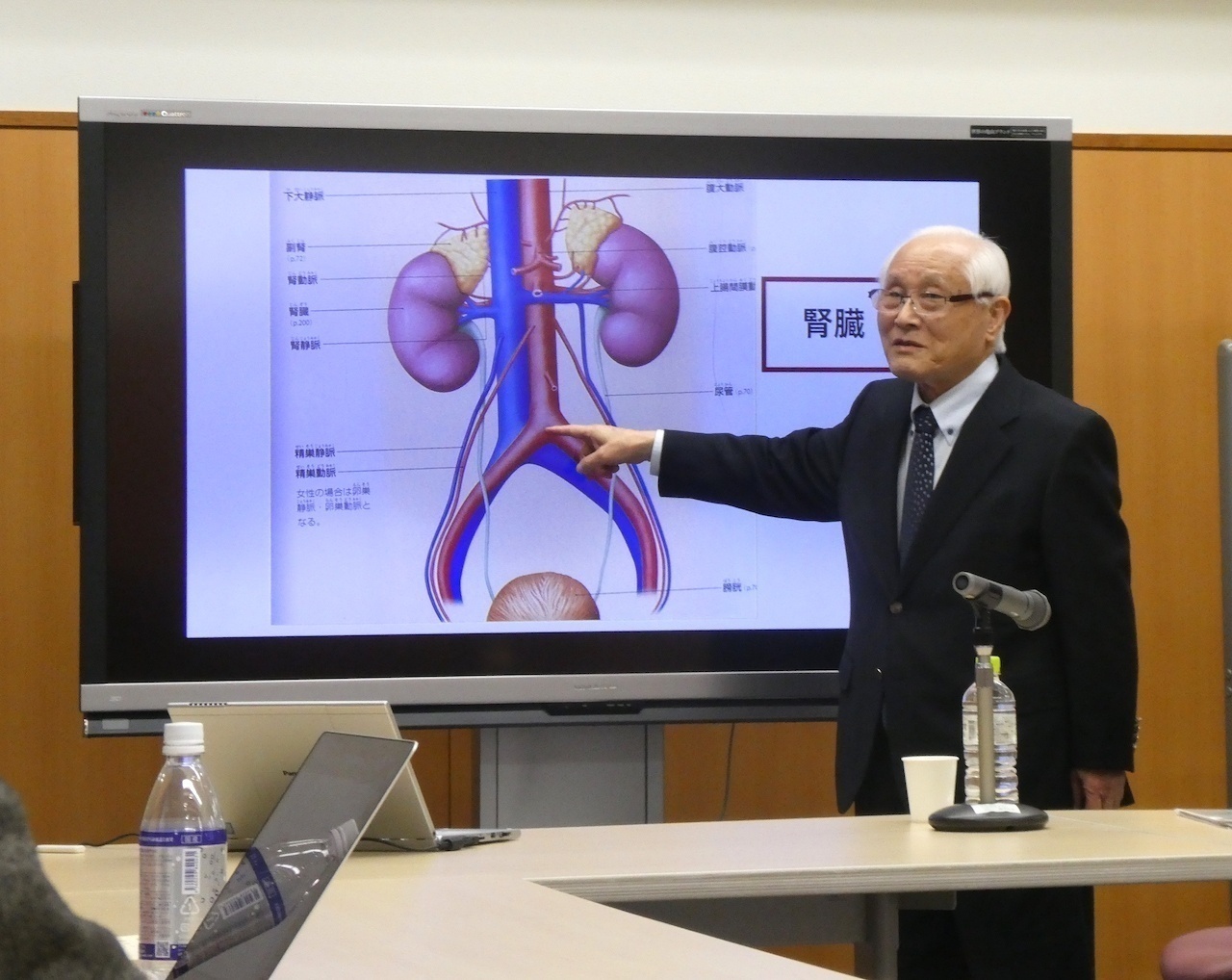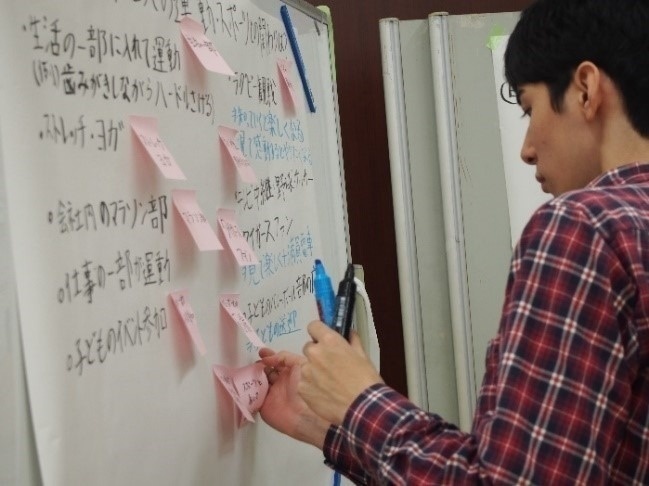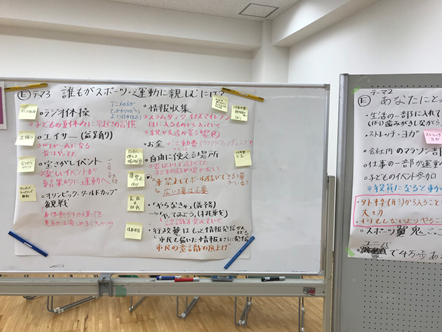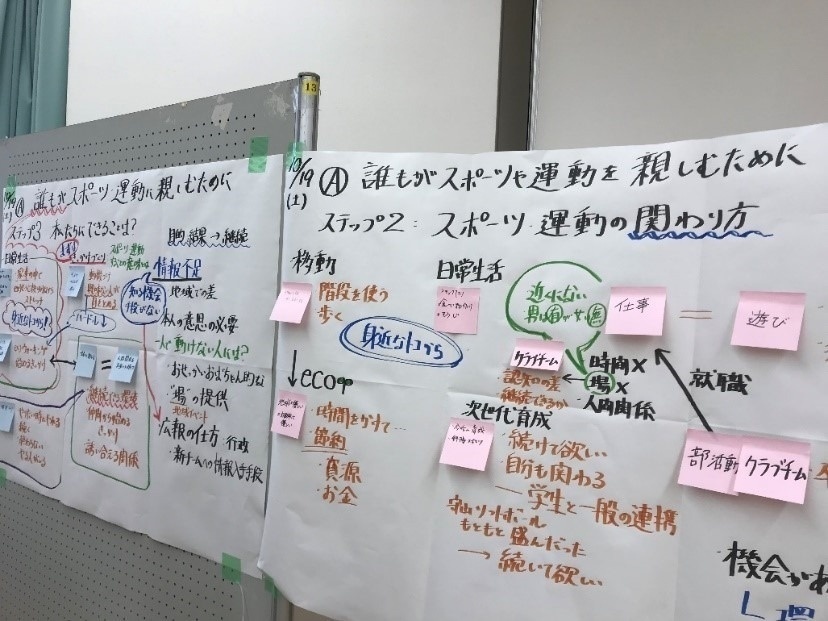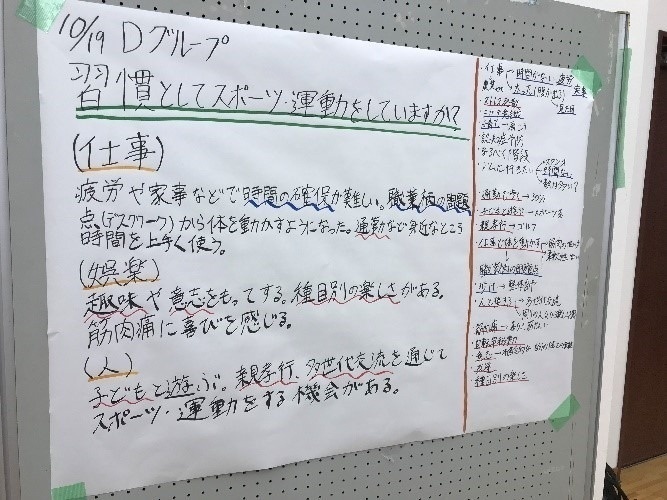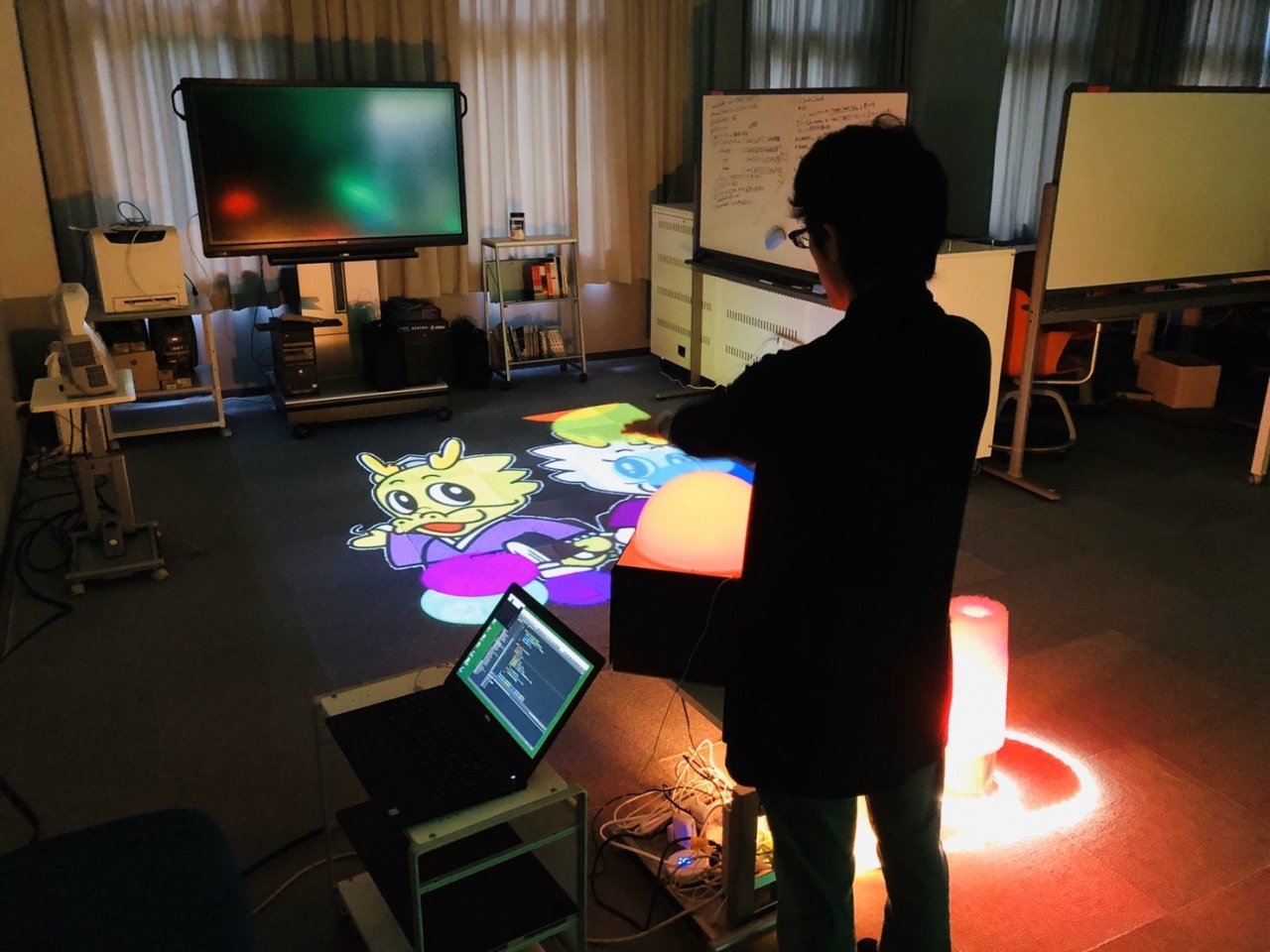特別展「日本の素朴絵」の入場者数が2万人を突破!【龍谷ミュージアム】

今朝の京都は気持ちのよい青空となり、暖かな気候となりました。さて、龍谷ミュージアムで好評開催中の「日本の素朴絵 -ゆるい、かわいい、たのしい美術-」は、本日午後に入場者数が2万人を突破しました。
記念すべき2万人目となられましたのは奈良県橿原市在住の赤井 貞代さん。赤井さんには石川副館長から特別展の図録、中村芳中のクリアファイル、鍬形蕙斎の一筆箋、つきしま絵巻と竹虎図のポストカードなどのオリジナルグッズが贈られました。
赤井さんは、かつての職場の同僚でご友人の奥田 幸世さんと着物で美術館巡りをするのが趣味とのこと。本日は、様々な雑誌や新聞で紹介されている素朴絵を実際に観てみたいという奥田さんに誘われて、初めて龍谷ミュージアムに来られたそうです。2万人目になったことについて、赤井さんは「とても光栄で嬉しい」とおっしゃっておられました。
11月11日(月)の休館日を除き、本展は17日(日)の閉幕まで毎日開館いたします<11月5日(火)も臨時開館>。後期展示が始まり、先週から来館者が増えてまいりました。閉幕に近づくにつれ、さらに混雑することが予想されます。是非、お早めにご来館ください。
【関連サイト】
◆ 龍谷ミュージアム
◆ 「日本の素朴絵」特設サイト
◆ 「日本の素朴絵」公式Twitter
◆ 開館スケジュール
◆ 細見美術館「琳派21 没後200年 中村芳中」との入館料相互割引
【主なイベント】
<スペシャルトーク>
講義室で学芸員が展覧会の見どころを解説します。
○日時:11月2日(土)13:30~14:15
○会場:龍谷ミュージアム1階 101講義室
※事前申込み不要・聴講無料・観覧券必要(観覧後の半券可)
<ポスタープレゼント>
先着50名様に本展のポスター(B2サイズ・非売品)をプレゼントします。
○日時:11月5日(火)10:00~
○場所:龍谷ミュージアム地下1階受付
<ギャラリートーク>
展示室で学芸員が作品を解説します。
○日時:11月9日(土)13:30~14:15
○集合場所:龍谷ミュージアム2階 展示室入口
※事前申込み不要・聴講無料・当日の観覧券必要