教職説明会<2019年度入学生(教職課程履修希望者)対象>
2019年度入学生(教職課程履修希望者)対象
(1)教職課程は登録制になっています。詳しくは、「2019年度入学生用履修要項別冊 教職課程ガイドブック」3ページ、「1.教職課程履修のための手続き」をよく読んで、対応してください。
(2)4年間の流れは、「ガイドブック」43ページを見て把握してください。
(3)教職課程についての連絡は、掲示板(深草教職センター)で行います。
ここにメッセージを入れることができます。

Science Café 生き物のセカイをのぞき見る-地球スケールから顕微鏡スケールまで-
生命の設計図とも呼ばれる化学物質「DNA」 ー DNAは私たちの体だけでは...

【研究PJ成果報告】「女性に対する暴力被害調査」の調査結果を記者発表しました
本調査は、本学矯正・保護総合センターの実証研究プロジェクトの一つと...

龍谷大学社会学部 津島昌寛教授と法学部 浜井浩一教授が女性に対する暴力被害の実態として「女性の日常生活の安全に関する調査」(2016)の調査結果を発表
龍谷大学社会学部の津島昌寛教授と法学部の浜井浩一教授が、日本学術振...
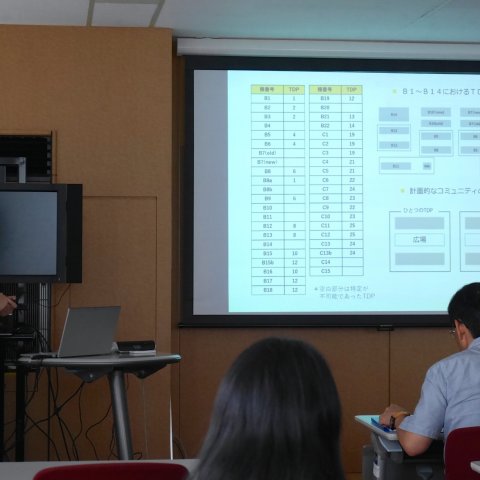
政策学研究修了生の吉田智美さんが日本都市計画学会関西支部第15回研究発表会奨励賞を受賞
7月30日に開かれた日本都市計画学会関西支部第15回研究発表会(開催地...

【研究PJ成果報告】 リーフレット<團藤重光の人権思想研究>を公刊しました
本リーフレットは、本学矯正・保護総合センターの團藤重光文庫研究プロ...

2019年度入学生(教職課程履修希望者)対象
(1)教職課程は登録制になっています。詳しくは、「2019年度入学生用履修要項別冊 教職課程ガイドブック」3ページ、「1.教職課程履修のための手続き」をよく読んで、対応してください。
(2)4年間の流れは、「ガイドブック」43ページを見て把握してください。
(3)教職課程についての連絡は、掲示板(深草教職センター)で行います。
龍谷大学経営学部の秋庭ゼミでは年3月16日(土)17:30-龍谷大学 町家キャンパスにおいて、若者に日本酒普及を図るサークル「日本酒文化研究会 TASHINAMI(たしなみ)」を設立サークル設立イベントを開催しました。
当ゼミでは産公学連携の一貫として、近年消費量が減少している日本酒の普及を図るための活動や調査をおこなってきております。実際に若者向けに普及を図るイベントとしてこれまで全6回のイベントを実施しておりますが、活動を地域レベルに拡大すべく、このたび大学において一般同好会を設立し、近隣の学生および京都伏見をふくむ酒造関係者の皆さんにも広く参加を呼びかける事としました。ここ数年、数多くの若手醸造家が酒造りに真摯に取り組み、日本酒の酒質レベルは急激に向上しており、そのおいしさは必ずや若い人々にも理解してもらえると確信しての決断です。
当日はサークル立ち上げのためのイベントとして、第7回日本酒勉強会「めくるめく銘酒の世界」を秋庭ゼミ日本酒プロジェクトと日本酒文化研究会TASHINAMIの共催で開催。利き酒選手権の優勝者で数多くのイベントを手がける講師を招聘し、それぞれの背景や飲み方について説明をしてもらいながら、日本酒の世界を体感してもらいました。
参加者からは「日本酒は敷居が高いと思っていたが、自分でも味の違いを感じることができた。」といった感想を聞くことができました。
龍谷大学を「香り」で表現したオリジナルブレンド紅茶「深草“OTOME”」を経営学部藤岡章子教授と藤岡ゼミナール(マーケティング専攻)の学生が研究プロジェクトの一環として企画開発しました。このプロジェクトは、ブランドを構成する要素の1つである「香り」に着目し、龍谷大学というブランドを「香り」で表現したものです。
良質な紅茶を高価格で取引し、紅茶の品質安定と、茶農家の生活安定に取り組む、高級紅茶ブランド「ムレスナティーハウス」の協力のもと、完成させました。
大学のイメージを「香り」で表現し、従来と異なるアプローチで龍谷大学の魅力を知ってもらうことがねらいです。
4月4日(木)には、三条商店街内に1日限定の店舗「龍谷マルシェ」を設置し、一般の方へ販売(税込140円)や試飲会などを予定しています。
詳細は以下からもご確認いただけます。
https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-3295.html


学生法律相談部による無料法律相談について、2019年度前期の日程をお知らせいたします。
【日程】毎週火曜日(春・夏・冬休み及び大学休業日・定期試験前などは除く)
4月:9日、16日、23日、30日
5月:7日、14日、28日
6月:4日、11日、18日、25日
7月:2日、9日、16日
【時間】
午後4時45分~午後6時
【申込】
当日・会場にて受付(予約不要)
【場所】
龍谷大学深草キャンパス 4号館5階
※刑事事件・税法関係・行政関係・訴訟中の事案などは、取り扱っておりません。
※相談内容に関する資料を持参していただけると幸いです。
※当学生法律相談部では、弁護士の行う法律相談同様、情報の守秘義務を遵守しております。
※荒天等により大学が休講になった場合、法律相談を中止いたします。
詳細は、添付されているPDFファイルをご確認ください。
2019年4月1日(月)に、「2019年度 入学式」が挙行されました。
その後各学科専攻に分かれて、クラス会が開催され、クラス担任の先生方から、大学生活や教育内容などについて熱心にお話いただきました。
<2019年度入学生>
★ 文学部入学生 921名
真宗学科 133名
仏教学科 112名
哲学科哲学専攻 78名
哲学科教育学専攻 72名
臨床心理学科 93名
歴史学科日本史学専攻 73名
歴史学科東洋史学専攻 68名
歴史学科仏教史学専攻 60名
歴史学科文化遺産学専攻 45名
日本語日本文学科 90名
英語英米文学科 97名
★ 文学部編入学生 17名
★ 文学研究科生 55名
修士課程 44名
博士後期課程 11名
★ 実践真宗学研究科 9名
ご入学まことにおめでとうございます。
文学部教職員一同、心よりお祝い申しあげます。