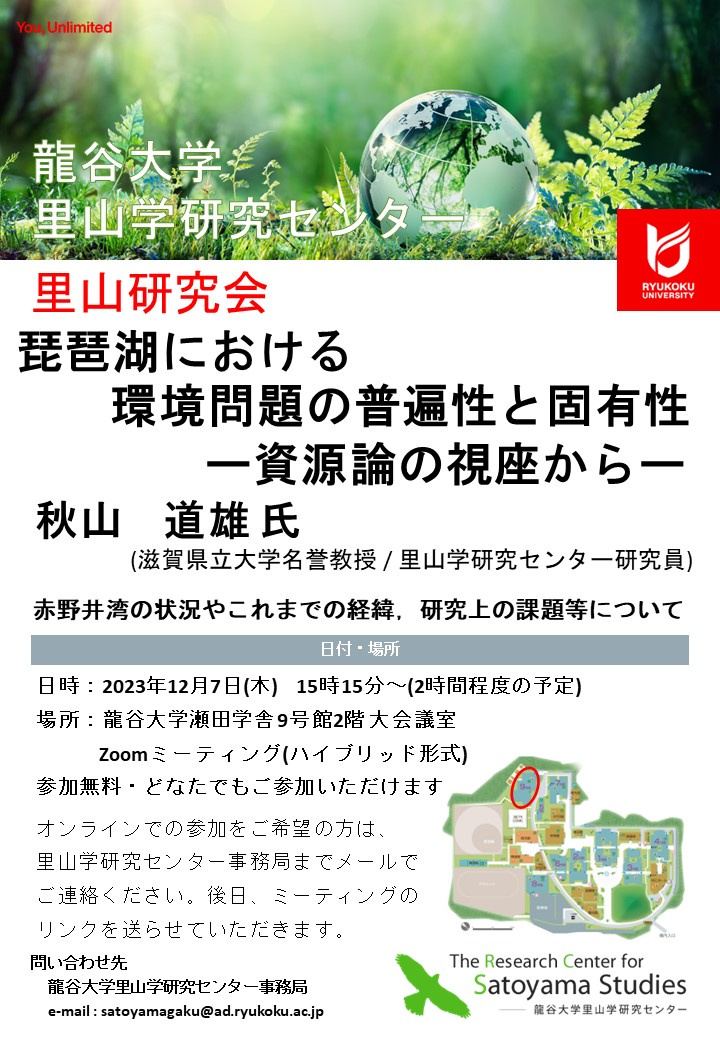日本史学専攻 卒業論文中間報告会を開催しました(2023.11.24)【文学部】

11月24日(金)に、日本史学専攻の各ゼミ代表者の5名が、現在執筆中の卒業論文について報告をおこないました。
出席した学生・教員から活発な質問が寄せられ、討論が白熱して予定の時間を超過する一幕もありました。
報告したゼミ代表の学生はもとより、聴講した他の学生にとっても、これから本格化する卒業論文執筆に向けて、刺激を受け、気を引き締める良い機会となったようです。
企画・運営、司会・進行から報告者へのサポートにいたるまで、大学院生諸君による献身的な奔走もあって、本報告会を成功裏に終えることができました。



2023年度 龍谷大学文学部歴史学科日本史学専攻 卒業論文中間報告会
日時:11月24日(金) 13:30~16:25
発表20 分 質疑応答10 分
【開会の挨拶】13:30 ~ 13:35
【中世史ゼミ】13:35 ~ 14:05
加藤 舜 「大蔵合戦における河内源氏と関東武士団」
【近世史ゼミ】14:05 ~ 14:35
田中 偲温「近世初期の久我家と源氏長者」
【近代史ゼミ】14:35 ~ 15:05
阪口久美子「明治・大正期におけるアイヌ民族の信仰
―シサム(和人)とアイヌプリ(アイヌ風)をめぐって―」
【現代史ゼミ】15:20 ~ 15:50
井口 築 「濱口雄幸内閣における内閣の意思決定過程について
―ロンドン海軍軍縮条約・金解禁問題の事例から―」
【古代史ゼミ】15:50 ~ 16:20
山口 夏旺「仁明朝以降の皇后不在期間について」
【閉会の挨拶】16:20 ~ 16:25