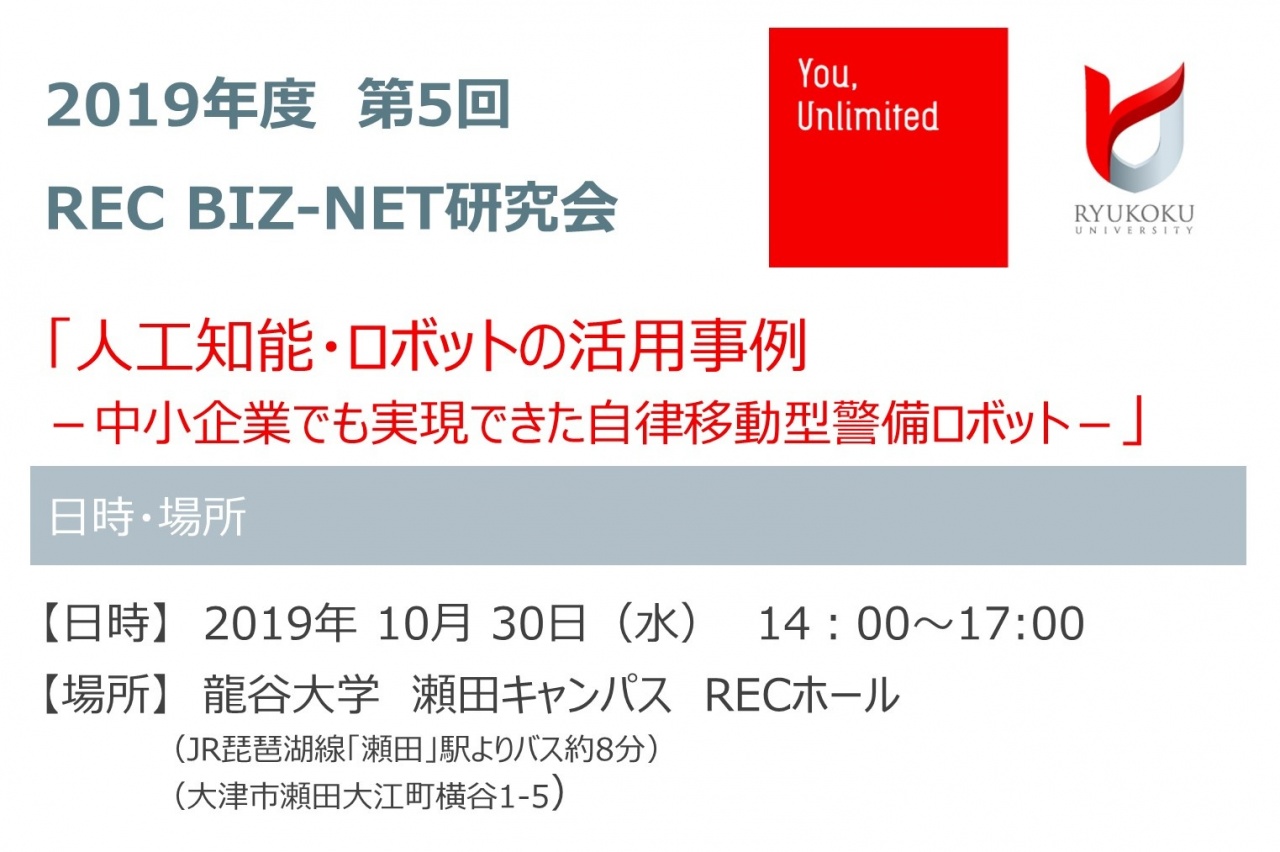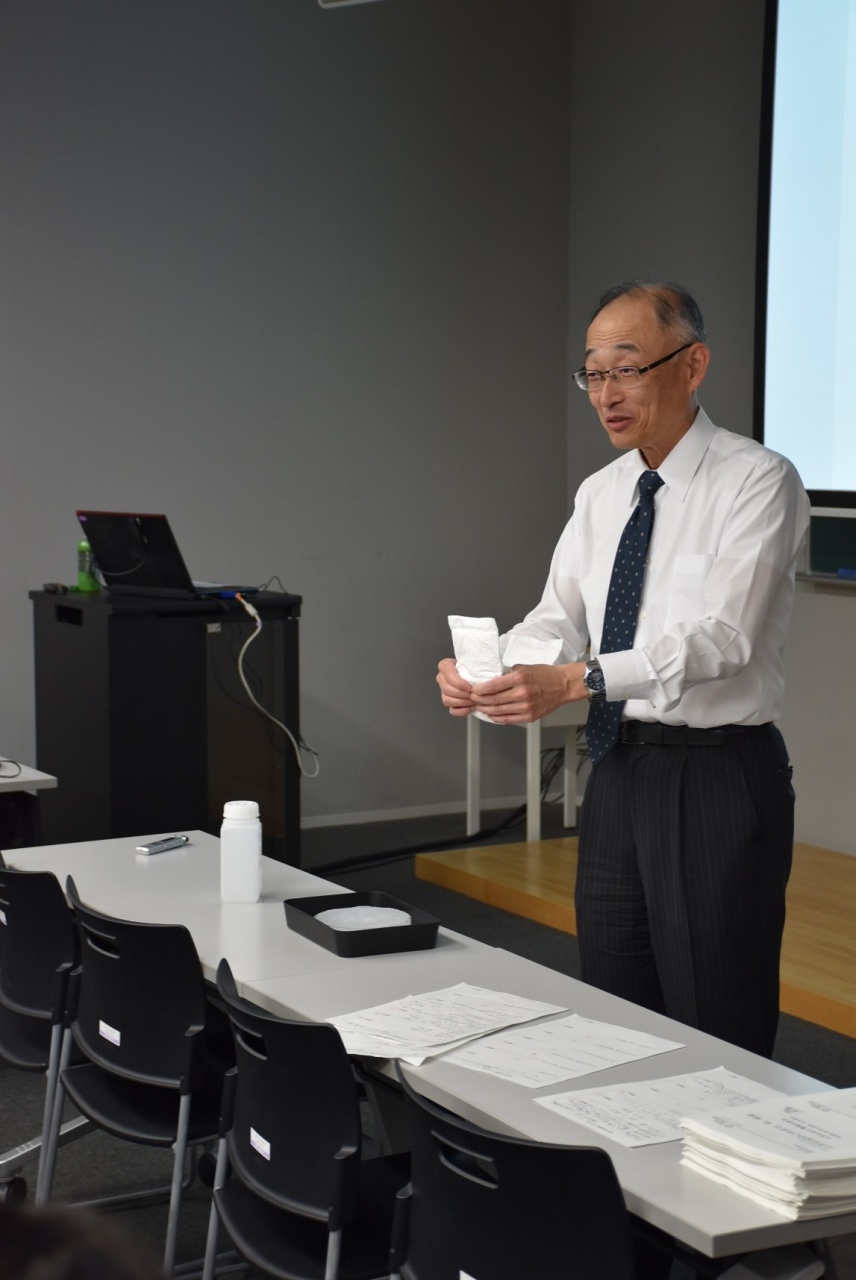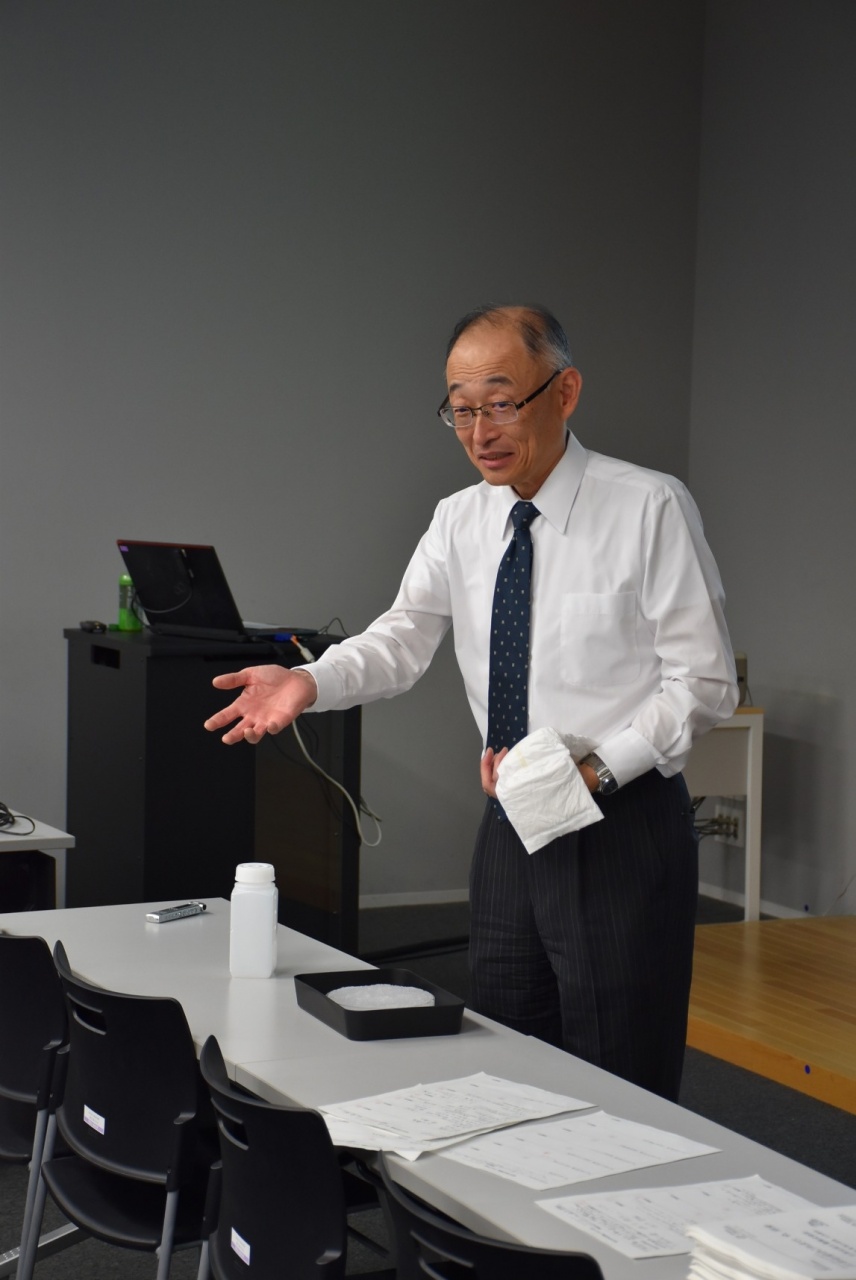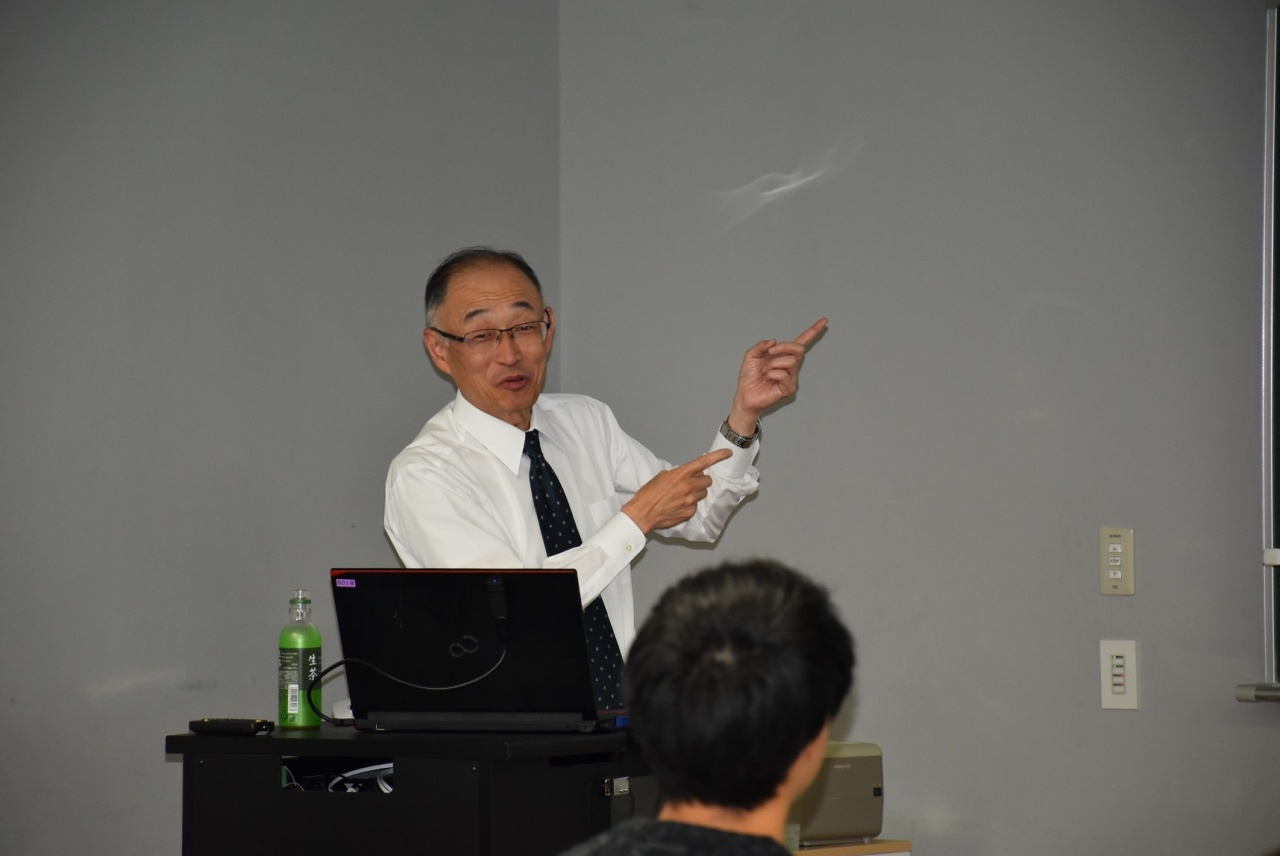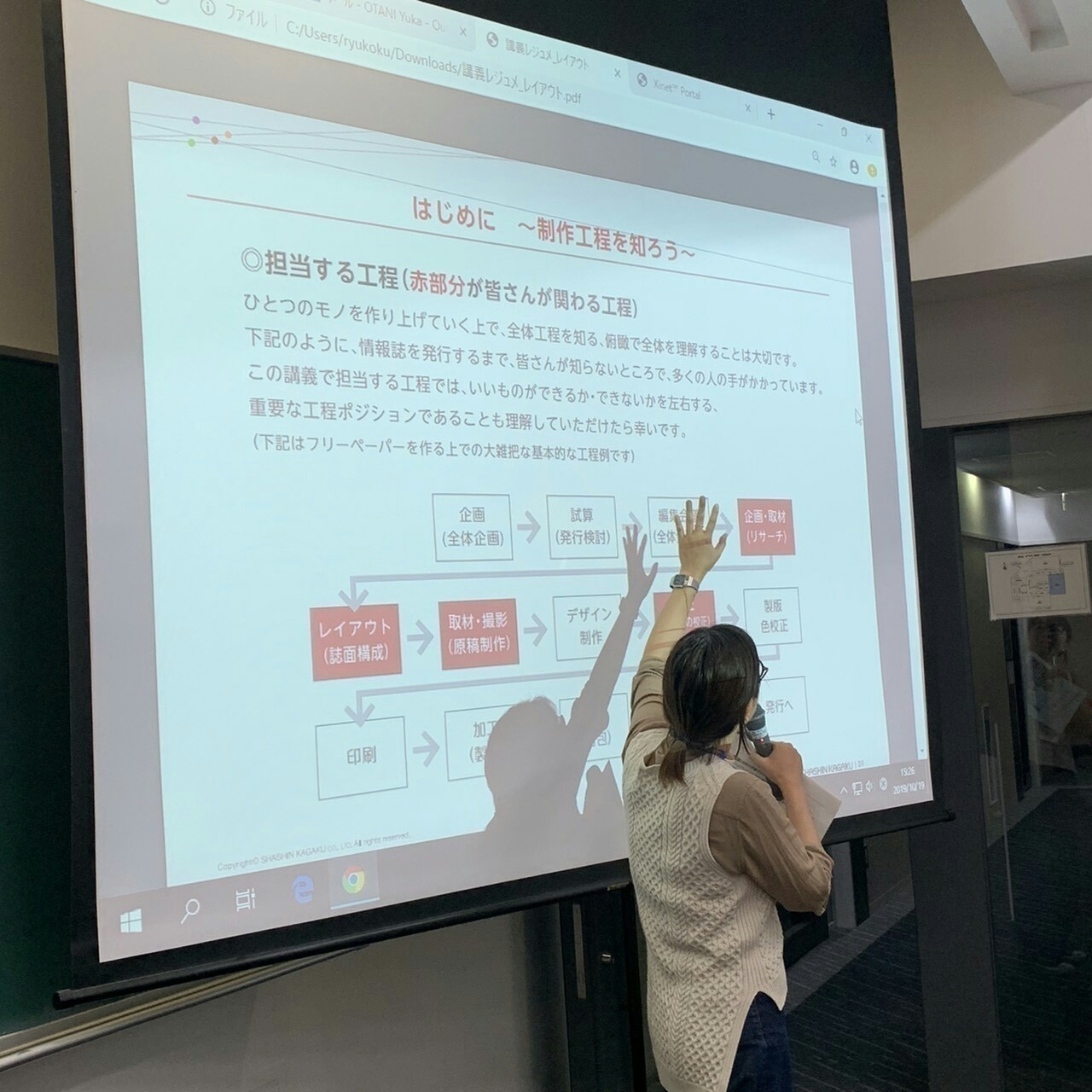第31回龍谷大学新春技術講演会
第31回龍谷大学新春技術講演会を開催します。
本講演会では、「先端技術でひらく持続可能な社会」をテーマに基調講演をしていただきます。また、本学の研究成果の一部をご紹介させていただきます。
当日のプログラムは次のとおりです。
なお、申込受付は1月5日で終了しています。
開催日:2020(令和2)年1月15日(水)
会 場:びわ湖大津プリンスホテル コンベンションホール「淡海」2階
テーマ:先端技術でひらく持続可能な社会
講演会 第1部 13:00~15:20
13:00~13:10 開会挨拶 龍谷大学 研究部長 清水 耕介
13:10~13:30 ご挨拶 経済産業省 近畿経済産業局
13:30~14:20 基調講演Ⅰ
材料・化学メーカーが生み出す製品付加価値
株式会社日本触媒
常務執行役員 吉田 雅也 氏
14:20~14:30 休憩
14:30~15:20 基調講演Ⅱ
安心・安全な給食を提供し続けるために
-セントラルキッチンの活用について-
日清医療食品株式会社
ヘルスケアフードサービスセンター京都センター長 郡司 慎也 氏
15:20~16:20 ポスターセッション・技術相談会
16:20~16:30 龍谷大学からのお知らせ
先端理工学部紹介 理工学部長 松木平 淳太
農学部紹介 農学部長 大門 弘幸
講演会 第2部 16:30~17:30
16:30~17:00 講演Ⅰ
インタラクティブ・アンビエンスをめざして
-情報が環境化する時代に-
龍谷大学 理工学部情報メディア学科 教授 外村 佳伸
17:00~17:30 講演Ⅱ
匂いを介した植物間のコミュニケーションとその利用
龍谷大学 農学部植物生命科学科 准教授 塩尻 かおり
懇親交流会 17:30~
お問い合わせ先
龍谷大学研究部(瀬田)
TEL:077-543-7746
FAX:077-544-7195